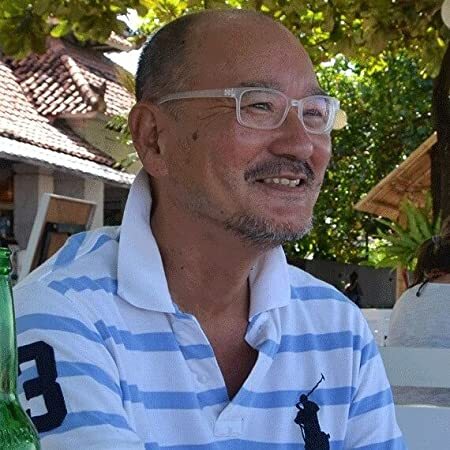その後、電話帳出版のシステム開発プロジェクトに従事した時は社内システム部の所属となり神谷町にある第41森ビルで仕事をした。桜田通に面して17森ビルから歩いても30分程度の距離にあり、最寄りは地下鉄神谷町駅だった。
1967年ごろから新聞で電算写植システムが導入され始めていて、1970年代終わりには電電公社の電話帳もCTSで作成する方針が固まり1980年代初めに稼働が始まった。
ここでCTSは(Computer Typesetting System)であり(Cold Type System)でもある。溶融金属活字を使う「ホットタイプ・システム」に対して、写植システムでは文字版下を作成するのでコールドタイプだからである。
私の所属した電話帳出版のシステム開発プロジェクトは当時普及を始めた電子印刷システムを電話帳出版に利用するシステム開発がミッションで、総勢20名にも満たない小ぶりなチームだった。第17森ビル時代とは打って変わって開発計画がなかなか定まらずにシステム開発の前段階である調査期間が異常に長かった。日本人の姓名に使用する漢字分布や配列の研究などに2年ほど携わった。
当時はほとんどの人が電話帳に姓名を掲載していた。従い電話帳掲載の姓名と使用文字・特殊な読み方=難読姓を調べることは国語研究上のかなり貴重な資料になり得た。当時でも人名に関する辞典や研究書はあったがここまで網羅的にほぼ全日本人について調べたことは無いと思う。その意味で調査は極めて貴重な生産物なのだが、おそらく保存されていないだろうと思う。当時の青焼き資料がどこかにあればNTTデータで製本して出版するかそれがかなえられなければ国立国語研究所に寄贈する方法もあったのだが。
電話帳編集システムで苦労したのが配列順の問題だ。配列など読み仮名のソートキーでソートすればなにも問題ないのではと考える方が大半だろう。いやごく少数の方を除けばほとんどすべてと言っていいかも知れない。電話帳の姓名の配列順番をじっくり眺めると単なる読み仮名だけでソートした者では無いことがわかってくる。もっとも昨今では電話帳の登録も減り、電話帳そのものの意義も変わってきているのでその配列についてことさら書き記しておくこともあまり意味のないことかも知れないと考えていたが、それでも心の隅ではせっかく苦労して開発したソートキーの説明をどこかに残しておきたいとの思いはあった。
一橋大学附属図書館報 “鐘” No.7 1981年5月20日発行に日本語の分かち書きについて法則が確立されていないことで聖職と生殖がごちゃ混ぜになるとの記事がある。
聖書--聖書講座--生殖--聖書物語--清少納言--聖書年代記--青少年--聖書における人間と社会。このような配列に対し図書館測も利用者の方も多少の抵抗を感じながら規則に従っているのが現状である。これは電話帳配列についての難しさを代弁してくれている。
さらにはコンピュータソフトの開発よりもむしろ電話帳編集全体を満足なレベルに仕上げるための核となる電子写植機や日本語入力装置などのハードウェアの開発と電話帳に使用される文字の調査に全力を挙げていた。
それまでは全国で8か所あった電話印刷会社、例えば近畿電話印刷などで活版職人が鉛活字を拾って原版を組み、写植フィルムを版下として作成し印刷機に回すという工程を踏んでいた。
所沢の電話印刷会社に打ち合わせに赴くと熟年の活版工が鉛に染まったエプロンがけをして鉛活字を木枠で囲ったボードからピンセットで拾っていた。平均年齢は50代を優に越えていた。
電話帳の発行と並んで案内簿と呼ばれる電電公社社内の案内台で使用される電話帳の発行も重要な印刷物だった。番号案内104でコールされると全国各地にある案内台の各デスクの棚には案内簿と呼ばれる数十分冊にも分けられた印刷物が並んでおり、それを参照しながら電話番号案内を行う。
電話帳は1年半に一回の更新および発行でよいが案内簿は毎週常に最新に更新されていなければならない。システムの目的はむしろ案内簿のメンテナンスにあった。後にこれも電話帳システムの展開系である電子番号案内システムに移行することになり、案内簿の役割は終わる。
初期の電話帳システムでは電話帳版下と呼ばれるフィルム=電話帳各ページをポジで透明フィルムに印刷した原版を作成する装置=電子写植機を開発することに装置開発の力点が置かれていた。活字並とまではいかないが、専門家がみて納得できるレベルの美しさであることが要求された。しかも文字の大きさは5.5ポイントと大変小さい。欧米ではすでにこうした第三世代の電子写植機が1972年から開発されていたが日本では文字の複雑さと多種類のために開発が遅れていた。
電子写植機の開発はNTTデータ通信本部と富士通が担当した。電子写植機はフィルムに文字をトナーで静電吸着させる仕組みで、今ではコピー機でもかなりの版下ができるようになったが、当時はCRT方式で文字の形に光を当てトナーを吸着させる方式であり相当の物理的精度が必要であった。そのため頑丈さが要求されかなり大きな装置が必要であった。1*2*3メートル程度の大きさがあったと記憶している。
この装置の開発ポイントはいかに活字に肉薄できる版下ができるかで、当時の製本業界の専門家からみれば電子版下などは活字製本の美しさからみて足元にもよれないレベルであった。富士通側は電話帳版下に要求される5.5ポイントサイズ(1ポイント≒0.3514mm幅)を美しく仕上げるため、光学的メカの部分に相当苦労していた。結果的にはあの虫眼鏡で見ないといけないほどの電話帳文字を富士通の努力で開発することに成功した。
もう一つのハードウェア開発は漢字入力装置で、当時日本語の入力をどのような方式にするのがベストか日本中で議論があった。今でこそパソコンのローマ字変換入力が当たり前になっているが、当時は専門的に入力するには日本文字一文字に2ストローク必要だということで入力速度に問題があると言う批判があった。
実際に測定してもベテランの漢字入力装置熟練者のほうがワープロ入力よりも速かった。日本語変換のソフトが当時まだ不十分で誤変換の訂正にも時間を取られた。そうした事情があり当時の漢字タイプライターに近い方式を採用した。今でこそ絶滅したが漢字和文タイプライターを使える技能者は職業訓練所で教えていることでもあり、当時かなり一般的な入力方法であった。
この入力版のどの位置にどの漢字を配列するかで入力速度に影響がでるため、かなりの研究時間を配置に取っていた。利用頻度の高い文字約3000文字を打ちやすい位置ブロックに収容するために電話帳に収録されている漢字の頻出度を全文字調査するということを実施していた。電話帳に収容されている3千万か4千万人の人名と使用される文字の調査であった。広い意味でのシステム開発には違いないのだが多数のスタッフが電話帳の文字を諸橋大漢和を座右において黙々と調査している姿は国語研究所の趣であった。
1970年代後半、コンピュータに漢字を含む日本語・記録させることについて、多くの議論があり、今からは想像がつかない程の揺籃期であった。このことを示すある一つの論文がある。当時の国立国語研究所のある研究員が論文を発表していた。それによると日本語をコンピュータに記録するには倍の記憶容量を要し、今後の発展のハンディになる。従い日本語はすべて英語に改めよという過激な内容であった。梅棹忠夫氏の日本語ローマ字化提唱に匹敵するほどの大胆な提案をまじめに行っていた。
今では記憶容量もキロからテラになろうとしており日本文字が2バイト必要とすることなど誰も気にしないし、ましてそのために日本語がハンディになるなど考えも及ばないが、記憶容量が国の産業全体の足を将来引っ張るかの心配をする時代もあったのだ。当時は日本語とコンピュータに関してはあらゆることが新鮮な調査・研究・開発のテーマになり得た。
その後平塚清が定年退職後、システム開発が横浜西局で本格的に始まり完成した。この頃横浜西局で眞藤恒を垣間見たことがある。リクルートのスパコンが設置されていた関係ではなかったか。
平塚清士は日常のレポートはもとより電気通信学会やその後身の情報通信学会の論文発表などへの参加も積極的に促された。年に数回全国の地方都市で開催される研究論文発表会には仕事の成果をまとめて先輩の誰かしらが発表を行っていた。ずっと後のことになるがある日私にもその発表の機会が巡ってきた。
開催地は東北大学キャンパスで仙台まで発表者も含めて5,6名くらいが行ったであろうか。その日の朝は保養所の食堂に集まり全員で飯を食う。一人当たりたかだか5分か10分の論文発表だが質疑応答もあるので私も含めた発表者は多少緊張している。保養所では朝からビールを出してくる。ここでAさんはビールを注がせ、訓辞を始める。
「発表の前には必ず、まずおおきく三回深呼吸をするんだ。それで落ち着く。」さらに極めつけは「ビールをぐっと一息に飲んでいけ。そうすると度胸がついて舌が滑らかになる」断るわけにも行かず言われたとおりにビールを飲んで出かけたがこれはあまり効果がなかった。そればかり発表時には頭が痛くなって困った。
酒席といえば忘れられないシーンがある。ある年の年納めの時だ。当時は年末の休暇にはいる前日は仕事納めと称して比較的早い時間から若い者が新橋まで酒のつまみや寿司などの買い出しをして仕事場に並べ、全員で11時頃から飲み始める。そのうちデータ通信本部の最高幹部達も各チームの酒盛りに回ってくる。普段はその後午後の早い時間に麻雀などに流れていくのが通例であった。
そのときは回ってきた部長氏と平塚清士は議論を始めた。なにか仕事の方針に関して意見が異なるらしい。かなりの激論になっているようだが我々は飲み食いとお隣同士のおしゃべりに忙しいのでそれほど関心を持って聞いてはいない。やがてお開きになり、エレベータホールまでその部長氏を送ってきた平塚清士はやおらその幹部の首を後ろから両手でホールドロックし絞め始めた。酔っているとは言え大柄な平塚清士に首を絞められた部長氏はひっくり返り尻餅をついた。あわてた周りの部下に止められてようやく事なきを得て収まった。部長氏は部下達の前で首を絞められ尻餅までついたのだ。大変な屈辱だろう。恥をかかされた怒りのあまり平塚清士の部下達を叱り飛ばしてからエレベータに乗り込み帰途に着いた。翌年の仕事始め早々、平塚清士は平謝りしたそうだ。
別の年の年納めのおり、やはりデータ通信本部長輿寛次郎が各チームを激励するために回ってきた。輿寛次郎は丁度私の横に座られたので礼儀として私の手元にあった一升瓶で輿寛次郎の茶のみ茶碗に日本酒を注いだ。その本部長輿寛次郎はぐっと一息に飲み干した。顔つきはニコニコとしている。
すると私の左隣に座っていた同僚が盛んに脇をつつく。彼が耳打ちしてきた。「それは水だよ チェーサーだよ。水割り用に置いてあるのだ」と注意してくれたがもう遅い。しまったと思ったが後の祭りだ。しかしくだんの本部長輿寛次郎は顔色一つ変えずに周りと雑談を交わしている。飲み干した後にきっと水だと気がついたことと思うが、部下に恥をかかせてはいけないと思ったのであろうか。なんだか司馬遼太郎の「坂の上の雲」に登場する秋山好古を髣髴とさせる泰然自若の趣をもつ本部長輿寛次郎であった。