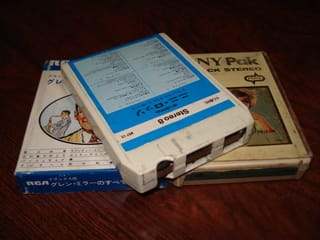あれはまだ20代前半の頃だった。
3年間付き合っていた彼女との間に、亀裂が入った・・・
”覆水盆に返らず”とはよく言ったもの・・・
一度切り損ねたステアリングは、修正する事が出来なかった。
結論の出た次の週末・・・
北志賀の林道を走っていた。
当時は、まだ砂利道の区間が多く、ハイスピードで走っていた私は、覚えたての”カウンターステア”と、少し自虐的になっていたせいもあり、自分のコントロールを超えたスピードでドリフトしていた。
雪も溶け、冬季閉鎖が開けたばかりの林道は、行楽客の車も走っている・・・
シフトロックでリアがスライドし、ブラインドコーナーを抜けた瞬間、白いクレスタが突進してきた。
相手はフルブレーキング・・・
しかし、完全なアンダーステア・・・
やばい・・・
次の瞬間、カウンターをオーバーに当てた私は、自ら側溝の中の人となった。
まぁ、事故には成らずに良かった、か・・・
その後、他の通行人や林業の大型トラックに牽引され、側溝から這い上がる事は出来たが、左フェンダーには大きな痕が残っていた。
その時に、何かが吹っ切れた。
これからは、自分の時間は100%自分のものだ。
昔からの夢であった、”モータースポーツ”に足を突っ込んでみようと・・・
それから、左フェンダーの修理費用は、車の改造費に充てられる事になった。
6点式ロールバー
強化クラッチ
マツダスピード、ショック&コイル
マーベル、ブレーキパッド
マツダスピード、4Pリミテッドスリップデフ
フルブッシュ
ウイランズ、4点式シートベルト
ポテンザ71S&ウェッズスポーツ
ポテンザ610S&スーパーラップホイール
雪山練習用スタッドレス
他にもあったと思うが思い出せない・・・
国内B級ライセンスを取得し、格式の低い競技から参加した。
競技種類は、スピード競技である”ジムカーナ”
工事用のパイロンを広いアスファルトグランドに立ててコースを作り、そのコースを走りタイムを競う競技である。
これに、のめり込んだ・・・
車をコントロールする醍醐味・・・
競技中の緊張感・・・
タイムへの挑戦・・・
これに全精力を注いだ。
残念ながら、リザルトを残す事は出来なかった・・・・
しかし、在りし日の思い出として、今でもふと思い出すことがある。
あの緊張感・・・
やっぱり素敵だ。。。
(写真は雑誌スピードマインドに掲載された、若き日の谷やん)