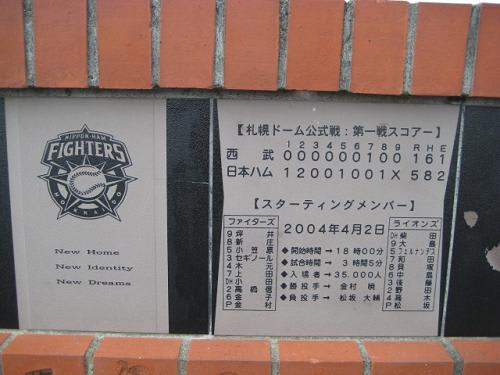6月5日(土)
巨人ファンのO君が東京ドームで観戦したいと言うので、チケットを予約しに動くも、すでに売り切れ。ヤフオクでもプレミアがついて高い。金券ショップでも同様であった。
今季、巨人は絶好調であるし、ファンの熱気も例年以上にヒートアップしている。日ハムは今季は低迷しているとはいえ、昨年のパリーグ覇者である。いずれ、上昇してくるであろう。しかも、その日はローテーション的にダルビッシュが先発濃厚である。東京ドームでの巨人戦はただでさえ、チケットが入手困難であるが、この内容ではプレミアがついて当然である。
しかし、半分諦めかけていたある日、ふと訪れた神田の金券ショップでS指定席通常価格5900円のところが、4000円で売っていたので、当然、その場で即座に購入した。同様の席がプレミア価格で軒並み10000円以上していたのに、この店だけ、一体、どうなっているのだろう?値決めが下手なのか、野球に詳しくないのか。
2007年にO君と一緒に大阪ドームで野球観戦した時も、オリックスVS日ハムであった。しかも、先発はダルビッシュであった。ダルビッシュが押さえて、稲葉が決勝打を放つ日ハムの必勝パターンで見事に勝利した。日ハムファンではないが、日ハムには何故か縁を感じる。昔、日ハムが札幌に移転する前、東京ドームで何度か観戦した時も全て勝利した記憶があるし、2軍が鎌ヶ谷に移転する前、相模原に本拠地を置いていた頃、当時、住んでいた家が近くだったので、横浜との2軍戦を見に行っていたが、日ハムが負けた記憶がない。
以上の実績から考察すると、過去、日ハム戦を観戦して負けた事がないと仮定すれば、当然、勝率は10割である。試合観戦数は思い出せる範囲で、1軍で5,6試合程度、2軍では10試合前後、通算成績は16戦16勝というありえない好成績である。私は日ハムにとっては勝利の女神のような存在である。しかし、残念ながら、日ハムは好きでも嫌いでもない。はっきりいって無関心に近い存在である。パリーグの試合は他球団の試合、選手が見たくて、東京ドームで行われている対日ハム戦を見に行ったのである。それ以外は何となく野球を見に行きたい気分だが、その日に東京でセリーグの試合が無く、たまたまその日に東京ドームで試合をしている日ハム戦でも見ようか、他に選択肢が無いからしょうがないな、といった感じである。大阪ドームに行った時は行ったことのない球場だから一度は行ってみたいので、行ってみたら、たまたま日ハム戦だったというだけである。相模原で行われていた、2軍戦に至っては100%横浜の試合が目的であり、日ハムにはほぼ無関心であった。
しかし、相模原での2軍戦で横浜が勝った記憶がないというのは奇妙である。10試合前後も見ているのに不自然である。おそらく、当時の横浜の2軍はとても弱く、日ハムの2軍は将来有望な若手が数多く活躍して、相当強かったのであろう。その結果、その時に2軍で汗を流していた選手達がその後の常勝軍団、日ハムの主力選手へと成長していったのであった。反対側からの視点で見ると、横浜がその後、長期に渡って低迷する原因は、相模原に住んでいた時期の1996年~1999年にまでさかのぼる。1998年に横浜は38年ぶりの念願の優勝を果たす。前年は2位、優勝の翌年は3位と、その後の横浜はかつてのBクラスが指定席の弱小球団が嘘のように、Aクラスの時代がしばらく続いた。優勝時のメンバーの主力選手の脂の乗り切った時期と重なるが、それに慢心してか、球団が次世代を担う2軍、若手選手の育成、発掘に熱心でなかったことが、今の最下位が指定席という無惨な結果につながっている。常勝チームは主力選手の世代交代がスムーズである。つまりは層が厚いのである。スカウトの選手を見る目が確かで、2軍のコーチの育成手腕も確かである。
あの時期の横浜は確かに優勝した事実が証明するように強かった。その前後の数年間はAクラスの常連であり、素晴らしい選手が集まっていたが、いかんせん層が薄かった。その主力選手がひとり、ふたりと欠けていくと、またたく間に弱小球団に逆戻りしてしまった。選手発掘能力の低いスカウトによるドラフト戦略の失敗、また、2軍コーチの育成能力の欠如、など理由は誰もが理解できる明瞭な事である。その後の急激な弱体化、そして現在に至る出口の見えない長いトンネル、暗黒時代の始まりは、意外な事に実は優勝した1998年前後から始まっていたのではと考えられる。
しかし、悲しいかな、長年、この球団のファンをしていると、長いトンネルがトンネルとも思えなくなってくるのである。それが当たり前の光景に見えてしまうのである。小中学生の頃、横浜(当時は大洋)が優勝できるなんて夢にも思っていなかった。もちろんファンなので勝利を願っているし、勝てば嬉しく、負ければ悔しい。しかし、シーズン通しての希望は高く持ってもせいぜい3位、現実的な目標は4位か5位、最下位だけは避けてもらいたい、その程度の希望、目標が長年続くと、おそらく、生きているうちに優勝は無いだろうと半分は本気でそれほど悲観的に思わざるを得なくなってしまうのだが、大洋ホエールズから横浜ベイスターズと球団名を変えてからは球団の優勝への意気込み、本気が伝わるようになってきた。徐々に大洋カラーが消えて、チームカラーが変り、選手達が実力をつけていき、とうとう1998年には念願の2度目の優勝を果たす。38年ぶりの優勝は日本最長記録であった。
優勝の瞬間は球団が弱い時代から、ずっと応援してきた仲間達と一緒に横浜スタジアムで喜びあった。感極まって涙する仲間達。弱小球団を長い間、応援してきて優勝して涙が出てこない人間はそこにはいなかった。そんな中で、私は実感が湧かず、頭がぼーっとして、夢を見ているような感じで涙は出てこなかった。ぼーっとした頭で、涙を流す仲間達を傍観者的に見ていたのだが、優勝直後にOBのインタビューが行われ、(大洋時代の投打の主力、田代と遠藤が来ていたのだ。なんという粋な計らいであろう!)嬉しさ爆発といった感じで饒舌に受け答えする田代のインタビューの後で、遠藤にマイクが向けられたのだが、饒舌な田代と対照的に、なかなか遠藤の言葉が出てこない。言葉が出てこない時間が続いた後、遠藤が突然、メガネを取った。そして、その瞬間、彼の目から涙がこぼれ落ちた。涙が邪魔をして言葉にならず、「嬉しいです。」と一言、言うのがやっとであった。
私は遠藤の目から、涙がこぼれ落ちたのを見た瞬間、突然、号泣し、その場にしゃがみ込んでしまった。優勝した瞬間に涙を流した仲間達の中で、ただひとり涙を流すことなく、優勝したという実感がなく、多分、夢でも見ているのだろうと、傍観していた感すらあった私であったが、遠藤の涙を見た瞬間、目の奥からではなく体の奥、より正確に言えば、心臓のど真ん中の奥底のあたりから涙が込み上げてきたのである。それは不思議な事に、優勝の嬉し泣きではなく、遠藤に優勝させてあげたかったという悲しい涙であった。優勝したのは当たり前だが、もちろん嬉しかった。今までに経験した事のない嬉しさであった。しかし、その嬉しさよりも、どういう訳だが、悲しさの方が上回ってしまったのである。号泣というよりは、嗚咽に近い泣き方であった。最後にこんな泣き方をしたのはいつの日だったのだろうと思った。多分、思い出せないくらい遠い昔、小さな子供の頃であろう、今までに経験した事のないほどの、とても悲しい出来事があった時以来だと思った。しかし、その悲しい出来事が一体、何なのかは未だに全然思い出せないし、見当もつかない。大した出来事でなくても、小さな子供にとっては、かなりのショックで悲しい出来事だったのかもしれない。
今でも、あの日の遠藤が涙を流した瞬間のことは、まるでスローモーションを見るかのように脳裏に鮮明に焼きついている。12年も前の出来事であるが、まるで、昨日の事のように思える。そして、あの瞬間を思い出すと、今でも目頭が熱くなってくる。いつか機会があったら遠藤に聞いてみたいと思っている。あの時の涙の意味を。嬉しさなのか、悲しさなのか、あるいはその両方が混ざり合ったものなのか。それとも、それ以外の何かがあるのか。
あの歓喜の優勝の瞬間を横浜スタジアムで過ごした一緒に喜びあった仲間達、にわか横浜ファンではない、オールドファンの多くが、本音のところでは、私と同じ思いを抱いていたに違いない。横浜ベイスターズの優勝ではなく、本当は大洋ホエールズの優勝が見たかったんだと。
優勝の嬉しさの余韻が覚めやらぬ、優勝の瞬間の5分くらい後だったか、となりにいた仲間のひとりが、ぽつりと「もう優勝はしばらくいいや・・・」と言った。私も全く同じ気持ちだった。彼と私以外の多くのファンも同じ気持ちだったと思う。普通のプロ野球ファンなら毎年のように応援するチームに優勝して欲しいと思うのが当然である。特に強い球団のファンほど、当たり前のようにそう思うであろう。しかし、横浜ファンは違うのである。一生に一度、優勝を見ることができた。それだけでもう満足なのである。極端な話、優勝のその瞬間に死んだとしてもこの世に未練は無いのである。
その発言の数分後、彼はこう言った「でも、死ぬまでにもう一度だけでいい、優勝を見てみたい。今と同じ気持ちを一度だけでいい。経験したい。」全く同感であった。世界中でこんなに慎ましいプロ野球ファンがいるだろうか。答えはひとつ。横浜ベイスターズファンのみである。私は日本一の野球ファンは横浜ベイスターズファンだと思っている。そして、こんな最高の仲間達とめぐり合えた自分は最高に幸せだと思っている。横浜ベイスターズが縁で出会い、集まり、強い絆を共有できた仲間達である。きっと、一生、付き合っていける仲間達であると、その時、確信したのであった。
そんな日本一のファンに愛され、支えられている横浜ベイスターズは日本で、いや世界で最も幸せな球団だと思う。しかし、球団はこの日本一、世界一、心優しいファンに甘え、あぐらを掻いていないだろうか。この日本一、世界一、心優しいファンがいなかったら、とっくの昔にこの球団は消滅していたか、それとも、身売りされて、横浜ではないどこか違う都市に移転していたのではないかと思う。球団関係者には、今一度、プロ野球球団とは一体何か、何を追い求め行動し、どういう結果を出さなければいけない使命を帯びている集団なのか、その使命を果たすことが生存条件なのだという事を真剣に考えて欲しいと願っている。
横浜ベイスターズの事を語り始めると止まらなくなってしまう。だいぶ脱線したが、今日は、巨人VS日ハムのゲームである。今回はO君のいわばおつきあいである。O君は横浜生まれで、これまでの人生で神奈川県から転居したことの無い、生粋の神奈川県民だが、熱烈なG党である。神奈川県出身者の大半はそんなものである。神奈川県出身の横浜ファンに出会うことの方が難しい。大半の神奈川県民にとって横浜ベイスターズは無くても困らない存在で、別に好きでも、嫌いでもない。無関心なのである。むしろ高校野球の方に関心が向いている。さすが、高校野球界でかつて「神奈川を制する者は全国を制す。」とまで言われただけの事はある。これも県民性であろう。高校野球の県大会がこれほど盛り上げる県も無いだろう。参加高校数は全国で断然トップである。
O君はG党の多くがそうであるように、巨人以外の球団に好き嫌いはない。巨人以外はプロ球団にあらずといった感じで、他球団の事は極めて無関心である。当然、本来は地元の球団であるはずの横浜ベイスターズにも極めて無関心である。しかし、彼に郷土愛が無いのかと言うと、そういう訳ではない。高校野球、自分の母校の応援は巨人以上に熱狂的である。O君の母校は60、70年代に甲子園の常連として黄金期を誇った時代があり、今でも毎年、ベスト32、16、8程度には進出する程の強豪である。(神奈川県でベスト16、8はすごい事である。その時点で4,5回は勝っていないといけないのだ。田舎の県ならとっくに決勝戦になってしまっている。)毎年、チームの戦力分析を細かく行い、年に2,3回以上は必ず応援に足を運ぶほどの熱心さである。
良席での観戦なので、試合前練習からじっくり見たい。今まで、東京ドームで観戦した時は外野席と取引先企業に招待された、シーズンシートの1塁側でした見た事が無い。バックネット裏は初めてである。

到着した頃は、ちょうと日ハムの打撃練習中であった。



バックネット裏のシートはクッション付きで座り心地が良さそうだ。雨の心配の無いドーム球場ならではの配慮である。

中継用のカメラ。

記者席。

1塁側で巨人の投手が子供とキャッチボールをしている。どこかで見た顔だと思ったら、元横浜のストッパーで現在は巨人のストッパーのクルーンであった。

大洋時代は外国人選手をとるのが上手だったが、名スカウト牛込氏の退任後、やって来くるのはハズレ外人ばかりになってしまった。その中でも、数少ない当たり外人がクルーンとウッズであったが、どういう訳か、フロントは同一リーグの球団に放出してしまう。その資金で安い外人を大量にとってきては、失敗する。これを何度も繰り返している。安物買いの銭失いとはまさにこの事である。フロントの学習能力の無さ、無責任さには本当に頭に来る。監督、選手に責任を取らせてばかりで、自らは責任を負わない。まずはフロント陣の刷新から始めないといけない。そのフロント陣でなぜか、のうのうと生き残っている人物がいる。現在の業務部長・連盟担当笹川博史という人物である。この人物の経歴を見ると、要注意人物である事は一目瞭然である。
笹川 博史(ささがわ ひろし、1953年5月5日 - )
大宮高校から、1971年ドラフト7位で大洋ホエールズへ入団。長身の大型捕手として期待される。1980年、博から博史に改名。一軍出場することなく、1981年に現役引退。
1982年にスカウトになり、1986年からはスコアラーを務める。その後フロント入りした。1998年に運営部長に就任し、選手の査定などを担当。2003年に失敗続きのFA、外国人選手獲得、トレード補強戦略の責任をとらされ、運営部長から運営部長へ更迭。(???更迭されていないでないか?意味不明である。)2009年から取締役・業務部門統括に就任。(これほど見事に失敗続きの人物なのにどういう訳か取締役にまで出世している。)
選手としては全く活躍できず(一度も1軍に上がることなく、よく10年間もプロで飯を食えた事はある意味ですごいと思うが)、スカウト・フロントでも失敗続きであるこのような人物が長年球団に留まり続け、どういう訳か、取締役にまで出世するのである。選手としてもスカウト・フロントとしても全く能力は無いが、上に取り入る能力、処世術によほど長けているのだろう。大卒では無いが、大宮高校という埼玉県屈指の進学校出身なので、そこそこ地頭はいいのだろう。しかし、その頭を自らの保身の為にしか使わない。この人物が横浜の癌である事は明らかで、球団に留まっている限り、現在のチーム体質は絶対に変らない。この癌を排除できるのは球団社長、オーナーしかいないのであろうが、そこは上に取り入ることで、今まで生き残ってきた人物である。あの手この手で、既に、自らの保身を画策済みであろう。上層部自らが球団に巣食う癌を排除できないのならば、唯一、可能性があるのはファンの力である。ファンの力で球団に巣食う癌を排除しなければならない。今までの成績不振の責任を監督、選手の責任とし、ファンの批判の目を監督、選手に向かせて、その影で、ひたすらに自らの保身を保ってきた笹川。ファンの力で笹川批判を発生・拡大させ、一刻も早く退任させない限り、球団の将来は無いと断言できる。この笹川という人物、選手として、スカウトとして、フロントとして、3度もファンを裏切っているにも関わらず、未だに球団に留まり続け、高給を受け取り続けている。まともな神経の持ち主ならば、とっくに自ら身を引いているはずである。こういう人間の事を会社員なら社賊という。笹川は球団職員なので球賊である。
球賊笹川の事を考えるだけでも、ムカムカしてストレスになる。ドーム内を散歩して気を紛らわしたい。


試合開始の時刻が近づいてきた。ラジオの実況席には小さな巨人、若松氏が座っている。近くで見る若松氏は本当に小柄でどこにでもいるおとなしそうなおじさんといった雰囲気である。とても偉大なプロ野球選手だったとは思えない。

試合開始前、アナウンサーが実況を開始する。「ニッポン放送ショウアップナイター、本日の解説は若松勉さんでお送りします。若松さんよろしくお願いします。」横で生実況を聞く事ができるなんて思いもよらなかった。そういえば、小中学生、高校生の頃はよくラジオで野球中継を聞いたが、それからラジオで野球中継を聞く事は無くなってしまった。自分でテレビを持つようになったからだ。

中継も始まり、スターティングメンバーの発表の時間も迫ってきたので、急いで席に戻る。
いよいよスターティングメンバーの発表。巨人の先発はセリーグの最多勝、防御率争いでトップに立つエース東野、日ハムの先発は当然、全日本のエース、ダルビッシュかと思いきや、意表を突いて糸数である。ダルビッシュは右肩痛で登板回避らしい・・・。ダルビッシュはまだ若いのに、年々、ガラスのエース化している。先発糸数とアナウンスされた瞬間、金返せと言いたくもなったが、このようなサイドスローの軟投派タイプに巨人の強力打線は案外弱いかもしれないと思った。ごく普通の公立高校の軟投派投手が強豪私学の強力打線をのらりくらりとかわしていくみたいに。しかし、高校野球の場合は押さえられてもせいぜい1順目までである。2順目からは打線に慣れられて、連打を浴びて、一気にコールド負けとなるパターンが多いがプロ野球ではどうだろう。今の東野ならば、さほど打たれる事無く、長いイニングを投げるであろうから、日ハムの継投策がピタリとハマり、巨人打線を押さえる事ができれば、案外、ロースコアの接戦になるかもしれない。
試合開始。

初回、日ハムは東野の立ち上がりをとらえ、2安打するも、走塁ミスもあり、無得点。もったいない攻撃内容であった。今年の日ハムはまだ乗り切れていない。そつなく野球をこなすチームのはずだが、チグハグである。
糸数の立ち上がりは、無難に1番坂本を打取る。しかし、警戒のあまり、2番高橋に四球を出してしまう。2番に高橋とは反則ではないか?強大戦力の巨人ならではの選手の使い方である。しかし、その後、小笠原を併殺に打ち取り、チェンジ。

立ち上がりを見た限り、東野にいつもの凄み、安定感がない。不安定な印象を受ける。糸数はサイドからの直球は138km前後だが、のらりくらりとかわしていくような気がする。
最初の予想通り、ロースコアの接戦になる可能性が高いかもしれない。今日は、意外な選手の一振りが試合を決めるかもしれない。