東京公演巡り
聖跡蒲田梅屋敷公園
(せいせきかまたうめやしきこうえん)

東京都大田区蒲田にある区立公園です。
江戸時代には梅の名所「梅屋敷」として人で賑わっていました。
その後、所有者が代わり面積も小さくなりましたが、昭和二十八年より区立公園となりました。
約100本の梅の木が植えられています。
入り口


梅屋敷の由来

梅屋敷の由来梅屋敷は、山本忠左衛門が和中散(道中の常備薬)売薬所を開いた敷地三千坪に、その子久三郎が文政の頃(1818~1829)に、梅の木百本をはじめとしてカキツバタなどの花々を植え、東海道の休み茶屋を開いたらことに始まるといわれています。当時は後の十二代将軍徳川家慶が鷹狩りの休み所とした程の屋敷で、その雅趣ある風情は多くの文人、行楽客、東海道の旅人を集め、特に梅の開花期には非常な賑わいを見せたようでした。大田区
明治天皇と梅屋敷

明治天皇と梅屋敷梅屋敷は、明治元年(1868)から明治三十年(1897)の間に天皇の九度の行幸がありました。天皇はことのほか梅屋敷の風致を好まれ、明治六年(1873)三月六日のご観梅のときには小梅一株をみずからお手植なされ、この梅は仙粧梅と称されて後に人々に愛されたといわれています。その後昭和八年(1933)に史蹟として保存指定を受け、昭和十三年(1938)に東京市へ寄付、さらに昭和二十八年(1953)に大田区に譲与され、現在に至っています。大田区
梅屋敷と和中散売薬所跡
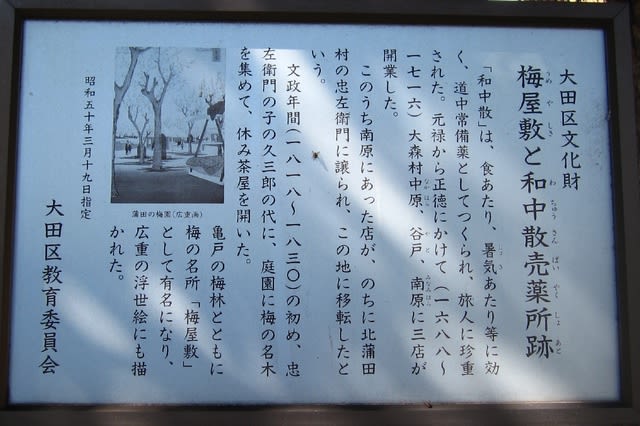
大田区文化財梅屋敷と和中散売薬所跡「和中散」は、食あたり、暑気あたり等に効く、道中常備薬としてつくられ、旅人に珍重された。元禄から正徳にかけて(一六八八~一七一六)大森村中原、谷戸、南原に三店が開業した。このうち南原にあった店が、のちに北蒲田村の忠左衛門に譲られ、この地に移転したという。文政年間(一八一八~一八三〇)の初め、忠左衛門の子の久三郎の代に、庭園にある梅の名木を集めて、休み茶屋を開いた。亀戸の梅林とともに梅の名所「梅屋敷」として有名になり、広重の浮世絵にも描かれた。昭和五十年三月十九日指定大田区教育委員会
所在地
東京都大田区蒲田三丁目25番6号
最後に
明治天皇が9度も訪れた梅屋敷。



わたしが訪れたのは、初秋だったので、天皇が好まれた梅を愛でることができませんでしたが、他の花々が癒しを与えてくれたことを、今でも覚えています。
優しい時が流れているような、そんな心地よい公園でした。
明治天皇が何度も訪れたことが何となくわかるような気がします。
いい公園でした。












