-登山家・跡部昌三の言葉-
「悪天候は人を死地に追い込むためにあるのではないということである。
厳冬1月も寒冷さ、風雪の狂う高所では、人の生存を拒否しているようであ
るがそこへ登ろうとするものは、それがどのようなものかは、すでに分かっ
ているはずである。また、それに立ち向かう自由と、さける自由は登山者自
身に許されている」
「その五体を安全に守ってくれるのが、山の常識であり、山の技術である。
知識だけではなく、ことにのぞんで反射的に行使されるまでに身についてい
なくてはならない。それは何も高度な技術を要求していない。要するに山で
の危険というものは、山にあるのではなくて登山者自身にのうちにある、と
いうことを、はっきり知っておくことである。」
東海銀行山岳部「さすらい」2号(昭和38年)の寄稿から
(西山秀夫氏の「小屋番の山日記」から)
西山秀夫氏
東海白樺山岳会会員、鈴鹿、奥美濃、奥三河、南木曽など中京圏の山と谷の案内記事を「岳人」にときどき執筆されています。
日本山岳会東海支部の50周年誌編集にも関わられたようで、1970年の東海支部のマカルー東稜遠征のこと、原真氏のことなど、東海支部全盛の頃の興味深い事柄、また山岳遭難についての考察が落ち着いた文体でそのブログで語られている。
跡部昌三
私などは京都・ナカニシヤ書店刊行「わっさかわっさか沢歩き記録集」の同人わっさかわっさかの代表者というイメージがあります。
その本には、大阪市大山岳部OB青島靖氏と登られたの白山の沢の記録もあり、最近まで現役として山に行かれている方と想像していた。
しかし、グーグルで検索すると、昭和40年から東京中日新聞社刊行の「岳人講座」シリーズの諏訪多栄蔵・高須茂と共同の監修者となっている。
そういえば、「岳人」の古本=昭和30年代後半=で、名古屋の登山用品店「跡部昌三の店」なんていう広告が載っているのを見たことがある。
(ちなみにその号の「岳人」には、深田久弥の”ヒマラヤの高峰”の連載、記録速報では奥美濃川浦谷遡行・沖允人=川浦谷銚子洞の遡行が記録として扱われる!=、といった古き良き時代を感じさせるものがあります。)
閑話休題
跡部昌三氏、かつて岳界をリードした大御所、このオールド登山家の、「山での危険というものは、山にあるのではなくて登山者自身にのうちにある、ということを、はっきり知っておくことである。」 という言葉、肝に銘じたいものである。
「悪天候は人を死地に追い込むためにあるのではないということである。
厳冬1月も寒冷さ、風雪の狂う高所では、人の生存を拒否しているようであ
るがそこへ登ろうとするものは、それがどのようなものかは、すでに分かっ
ているはずである。また、それに立ち向かう自由と、さける自由は登山者自
身に許されている」
「その五体を安全に守ってくれるのが、山の常識であり、山の技術である。
知識だけではなく、ことにのぞんで反射的に行使されるまでに身についてい
なくてはならない。それは何も高度な技術を要求していない。要するに山で
の危険というものは、山にあるのではなくて登山者自身にのうちにある、と
いうことを、はっきり知っておくことである。」
東海銀行山岳部「さすらい」2号(昭和38年)の寄稿から
(西山秀夫氏の「小屋番の山日記」から)
西山秀夫氏
東海白樺山岳会会員、鈴鹿、奥美濃、奥三河、南木曽など中京圏の山と谷の案内記事を「岳人」にときどき執筆されています。
日本山岳会東海支部の50周年誌編集にも関わられたようで、1970年の東海支部のマカルー東稜遠征のこと、原真氏のことなど、東海支部全盛の頃の興味深い事柄、また山岳遭難についての考察が落ち着いた文体でそのブログで語られている。
跡部昌三
私などは京都・ナカニシヤ書店刊行「わっさかわっさか沢歩き記録集」の同人わっさかわっさかの代表者というイメージがあります。
その本には、大阪市大山岳部OB青島靖氏と登られたの白山の沢の記録もあり、最近まで現役として山に行かれている方と想像していた。
しかし、グーグルで検索すると、昭和40年から東京中日新聞社刊行の「岳人講座」シリーズの諏訪多栄蔵・高須茂と共同の監修者となっている。
そういえば、「岳人」の古本=昭和30年代後半=で、名古屋の登山用品店「跡部昌三の店」なんていう広告が載っているのを見たことがある。
(ちなみにその号の「岳人」には、深田久弥の”ヒマラヤの高峰”の連載、記録速報では奥美濃川浦谷遡行・沖允人=川浦谷銚子洞の遡行が記録として扱われる!=、といった古き良き時代を感じさせるものがあります。)
閑話休題
跡部昌三氏、かつて岳界をリードした大御所、このオールド登山家の、「山での危険というものは、山にあるのではなくて登山者自身にのうちにある、ということを、はっきり知っておくことである。」 という言葉、肝に銘じたいものである。











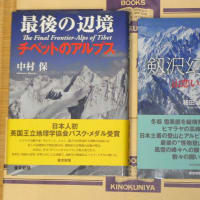








ものされることを期待してま~す。