先日、大学の図書館で宮崎勤の逮捕当時の新聞記事を調べたので引用してみる。
なお、記事のコピーは手続きが面倒だったので取っていません。自分でノートに書き写したものをここに書いているので、誤りがあった場合はごめんなさい。
また、Wikiにもあるとおり、本来の表記は「宮勤」であることに注意のこと。
8月11日付 朝日新聞
・見出し「孤独に潜む異常さ」「友はアニメ・ビデオ 宮崎、付き合い避け無口」
・宮崎の自室の写真を掲載
・明らかに、「アニメ等の愛好者」「人付き合いが少ない」の二点を犯罪の異常性と結び付けている。
・対照的に家庭環境に関する記述は少ない(当時は情報があまり出ていなかったせいもあるが)。後に「解離性家族」などと評される宮崎の家庭環境は、趣味以上に彼の人格形成に大きく関わった可能性があるし、彼について扱った書籍の多くでもその可能性のほうが濃厚とされている。
・アニメ好きと人付き合いを好まないことに接点を見出すのは、後に明らかになる、宮崎がビデオの貸し借りを行うサークルに入会していた事実と矛盾する。
単に宮崎がコミュニケーションに難が有っただけで、ビデオサークルに参加する大抵の人は、他者との円滑なコミュニケーションが可能でなければ活動が成り立たないはずである。
同日の社説
・歪んだ性的意識に基づく事件は他国のほうが余程多い。最たる例としては南アフリカの「処女とセックスすればエイズが治る」という迷信に基づく性犯罪の多発だが、先進国でも↓のような事は起こっている。
父が娘を地下室に24年間監禁、7人の子供を産ませる…オーストリア (痛いニュースさま)
8月12日付 朝日新聞夕刊
・慶応大学法学部 宮沢浩一教授(当時)
・精神医学者、慶応大学助教授 小此木啓吾
「現代人はテレビやビデオを一緒に暮らす相手とするが、それらは人格のない機械である。ゆえに現代人は他者が不在の場合でも「相手がいる」という幻想を抱くようになる。宮崎の犯行も、そういった幻想の中で行われたことではないか。
現代の子どもは友人よりもテレビゲーム、コンピューターとの付き合いが多くなっている。人間との対話を教えるべきである。」といった内容。
バーチャル世界がどうたら~という戯言は、やはり宮崎事件の時点で既に存在していた。
・犯罪社会学者 元東洋大学教授 岩井弘融
「宮崎の犯行は彼の趣味であったビデオの影響を受けている」とし、
また、警察も彼の所有するビデオに注目していたらしく、16日~20日頃の記事では、警察が彼の自宅から6500本のビデオを押収し、40人あまりを動員して一本ずつ検証していた事が報じられている。
この捜査の結果、そのビデオのなかから宮崎が自分の犯行を収録したものが発見され、決定的な証拠となるのだが、捜査自体の動機はやはりビデオが宮崎に与えた影響というような面から行われたものらしい。12日の記事から抜粋すると
そして宮崎が自分の犯行を記録していたという報道を受けて、22日には以下のような記事が載っている。
・平井富雄・東京家政大学教授(精神医学)
宮崎は犯行の記録を保存したいという欲求を持っており、
そして報道、警察の方針の影響を受けたのか、各自治体でホラービデオの規制が議論されるようになる。私の確認した限りでは、20日の記事で山梨県がホラービデオを有害図書に指定する方針を示したこと、23日の記事では千葉県福祉審議会がギニーピッグシリーズから「血肉の華」「悪魔の実験」の2本を有害図書指定するよう答申があり、東京都でもビデオの販売、貸し出しを行う都内の業界四団体に対して「扱いに慎重を期すよう」要請したと報じられている。
また同時期に、NHKと日本テレビでは映画番組の枠でホラー映画特集を行う予定だったようだが、事件の影響で中止している。NHKについては、視聴者広報室の「社会的影響を考えて変更」「中止した番組は、時期を見て放送したい」とのコメントがある(16日の記事より)。
この時期は、アニメよりもむしろホラービデオに注目が集まったらしく、その点は現在一般的に言われるところの「オタク」報道と若干異なっている。しかし、この流れからは、いつぞやの暴力ゲーム規制に非常に良く似た構図を見て取れる。
しかし、これらの報道や行政のあり方には当時から疑問を持っていた人が少なくなかったらしい。
16日の「声」欄にはアニメファンを自称する28歳の男性からの投書で、報道のあり方に対して苦言が呈されている。一部抜粋する。
8月末には、少なくとも朝日新聞では所謂「犯人探し」は一応の終息となったらしく、事件後数日にあったような過剰な報道は鳴りを潜めている。
24日には、フリージャーナリスト宮淑子氏と、のちにこの事件に深く関わる事になる大塚英志氏のインタビューが掲載されている。
以下抜粋する。
(宮)
少なくとも現在のマスコミの状況の一端は、講談社「メカビ Vol.01」に収録された、「オタクとマスコミ―取材の最前線から」と題した、小原篤氏(朝日新聞)、渡辺圭(毎日新聞)、福田淳(読売新聞)の対談のなかからある程度うかがい知る事が出来る。
なお、記事のコピーは手続きが面倒だったので取っていません。自分でノートに書き写したものをここに書いているので、誤りがあった場合はごめんなさい。
また、Wikiにもあるとおり、本来の表記は「宮勤」であることに注意のこと。
8月11日付 朝日新聞
・見出し「孤独に潜む異常さ」「友はアニメ・ビデオ 宮崎、付き合い避け無口」
・宮崎の自室の写真を掲載
宮崎は両親と妹二人の五人暮らし。妹らと自宅母屋の離れに住んでいた。六畳一間が宮崎の城。壁の三方はテレビから録画したらしいアニメ、SFなどのビデオテープでぎっしり埋めつくされている。床にはマンガ本にまじって、幼児の性的嗜虐(しぎゃく)をテーマにする雑誌もあった。
自宅近くの「あきかわ書房」では十日、「常連」が来ないことが話題になっていた。宮崎は毎月十日、決まってこの書店を一人で訪れ、この日が発売の月刊アニメ雑誌「アニメージュ」「アニメディア」の二誌を買っていた。どちらもテレビアニメのファンを対象とした専門誌で、読者は中学、高校生が中心。
ときにはビニール袋入りのポルノ雑誌を買うこともあったという。
(中略 ※職場の同僚や学生時代の同級生のインタビュー。宮崎が人付き合いが少なく、周囲からの印象の薄い人物という旨の記述。)
中学校の記録には、担任の教諭に「マンガ新聞を作りたい」と話していたことも残されている。周囲の人との接点を失う一方で、アニメの世界に迷い込み、現実と幻想の見境もつかないまま幼児殺しの犯行に走ったのだろうか。
・明らかに、「アニメ等の愛好者」「人付き合いが少ない」の二点を犯罪の異常性と結び付けている。
・対照的に家庭環境に関する記述は少ない(当時は情報があまり出ていなかったせいもあるが)。後に「解離性家族」などと評される宮崎の家庭環境は、趣味以上に彼の人格形成に大きく関わった可能性があるし、彼について扱った書籍の多くでもその可能性のほうが濃厚とされている。
・アニメ好きと人付き合いを好まないことに接点を見出すのは、後に明らかになる、宮崎がビデオの貸し借りを行うサークルに入会していた事実と矛盾する。
単に宮崎がコミュニケーションに難が有っただけで、ビデオサークルに参加する大抵の人は、他者との円滑なコミュニケーションが可能でなければ活動が成り立たないはずである。
同日の社説
世界でもまれなほど、だれでもが、ビデオやコミック雑誌などで手軽に性的な刺激に接触できる日本社会の最近のありようが、性のゆがんだイメージだけを増幅させ、こうした事件の下敷きになってはいまいか。
この若者がアニメ好きだったこと、テレビに映し出された自室にビデオテープがぎっしり並んでいたことが、気になる。事件の異常さは、社会のどこかに病んだ部分があることを物語っている。
・歪んだ性的意識に基づく事件は他国のほうが余程多い。最たる例としては南アフリカの「処女とセックスすればエイズが治る」という迷信に基づく性犯罪の多発だが、先進国でも↓のような事は起こっている。
父が娘を地下室に24年間監禁、7人の子供を産ませる…オーストリア (痛いニュースさま)
8月12日付 朝日新聞夕刊
・慶応大学法学部 宮沢浩一教授(当時)
二十六歳の男性が、アニメなどの世界に浸りきっている異常さ。それを見逃している家族の精神的きずなの崩壊。ほかにもビデオの影響についてのコラム。以下に概要を示す。(私のバイアスがかかった要約となっている可能性がありますので、詳しくは各自ご確認ください。)
(中略)
欧米では、成人間の性的行為の描写には自由を保証するが、異常性愛的なものは、少なくともおおっぴらには売れない。日本では性器や性毛などにこだわりノーマルなセックスの表現を規制する半面、SMものや残虐なものは野放し、というアンバランスが目立つ。アニメであれ、子どもを切り刻むような映像が流布している社会は、まともではない。とうとうここまで行き着いたかという感じでもある。
・精神医学者、慶応大学助教授 小此木啓吾
「現代人はテレビやビデオを一緒に暮らす相手とするが、それらは人格のない機械である。ゆえに現代人は他者が不在の場合でも「相手がいる」という幻想を抱くようになる。宮崎の犯行も、そういった幻想の中で行われたことではないか。
現代の子どもは友人よりもテレビゲーム、コンピューターとの付き合いが多くなっている。人間との対話を教えるべきである。」といった内容。
バーチャル世界がどうたら~という戯言は、やはり宮崎事件の時点で既に存在していた。
・犯罪社会学者 元東洋大学教授 岩井弘融
「宮崎の犯行は彼の趣味であったビデオの影響を受けている」とし、
死体の切断、『今田勇子』の手紙などには、自らの犯行をビデオストーリー化した後が如実にうかがえる。と述べている。
また、警察も彼の所有するビデオに注目していたらしく、16日~20日頃の記事では、警察が彼の自宅から6500本のビデオを押収し、40人あまりを動員して一本ずつ検証していた事が報じられている。
この捜査の結果、そのビデオのなかから宮崎が自分の犯行を収録したものが発見され、決定的な証拠となるのだが、捜査自体の動機はやはりビデオが宮崎に与えた影響というような面から行われたものらしい。12日の記事から抜粋すると
見出し「宮崎、詳しい供述次々 残酷ビデオからも影響?」とある。また16日の記事で、押収されたビデオや雑誌などが
捜査本部は、(注・ビデオテープが)宮崎の倒錯した性格を知る手がかりになるとみて調べている
マジックで「アニメビデオ」「少女雑誌」「少女写真」などと大書きされた段ボール箱に次々と詰められていった。とあることから、物品のジャンルごとの影響の違いについて検討する意図があったらしい。
そして宮崎が自分の犯行を記録していたという報道を受けて、22日には以下のような記事が載っている。
・平井富雄・東京家政大学教授(精神医学)
宮崎は犯行の記録を保存したいという欲求を持っており、
(注・ホラービデオを)再現して楽しもうというのと、自分だけのリアルなホラービデオを作りたいという、二つの欲望からだと思う。結局、彼を犯行に走らせた決定的な動機は、ホラービデオだったということではないか。
そして報道、警察の方針の影響を受けたのか、各自治体でホラービデオの規制が議論されるようになる。私の確認した限りでは、20日の記事で山梨県がホラービデオを有害図書に指定する方針を示したこと、23日の記事では千葉県福祉審議会がギニーピッグシリーズから「血肉の華」「悪魔の実験」の2本を有害図書指定するよう答申があり、東京都でもビデオの販売、貸し出しを行う都内の業界四団体に対して「扱いに慎重を期すよう」要請したと報じられている。
また同時期に、NHKと日本テレビでは映画番組の枠でホラー映画特集を行う予定だったようだが、事件の影響で中止している。NHKについては、視聴者広報室の「社会的影響を考えて変更」「中止した番組は、時期を見て放送したい」とのコメントがある(16日の記事より)。
この時期は、アニメよりもむしろホラービデオに注目が集まったらしく、その点は現在一般的に言われるところの「オタク」報道と若干異なっている。しかし、この流れからは、いつぞやの暴力ゲーム規制に非常に良く似た構図を見て取れる。
しかし、これらの報道や行政のあり方には当時から疑問を持っていた人が少なくなかったらしい。
16日の「声」欄にはアニメファンを自称する28歳の男性からの投書で、報道のあり方に対して苦言が呈されている。一部抜粋する。
私としては、ただでさえ対人関係が苦手で、内気な人が多い「アニメファン」が、これを機会に世間から色眼鏡で見られ、いじめの対象になることを懸念している。また24日の同欄では26歳の男性から
被疑者がビデオファンだったからビデオが規制されるというなら、彼の趣味がすべて行政的規制の対象にされかねないことになるが、そんな話がおかしいことはあえて言うまでもない。ビデオが今回の事件に影響を与えたという考えは、あくまでも一つの意見であり、推測に過ぎないことを認識すべきである。この他にも、24日の同欄には報道に批判的な投書がいくつかある。
8月末には、少なくとも朝日新聞では所謂「犯人探し」は一応の終息となったらしく、事件後数日にあったような過剰な報道は鳴りを潜めている。
24日には、フリージャーナリスト宮淑子氏と、のちにこの事件に深く関わる事になる大塚英志氏のインタビューが掲載されている。
以下抜粋する。
(宮)
(注・事件後、宮崎の自宅周辺に野次馬が多数現れたことについて)犯罪者やその家を見に行こうという心理は、昔、罪を犯した人に石を投げたのと同じ気持ちだと思う。同じ社会の中で生きる大人としての痛みを感じていないのではないでしょうか。(大塚)
(中略)
宮崎一人を異常者として断罪すれば、社会は安心できるかもしれないが、こうした(注・男性が女性に対し、暴力で性的に力を誇示する)文化そのものを変えていかなくては
宮崎に対する反応は、まるで魔女狩り同じ新聞で数週間前に書かれていたことを踏まえるとマッチポンプであると批判できなくもないが、記者によってスタンスに違いがあることによってこういった記事が掲載されているとも考えられる。
(中略)
本当は社会そのものに『宮崎的なもの』があるのに、それを認めたくないから、必死になって彼を異端者にしようとしているんじゃないかな
(中略)
今の社会には、常にだれかを排除し続けなければならない仕組みがあるように思うんです。宮崎がビデオやアニメのマニアだったことから、こうしたメディアと犯罪を安易に結びつけて、マニアの子たちを異常視する風潮が生まれるでしょうね
少なくとも現在のマスコミの状況の一端は、講談社「メカビ Vol.01」に収録された、「オタクとマスコミ―取材の最前線から」と題した、小原篤氏(朝日新聞)、渡辺圭(毎日新聞)、福田淳(読売新聞)の対談のなかからある程度うかがい知る事が出来る。
編集部 でも、このような試み(注・「メカビ」創刊)ができたのは、皆さんが先達として道を開いてくれたからだと思うんですよ。僕はゲーム少年だったんですけど、ゲームやってると、宮崎勤とすぐに関連付けられるような時期があってきつかったんです。新聞の社会面を見ると「ゲームを規制せよ」みたいなことが書いてあって。
渡辺 それはありますよね。ウチなんか頭の固い社会部ですから、二言目にはゲームなんかすぐ規制しろですからね。
福田 それはもう、ウチだってねぇ。社会面では「ゲームはいかがなものかと思う」って書かれてる(笑)。実は同期の記者が書いてるんですけど。
渡辺 わかんないから、とりあえず規制しとけば間違いないって、手っ取り早く考えちゃう。
編集部 そういう中で皆さんが、果敢にマスコミの内部で、オタクをポジティブに書いてくれたので、ずいぶん勇気づけられました。やっぱり、新聞に書いてあることなら、みんな正直に信じてくれるので。
一同 それはない(笑)。
(中略)
編集部 僕が学生のころなんか、大手メディアガオタクを叩いていた。「生きにくい世の中だなー」とか思うことも多かったんですけれど。
小原 今でもオタクを叩く記事だって、なくはないだろうね。
渡辺 絶対ありますよ。
福田 まあ部によって違うでしょうけれど。社会部なんかには、そういう記事を書く人がいるかもしれませんね。でもこれは、社の方針というよりは、記者個人のスタイルですよ。
渡辺 新聞社っていうのは、どっちかっていうと個人営業ですからね。やりたいことをやってもいいし、やらないんだたら別にやる仕事はある。ただルーチンに穴を開けるなっていう、それだけです。
(中略)
編集部 僕としては「オタクは新聞のような大マスコミに批判されてきた」っていう意識があるんですが、今回『メカビ』にこういう記事が載ってると、批判する新聞記者もそんなに悪い人たちではないのかな、って(笑)。
渡辺 まあ、場合によりますよね。たとえば社会面に、「誘拐犯がゲーム好きだ」「誘拐犯の家に行ったらゲームが出てきた」って書かれると、もうアウトですから。もう終わったー、と思いますよね。
福田 そうだったら、報道しなきゃいけないわけですからね。事実があれば。でも、べつにねぇ、オタクだって、犯罪者もいればそうでない人もいるし。普通の人にだって同様にいるわけだし。だから、オタクが犯罪起こしたからって、オタクがみんな犯罪者ってのは飛躍しすぎてるということですよね。
渡辺 ただ、バイアスはかけやすいんですよね。一個理由ができちゃったら、そこでいけるよねってなっちゃうんで。
小原 たとえば10代くらいの少年で、学校をドロップアウトしたとなったら、ごく普通の生活の流れとして、ゲームに耽溺する確率が高いわけですよ。学校行くのが嫌になって自分の部屋にこもる時間が長くなると、ゲームをたくさんやる。これは当然ありえますよね。そして少し自暴自棄になって、何か犯罪を犯した。それもありうるパターンです。すると、当然のようにその記事にはゲームってのが入る。そして「一日何時間もゲームに熱中していた」という紙面になる。嘘じゃない。嘘じゃないけど、それがどこまで犯罪と関係があるんだろうか。言ってみればありがちな流れの一〇代の犯罪でも、そこでゲームって書いちゃう。正直、それはどうかなってところがありますね。
渡辺 そうですね。ただ、そうやって書いちゃう瞬間に、もう世間一般では「ああそうだ、またゲームだ」ってなっちゃうんだよね。・・・・・・そうじゃないんだけどなーって(笑)。












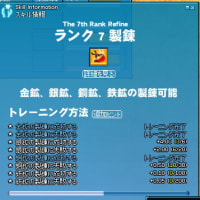






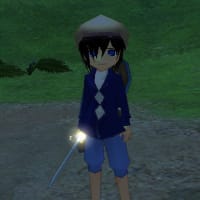
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます