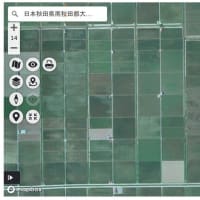今週末まで東京モーターショーが開催されている。
ニュースではEVを中心に報道がされているが、一部のメディアでは『入場料が高いだけで、夢を買う車もなく、EVはハリボテだらけ』と酷評をしている所もある。
このブログでも時々気になる事としてEVについても触れているが、化石燃料を使用するエンジン車からの移行については、国力として数十年先の時流を整理し、自動車産業をリードしていかないと、日本は世界から技術的に沈没する可能性も出てくるかもしれない。
この問題については、NHKの深読みでも『自動車大国ニッポンの未来は』というタイトルで議論がなされていたが、『真剣に考えていくべきだ』というコメンテーターの方と、『まだ少し様子見でもいいのでは』との意向の学者もおられた。
このEV車一つでも、10年、20年さらには50年先にどうあるべきか。ここでの新しく出てきそうな『わくわく感』を想像し、これに向けた新しい技術開発を常に創成していかないと、今朝の日経の『瀬戸際の技術立国 新たな創造の循環』という事は難しくなってくるのではないかとも思える。
前述の『真剣に考えていくべきだ』というコメンテーターの方は、今の中国でのEV車の開発の動きが、国民がさらに車を保有した場合の環境問題や燃料問題からEV車への移行は必然的であり、電気が足りなくなるのではとの問題については、中国では風力発電や太陽光発電など全体のソリューションの中でとらえており、これらの産業も副次的に成長し国力を支える事になるとの事であった。
この壮大な流れの中には電器産業を含めたハイテックな技術が織り込まれ、ここから出てくる色々な技術が副次的に産業を拡大させるとの思いが、今回の中国の巨頭体制、世界一構想の裏付けになっているのかもしれない。
逆に日本では電器産業が海外との競争に敗れ疲弊する中で電子産業の弱体化が起こり、かっては世界をリードしていたAI開発も世界から取り残され、さらには今後自動運転をつかさどるCPUや画像センサーなども中国技術が席巻してくるなど、何か新しい動きを考え出さない限り、間違いなく日本は技術で沈没することになる。
過去化学産業や車でも一大勢力であったフランスのように農業国として転身できればいいが、日本は島国で隣接国へ簡単に販売もできず、やはり技術立国で外貨を稼がない限り成り立たなくなるのは見えている。
ではなぜ日本は伸びないのか。色々と考えて見たくなることがある。
今日のテーマの自動車だけで見ると、EVになって困るのは誰かを考えると、今回の神戸製鋼やSUBARUでの問題でも報道があった通り、自動車産業はともかくとして、ここへの供給をしている既得権を持った鉄鋼メーカーや、系列と言われる部品メーカーではなかろうか。
EV車となると、ガソリンなどの燃えやすい燃料を搭載しないため、ボデーは鉄やアルミである必要がなく、何でもよく、逆にバッテリーの負荷を考えると軽量化のためには外回りは紙素材でも可能性はある。
衝突での安全性確保のためには剛性の高いハイテンのような高度な鉄素材も求められるが、『ぶつからない車』が主流となるとこの必然性は薄れてくる可能性もある。逆に鉄も軽くて丈夫にするための技術をこれから真剣に磨いておかないと、50年先には車からは素材として無くなるのかもしれない。
このブログのどこかでも書いた記憶があるが、『鉄腕アトム』や『ドラエモン』で夢見ていた事を『こんな風にならないか』と具現化し、ここから基幹技術を開発し、軽薄短小、高機能化とどんどん創造たくましく磨き上げて来たことで今の素晴らしい車が出来上がっているが、今回のモーターショーでは海外のEV車の急な動きから、付け焼刃的にコンセプトを提言しているだけの様にも思える。
この前、どこかの番組で『電気自動車は暖房が出来ない』『なぜならバッテリーだから』とのEVを否定的に考える意見も出されていたが、EV車として『走ることの楽しみ』は当然として、『EVスタンドが無くても緊急脱出可能』とか『寒くても走れます』など、新しい技術を創生しながらEVを開発する事も必要ではないかと思える。これがもしEVが主流になるのであれば究極の目標なのかもしれない。
かってVWにはガソリンメーターが無かったが、ガス欠の際には緊急用のレバーがアクセルペダルの横についており、こんな工夫が世界で愛される車だったのかとも思われる。
現実的には2035年でもガソリン車がまだ85%、残りがEVで5%程度、残りがPHEV、FCVになるのではとの報道もあり、PHEVがガソリンを駆動系に直接使用するのではななく、発電しながら走る日産のようなEVシステムになるのであれば伸長の可能性も変わるとの事も言われている。
又、現状電気自動車にはバッテリが必須であり、Ni∸水素型からLiBへ急速に移行しているが、耐久性や安全性の面では限界があり、トヨタなどは全個体電池の開発を急いでいるとの報道もあり2025年あたりが変換点になるとの記事も出ている。全個体電池になってのメリットがいまいち見えていない所であるが、蓄電容量が倍増するのであればEV車への展開は相当期待が持てる。
何れにしてもノーベル賞候補のLi-BもLiの確保や印刷での生産技術向上でのコストダウンと共にリサイクル対応なども今後必要な技術展開なのかもしれない。これも日本として新たな技術展開のリードできるところかもしれない。
エネルギー問題と共に環境問題で「Well to Wheel」(井戸から車輪まで)という概念でCO2削減を謳い『燃料電池車と電気自動車、どちらが「真のエコカー」なのか?』との議論がFCV側から出されているが、興味深い所である。
EVを否定的に話される学者さんたちが良く持ち出さされる数値に、EV車フル充電するのに一般家庭15-17戸分の電気が必要になるとか、2000万台のEV車が走り出すと100万Kwクラスの原発が1基必要になるのとの意見もあり、先に書いた再生エネルギの確保と両輪で進めないと不可能な数値なのかもしれない。
どこかのブログで見た数値がノートに残っているが、日産リーフの場合、搭載バッテリが30kWhであり、家庭で充電の場合100V15A仕様であれば、1500Whが限界であり20時間も充電時間が必要。200V15Aでもこの半分にしかならず、充電効率を考えると半日で80%程度しか充電できない可能性があるとの事。
これを考えると30分から1時間での急速充電しかないかとも思えるが、200V300Aクラスの工場へ配電するような幹線を引く必要があり、コンビニなどで簡単にともいえないのかもしれない。
(過去のブログでも記載したが、東京山の手線の内側に充電スタンドが出来ないのもうなずける。)
電気の問題はこの充電対応以外に、車の中の制御系の電圧を12Vから48Vへ移行される動きや、駆動系への昇圧技術、このための電装技術などまだまだ基盤技術として必要な事がたくさんあるが、ドイツのコンチネンタルやボッシュが先行しており、これにEV車となるとモーター技術が組み合わされるので、日本のHVやPHEVでの基礎技術がうまく転用できればいいのであるが、エンジンとモーター駆動の切替えだけを一所懸命取り組んできたトヨタやホンダなどは、早くマイルドハイブリッドへ移行する中での技術を磨く必要があるのかもしれない。
モーターは電気を大きく消費するので、少ない電流でいかに駆動するかを設計することが必要であり、今までの大型のモーターを制作して来たメーカーと共に、自動化機器を制御するために小型モーターを制作してきたところもあらたに参入の可能性も見えて来たのではないか。ガソリンで動く車でもワイパーから始まり、パワーウインドウ、パワーシートなどモーターを必要とするところはたくさんあり、この中でEV車の技術を虎視眈々と眺めて来たところは、一気に開花する可能性もある。
最近出ていた記事では冷房を作っているダイキンのモーター技術なども、どこかとタイアップするとの事であったが、今までの重電での交流モーターではなく、直流モーターで馬力を確保できることを考えることも重要なのかもしれない。このあたりも、日本が少し技術的に遠のいていた所が、逆に急に必要となる可能性も出て来たが、大手電機メーカーのモーター部門が立て直せるか心配な所である。
話があっちこっちに行ってしまったが、10年ほど前に『スマート電化』と言う言葉がはやり、太陽光やエコキュート発電での売電で,『スマートグリッド』と言う言葉も出ていたかと思うが、この中で『直流化』した家の提案もあったかと思う。昨今家電は交流を必ずしも必要とするものが少なくなり、パソコンでもわざわざ充電器で直流化し充電をしたり、テレビでもアダプタが必要になるなど、直流の回路があってもと思う所がある。
この『直流化』の話はたしか、太陽光パネルが直流であり、これを整流して売電するがロスがあるとの事でも議論がされていたかと思うが、家庭内蓄電やEV車への充電など『直流化』も一つ技術革新なのかもしれない。
ここまで思いつくことで色々と書いて来たが、『こんなものあったら楽しいね』『これ面白そう』と夢を追い続けることが技術革新であり、今日の日経の記事で刺激される企業が。さらには、ベンチャーマインドで先を思いつく若手がたくさん生まれてくることを祈りたいが、物があふれて、スマホで情報を得るだけでは・・創造性の醸成はどうなのか。
パナソニックが自動運転の検討を進めているニュースもあったが、『アイリスオーヤマEV車を検討開始』『ソニーがEV駆動新車発表』・・なんて言うわくわくする記事が出れば世界中驚くのかもしれないが。
<追記>
これもブログのどこかで書いていたことであるが、新たな技術革新で世界中の資源が取り合いになる可能生がある。
日経新聞に8月頃、なんでこんなところに『金』の記事が出ていたが、EV車、特に自動運転車が出てくると、電子部品がさらに高性能化、信頼性向上は必須であり、コネクタ類が『金メッキ』という事でのことなのか・・
何れにしても先を見ておく必要があり、『風と桶屋』の関係以上に複雑化も・・
(MEMO)
日経新聞に金(GOLD)に関する記事
(日経ヴェリタスセレクト 金投資 3つのトリビア 2016/7/24)
■金はなぜ希少なの?
人類が採掘した金の量 約18万3600トン( 2014年末時点)
(公式プール 4杯分にも満たない。)
⇒ 世界の金の埋蔵量 5万6000トン
ニュースではEVを中心に報道がされているが、一部のメディアでは『入場料が高いだけで、夢を買う車もなく、EVはハリボテだらけ』と酷評をしている所もある。
このブログでも時々気になる事としてEVについても触れているが、化石燃料を使用するエンジン車からの移行については、国力として数十年先の時流を整理し、自動車産業をリードしていかないと、日本は世界から技術的に沈没する可能性も出てくるかもしれない。
この問題については、NHKの深読みでも『自動車大国ニッポンの未来は』というタイトルで議論がなされていたが、『真剣に考えていくべきだ』というコメンテーターの方と、『まだ少し様子見でもいいのでは』との意向の学者もおられた。
このEV車一つでも、10年、20年さらには50年先にどうあるべきか。ここでの新しく出てきそうな『わくわく感』を想像し、これに向けた新しい技術開発を常に創成していかないと、今朝の日経の『瀬戸際の技術立国 新たな創造の循環』という事は難しくなってくるのではないかとも思える。
前述の『真剣に考えていくべきだ』というコメンテーターの方は、今の中国でのEV車の開発の動きが、国民がさらに車を保有した場合の環境問題や燃料問題からEV車への移行は必然的であり、電気が足りなくなるのではとの問題については、中国では風力発電や太陽光発電など全体のソリューションの中でとらえており、これらの産業も副次的に成長し国力を支える事になるとの事であった。
この壮大な流れの中には電器産業を含めたハイテックな技術が織り込まれ、ここから出てくる色々な技術が副次的に産業を拡大させるとの思いが、今回の中国の巨頭体制、世界一構想の裏付けになっているのかもしれない。
逆に日本では電器産業が海外との競争に敗れ疲弊する中で電子産業の弱体化が起こり、かっては世界をリードしていたAI開発も世界から取り残され、さらには今後自動運転をつかさどるCPUや画像センサーなども中国技術が席巻してくるなど、何か新しい動きを考え出さない限り、間違いなく日本は技術で沈没することになる。
過去化学産業や車でも一大勢力であったフランスのように農業国として転身できればいいが、日本は島国で隣接国へ簡単に販売もできず、やはり技術立国で外貨を稼がない限り成り立たなくなるのは見えている。
ではなぜ日本は伸びないのか。色々と考えて見たくなることがある。
今日のテーマの自動車だけで見ると、EVになって困るのは誰かを考えると、今回の神戸製鋼やSUBARUでの問題でも報道があった通り、自動車産業はともかくとして、ここへの供給をしている既得権を持った鉄鋼メーカーや、系列と言われる部品メーカーではなかろうか。
EV車となると、ガソリンなどの燃えやすい燃料を搭載しないため、ボデーは鉄やアルミである必要がなく、何でもよく、逆にバッテリーの負荷を考えると軽量化のためには外回りは紙素材でも可能性はある。
衝突での安全性確保のためには剛性の高いハイテンのような高度な鉄素材も求められるが、『ぶつからない車』が主流となるとこの必然性は薄れてくる可能性もある。逆に鉄も軽くて丈夫にするための技術をこれから真剣に磨いておかないと、50年先には車からは素材として無くなるのかもしれない。
このブログのどこかでも書いた記憶があるが、『鉄腕アトム』や『ドラエモン』で夢見ていた事を『こんな風にならないか』と具現化し、ここから基幹技術を開発し、軽薄短小、高機能化とどんどん創造たくましく磨き上げて来たことで今の素晴らしい車が出来上がっているが、今回のモーターショーでは海外のEV車の急な動きから、付け焼刃的にコンセプトを提言しているだけの様にも思える。
この前、どこかの番組で『電気自動車は暖房が出来ない』『なぜならバッテリーだから』とのEVを否定的に考える意見も出されていたが、EV車として『走ることの楽しみ』は当然として、『EVスタンドが無くても緊急脱出可能』とか『寒くても走れます』など、新しい技術を創生しながらEVを開発する事も必要ではないかと思える。これがもしEVが主流になるのであれば究極の目標なのかもしれない。
かってVWにはガソリンメーターが無かったが、ガス欠の際には緊急用のレバーがアクセルペダルの横についており、こんな工夫が世界で愛される車だったのかとも思われる。
現実的には2035年でもガソリン車がまだ85%、残りがEVで5%程度、残りがPHEV、FCVになるのではとの報道もあり、PHEVがガソリンを駆動系に直接使用するのではななく、発電しながら走る日産のようなEVシステムになるのであれば伸長の可能性も変わるとの事も言われている。
又、現状電気自動車にはバッテリが必須であり、Ni∸水素型からLiBへ急速に移行しているが、耐久性や安全性の面では限界があり、トヨタなどは全個体電池の開発を急いでいるとの報道もあり2025年あたりが変換点になるとの記事も出ている。全個体電池になってのメリットがいまいち見えていない所であるが、蓄電容量が倍増するのであればEV車への展開は相当期待が持てる。
何れにしてもノーベル賞候補のLi-BもLiの確保や印刷での生産技術向上でのコストダウンと共にリサイクル対応なども今後必要な技術展開なのかもしれない。これも日本として新たな技術展開のリードできるところかもしれない。
エネルギー問題と共に環境問題で「Well to Wheel」(井戸から車輪まで)という概念でCO2削減を謳い『燃料電池車と電気自動車、どちらが「真のエコカー」なのか?』との議論がFCV側から出されているが、興味深い所である。
EVを否定的に話される学者さんたちが良く持ち出さされる数値に、EV車フル充電するのに一般家庭15-17戸分の電気が必要になるとか、2000万台のEV車が走り出すと100万Kwクラスの原発が1基必要になるのとの意見もあり、先に書いた再生エネルギの確保と両輪で進めないと不可能な数値なのかもしれない。
どこかのブログで見た数値がノートに残っているが、日産リーフの場合、搭載バッテリが30kWhであり、家庭で充電の場合100V15A仕様であれば、1500Whが限界であり20時間も充電時間が必要。200V15Aでもこの半分にしかならず、充電効率を考えると半日で80%程度しか充電できない可能性があるとの事。
これを考えると30分から1時間での急速充電しかないかとも思えるが、200V300Aクラスの工場へ配電するような幹線を引く必要があり、コンビニなどで簡単にともいえないのかもしれない。
(過去のブログでも記載したが、東京山の手線の内側に充電スタンドが出来ないのもうなずける。)
電気の問題はこの充電対応以外に、車の中の制御系の電圧を12Vから48Vへ移行される動きや、駆動系への昇圧技術、このための電装技術などまだまだ基盤技術として必要な事がたくさんあるが、ドイツのコンチネンタルやボッシュが先行しており、これにEV車となるとモーター技術が組み合わされるので、日本のHVやPHEVでの基礎技術がうまく転用できればいいのであるが、エンジンとモーター駆動の切替えだけを一所懸命取り組んできたトヨタやホンダなどは、早くマイルドハイブリッドへ移行する中での技術を磨く必要があるのかもしれない。
モーターは電気を大きく消費するので、少ない電流でいかに駆動するかを設計することが必要であり、今までの大型のモーターを制作して来たメーカーと共に、自動化機器を制御するために小型モーターを制作してきたところもあらたに参入の可能性も見えて来たのではないか。ガソリンで動く車でもワイパーから始まり、パワーウインドウ、パワーシートなどモーターを必要とするところはたくさんあり、この中でEV車の技術を虎視眈々と眺めて来たところは、一気に開花する可能性もある。
最近出ていた記事では冷房を作っているダイキンのモーター技術なども、どこかとタイアップするとの事であったが、今までの重電での交流モーターではなく、直流モーターで馬力を確保できることを考えることも重要なのかもしれない。このあたりも、日本が少し技術的に遠のいていた所が、逆に急に必要となる可能性も出て来たが、大手電機メーカーのモーター部門が立て直せるか心配な所である。
話があっちこっちに行ってしまったが、10年ほど前に『スマート電化』と言う言葉がはやり、太陽光やエコキュート発電での売電で,『スマートグリッド』と言う言葉も出ていたかと思うが、この中で『直流化』した家の提案もあったかと思う。昨今家電は交流を必ずしも必要とするものが少なくなり、パソコンでもわざわざ充電器で直流化し充電をしたり、テレビでもアダプタが必要になるなど、直流の回路があってもと思う所がある。
この『直流化』の話はたしか、太陽光パネルが直流であり、これを整流して売電するがロスがあるとの事でも議論がされていたかと思うが、家庭内蓄電やEV車への充電など『直流化』も一つ技術革新なのかもしれない。
ここまで思いつくことで色々と書いて来たが、『こんなものあったら楽しいね』『これ面白そう』と夢を追い続けることが技術革新であり、今日の日経の記事で刺激される企業が。さらには、ベンチャーマインドで先を思いつく若手がたくさん生まれてくることを祈りたいが、物があふれて、スマホで情報を得るだけでは・・創造性の醸成はどうなのか。
パナソニックが自動運転の検討を進めているニュースもあったが、『アイリスオーヤマEV車を検討開始』『ソニーがEV駆動新車発表』・・なんて言うわくわくする記事が出れば世界中驚くのかもしれないが。
<追記>
これもブログのどこかで書いていたことであるが、新たな技術革新で世界中の資源が取り合いになる可能生がある。
日経新聞に8月頃、なんでこんなところに『金』の記事が出ていたが、EV車、特に自動運転車が出てくると、電子部品がさらに高性能化、信頼性向上は必須であり、コネクタ類が『金メッキ』という事でのことなのか・・
何れにしても先を見ておく必要があり、『風と桶屋』の関係以上に複雑化も・・
(MEMO)
日経新聞に金(GOLD)に関する記事
(日経ヴェリタスセレクト 金投資 3つのトリビア 2016/7/24)
■金はなぜ希少なの?
人類が採掘した金の量 約18万3600トン( 2014年末時点)
(公式プール 4杯分にも満たない。)
⇒ 世界の金の埋蔵量 5万6000トン