
練馬区立美術館はローカルな場所にあり、地味な存在だが、時々興味をそそる特別展を開催する。

8年前にはこんな記事をアップしている。この時は圧倒されたが・・・今回はひょんなことから情報が入ってきて、「遊べる浮世絵」展というのをやっていると。
おお、歴史マニアで落語をやる小生としては江戸時代のネタとして興味もあるし、見てみたいものである。
来てみてわかったのは、こちらの企画は「くもん」が協賛しているということ。浮世絵はもともとブロマイドだったり、旅行の写真集だったりファッション雑誌だったりする要素があった。このアングルからの視点でも十分楽しめた。
こちらではそれらに加えて、子供の遊びの要素、玩具だったり絵本だったりする要素もあったことを紹介していた。

たとえば、こちらは床に描かれた巨大な双六だ。もちろんこれは浮世絵ではなく、企画展用に作ったものだが、子供の遊び用に作られた双六コレクションもすごかった。
さらにオヤジ世代には懐かしい雑誌の付録のようなものもあった。切って組み立てると鎧になったり、童話の名シーンになったりするという・・・
平日の日中ということで、子供たちはいなかったが、子供たちには雑誌の付録のように組み立てができるコーナーもあった。
展示のボリュームとしてはまずまずといったところだったが、面白かったのは12カ月の月ごとの行事の浮世絵だった。


一月からの行事を並べるといえば・・・そう落語の「棒鱈」の田舎侍の唄の世界だった。また、今でも版木を使って当時の浮世絵の印刷も可能という。
改めて浮世絵のすばらしさを感じる機会となった。
さらに持論であるが、本当に江戸時代から我々は進歩しているのだろうか・・・精神世界では当時の日本人の豊かさは現代よりはるかに・・・ではなかったかと。
写真ではなく、あえて版画であっても、その中の子供や母親の目線ひとつに心根が映し出されているように感じたのだが・・・
























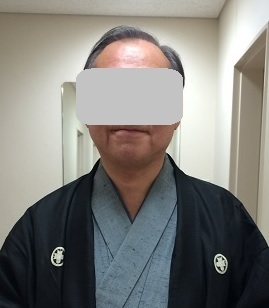

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます