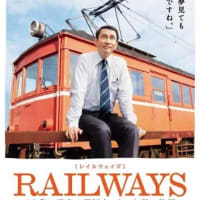自然を楽しみながら歩いて移動する自然散策はハイキングでドイツ語ではワンダーフォーゲルと呼ぶ。渡り鳥という意味である。鳥の世界にも多くの生活スタイルがあるが、人間の旅に置き換えると、温泉宿の湯治滞在が留鳥(りゅうちょう)、国内旅行が漂鳥(ひょうちょう)、外国旅行が渡り鳥(わたりどり)、酔っ払ってしまい留置場の世話になるのが迷鳥(めいちょう)という詭弁が浮かぶ。ピクニックは野外で食事することが主目的である。
渡り鳥のハシボソミズナギドリは、オーストラリア南部にちらばる小島で、春にヒナが誕生すると親鳥はヒナの餌のオキアミを確保する為に、南極海に獲りに行く。巣穴の中で餌を多量に与えられた親鳥より太った子鳥を残し、北半球への長い渡りに出発する。親鳥の無償の労働の餌で蓄えた脂肪で、成長した子鳥は巣立ち、親鳥の後を追う。餌の生育にあわせての南極から日本近海を通過し、北極海まで旅をする。繁殖を控えた親鳥は北アメリカ沿岸を南下した後、太平洋を横切って繁殖地へ戻る冬を知らない寒さが嫌いな渡り鳥である。
キョクアジサシは夏の北極圏で繁殖し、非繁殖期は夏の南極周辺海域ですごし、繁殖期にはふたたび北極圏へ渡る。白夜を求めて旅をする夜の嫌いな鳥で、渡りの距離は往復32000㎞になる。
二つの鳥は逆の動きをする。新幹線の上りと下りの関係であるし、飛行機が都市間を移動するのに似ている。人間は数日で往復するが、鳥は一年周期の旅である。人間は急ぎ過ぎる。鳥の一生に比べたら、人生80年で極めて長いのであるから、ゆっくり時を過ごさないと地球がビックリする。
渡り鳥の為の法律は、イランの都市ラムサールの会議で湿原の保存がなされ、生息環境を保護するため渡り鳥条約を、日本が他国と結んでいるが、渡り鳥は知らない。渡り鳥は鳥インフルエンウイルスを密輸するが、検疫することが出来ない。渡り鳥はパスポートが無いのである。そもそも渡り鳥には国境が無いのである。
鳥ではないが、北アメリカの蝶であるオオカバマダラは、南北3500kmほどに及ぶ分布域内で、1年のうちに北上と南下を行うことが知られている。ただし南下は1世代で行われるが、北上は3世代から4世代にかけて行われる。
春にはカリフォルニアやメキシコで見られ、世代交代を繰り返しながら徐々に北上し、夏になると北アメリカ中部まで達する。そして夏に、北アメリカ中部で羽化した個体が南下をはじめる。この世代は多くの花から蜜を吸い、体内に脂肪を大量に蓄える。この脂肪をエネルギーにして、一世代で生まれ故郷を目指すが、旅立ちを始めた蝶の世代交代した孫や孫の孫で、まごまごしないで、故郷を識別できることは驚異である。西洋科学ではDNAで、仏教は阿頼耶識であるとするが、人間の浅い知識で評論する事項でなく、何か偉大なものの、思し召しで自然の驚異を感じるのである。
織田信長の時代は『敦盛』の一節「人間五十年 下天のうちをくらぶれば 夢幻の如くなり ひとたび生を享け 滅せぬもののあるべきか」にあるが、現代は80歳が平均寿命である。理由は食生活の改善である。食うに困らないなら、戦国時代にはならず、元禄時代である。
蝶の北上する世代より南下する世代の寿命が長い理由も、食糧事情である。自然に逆らわないで、同じ種族の生存パターンを変えない蝶と、自然に盾突く人間と、どちらが賢いのか。生物には天寿を全うする食料が最大関心事であるはずで、特に人間は食品を大切にしないといけない。
最新の画像[もっと見る]