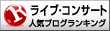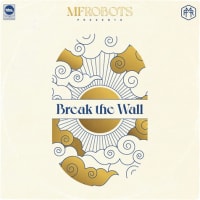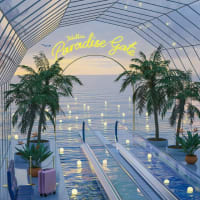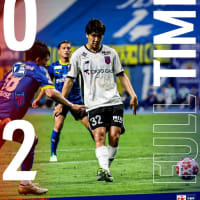“韓国のm-flo”とも呼ばれたクラジクワイ・プロジェクト(CLAZZIQUAI PROJECT)の3rdアルバム。ユニット名の由来の1つにもなったジャミロクワイ(Jamiroquai)にインスピレーションを受けたサウンドを下敷きとした、ジャズ、ボッサ、ラテンなどの要素を巧みに用いたラウンジ・ミュージックが本作でも遺憾なく発揮されている。
“韓国のm-flo”とも呼ばれたクラジクワイ・プロジェクト(CLAZZIQUAI PROJECT)の3rdアルバム。ユニット名の由来の1つにもなったジャミロクワイ(Jamiroquai)にインスピレーションを受けたサウンドを下敷きとした、ジャズ、ボッサ、ラテンなどの要素を巧みに用いたラウンジ・ミュージックが本作でも遺憾なく発揮されている。全16曲のうち、終盤2曲「Walk away」はボーナス・トラック、「Last tango」はM-6のオリジナル(韓国語ヴァージョン)、さらにM-4、M-11にインタールードが組み込まれているので、本編は実質12曲となるか。
オープナーとなる「Prayers」は、本来のクラジクワイ色で全面を飾りあげたハウス・チューン。マイナー調メロディ・ラインやヴォーカルにジャミロクワイ風のギター・カッティングが刻まれる、彼らの真骨頂となるサウンドを展開。ライヴでもクライマックスに演奏されそうだ。続く「Lover boy」も従来の爽快なサウンドを貫いたライト・ファンク調。ノイジーなイントロから清涼感のあるツイン・ヴォーカルが弾けるハッピー・テイストのナンバーだ。
また、「Fiesta」はサンバのリズムと融合したアシッド・ジャズ全開のダンス・チューン。タイトルよろしくホイッスルが導入されるなど情熱的ではあるが、一気に爆発させるというよりはほどよくスタイリッシュなスタンスを崩さずにいて、彼らのバランス感覚、たとえば、スパニッシュ風ギターの哀愁とパーカッションの叩き出す陽気さの二面性の見事な邂逅など、その絶妙な加減が垣間見られる。クールなハウス・チューン「Next love」も同様で、低温でヴァースを進んだかと思えば、コーラスでそれまで内包していた突き抜けたい心情や希望を高らかに歌い上げていく展開への均整が見事だ。
彼らの耳あたりの良いサウンドを活かしたミディアム・スローには、柔和で優しさを感じるナチュラル・テイストの「Gentle giant」が。童心に帰れるようなおとぎ話的な仕掛けも多く、終盤のオルゴール人形風のアクセントなどはなんともファンタジックで、思わず笑顔がほころぶようなハッピー・ソングだ。
アコースティック風アレンジを施した「Romeo n Juliet」も愛情溢れるジャジー・チューン。サンバを基調にしたバックと照りのあるホーンがまったりとした感覚を生んでいる。注目は、愛の語らいのように寄り添うツイン・ヴォーカルもそうだが、途中で入り込むラップで、これにより甘ったるさだけが残らないような配慮がうかがえる。
ナチュラルさがより発揮されるスロー系は、「Last tango」「Friday bules」「The light」の3曲。
「Last tango」は、ピアニカを用いたタンゴ調サウンドが切ない情感を醸し出すスロー・バラード。昼下がりの午後のカフェに似合いそうな別れを惜しむ男女のストーリーを、アレックスとホランが演出するムーディな作品。「Friday blues」はアレックスの甘く切ないヴォーカルが沁み込むスロー・バラード。合間に挟み込まれるブルージーなギターが効果的で、儚さを感じさせる。一方、女性ヴォーカルによるチル・アウト・チューン「The light」は、ささやかな幸せを感じさせる温もりのあるスロー・バラードだ。
今作はこれら以外に、彼らの新境地が窺える楽曲が加わった。
まず、イントロからU2やニュー・オーダー(NEW ORDER)あたりを感じさせるミッド「Our lives」は、彼らの新たな試みの一つといえる。比較的タイトなギター・サウンドに浮遊するように乗る男女ハイトーン・ヴォーカルが魅力。時折、ジョージ・マイケル(George Michael)風のサウンド(「Father Figure」あたり)も感じさせるなど、爽やかなUKロック調サウンドを披露している。「Flower children」は、ポエトリー・リーディング風のヴォーカルを添えた幻想的なイントロからスタートするクロスオーヴァー・トラック。ジャジーではあるが、コーラスではしっかり彼ららしい陽気さを見せるといったフットワークの軽さが感じられる。そして、フュージョン系ハウス・トラック「Glory」は、天空から清々しい風景を俯瞰するかのごとく浮遊感を持ったハイトーン・ヴォーカルが肝。まさに“後光(=Glory)”のように高みから注ぎ込まれるようだ。
また、ボーナス・トラックとして収録された「Walk away」は、DJクラジクワイがヴォーカルで参加したミディアム・スロー。マイナー調ロックを下敷きに、物悲しさをたたえた、大人の芳香と悲哀を感じさせている。
前作『カラー・ユア・ソウル』と比較すると、今作は、一気に聴けるという意味ではややその勢いが足りないのではないかと感じた。序盤などはこれぞクラジクワイという爽快で軽快なハウス・ミュージックを聴かせてくれるが、トータルな意味では、やや地味になったという印象を受ける。ラウンジ・ミュージックは耳や脳にグイグイと食い込んでくる濃厚さに重きを置いていないため、ややもするとBGMとしてのみのクオリティに特化してしまう傾向がある(逆を言えば、そこまで濃厚でうるさく感じさせないため、ラウンジ・ミュージックとして通用するということもあるのだが)。
ただ、それは、前作が若々しさが活きたヤングのアルバムだとすると、今作は苦味や渋味を知ったアダルトな要素がふんだんに散りばめられた大人のアルバムと解釈することができる。人生すべては勢いではまかり通らない。押す時引く時のさじ加減、これが大切なんだよ、とでもいいたげな余裕が窺えるのだ。それが、実験的というか新境地というか、ロック調やクロスオーヴァー、フュージョン・テイストの楽曲に表われているのだと思う。前作で勢いよく飛び出して、今作で視野を広げた……そんな成長が見てとれるアルバムだ。この音楽性振幅を広げるためのあくなき探求が確信なるサウンドへ転化できる時(次作になるといいが)には、また大きなうねりとなって私たちの耳へと伝わるに違いない。そう予感させる作品だ。