明治41年(1908年)、横浜駅(※初代横浜駅=現在のJR桜木町駅)構内の食料・雑貨の売店として創業した「崎陽軒」。発足したばかりのころは「シウマイ」は開発されておらず、目玉商品がなかった。駅弁は販売していたが、当時の東海道線の下り列車では始発の東京駅で駅弁の購入を済ませる人が多く、反対の上り列車では横浜駅から終点の東京駅まで約30分なのでゆったりと駅弁を味わう時間的余裕がない。その結果、横浜駅では駅弁の売れ行きもかんばしくなかったのである。
会社の存続に危機意識を抱いた崎陽軒の初代社長・野並茂吉は、当時の横浜駅構内ホームでの店舗販売という恵まれているとは言い難い条件を、逆転の発想で克服する。
昭和に入り、当時は南京町と呼ばれていた横浜中華街で、突き出しに出された点心のひとつ「焼売(しゅうまい)」に着目。ただし、大きな問題点が壁として立ちはだかった。「しゅうまい」はつくりたての温かいうちに食べるとおいしいが、冷めるとおいしさが損なわれてしまうのだ。
横浜駅で販売するにあたり、つくった後、駅まで運ぶ時間、店頭に並べて売れるまでの時間などを計算すると、「しゅうまい」は冷めておいしさが失われてしまい、人々に受け入れられない。そこを逆手にとり、つくってから時間がたって冷めてしまってもおいしい「しゅうまい」をつくろうと考えたのである。横浜中華街(南京町)の点心職人・呉遇孫(ご ぐうそん)をスカウトし、約一年間、研究と試作を繰り返した結果、崎陽軒独自の「冷めてもおいしいシウマイ」は完成した。
豚肉とホタテ貝柱を混ぜ合わせる独自の調理法を編み出して誕生した「冷めてもおいしいシウマイ」は、昭和3年(1928年)、「横浜駅崎陽軒のシウマイ」(12個入り・一折り50銭)として、横浜駅(※現在の三代目横浜駅)で販売がスタートした。
しかし、販売が開始されてすぐに人気を集めたわけではなかった。飛躍のきっかけは、第二次世界大戦後の昭和25年(1950年)、「シウマイ娘」をPRのために導入したことにある。
鉄道での駅弁などの飲食料品の販売といえば、現在では駅構内の売店か車内で売るスタイルが定着している。しかし、かつては駅のホームに立った販売員が、かごや箱に入れた飲食料品を列車の車窓を通して乗客に販売するという方法が一般的であった。
そこで、横浜駅のホームに「シウマイ」の販売員として投入されたのが「シウマイ娘」である。鮮やかな赤いチャイナドレス風の制服に「シウマイ」と書かれたミス・コンステスト受賞者風のたすきを掛け、手かごに入れたシウマイを「シウマイはいかがですか?」と呼びかけながら車窓で売り歩くのだ。
崎陽軒の「シウマイ娘」は世の中の注目を集め、「同じシウマイを買うなら、シウマイ娘から」とアイドル的な人気を博すようになった。登場から2年後の昭和27年(1952年)には、獅子文六による毎日新聞の連載小説「やっさもっさ」で横浜を舞台にしたシウマイ娘・花咲千代子と野球選手・赤松太郎の恋愛物語が描かれ、評判を集めた。翌年の昭和28年(1953年)になると、この小説は松竹大船により映画化までされた。野球選手役は佐田啓二、シウマイ娘役は桂木洋子という当時の映画界のスターコンビが務めている。
全国的に知名度が高まった「シウマイ娘」は、当時の女性のあこがれの職業ともなり、崎陽軒の「シウマイ」の売り上げアップに大きく貢献した。いわば現在の企業のキャンペーンガール的な役割も担っていたのである。
日本初のキャンペーンガールは、昭和41年(1966年)、資生堂が夏のキャンペーンのために起用した前田美波里である。その16年前の昭和25年(1950年)にデビューを果たした崎陽軒の「シウマイ娘」は、まさにキャンペーンガールの先駆けともいえる存在であった。
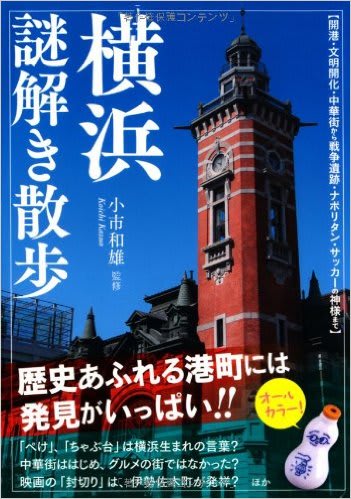
横浜謎解き散歩(KADOKAWA 新人物文庫)
※アマゾンで在庫切れの場合、下記でもネット上でご購入いただけます。または、お近くの書店でご注文ください。
●KADOKAWA
●カドカワストア
●紀伊國屋書店ウェブストア
●有隣堂









