4Pと4Cについて。
令和元年秋期 問68
売り手側でのマーケティング要素4Pは,買い手側での要素4Cに対応するという考え方がある。4Pの一つであるプロモーションに対応する4Cの構成要素はどれか。
と言うことで、
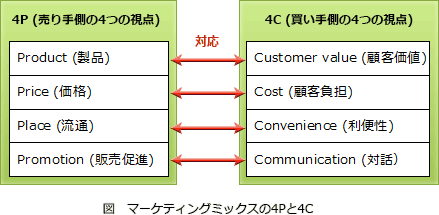
これを暗記すればいいのだが、私は腑に落ちない。
マーケティングミックス - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9
Product(製品):製品、サービス、品質、デザイン、ブランド 等
Price(価格):価格、割引、支払条件、信用取引 等
Promotion(プロモーション、販売促進):広告宣伝、ダイレクトマーケティング 等
Place(流通):チャネル、輸送、流通範囲、立地、品揃え、在庫 等
Consumer(消費者のニーズやウォンツが商品)あるいはCustomer solution(顧客ソリューション)
Customer cost(顧客コスト)
Communication(コミュニケーション)
Convenience(流通は利便性)
がどうも対応しているとは思えないのだ。これを考えていこう。
1.Product(製品)とConsumer(消費者)について
これは説明をはしょりすぎている。
元々大衆で構成される社会で「〇〇がしたい」と言うニーズ(生活需要)があって、それに合致できる商品を提供できるか否かがこのセットになっている。
2.Price(価格)とCustomer cost(顧客コスト)
これも強引にくくりすぎている。4Cの頭文字に置きたかったからCustomer costとしたのだろうが、顧客から見てもPrice(価格)はPrice(価格)だ。
要はその商品が提供された時にどの価格で商談成立しますか、と言う具体的な金額面での話がここに落とし込まれる。
3.Promotion(プロモーション、販売促進)とCommunication(コミュニケーション)
これは一つずつ考える必要がある。
Promotionは4Pの頭文字に置きたかったからPromotionとしたのだろうが、実際にあるのは広告宣伝費(Advertising)である。
また、Communication(コミュニケーション)は、どの商品を買うべきか、と言う点において、マクロ観点では広告だが、ミクロ観点では口コミだ、と言うことを言いたかったのではないか。
要はここの分類に該当するのは、商品を購入するにしても、どういう商品があるのか、どれがいいのか、と言う購買とそれに至る判断材料の提供をどうするか、と言うことにおいて、企業側のマーケティング観点からは広告、消費者側の購買観点からは口コミ、と言う、商品購買プロセスにおける消費者側の認識付与をどうするかと言う点においてこの分類が語られるように私は考える。
4.Place(流通)とConvenience(利便性)
これは分かりにくいが、物品をどう供給するか、物品をどう取得するかと言う、配送供給体制を企業側と消費者側の2観点で分類したものだ。
Convenience(利便性)は本当に強引な言葉の選択だったと思う。
本来は、消費者側のものの確保や購入経路の確保であって、その獲得の用意さ(しやすさ・便利さ)と言うのは本義として語るべきところではないように思う。
令和元年秋期 問68
売り手側でのマーケティング要素4Pは,買い手側での要素4Cに対応するという考え方がある。4Pの一つであるプロモーションに対応する4Cの構成要素はどれか。
と言うことで、
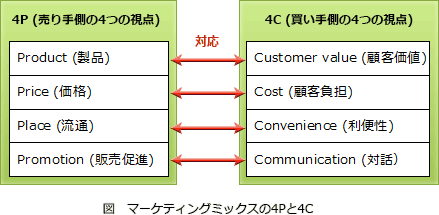
これを暗記すればいいのだが、私は腑に落ちない。
マーケティングミックス - Wikipedia
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9
Product(製品):製品、サービス、品質、デザイン、ブランド 等
Price(価格):価格、割引、支払条件、信用取引 等
Promotion(プロモーション、販売促進):広告宣伝、ダイレクトマーケティング 等
Place(流通):チャネル、輸送、流通範囲、立地、品揃え、在庫 等
Consumer(消費者のニーズやウォンツが商品)あるいはCustomer solution(顧客ソリューション)
Customer cost(顧客コスト)
Communication(コミュニケーション)
Convenience(流通は利便性)
がどうも対応しているとは思えないのだ。これを考えていこう。
1.Product(製品)とConsumer(消費者)について
これは説明をはしょりすぎている。
元々大衆で構成される社会で「〇〇がしたい」と言うニーズ(生活需要)があって、それに合致できる商品を提供できるか否かがこのセットになっている。
2.Price(価格)とCustomer cost(顧客コスト)
これも強引にくくりすぎている。4Cの頭文字に置きたかったからCustomer costとしたのだろうが、顧客から見てもPrice(価格)はPrice(価格)だ。
要はその商品が提供された時にどの価格で商談成立しますか、と言う具体的な金額面での話がここに落とし込まれる。
3.Promotion(プロモーション、販売促進)とCommunication(コミュニケーション)
これは一つずつ考える必要がある。
Promotionは4Pの頭文字に置きたかったからPromotionとしたのだろうが、実際にあるのは広告宣伝費(Advertising)である。
また、Communication(コミュニケーション)は、どの商品を買うべきか、と言う点において、マクロ観点では広告だが、ミクロ観点では口コミだ、と言うことを言いたかったのではないか。
要はここの分類に該当するのは、商品を購入するにしても、どういう商品があるのか、どれがいいのか、と言う購買とそれに至る判断材料の提供をどうするか、と言うことにおいて、企業側のマーケティング観点からは広告、消費者側の購買観点からは口コミ、と言う、商品購買プロセスにおける消費者側の認識付与をどうするかと言う点においてこの分類が語られるように私は考える。
4.Place(流通)とConvenience(利便性)
これは分かりにくいが、物品をどう供給するか、物品をどう取得するかと言う、配送供給体制を企業側と消費者側の2観点で分類したものだ。
Convenience(利便性)は本当に強引な言葉の選択だったと思う。
本来は、消費者側のものの確保や購入経路の確保であって、その獲得の用意さ(しやすさ・便利さ)と言うのは本義として語るべきところではないように思う。










