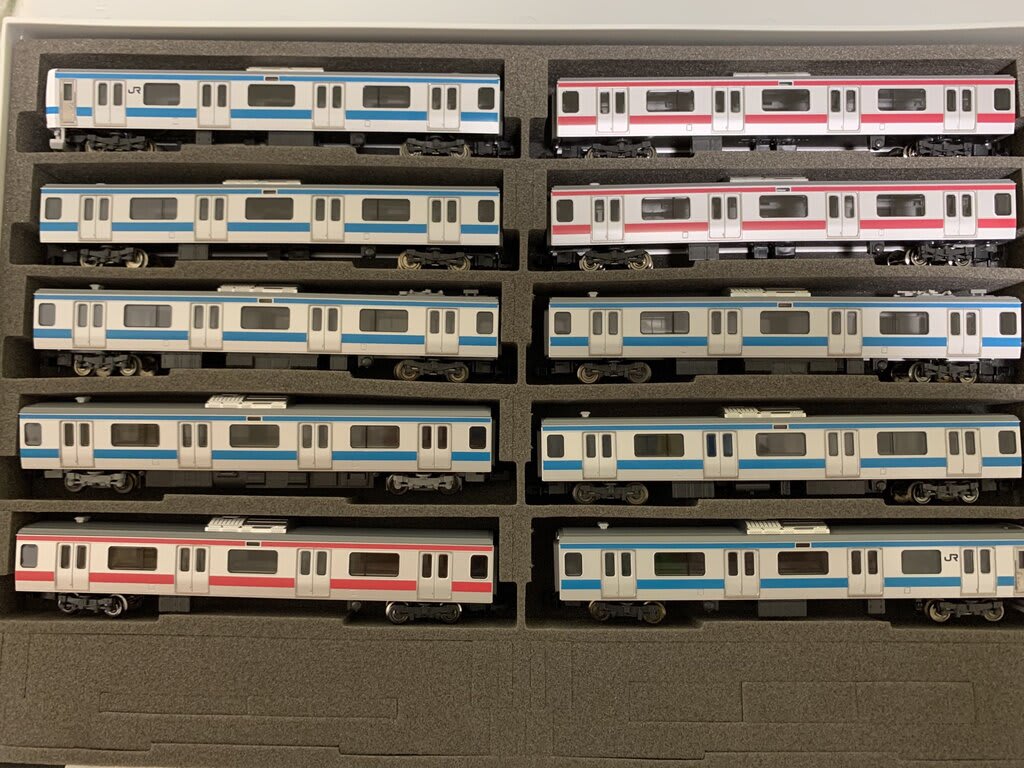久々に客レ組んだのでブログ化。
京都~出雲市間で運行されていた、夜行普通列車「山陰」号です。
せっかくだからオタク・長文語りで模型化時の注意点をご紹介。
山陰号の特徴は、なんといっても普通列車なのに寝台車が連結されていること。「山陰」の名称がついたころから運行終了まで一貫して10系寝台車を使用していました。
当初は出雲区生え抜きの車両を使用していましたが、晩年ごろに「日本海」などで使用していた宮原区のアコモ更新車に置き換えられました。ただし、日本海の潮風を受けて文字通りボロボロでしたが…
一方、座席車は旧型客車を使用していましたが、廃止1年前頃、当時最新鋭の12系客車に置き換えられます。座席車は新車なのに有料の寝台車はボロという恐ろしい編成…
さて、ポイントの解説です。
…といっても編成さえなんとなく合ってればいいと思います。こういう雑多な客車列車にもちゃんと運用があって、編成中の車掌車の位置やらなんやらが決まっているので、なんとなくそれに合わせるとそれっぽくなりますので。
まずは旧客時代。

基本編成は
<スハフ∔オハ∔オハ∔オハ∔スハフ>∔オハネフ12orスハネ16+マニ+スユニ
です。
座席車および寝台車の担当は出雲客車区、荷物車は宮原客車区でした。座席車は43系更新車(青色の車)が優先的に使用され、たまに35系客車や未更新車が混ざる、ということが多かったようです。10系や60系は座席幅が狭いので基本的に避けられていました。
模型的にはKATOの旧型客車(青)に何両か追加するのが楽でいいと思います。
(2024/5/22 追記:とか言ってたらそのものズバリのがカトーから発売されましたね。当然ですが、あれを買うのが一番いいです。あれに茶色のスハ43を1両足すとか、オハフ45を追加するとかで十二分に遊べます。)
中古で集めるのもそんなに難しくないです。旧客やるならどうせ必要になる車両群なので、まあ買って損はないですね。
寝台車はオハネフ12中心で、スハネ16が使用されることもあったようです。多客期は寝台車が2両、ということもありました。
模型でも各社の10系寝台で問題ありません。
荷物車はお好みで。マニ36、マニ60、スユニ61あたりがよく使用されていました。このあたりは模型でも入手もしやすいかなと。なお、時代設定上、マニ50は使用できないので注意。
末期(1980年代)はスユニ50+マニ36も多かった(というか郵便車は一気に置き換えられたので末期はそもそもスユニ50しか居なかった)のですが、スユニ50は模型では現状ほぼ入手不可能です…。
(2024/5/22追記:とか言ってたらカトーから単品で出ましたね。 出たなら買うしかないです。末期の客レをやるならぜひ欲しい車両ですので買いましょう。普通客レに手を出した時点でスユニ50から逃れることはできませんので。)
私はヤフオクで利尻のバラシを買いました。本来はクロポキット以外はNGですが、それくらい必要な車両なのです…。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
つづいて12系時代。

<スハフ∔オハ∔オハ∔オハ∔スハフ>∔オハネフ12
これが山陰号の基本組成です。担当は出雲客車区でした。
置き換えとほぼ同時期に郵便・荷物扱いが廃止され(12系に変更になってから3か月後に荷物扱い廃止)、荷物車や郵便車が連結されていないので、最盛期に比べてこぢんまりした編成に感じられます。
座席車は12系初期車。出雲客車区は「12系の配置数=運用数」で余裕ゼロのため、ときどき米子客車区から車両を借り受け、変則的な編成を組んでいました。繁忙期にもやはり車両を借り受けて、2両ほど座席車を増結することも。変則編成・増結の場合は電源の都合上〈スハフ+オハorオハフ〉を借り受けることが多かったようです。
模型的にはまあ、適当な12系を集めればそれっぽくなります。
一方、寝台車は全車オハネフ12。先述の通り、もともと山陰地区にいた10系ではなく、宮原区から転属してきた「日本海」の中古です。
こちらは出雲区に5両押し付け配置されていて、運用にもかなり余裕があった(というか完全に山陰号専用だった)ので、借り受け等はありません。
当時としても見劣りする三段寝台で内外オンボロなのに有料寝台ということで、利用率は高くなかったらしく、繁忙期でも増結はされなかったようです。
模型的には任意のオハネフ12でいけます。洗面所窓が擦りガラスに交換されていたので正確にはどのメーカーでもタイプ品にはなります…
ちなみに機関車はDD51あたりが良いと思います