コメ取引で入札で買いに行くというものが極端に減っている。
2006年産米入札の落札率は、
初回(8月30日)が23,3パーセント
2回(9月6日)が3,5パーセント
3回(9月13日)が6,3パーセント
2005年産も低かったが平均67,1パーセントあったそうだ。
米卸、コメ会社が「入札」でコメを買いに行かないということです。
特定契約という価格も数量も決めた取引がどうなるか?
米卸の先の量販店や大手業務筋と直接契約という話しもあるので混迷しているでしょう。
今や、
入札のコメ価格は一番高いコメの指標?
そんなことまで云われるようになりました。
コメ取引は多様化したのです。
JA系統は生産量の半分以下しか集荷できていません。
何度も述べていますが、
減っているコメ流通と
伸びているコメ流通があるのです。
コメ会社も熾烈な価格競争をしています。
まともな仕入では勝負できない状況にあるのです。
いつもそうですが、
取引ルールや制度改正は、
実態に近づけているだけですから・・・













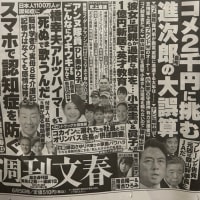







野菜がそうですが、もう大型共販の商品など消費者は求めていません。大手スーパーの売上不振がそのことを物語っています。どこもオンリーワンの商品を求めています。となれば小が大を呑む時代です。有能な生産者は農協を脱藩し、自分で独自の販売網を作りあげています。パソコンのネットづくりも普及し、宅配業の物流革命で環境も整ったのです。
青果物では市場外流通のシェアがますます高くなっています。とくに業務筋は市場流通の壁を破壊してきました。国内の生産者が供給責任を果たさないなら、海外産地開拓だということで輸入野菜が増加傾向してきました。経過を知らないマスコミは貿易問題のように報道しました。無論、内外価格差の問題はあったものの厳密には国内問題だったのです。
もっと厳しいことを言わせて貰うと、すでに日本には国家の基を形成する農業問題はないのかも知れません。農業所得が100万円前後では、実態はもう「趣味の農業」でしょう。これでは後継者を育てられないのは当然のことです。しかし、だから農業を保護せよという論理はもう通用しません。大組織は時の経過と共に滓が溜まります。この滓をクリーニング、浄化する必要があるのだと思います。
「日本農業再生」良いタイトルですね。
新しい総理大臣が明日誕生しますが、食の問題も大きく政策に取り上げて欲しいですね。
農業は素晴らしい産業であり、やりがいのあるビジネスでもある。
また、日本にとっても、人類にとってもなくてはならないものでもあります。
日本のハイテク技術や、頭脳を農業に注ぎ込めば「生産性の高い」農業に再生できると思う。
視点を変えればすごく将来性のある仕事だと思いますね。