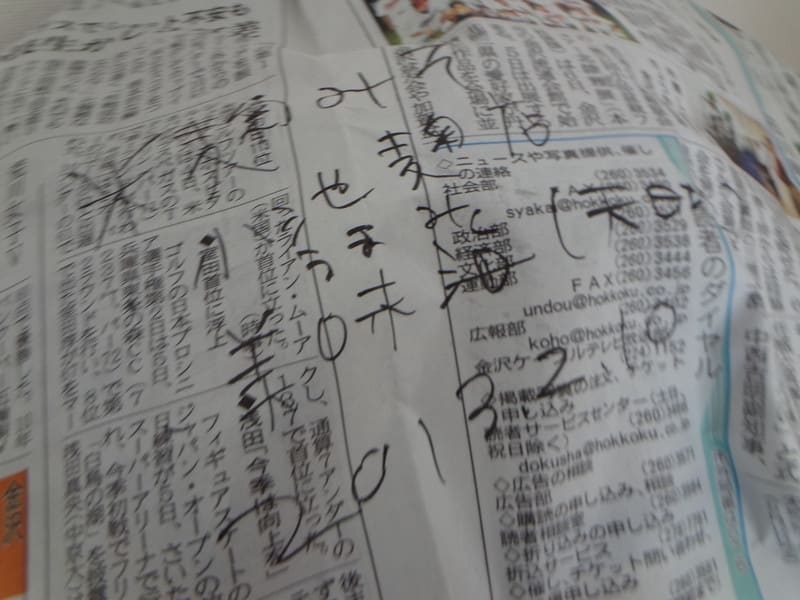2012年秋。
子どもたちが幼稚園の給食などで食べるお味噌を、手づくりの味噌にできたら・・・という動きが生まれました。
この動きと連動して、子どもたちがお世話になっている幼稚園の古民家≪たいようの家≫で、手づくり市をさせていただく話も出て、この市で募金を集めさせていただいたり、出店者さんからの出店料をお味噌づくりの資金にあてさせてもらうことになったりしました。
そして、2013年2月27日、幼稚園の多大なご協力のもと、大勢のお母さんたちに参加してもらって、この手づくり味噌仕込みが行われました。
思い立っても、なかなか実現できることではないことだと思いますが、このような母親たちの思いや活動を、全面的に応援してくれる先生方、そして幼稚園なのでした・・・。
大切な古民家でさせていただいて、当日までさまざまなことに相談に乗ってくださった先生方や幼稚園に感謝感謝です!
今日は、野外で火をおこし、≪おくど≫を使って大豆を茹でる予定でしたが、朝になっても小雨がやまず、やむを得ず給食室のガス台で、大鍋4つを使い、10kgの大豆を茹ではじめました。
10時くらいになると、小雨がやんだので今からでも≪おくど≫で豆を茹でよう!と、母たちは火をおこし、途中まで給食室で茹でた豆を屋外に移し、豆を茹で始めました。
・・・せっかくだから、お家ではできない、≪おくど≫を使って豆を茹でる風景が見たいですよね!
パチパチ燃える火を見ながら豆のアクをすくい、みんなでザワザワと作業するのはとっても楽しい。
午前中は大豆をやわらかくなるまで茹でて、作業する場づくりをしながらザワザワ過ごしました。
昼過ぎに豆がやわらかく茹であがる予定です。
早めにお昼を済ませて・・・さあ、仕込み作業はいよいよここからが本番です!
塩きり麹を作っておいて、茹であがった大豆をみんなで一斉につぶします。初めての方がほとんどでしたが、みんなとっても上手に粒が全然残らないくらいきれいにつぶしてくれました。
多分、茹であがりは全部で22kgくらいあったと思います・・・!
つぶした豆が人肌くらいの温度に下がったら、塩きり麹とつぶした豆を混ぜ合わせます。
ここで、本日の先生、平瀬さんがそれぞれの作業台をまわってくださって、煮汁をちょうどいい塩梅に加え、仕上がりまで丁寧見てくださいました。
参加されたお母さんたちも、お味噌に関心持たれている方がたくさんみえたので、平瀬さんがいらっしゃるうちに、たくさん質問させていただきました?
八丁味噌の仕込み方や、たくあんの仕込み方など・・・、平瀬さんのお話を聞きつつ、みんなでワイワイと混ぜる作業。
しっかり混ぜ合わせたら、いよいよ味噌玉づくりです。
たくさんの味噌玉が、各作業台に積まれて・・・いよいよ味噌玉投げ大会ですかね!
10号のカメ2つを並べて、それぞれ大豆5kgで仕込んだ味噌(計10kg)を投げ込みます!
みんなバシっと入れて楽しんで、なんとか無事に味噌仕込みが終了です。
お疲れさまでした~~~。
この時期になってインフルエンザが流行し、学級閉鎖になったクラスもあったり、子どもの体調不良で残念ながら欠席された方も数名みえましたが、当日参加できなかった方も、この味噌づくりを気にかけてくださったすべての方の心がこの会に集まって実現できたのだと思います。
小さい子どもさんをおんぶしたりあやしたりしながら、朝から1日お手伝いいただいた方もたくさんみえました。
初めての試みで、たくさん不器用なところもあったと思いますが、まずは無事にお味噌を仕込むことができました。かかわってくださったみなさん、ありがとうございました!
参加するために、ご家族のご理解やご協力もたくさんいただいていると思います。ご家族や、忙しい母を見守ってくれた子どもたちにもありがとうですね!
母がバタバタしていると、家族全員がちょっとバタバタしちゃいますよね。
我が家も今朝からわたしがバタバタしていたので、明日あさっては、のんびりすごしてゆったり子どもたちと接していけたらいいなと思っています。
いろいろと課題もあるので、金曜日にまずm.joyちゃんとふたりで反省会をして、またみなさんにも改めてご報告させていただければと思います。
まずは、「てのしごと」にて、取り急ぎご報告でした♪