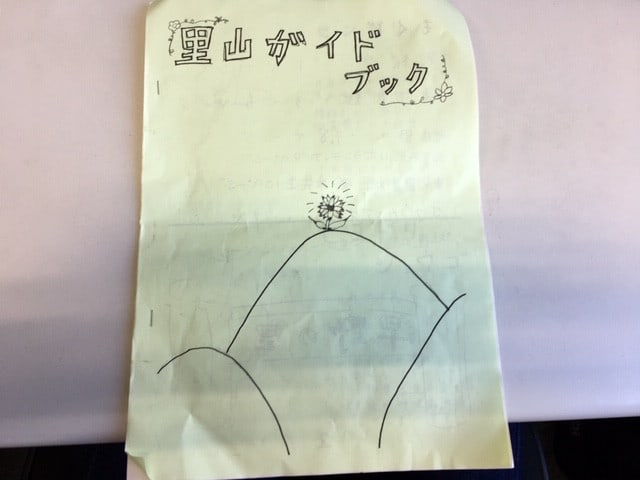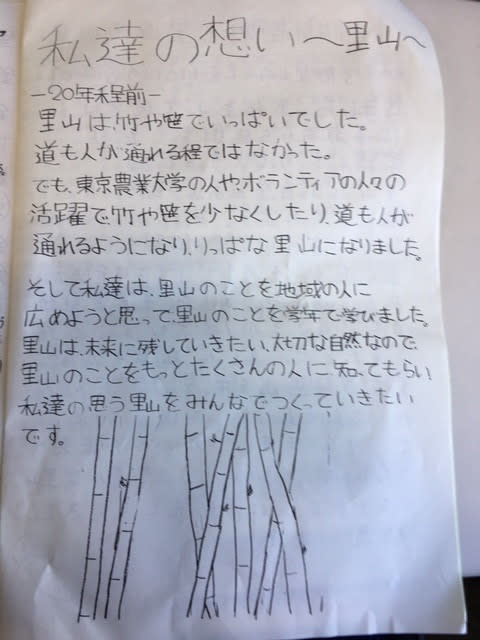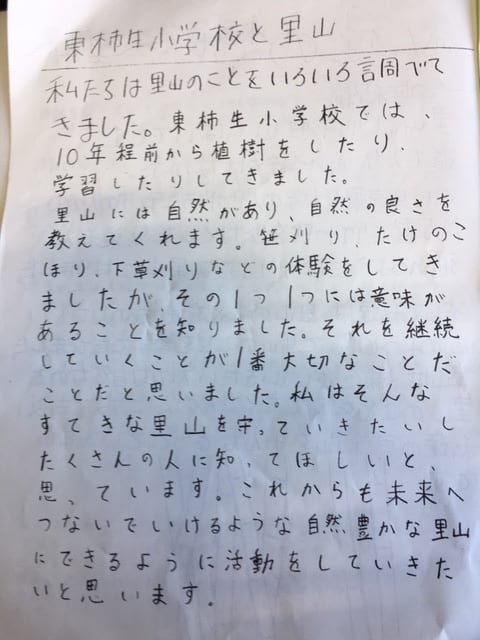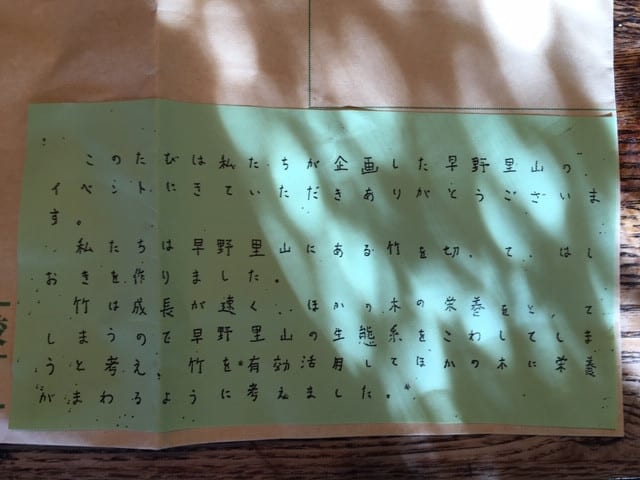里山で環境学習!小学生がたけのこ堀で里山保全を学びました
今年も早野地区で、近隣小学校の環境教育が開催されました。今回は、東柿生小学校の6年生に加えて、虹ヶ丘小学校の6年生も参加し、総勢約80名の生徒たちが集まりました。
テーマは、前回に引き続き里山の竹管理。具体的には、たけのこ掘りを通して、竹林整備と環境保全について学びます。
竹林は、放置すると竹が密集し、里山の生態系に悪影響を与えてしまいます。そこで、春のたけのこの段階で間引くことで、竹林の適切な管理を目指します。

今回も、東京農業大学の鈴木教授にご協力いただき、生徒たちは実際にたけのこを掘りながら、里山について学びました。
まずは、鈴木教授からたけのこの掘り方についてレクチャーを受けました。

生徒たちは3人1組のチームになり、いざ、たけのこ掘りに挑戦!最初は、慣れない山道に戸惑いながらも、次第にコツを掴み、夢中でたけのこを掘り進めていました。




たけのこ掘りの後は、鈴木教授と生徒たちの意見交換会が行われました。
鈴木教授が「たけのこ掘りをやってみてどう思った?」と問いかけると、生徒たちからは「環境保全になる」「SDGsにつながる」といった意見が挙がりました。
さらに、鈴木教授が「たけのこを掘ることが、なぜ環境保全につながるのか?」と質問すると、生徒たちからは「たけのこが成長して竹になると、里山に日光が当たらなくなり、生態系が壊れてしまうから」という答えが返ってきました。
生徒たちが里山の環境問題についてしっかりと理解していることにびっくり。

今回の環境教育を通して、生徒たちは里山の環境保全の大切さを学ぶことができました。この経験が、生徒たちの今後の学びや行動に繋がっていくことを願っています。