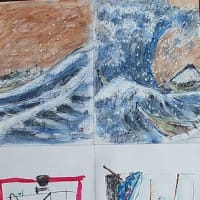朝日記231011 神出瑞穂「日本人のこころの形 無自覚日本人考」への所見
畏友神出さんの著書へのアマゾン投稿初見です 2013
2013年2月27日に日本でレビュー済み
わたくしの読書所見
神出瑞穂著
「日本人のこころの形 −無自覚日本人考 −」を読んで
荒井 康全
*日本人のアイデンティティが問われている。 日本人のこころとはなにか。
著者は、ストレートな問いかけから始まる。読者である私は、一瞬たじろいでしまったことを告白する。
*古く「和魂漢才」や明治の「和魂洋才」など「x魂y才」の表現型のなかで 日本人の「心」の軌跡が縷々語られる。 また、「大和魂」、「和」、「もののあはれ」、「穢れ」と「浄め」など日本人の人口に膾炙した「ことば」についても、その概念が見事に分類・整理され、また丁寧に説き起こしてある。1938年生まれの筆者には、ごく自然な感覚で着いていける内容でもある。 読書の醍醐味を大いに感じたことを告白する。
*さて、筆者は なぜ この本が分かりやすいのかということを自らに問いかけることになった。 分かりやすいいということと それによって、読者が「自覚」を覚えることと どのようなつながりがあるかとなど、妙な感じにとらわれることになったのである。
*そして、さらに、もし、この著書が英語で書かれたらどうなるかということにも興味を持ったのである。
*これらは、「日本人のこころはなにか」質問の意味するところを、いったん「裸の」人間という次元まで戻して考える刺激を私に与えることになった。
*多分、著者と同じ手法とおもうが筆者は「わたくしのことばあそび」と称する‘あそび’をこの十年来の習慣としている。ここでは 「こころ」と「魂」を選び 日本語と英語の辞書で 語源や類似語・反意語を並べることを試みたのであった。
*たとえば「魂」をいま選んだとしよう。日本語の辞書 では 「たましい」、「こころ」 「精神」、「人間の体の中にあって、広く精神をつかさどっているもの」などとして出てこよう。 外国語の対応では、mind (英)、Seel(独)、'me(仏)、psych'(ギリシャ)などが出てこよう。
*つぎに、身近さということで 英語のmindに焦点 を当てこの類似語を眺めてみる。大体 以下の類似語であった。
understanding, brain, consciousness, intellect, disposition, intelligence, reason, sense, soul, spirit
*類似語の意味の距離で、mindにいちばん近いのはintellectであった。単純に
自分の好みの切り口として このintellectを選ぶことにしよう。(もちろん、mindを選んでもよい)
*その結果、intellect(知性、知力)とは、なにかという切り口に質問が変換されることになってしまった。
*さて、そうすると 個々の日本人の固有の知性的なもののとらえかた(思考の仕方、行動の仕方)においての特徴はなにかという設問に置き換わるであろう。さらに加えて、そのとらえ方への価値の置き方に共通の特徴があるかという形に置き換わるであろう。 この点では 当然ながら本著書は満たそうとしていると理解している。
*さらに重要なことは 異なる文化背景の国(たとえば英語圏、中国語圏、東南アジア圏)との比較としてどういう特徴があらわれるのかということにもなろう。
*つぎに、思考、行動、価値のどの部分を 日本人は自覚(identity)しているかがくる。
*自覚について、啓蒙( enlightment ) 活動はなぜ必要であるか。 それは何故か。
*そして これを考える上で何か具体的な思考対象を持つことを提案があるとよろしいのではないかと考えるに至ったのである。
*筆者が気付いたのは、目下 提案中の自民党案憲法と現憲法のそれぞれの「前文」比較などが最良の思考教材となるのではないかと考えたのであった。
*なぜなら憲法の「前文」には、わが日本が存在することの人類社会へのミッション、この国がかくありたいと思うヴィションへの決意、そしてその根底をなす価値感を明らかにすることが必須であるからである。
*結局 これに答えることが「日本のこころはなんですか」の答となるのではないかと思った次第である。
*ひとつ、加えると、著者の執筆動機になった「日本のこころはなんですか」と尋ねられて即答できなかったことは 恥かどうか分かれるところとおもう。
神出瑞穂著
「日本人のこころの形 −無自覚日本人考 −」を読んで
荒井 康全
*日本人のアイデンティティが問われている。 日本人のこころとはなにか。
著者は、ストレートな問いかけから始まる。読者である私は、一瞬たじろいでしまったことを告白する。
*古く「和魂漢才」や明治の「和魂洋才」など「x魂y才」の表現型のなかで 日本人の「心」の軌跡が縷々語られる。 また、「大和魂」、「和」、「もののあはれ」、「穢れ」と「浄め」など日本人の人口に膾炙した「ことば」についても、その概念が見事に分類・整理され、また丁寧に説き起こしてある。1938年生まれの筆者には、ごく自然な感覚で着いていける内容でもある。 読書の醍醐味を大いに感じたことを告白する。
*さて、筆者は なぜ この本が分かりやすいのかということを自らに問いかけることになった。 分かりやすいいということと それによって、読者が「自覚」を覚えることと どのようなつながりがあるかとなど、妙な感じにとらわれることになったのである。
*そして、さらに、もし、この著書が英語で書かれたらどうなるかということにも興味を持ったのである。
*これらは、「日本人のこころはなにか」質問の意味するところを、いったん「裸の」人間という次元まで戻して考える刺激を私に与えることになった。
*多分、著者と同じ手法とおもうが筆者は「わたくしのことばあそび」と称する‘あそび’をこの十年来の習慣としている。ここでは 「こころ」と「魂」を選び 日本語と英語の辞書で 語源や類似語・反意語を並べることを試みたのであった。
*たとえば「魂」をいま選んだとしよう。日本語の辞書 では 「たましい」、「こころ」 「精神」、「人間の体の中にあって、広く精神をつかさどっているもの」などとして出てこよう。 外国語の対応では、mind (英)、Seel(独)、'me(仏)、psych'(ギリシャ)などが出てこよう。
*つぎに、身近さということで 英語のmindに焦点 を当てこの類似語を眺めてみる。大体 以下の類似語であった。
understanding, brain, consciousness, intellect, disposition, intelligence, reason, sense, soul, spirit
*類似語の意味の距離で、mindにいちばん近いのはintellectであった。単純に
自分の好みの切り口として このintellectを選ぶことにしよう。(もちろん、mindを選んでもよい)
*その結果、intellect(知性、知力)とは、なにかという切り口に質問が変換されることになってしまった。
*さて、そうすると 個々の日本人の固有の知性的なもののとらえかた(思考の仕方、行動の仕方)においての特徴はなにかという設問に置き換わるであろう。さらに加えて、そのとらえ方への価値の置き方に共通の特徴があるかという形に置き換わるであろう。 この点では 当然ながら本著書は満たそうとしていると理解している。
*さらに重要なことは 異なる文化背景の国(たとえば英語圏、中国語圏、東南アジア圏)との比較としてどういう特徴があらわれるのかということにもなろう。
*つぎに、思考、行動、価値のどの部分を 日本人は自覚(identity)しているかがくる。
*自覚について、啓蒙( enlightment ) 活動はなぜ必要であるか。 それは何故か。
*そして これを考える上で何か具体的な思考対象を持つことを提案があるとよろしいのではないかと考えるに至ったのである。
*筆者が気付いたのは、目下 提案中の自民党案憲法と現憲法のそれぞれの「前文」比較などが最良の思考教材となるのではないかと考えたのであった。
*なぜなら憲法の「前文」には、わが日本が存在することの人類社会へのミッション、この国がかくありたいと思うヴィションへの決意、そしてその根底をなす価値感を明らかにすることが必須であるからである。
*結局 これに答えることが「日本のこころはなんですか」の答となるのではないかと思った次第である。
*ひとつ、加えると、著者の執筆動機になった「日本のこころはなんですか」と尋ねられて即答できなかったことは 恥かどうか分かれるところとおもう。
*ここで「こころ」を正して「ドイツ人のこころはなんですか」と逆に問うことも正当であるとも思う。 なぜならドイツ人特有で、ときに質問が唐突すぎて質問の真意がわからないときがあることを経験しているからである。
*多々弁じたが、この著者の分類からすると筆者は「無自覚的日本人」になることを甘受することになろう。
ものの思考の出発点としてやはり啓発された本ということになる。 以上
~~~~~
- グローバルサムライ (phytonエンジニア)氏からのコメント
- 2025-03-18 03:41:45
- 最近はChatGPTや生成AI等で人工知能の普及がアルゴリズム革命の衝撃といってブームとなっていますよね。ニュートンやアインシュタイン物理学のような理論駆動型を打ち壊して、データ駆動型の世界を切り開いているという。当然ながらこのアルゴリズム人間の思考を模擬するのだがら、当然哲学にも影響を与えるし、中国の文化大革命のようなイデオロギーにも影響を及ぼす。さらにはこの人工知能にはブラックボックス問題という数学的に分解してもなぜそうなったのか分からないという問題が存在している。そんな中、単純な問題であれば分解できるとした「材料物理数学再武装」というものが以前より脚光を浴びてきた。これは非線形関数の造形方法とはどういうことかという問題を大局的にとらえ、たとえば経済学で主張されている国富論の神の見えざる手というものが2つの関数の結合を行う行為で、関数接合論と呼ばれ、それの高次的状態がニューラルネットワークをはじめとするAI研究の最前線につながっているとするものだ。この関数接合論は経営学ではKPI競合モデルとも呼ばれ、トレードオフ関係の全体最適化に関わる様々な分野へその思想が波及してきている。この新たな科学哲学の胎動は「哲学」だけあってあらゆるものの根本を揺さぶり始めている。こういうのは従来の科学技術の一神教的観点でなく日本らしさとも呼べるような多神教的発想と考えられる。