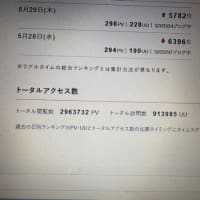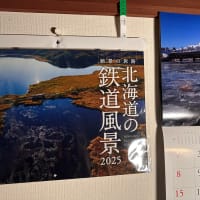何度も何度も行きつ戻りつしながら、また、レノア・テアの『恐怖に凍てつく叫び』も並読しながら、エリアナ・ギルの『虐待を受けた子どものプレイセラピー』を読んでいた。どちらも大好きな西澤哲先生の翻訳によるもので、たいへんなめらかな日本語に訳されていて、読みやすかった。
それなのに、半年近く読んでいるのは、自分で理解し、実践できるまでの深さを得るために醸す必要があったからだろう。
最近、子どもたちを見ていて思うことは、トラウマチックな出来事に出会ったとき、子どもたちはどうしてもそれを再現せずにはおれないのだということ。
それは、以前読んだ愛育養護学校の津守真さんが『保育者の地平』で書いておられる「子どもは、それを受けとめる者がいる時に、表現者となる」ということや、社会評論家の芹沢俊介さんが、『もういちど親子になる』で述べている「子どもは全てを受け入れてくれるおっぱいと出会うことでのみ、変わることができる」ということの根本的理論なのだと気づかされた。
そして、それらの再現は、単なる遊びやまねごっこや、ごっこ遊びの中に、いかに多く含まれているかということにも気づかされた。
2002年に、西澤哲さんの講演を札幌で開かれていた日本子ども虐待防止学会で聞くことができたが、その時に、西澤さんがおもしろいことを言っていた。
「虐待を受けてきた子は、”お医者さんごっこ”をするにしても、”看護師さんごっこ”をするにしても、行為者の側をやりたがる。患者、無防備な受け手には恐くてなることができないのだ。」と。そして、こうも言って会場の失笑をかった。「だから、医療・福祉の現場は、(被虐待)関係者が多くなるんです。」と。私は個人的には、そこに、”教育”という現場も入るのではと思っている。
私のかかわっている子は、最近私にオニ役をさせ、オニに襲われる子どもになって遊び、「え~~ん、え~~ん」と泣き真似するようになってきた。それまでは、オニ役や怒っている大人の役をやりたがり、私に子どもの役をさせていたのに。
そこに行きつくまでに、その子の中でどんな葛藤があったのかは、私には知る術はないが、まったくこちらが意図したものではないのに、次々と順をふんで現わされてきたそれらの遊びの中に、その子の変化をみることができた。
そして、その変化の重大さ・大切さを、この本は導き、教えてくれた。
力による支配を、ファンタジー化することで、子どもはそれを越えようとしているように私には思えた。
私がこの本で一番好きなのは、65ページの、著者がセラピーに訪れた子どもにあいさつする場面だ。
「私の名前は、エリアナよ。私は、子どもたちとお話ししたり、遊んだりする人なの。子どもたちと、いろんな考えや気持ちについてお話しすることもあるし、好きなことをして遊んだりもするのよ。」 これを読み、号泣した。
たった、これだけの簡潔なあいさつなのだが、虐待を受けた子どもや、やんちゃな子に接した人ならわかると思うが、このあいさつにたどりつくまでに、エリアナ・ギル先生もどれだけの失敗や行き詰まり感、自責の念を感じたことだろう。私はそれに思いを馳せ、感極まって泣いてしまった。
『虐待を受けた子どものプレイセラピー』、私はセラピーの専門家でも、資格をもつ人間でもないが、これからもこの本をバイブルとしながら、子どもの表現する世界を見ていくだろうと思う。
子どもと接する方にはぜひ読んでもらいたい本です。
 | 虐待を受けた子どものプレイセラピー |
|---|---|
| エリアナ・ギル | |
| 誠信書房 |