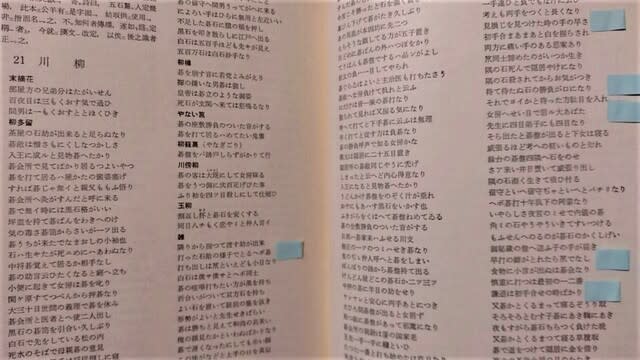
【ザル碁ヘボ碁あるある / いにしえの川柳、狂歌から】
似たような古川柳に
〝一目の負けそこら中かきまわし〟
というのもあります
取った碁石(アゲハマ)は
相手陣地を数える前に
埋めることができます
一つの石で一目減るのですから
〝貴重な捕虜〟は時として
勝敗を左右します
碁笥(碁の入れ物)のフタを裏返しにし、
相手に見えるように置くのが基本マナー
途中の形勢判断の材料となるためです
ところが、
あちこちにバラバラに置かれると
目算をするのに具合が悪いのです
行儀の悪いアマに散見されますが
平成四天王同士のタイトル戦でも
フタに石を置いていたのですが
数え終わった二人が納得できず
座布団をひっくり返したことも
半目勝った方が「半目負け」を覚悟し
半目負けた方が「半目勝ち」と信じていました
両者が目算を間違えていたのです
これはなかなかのビックリでした









