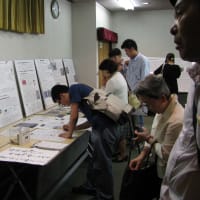ここに掲載するのは、6月14日の東京開催における、八尋光秀弁護士の基調講演の元原稿です。八尋先生のご好意により、掲載させていただくことになりました。
弁護士である前に、人として福岡事件に向き合う八尋さんの姿勢・思いが強く打ち出された、感動的な文章です。当日来られなかった方は是非とも、また会場で聴かれた方も、今一度目を通していただければと思います。
福岡事件 講演原稿 於:東京YMCA青少年センター
1 ハンセン病療養所にある梵鐘
皆さんはハンセン病療養所をご存知でしょうか。私たちの国に国立ハンセン病療養所 は全部で13園あります。青森、宮城、群馬、東京、静岡に各1園づつ。岡山に2園、香川、熊本に各1園、鹿児島、沖縄にはそれぞれ2園です。このうち鹿児島県鹿屋市にあるハンセン病療養所を星塚敬愛園といいます。
かつて、ここは星塚村と称し、郵便局も床屋も売店もある、選挙も火葬も葬儀もできる療養所でした。園の周囲には、杉の生垣めぐらし、あるいは深い側溝を掘り、その中に水を湛え、茨を活けて完璧な隔離の塀としました。巡視による巡回があり、外出には許可を要し、無許可での外出は逃亡とみなされて、監禁懲罰の対象としました。身ごもった胎児はすべて抹殺され、断種・堕胎を結婚の条件としました。
患者の治療や介護だけではなく、水や食料や燃料の確保からそのほかの生活必需品の手当てまで、患者作業によって賄われました。
患者隔離は絶対で、入所の時に、生まれ育った生活からも親戚や知人、友人、恋人であり家族からも、終生のものとして、線を引くように、断絶を強いました。それは、思春期前の子どもであっても、家族を持つ大人であっても同じ扱いでした。
やがて死を迎えるとき、看取る者は医師ではなく看護者でもない。家族でもなく友人でもない。同じ隔離の仲間だけで寂しく見送りました。火葬も葬儀もまた仲間の手によるものでした。弔うものは、自らの生と死の孤独を、そのつど突きつけられました。こうやって、ひとり寂しく死んでゆくのだと何度も何度も。そんな絶望の隔離の中で、自らの命を閉じる仲間も少なくありませんでした。
ハンセン病療養所は、どこまでも静謐で、人間の悲しみと孤独と絶望が澱をなして深く沈んでいるようです。
そのハンセン病療養所星塚敬愛園の中庭にある寺院のとなりに、梵鐘が吊るされています。朝と夕べに撞木で突く鐘の音が園内に響きます。その梵鐘は昭和32年に寄贈されたものです。この鐘の音が入所者の人々に生きる希望の火を灯し続けて、もう50年。今でも朝夕、この鐘が鳴り響いています。
この梵鐘の寄贈者は、この園に来たこともなければ、この園に隔離された人たちにあったこともありません。ましてや、ハンセン病療養所が行ってきた患者隔離による非人道的なまた未曾有とも言うべき人権侵害の数々、そしてそれがもたらした人間の悲しみに、責めを負うべき立場にもありませんでした。
ただ、無実を叫び続けるひとりの死刑囚。自らと同じ悲しみを強いられた人間として深く共感した、冤罪死刑囚です。彼は、無実の死刑囚として獄中で絶望の中にあってすでに10年。書画を描き、写経を続けていました。この積み上げた修練の作品を世に出して、梵鐘購入の資金としました。
この梵鐘の寄贈者こそ、無実の死刑囚こそ、西武雄です。福岡事件において、誤った裁判により首謀者とされ、死刑を執行された、西武雄その人です。西の悲嘆と孤独と絶望がハンセン病療養所星塚敬愛園に梵鐘を寄贈させました。
そのハンセン病療養所星塚敬愛園の人達もまた、この冤罪死刑囚の濡れ衣を雪ぐため、僅かな作業賃を出し合って、支援をし続けました。今もなお、隔離の住処からすでに執行されたこの無実の死刑囚の雪冤を心から願っています。
私たちは、彼らの深い悲嘆と孤独と絶望に、余りにも冷淡でした。冷酷ともいうべきでしょう。
ハンセン病療養所に勤めた医師であり、看護者であり、職員は自分の気ままな気分で人間を隔離し、堕胎し、断種を強いてきたわけではありません。私たちの誤った意識を実現するために、法律や政策に忠実に、かつ自らに課された職務に誠実に、ひたすら未曾有の人権侵害を繰り返してきたのです。
裁判官や検察官あるいは死刑執行人は、自分勝手に死刑を求刑し、死刑判決を下し、死刑を執行しているのではありません。犯罪に対する私たちのやり場のない憎しみの捌け口を求めるため、その便利な手足として、有罪を宣告し、死刑を命じてきました。
私たちこそが、紛れもなく、ハンセン病患者の人生を奪い、西武雄に死刑を執行した。その私たちは、彼らの悲嘆や孤独や絶望に目を瞑り、あるいは眼をそむけ、素知らぬふりをして、無邪気に振舞っていました。それが冷酷なことだなあと思うわけです。
西武雄は終生隔離を強いられたハンセン病患者に、ハンセン病患者は無実の死刑囚西武雄に、その悲嘆と孤独と絶望を互いに見出し、希望の火を灯し続けあって、自らの生を全うしようとしました。
冤罪再審福岡事件のもつ意味は、ハンセン病療養所のもつ歴史的な意味ともつながって、人間の命のありか、「命と命のかかわり」のなかにこそ見出されるものだと思います。
2 シュバイツァー博士の遺髪
私は、1995年10月に初めて星塚敬愛園に入りました。後に国賠訴訟の原告番号1番となられた、島比呂志さんに呼ばれたからです。国が「らい予防法」を廃止しようとしているのに、人権に深いかかわりを持つべき弁護士、弁護士会がハンセン病問題について一片の謝罪もせず法曹の責任を総括すらしないことは、無責任に過ぎると。
1998年7月に「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟を熊本地方裁判所に提訴しました。この訴訟は、後に2001年5月11日の全面勝訴判決、同月23日国の控訴断念を経て、ハンセン病問題を全面解決へと向かわせました。
私は、島さんに求められて星塚敬愛園に立つまで、「らい予防法」を知りませんでした。ハンセン病療養所を見たことがありませんでした。
私は、その後、何度も星塚敬愛園を尋ね、入所者の方々のお話を伺いました。その折々、幾度かは、その梵鐘の前に、謂われを知らず、ひとり頭を垂れていました。
古川泰龍師が私を尋ねてこられたのは、ハンセン病訴訟を提起した1年後のことです。私は、古川師にお会いするまで、ハンセン病問題と同様、福岡事件のことについて、これっぽっちの知識さえ持ち合わせて居ませんでした。
はじめは、お会いすることさえもお断りをいたしました。刑法学を専攻される大学教授のご紹介で、会うだけでも会ってというお願いでした。しかし、会えば断りづらくなります。当時の私はハンセン病訴訟とのかかわりで手一杯でした。
「このままでは裁判記録をいつ廃棄されるか分からない。廃棄させないために、今、再審請求する予定だと検察庁に通知し、記録の謄写だけはしておく必要がある。それだけでもいいので手伝って欲しい。」と説得されました。さすがに、これを断ることはできませんでした。古川泰龍師にお会いすることになりました。
古川泰龍師は生命山シュバイツァー寺と名乗られました。名刺を手に「あのシュバイツァー博士ですか。」といぶかしがる私に、その由来を語られました。
「シュバイツァー博士は「生命への畏敬」を説かれました。それは、あらゆる人間はひとりひとりそれぞれに意味のある、かけがえのない生命をもっている。どのようなときでも、どのような場面でも、ひとりひとりの人間の生命を一番に優先すると言う考えです。私はこの「生命への畏敬」という思想を宗派を超えて伝えて行きたい。そんな思いを込めて、シュバイツァー博士のご遺髪を祀り、生命山シュバイツァー寺を開山しました。」そうお教えいただきました。
さらには、かの星塚敬愛園に梵鐘を寄贈したものが無実の死刑囚である西武雄であり、福岡事件において正されるべき真実は死刑囚として命を奪われたその西武雄の無実であるとのことでした。
人間が絶望の極みの中にあって、互いに命のかかわりを深める営みが、希望を芽生えさせたことを知りました。そのことを私の立場で受け継ぎ伝えることが、私にできる「生命への畏敬」の実践であるということを理解しました。
私は、ハンセン病訴訟がひとつの成果を得た段階に至れば、福岡事件の再審請求に取り掛かることをお約束せざるを得ませんでした。
3 私はわらじがぬがれない
私はこれまで、多くの医療過誤訴訟やハンセン病訴訟、薬害HIV訴訟、薬害肝炎訴訟を追行してきました。また、鹿児島夫婦殺人事件をはじめとする数件におよぶ無実の被告人であり、無実の受刑者の訴訟を担ってきました。
ハンセン病訴訟では患者隔離政策によって命と人生を奪われた人たち。薬害HIV訴訟や薬害肝炎訴訟では経済利益を優先させた薬事政策や企業活動によって命を人生を奪われた人たち。さらには誤った刑事裁判や医療過誤によって、いずれも、かけがえのないその命と人生とを奪われた人たち。
私はそういう人たちが裁判と言う場で、奪われた命や人生を取り戻すためのスタートをきる。そのことを支え、勇気づけ、ときに提案し、命を人生を奪われた人間の悲嘆であり、孤独であり、絶望にかかわり、その回復の作業に身を置いてきました。
裁判は人間の活動の中でもとても限られたひとつの場面です。私は、シュバイツァー博士であり、それを受け継いだ古川泰龍師の「生命への畏敬」という思想に共感しました。裁判という特殊な場面において「生命への畏敬」を芯に据えて実践することを考えました。
古川泰龍師は「私はわらじがぬがれない」といいます。
「わらじをはいて 十年 無実の死刑囚を救うため
わたしは ひとり ひとり
街を 村を 訴え 叫び 歩きつづけた
一億もの人間がいるのだ
無実の死刑囚を孤立させてはならない
二十年先か 三十年先いつか
みんなが知って救い出してくれる
わたしはそれを信じて 今日も 明日も 歩く
たったひとりのいのちすら 守れない世の中を 私は信じることができない
無実で死刑にならない世の中を 私は信じたい、証明したい
でなければ、私は救われない、生きられない 私はわらじがぬがれない」と。
そう決意を表明された4年後、西武雄は処刑されました。それから20年余を経て、古川泰龍師は厚さ10センチを越えるガリ版刷りで製本された、この「真相究明書、9千万人のなかの孤独」と題する西武雄の再審請求書を手にして、私の前に現れられました。
冤罪は幾らでもあります。最近でも、いくつかの無罪事件が見つかりました。真犯人が現れたというのです。富山の氷見事件では、強姦事件で無実のタクシーの運転手さんが裁判で有罪とされ刑務所に入っていました。そこに真犯人が表れました。宇都宮でも同じ様な事件がありました。冤罪で真犯人が現れる確率はどれくらいのなのでしょう。10件に1件もないのではないでしょうか。100件に1件でしょうか。だとすれば、真犯人が現れる1件ごとに100件もの冤罪が隠されていることになります。
誤判は避けることはできません。冤罪もまた避けることはできません。あってはならないことですが、常にありうることです。冤罪で死刑になることもまた避けられない。それが死刑制度の持つ一つの側面です。私たちの社会はこれを許容しています。私たち自身が、私たちの愛する人が、誤判によって、無実で死刑になることを、私たち自身が容認している、それが死刑制度です。
「人間ひとりの命は全地球よりも重い」と訴えながら「私はわらじがぬがれない」と叫び続けながら、古川泰龍師は「生命への畏敬」を実践されました。
「人間ひとりの命は全地球よりも重い」と私もまた訴えます。
私たちの社会は、10人の命を救うため、百人の命を救うため、全国民の命を救うため、全地球を救うため、今一人の人間の命を奪う、そう説明して来ました。人間の命を天秤にかけて、数で、地位で、出生で、その守られるべき命と奪われるべき命の選別を正当化してきました。
そうでしょうか。目の前に息づくたったひとりの人間の命をも救うことのできない社会に何を期待できるでしょうか。憎しみの捌け口として、あるいは、社会不安を先送りするために、人間の命を奪うための詭弁としか思えません。
その奪われるべきとされる人間の命は、あらゆる場面で徹底的に手段や機会に見放されてきた命です。出生の環境に始まり、道徳的な手段に恵まれず、思い止まりの機会を得ることができず、やり直しのための手立てさえも与えられることがなかった。貧困と孤立と絶望の中で犯した罪に、今は悔い悲嘆の真っ只中にある、そんな命かもしれません。
4 デッドマン・ウォーキング・ノーモア
シスター・へレン・プレジャンは「デッドマン・ウォーキング」という映画の原作者です。この映画でスーザン・サランドンはアカデミー主演女優賞を、ショーン・ペンはベルリン国際映画祭で男優賞を、それぞれ受賞しました。
このシスター・へレン・プレジャンもまた、古川泰龍師の「生命への畏敬」の実践に共鳴したひとりです。「デッドマン・ウォーキング・ノーモア」と題して、この福岡事件再審請求を支援してくれています。死刑廃止とともに福岡事件の真相究明を求め、署名とキャンペーンに参加し行動をともにしてきました。
また、九州大学刑法学教授の内田博文さんは、この再審請求手続きにおいて、刑事訴訟法学の立場から専門的な意見書を作成してくださいました。さらに、奈良女子大学心理学教授の浜田寿美男さんは供述心理学の立場から専門的な意見書を作成してくださいました。いずれも、私たちの国で望みうる最高度の専門性と責任性に裏打ちされた意見書となりました。
そして、トシ・カザマさんは写真家として、アメリカの死刑の実態を伝えながら、福岡事件の支援と死刑制度の問題点を分かりやすく伝えてくださいます。「家栽の人」の原作者毛利甚八さんは、漫画原作者として少年の更生にかかわり続けた経験をもとに、人間が自らの罪から回復してゆくときの輝きを伝えながら、福岡事件の真相究明と死刑廃止を訴えてくださいます。
さて、今日おいでいただいています、鯉沼広行さん、金子由美子さん、ウォンウィンツァンさんはいずれも芸術家として、横笛であり、ピアノの楽曲を奏でながら、このキャンペーンを毎年支えて下さっています。
そして今日のシンポジスト、森達也さん、落合恵子さん、土井たか子さん、宮本弘典さんたちが、命のかかわりをめぐって、人間の命の重さと尊さについて、話をしてくださるものと思います。
死刑制度は誰のものでしょう。私たちは統治する立場にあると同時に統治される立場にあります。ですから、私たちは間接的に死刑をする立場にあるとともに潜在的に死刑を執行される立場にあります。命を奪うものとして、同時にまた命を奪われるものとして、今、現に、私たちの国の死刑制度にかかわっています。
私たちは主体であるとともに客体をもかねる存在として、今ある死刑制度を考え抜かなければなりません。そして、そこに「生命への畏敬」が実践されることを望みます。
私たちは、残虐極まりない殺人犯罪を見たときに、行為者に対する憎しみに狂うかもしれません。その人間を八つ裂きにもしたいと、心から願うかもしれません。私たちは心切り裂く無慈悲な行いに絶望し、その人間の命をいけにえとするかもしれません。
でもそれもまた無慈悲なことととして、私たちは、目の前の人間の息づかいに、その回復を願い希望の火を灯すことのほうを選ぶかもしれません。
さらには、無実の死刑囚を救えなかった社会の絶望を自らの絶望と感じながら、無実の死刑囚を救うことのできる社会への変革を希求するかもしれません。
福岡事件は、「生命への畏敬」という考えに最も高い価値を見出し、私たちの社会を再構成しようとする営みであり、人間ひとりひとりの命の回復を第一義に考えて、自らの活動をも収斂させようとする試みでもあります。
古川泰龍師の「生命への畏敬」の実践に共感した、古くからのご友人や学生さんたちを含み、多様な専門家の協力を仰ぎながら、世界に広がる多数の支援の方々とともに、無実の死刑囚西武雄の真相究明と死刑廃止を希求する取り組みです。
5 人間の命は命と命のかかわりのなかにある
ハンセン病療養所星塚敬愛園に住む上野政行さんは、もう85歳になられます。
ハンセン病患者隔離政策の被害者であり、歌人でもあります。
「咎人の如く吾は強いられ収容されき五十七年前」
この歌は2000年12月8日、熊本地方裁判所のハンセン病訴訟最終弁論で詠まれた歌です。上野さんは20歳の時に強制収容されて、もう65年間が過ぎました。
西武雄と手紙での親交を深め、梵鐘の寄贈を受けた方は山中吾郎さん。山中吾郎さんは星塚敬愛園に寺院を建て、西武雄の梵鐘を祀りました。上野政行さんは、山中吾郎さんの遺志をついで、会ったこともない無実の死刑囚西武雄の供養と彼が寄贈した梵鐘の世話をされています。
「強いられて受けし断種を老いて思う吾を限りの命かなしも」
そう歌い、上野さんは今もこの敬愛園で、西武雄の冤罪の晴れる日を祈りをもって待ち望んでおられます。
無実の死刑囚西武雄と誤った患者隔離政策によって終生隔離を強いられたハンセン病患者の方々との間に命と命のかかわりがありました。それは、私たちの見えないところで、私たちの大きな過ちの向こう側で、人間の肉体や精神をこえて、命と命のかかわりが存在し、「生命への畏敬」が実践されました。今もそれは息づいています。このような命と命のかかわりの中にこそ、人間の命のほんとうの価値があるのではないでしょうか。
「叫びたし 寒満月の 割れるほど」
西武雄のこの悲嘆は、私たちの悲嘆であり、社会の悲嘆です。
「誤判 わが怒りを 天に雪つぶて」
西武雄の絶望は、私たちの絶望であり、社会の絶望です。
「無実で死刑にならない世の中を 私は信じたい、証明したい でなければ、私は救われない、生きられない 私はわらじがぬがれない」と歌った、古川泰龍師であり、山中吾郎さん、上野政行さんの雪冤の祈りこそ、西武雄の希望です。
西武雄の梵鐘はハンセン病療養所に終生隔離された山中吾郎さんであり、上野政行さんの希望です。
私たちの希望もまた同じだと思います。私たちが、今ここから、福岡事件を通して、無実の死刑囚であり、終生隔離を強いられた方々と、さらには私たちともども、立場や党派、考えや思い、伝統や感情の違いを超えた、さらには肉体も精神も超えた、命のかかわりを紡ぐことが、私たちの希望であり、私たちの社会へ希望をつなぐものだと思います。
今日はたくさんの方々にお集まりいただきました。私の話はこれくらいにして、皆様、お待ちかねの多士済々の面々によるチャリティートーク&ライブを存分に楽しんでいただきたいと思います。ありがとうございました。
以上
弁護士である前に、人として福岡事件に向き合う八尋さんの姿勢・思いが強く打ち出された、感動的な文章です。当日来られなかった方は是非とも、また会場で聴かれた方も、今一度目を通していただければと思います。
福岡事件 講演原稿 於:東京YMCA青少年センター
弁護士 八尋光秀
1 ハンセン病療養所にある梵鐘
皆さんはハンセン病療養所をご存知でしょうか。私たちの国に国立ハンセン病療養所 は全部で13園あります。青森、宮城、群馬、東京、静岡に各1園づつ。岡山に2園、香川、熊本に各1園、鹿児島、沖縄にはそれぞれ2園です。このうち鹿児島県鹿屋市にあるハンセン病療養所を星塚敬愛園といいます。
かつて、ここは星塚村と称し、郵便局も床屋も売店もある、選挙も火葬も葬儀もできる療養所でした。園の周囲には、杉の生垣めぐらし、あるいは深い側溝を掘り、その中に水を湛え、茨を活けて完璧な隔離の塀としました。巡視による巡回があり、外出には許可を要し、無許可での外出は逃亡とみなされて、監禁懲罰の対象としました。身ごもった胎児はすべて抹殺され、断種・堕胎を結婚の条件としました。
患者の治療や介護だけではなく、水や食料や燃料の確保からそのほかの生活必需品の手当てまで、患者作業によって賄われました。
患者隔離は絶対で、入所の時に、生まれ育った生活からも親戚や知人、友人、恋人であり家族からも、終生のものとして、線を引くように、断絶を強いました。それは、思春期前の子どもであっても、家族を持つ大人であっても同じ扱いでした。
やがて死を迎えるとき、看取る者は医師ではなく看護者でもない。家族でもなく友人でもない。同じ隔離の仲間だけで寂しく見送りました。火葬も葬儀もまた仲間の手によるものでした。弔うものは、自らの生と死の孤独を、そのつど突きつけられました。こうやって、ひとり寂しく死んでゆくのだと何度も何度も。そんな絶望の隔離の中で、自らの命を閉じる仲間も少なくありませんでした。
ハンセン病療養所は、どこまでも静謐で、人間の悲しみと孤独と絶望が澱をなして深く沈んでいるようです。
そのハンセン病療養所星塚敬愛園の中庭にある寺院のとなりに、梵鐘が吊るされています。朝と夕べに撞木で突く鐘の音が園内に響きます。その梵鐘は昭和32年に寄贈されたものです。この鐘の音が入所者の人々に生きる希望の火を灯し続けて、もう50年。今でも朝夕、この鐘が鳴り響いています。
この梵鐘の寄贈者は、この園に来たこともなければ、この園に隔離された人たちにあったこともありません。ましてや、ハンセン病療養所が行ってきた患者隔離による非人道的なまた未曾有とも言うべき人権侵害の数々、そしてそれがもたらした人間の悲しみに、責めを負うべき立場にもありませんでした。
ただ、無実を叫び続けるひとりの死刑囚。自らと同じ悲しみを強いられた人間として深く共感した、冤罪死刑囚です。彼は、無実の死刑囚として獄中で絶望の中にあってすでに10年。書画を描き、写経を続けていました。この積み上げた修練の作品を世に出して、梵鐘購入の資金としました。
この梵鐘の寄贈者こそ、無実の死刑囚こそ、西武雄です。福岡事件において、誤った裁判により首謀者とされ、死刑を執行された、西武雄その人です。西の悲嘆と孤独と絶望がハンセン病療養所星塚敬愛園に梵鐘を寄贈させました。
そのハンセン病療養所星塚敬愛園の人達もまた、この冤罪死刑囚の濡れ衣を雪ぐため、僅かな作業賃を出し合って、支援をし続けました。今もなお、隔離の住処からすでに執行されたこの無実の死刑囚の雪冤を心から願っています。
私たちは、彼らの深い悲嘆と孤独と絶望に、余りにも冷淡でした。冷酷ともいうべきでしょう。
ハンセン病療養所に勤めた医師であり、看護者であり、職員は自分の気ままな気分で人間を隔離し、堕胎し、断種を強いてきたわけではありません。私たちの誤った意識を実現するために、法律や政策に忠実に、かつ自らに課された職務に誠実に、ひたすら未曾有の人権侵害を繰り返してきたのです。
裁判官や検察官あるいは死刑執行人は、自分勝手に死刑を求刑し、死刑判決を下し、死刑を執行しているのではありません。犯罪に対する私たちのやり場のない憎しみの捌け口を求めるため、その便利な手足として、有罪を宣告し、死刑を命じてきました。
私たちこそが、紛れもなく、ハンセン病患者の人生を奪い、西武雄に死刑を執行した。その私たちは、彼らの悲嘆や孤独や絶望に目を瞑り、あるいは眼をそむけ、素知らぬふりをして、無邪気に振舞っていました。それが冷酷なことだなあと思うわけです。
西武雄は終生隔離を強いられたハンセン病患者に、ハンセン病患者は無実の死刑囚西武雄に、その悲嘆と孤独と絶望を互いに見出し、希望の火を灯し続けあって、自らの生を全うしようとしました。
冤罪再審福岡事件のもつ意味は、ハンセン病療養所のもつ歴史的な意味ともつながって、人間の命のありか、「命と命のかかわり」のなかにこそ見出されるものだと思います。
2 シュバイツァー博士の遺髪
私は、1995年10月に初めて星塚敬愛園に入りました。後に国賠訴訟の原告番号1番となられた、島比呂志さんに呼ばれたからです。国が「らい予防法」を廃止しようとしているのに、人権に深いかかわりを持つべき弁護士、弁護士会がハンセン病問題について一片の謝罪もせず法曹の責任を総括すらしないことは、無責任に過ぎると。
1998年7月に「らい予防法」違憲国家賠償請求訴訟を熊本地方裁判所に提訴しました。この訴訟は、後に2001年5月11日の全面勝訴判決、同月23日国の控訴断念を経て、ハンセン病問題を全面解決へと向かわせました。
私は、島さんに求められて星塚敬愛園に立つまで、「らい予防法」を知りませんでした。ハンセン病療養所を見たことがありませんでした。
私は、その後、何度も星塚敬愛園を尋ね、入所者の方々のお話を伺いました。その折々、幾度かは、その梵鐘の前に、謂われを知らず、ひとり頭を垂れていました。
古川泰龍師が私を尋ねてこられたのは、ハンセン病訴訟を提起した1年後のことです。私は、古川師にお会いするまで、ハンセン病問題と同様、福岡事件のことについて、これっぽっちの知識さえ持ち合わせて居ませんでした。
はじめは、お会いすることさえもお断りをいたしました。刑法学を専攻される大学教授のご紹介で、会うだけでも会ってというお願いでした。しかし、会えば断りづらくなります。当時の私はハンセン病訴訟とのかかわりで手一杯でした。
「このままでは裁判記録をいつ廃棄されるか分からない。廃棄させないために、今、再審請求する予定だと検察庁に通知し、記録の謄写だけはしておく必要がある。それだけでもいいので手伝って欲しい。」と説得されました。さすがに、これを断ることはできませんでした。古川泰龍師にお会いすることになりました。
古川泰龍師は生命山シュバイツァー寺と名乗られました。名刺を手に「あのシュバイツァー博士ですか。」といぶかしがる私に、その由来を語られました。
「シュバイツァー博士は「生命への畏敬」を説かれました。それは、あらゆる人間はひとりひとりそれぞれに意味のある、かけがえのない生命をもっている。どのようなときでも、どのような場面でも、ひとりひとりの人間の生命を一番に優先すると言う考えです。私はこの「生命への畏敬」という思想を宗派を超えて伝えて行きたい。そんな思いを込めて、シュバイツァー博士のご遺髪を祀り、生命山シュバイツァー寺を開山しました。」そうお教えいただきました。
さらには、かの星塚敬愛園に梵鐘を寄贈したものが無実の死刑囚である西武雄であり、福岡事件において正されるべき真実は死刑囚として命を奪われたその西武雄の無実であるとのことでした。
人間が絶望の極みの中にあって、互いに命のかかわりを深める営みが、希望を芽生えさせたことを知りました。そのことを私の立場で受け継ぎ伝えることが、私にできる「生命への畏敬」の実践であるということを理解しました。
私は、ハンセン病訴訟がひとつの成果を得た段階に至れば、福岡事件の再審請求に取り掛かることをお約束せざるを得ませんでした。
3 私はわらじがぬがれない
私はこれまで、多くの医療過誤訴訟やハンセン病訴訟、薬害HIV訴訟、薬害肝炎訴訟を追行してきました。また、鹿児島夫婦殺人事件をはじめとする数件におよぶ無実の被告人であり、無実の受刑者の訴訟を担ってきました。
ハンセン病訴訟では患者隔離政策によって命と人生を奪われた人たち。薬害HIV訴訟や薬害肝炎訴訟では経済利益を優先させた薬事政策や企業活動によって命を人生を奪われた人たち。さらには誤った刑事裁判や医療過誤によって、いずれも、かけがえのないその命と人生とを奪われた人たち。
私はそういう人たちが裁判と言う場で、奪われた命や人生を取り戻すためのスタートをきる。そのことを支え、勇気づけ、ときに提案し、命を人生を奪われた人間の悲嘆であり、孤独であり、絶望にかかわり、その回復の作業に身を置いてきました。
裁判は人間の活動の中でもとても限られたひとつの場面です。私は、シュバイツァー博士であり、それを受け継いだ古川泰龍師の「生命への畏敬」という思想に共感しました。裁判という特殊な場面において「生命への畏敬」を芯に据えて実践することを考えました。
古川泰龍師は「私はわらじがぬがれない」といいます。
「わらじをはいて 十年 無実の死刑囚を救うため
わたしは ひとり ひとり
街を 村を 訴え 叫び 歩きつづけた
一億もの人間がいるのだ
無実の死刑囚を孤立させてはならない
二十年先か 三十年先いつか
みんなが知って救い出してくれる
わたしはそれを信じて 今日も 明日も 歩く
たったひとりのいのちすら 守れない世の中を 私は信じることができない
無実で死刑にならない世の中を 私は信じたい、証明したい
でなければ、私は救われない、生きられない 私はわらじがぬがれない」と。
そう決意を表明された4年後、西武雄は処刑されました。それから20年余を経て、古川泰龍師は厚さ10センチを越えるガリ版刷りで製本された、この「真相究明書、9千万人のなかの孤独」と題する西武雄の再審請求書を手にして、私の前に現れられました。
冤罪は幾らでもあります。最近でも、いくつかの無罪事件が見つかりました。真犯人が現れたというのです。富山の氷見事件では、強姦事件で無実のタクシーの運転手さんが裁判で有罪とされ刑務所に入っていました。そこに真犯人が表れました。宇都宮でも同じ様な事件がありました。冤罪で真犯人が現れる確率はどれくらいのなのでしょう。10件に1件もないのではないでしょうか。100件に1件でしょうか。だとすれば、真犯人が現れる1件ごとに100件もの冤罪が隠されていることになります。
誤判は避けることはできません。冤罪もまた避けることはできません。あってはならないことですが、常にありうることです。冤罪で死刑になることもまた避けられない。それが死刑制度の持つ一つの側面です。私たちの社会はこれを許容しています。私たち自身が、私たちの愛する人が、誤判によって、無実で死刑になることを、私たち自身が容認している、それが死刑制度です。
「人間ひとりの命は全地球よりも重い」と訴えながら「私はわらじがぬがれない」と叫び続けながら、古川泰龍師は「生命への畏敬」を実践されました。
「人間ひとりの命は全地球よりも重い」と私もまた訴えます。
私たちの社会は、10人の命を救うため、百人の命を救うため、全国民の命を救うため、全地球を救うため、今一人の人間の命を奪う、そう説明して来ました。人間の命を天秤にかけて、数で、地位で、出生で、その守られるべき命と奪われるべき命の選別を正当化してきました。
そうでしょうか。目の前に息づくたったひとりの人間の命をも救うことのできない社会に何を期待できるでしょうか。憎しみの捌け口として、あるいは、社会不安を先送りするために、人間の命を奪うための詭弁としか思えません。
その奪われるべきとされる人間の命は、あらゆる場面で徹底的に手段や機会に見放されてきた命です。出生の環境に始まり、道徳的な手段に恵まれず、思い止まりの機会を得ることができず、やり直しのための手立てさえも与えられることがなかった。貧困と孤立と絶望の中で犯した罪に、今は悔い悲嘆の真っ只中にある、そんな命かもしれません。
4 デッドマン・ウォーキング・ノーモア
シスター・へレン・プレジャンは「デッドマン・ウォーキング」という映画の原作者です。この映画でスーザン・サランドンはアカデミー主演女優賞を、ショーン・ペンはベルリン国際映画祭で男優賞を、それぞれ受賞しました。
このシスター・へレン・プレジャンもまた、古川泰龍師の「生命への畏敬」の実践に共鳴したひとりです。「デッドマン・ウォーキング・ノーモア」と題して、この福岡事件再審請求を支援してくれています。死刑廃止とともに福岡事件の真相究明を求め、署名とキャンペーンに参加し行動をともにしてきました。
また、九州大学刑法学教授の内田博文さんは、この再審請求手続きにおいて、刑事訴訟法学の立場から専門的な意見書を作成してくださいました。さらに、奈良女子大学心理学教授の浜田寿美男さんは供述心理学の立場から専門的な意見書を作成してくださいました。いずれも、私たちの国で望みうる最高度の専門性と責任性に裏打ちされた意見書となりました。
そして、トシ・カザマさんは写真家として、アメリカの死刑の実態を伝えながら、福岡事件の支援と死刑制度の問題点を分かりやすく伝えてくださいます。「家栽の人」の原作者毛利甚八さんは、漫画原作者として少年の更生にかかわり続けた経験をもとに、人間が自らの罪から回復してゆくときの輝きを伝えながら、福岡事件の真相究明と死刑廃止を訴えてくださいます。
さて、今日おいでいただいています、鯉沼広行さん、金子由美子さん、ウォンウィンツァンさんはいずれも芸術家として、横笛であり、ピアノの楽曲を奏でながら、このキャンペーンを毎年支えて下さっています。
そして今日のシンポジスト、森達也さん、落合恵子さん、土井たか子さん、宮本弘典さんたちが、命のかかわりをめぐって、人間の命の重さと尊さについて、話をしてくださるものと思います。
死刑制度は誰のものでしょう。私たちは統治する立場にあると同時に統治される立場にあります。ですから、私たちは間接的に死刑をする立場にあるとともに潜在的に死刑を執行される立場にあります。命を奪うものとして、同時にまた命を奪われるものとして、今、現に、私たちの国の死刑制度にかかわっています。
私たちは主体であるとともに客体をもかねる存在として、今ある死刑制度を考え抜かなければなりません。そして、そこに「生命への畏敬」が実践されることを望みます。
私たちは、残虐極まりない殺人犯罪を見たときに、行為者に対する憎しみに狂うかもしれません。その人間を八つ裂きにもしたいと、心から願うかもしれません。私たちは心切り裂く無慈悲な行いに絶望し、その人間の命をいけにえとするかもしれません。
でもそれもまた無慈悲なことととして、私たちは、目の前の人間の息づかいに、その回復を願い希望の火を灯すことのほうを選ぶかもしれません。
さらには、無実の死刑囚を救えなかった社会の絶望を自らの絶望と感じながら、無実の死刑囚を救うことのできる社会への変革を希求するかもしれません。
福岡事件は、「生命への畏敬」という考えに最も高い価値を見出し、私たちの社会を再構成しようとする営みであり、人間ひとりひとりの命の回復を第一義に考えて、自らの活動をも収斂させようとする試みでもあります。
古川泰龍師の「生命への畏敬」の実践に共感した、古くからのご友人や学生さんたちを含み、多様な専門家の協力を仰ぎながら、世界に広がる多数の支援の方々とともに、無実の死刑囚西武雄の真相究明と死刑廃止を希求する取り組みです。
5 人間の命は命と命のかかわりのなかにある
ハンセン病療養所星塚敬愛園に住む上野政行さんは、もう85歳になられます。
ハンセン病患者隔離政策の被害者であり、歌人でもあります。
「咎人の如く吾は強いられ収容されき五十七年前」
この歌は2000年12月8日、熊本地方裁判所のハンセン病訴訟最終弁論で詠まれた歌です。上野さんは20歳の時に強制収容されて、もう65年間が過ぎました。
西武雄と手紙での親交を深め、梵鐘の寄贈を受けた方は山中吾郎さん。山中吾郎さんは星塚敬愛園に寺院を建て、西武雄の梵鐘を祀りました。上野政行さんは、山中吾郎さんの遺志をついで、会ったこともない無実の死刑囚西武雄の供養と彼が寄贈した梵鐘の世話をされています。
「強いられて受けし断種を老いて思う吾を限りの命かなしも」
そう歌い、上野さんは今もこの敬愛園で、西武雄の冤罪の晴れる日を祈りをもって待ち望んでおられます。
無実の死刑囚西武雄と誤った患者隔離政策によって終生隔離を強いられたハンセン病患者の方々との間に命と命のかかわりがありました。それは、私たちの見えないところで、私たちの大きな過ちの向こう側で、人間の肉体や精神をこえて、命と命のかかわりが存在し、「生命への畏敬」が実践されました。今もそれは息づいています。このような命と命のかかわりの中にこそ、人間の命のほんとうの価値があるのではないでしょうか。
「叫びたし 寒満月の 割れるほど」
西武雄のこの悲嘆は、私たちの悲嘆であり、社会の悲嘆です。
「誤判 わが怒りを 天に雪つぶて」
西武雄の絶望は、私たちの絶望であり、社会の絶望です。
「無実で死刑にならない世の中を 私は信じたい、証明したい でなければ、私は救われない、生きられない 私はわらじがぬがれない」と歌った、古川泰龍師であり、山中吾郎さん、上野政行さんの雪冤の祈りこそ、西武雄の希望です。
西武雄の梵鐘はハンセン病療養所に終生隔離された山中吾郎さんであり、上野政行さんの希望です。
私たちの希望もまた同じだと思います。私たちが、今ここから、福岡事件を通して、無実の死刑囚であり、終生隔離を強いられた方々と、さらには私たちともども、立場や党派、考えや思い、伝統や感情の違いを超えた、さらには肉体も精神も超えた、命のかかわりを紡ぐことが、私たちの希望であり、私たちの社会へ希望をつなぐものだと思います。
今日はたくさんの方々にお集まりいただきました。私の話はこれくらいにして、皆様、お待ちかねの多士済々の面々によるチャリティートーク&ライブを存分に楽しんでいただきたいと思います。ありがとうございました。
以上