
甲斐よしひろが自身の曲作りについて語る際、彼は一貫して「俺自身からこぼれ落ちたカケラが歌になる」とか「熱い想いが歌になる」とか「生き方や生き様、本音の部分が歌に反映される」とかいった発言をしている。しかし既に何度も書いているように、そうした発言が繰り返されている割には、甲斐の人生論なり人生観、もしくは実体験がリアリティを伴って曲になっている例はそれほど多いとは思えない。
忌野清志郎や尾崎豊といったソングライターが実体験を伴ったノンフィクション的と言っていい曲作りをしていることは明白だろう。だが、彼らの描く「私小説的むき出し感の強い」詞の世界と甲斐よしひろのそれとを比べた場合、甲斐の作品は明らかにフィクションと思われるモチーフやシチュエーションが多い。つまり、冒頭の発言に裏付けられた作曲法(厳密には作詞法か)は決して甲斐バンドの作品作りにおいての基本方針ではないと言っていいくらいなのだ。
もちろん例外となる曲はいくつかある。「安奈」「漂泊者」がそうだろうし、「破れたハートを売り物に」「観覧車」もそうだろう。また「翼あるもの」は実体験を描いたものではないが、彼のあの時期の人生観だろうし、精神論を歌った曲といっていいだろう。しかし例えば「かりそめのスウィング」「ちんぴら」「ランデヴー」などは明らかに創作と言っていい歌詞だし、「HERO」「港からやってきた女」なども同様だ。また、先に挙げた「安奈」「漂泊者」「破れたハート~」「観覧車」といった曲にしても、歌詞を見ればそのディテイルは作られたものであることは明らかだ。清志郎の「スローバラード」における「市営グラウンドの駐車場」といった実体験におけるモチーフを歌詞に反映させるそれとは、明らかに違う姿勢がそこに見うけられる。念のために書いておくが、これは何も、真実を描いたノンフィクションの方が良くてフィクションは嘘つきだから良くない、といった比較ではないし、真実か嘘かということと作品の質が高いか低いかということとは、何の関係もない。ここで押さえておきたいのは、甲斐よしひろの発言と、実際に生み出された作品には、原則的には隔たりがあるということだ(もちろん曲作りを始めるきっかけやイマジネーションが実体験に関連していないとは言い切れないが、そもそもそれがフィクションであれノンフィクションであれ、作者にとってある種の実感のともなう出来事や想いというものが、物作りのとっかかりになるものではないだろうか)。
実際、「英雄と悪漢」で既に確立された甲斐バンドの歌の世界は、ノンフィクションの持つそれではなくて、フィクションゆえに迫ってくるリアリティの強さである。「リアル」を歌ったからといって、決して「リアリティ」をもって受け手に届くわけではないのだから。ただ、甲斐バンドの作品群はバンドがキャリアを深めて行くにつれ、その創作性・虚構性を強くし、逆に元来持っていたリアリティを弱めていった。それによって、甲斐バンドの作品世界と、甲斐の作曲法について語る自身の発言はさらに乖離していくことになるのだが、まあそれはまだまだ先の話だ。
さて、「ガラスの動物園」である。この作品集は、前述した観点から考えると、アルバム単位では唯一の例外となる、ノンフィクション性の強い1枚だろう。私小説性が強い、と言ってもいいかもしれない(あえてもう一枚挙げるとすれば、「破れたハートを売り物に」だろうか)。特に「らせん階段」で始まり、「東京の一夜」から「昨日鳴る鐘の音」で終わるA面は、東京を活動の拠点としたバンドのいちヴォーカリスト、いちソングライターとして、故郷(福岡)と、自分と、東京との距離感を何度も確かめているようにすら感じられる。と同時に、「新宿」と「東京の一夜」に挟まれる形で聴ける「テレフォン・ノイローゼ」やB面の流れは、「東京に敷石がないショック」から導きだされた「街(東京)に蠢く男と女のかけひき」という路線を、ある程度意図的に試していた感もあるのだけれど(つまり、全編べったり私小説路線、というわけでもないというか)。レコーデイング期間が当時としては異例の長さ(6ヶ月を要した)ということだが、それは恐らく、甲斐よしひろの私的な歌世界をいかにバンドとしてまとめるかに腐心した結果ではないだろうか。いずれにしろ、甲斐よしひろのパーソナリティが強く打ち出された結果、「英雄と悪漢」と比べるとサウンド的・バンド的ダイナミズムにおいて弱いと感じられる面もある。それが逆にアルバム的まとまり感を強くさせているのだろう。実際、本作の評価は高いし、ほとんどの収録曲が佳作、良作と言っていい。
ちなみに、各メンバーの持った煙草の火の軌跡を生かしたジャケット写真の元ネタはストーンズの「Black And Blue」の中ジャケ。「英雄と悪漢」裏ジャケの「December's Children」に続くストーンズだけど、音楽面におけるストーンズからの影響や引用はここでも少なく、むしろCCR的要素が多く見られる。甲斐よしひろはアマチュア時代にCCRの曲を多くカバーで演っていたという。この辺りも、本作がバンド色よりもパーソナル色、私小説的色が強くなっていることと何か関連があるのかもしれない。












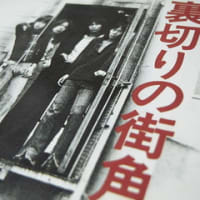


※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます