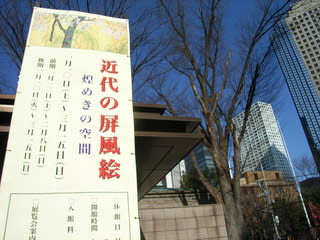久方ぶりに、ひまわりを見に行った。といっても屋外ではない。ゴッホの絵だ。新宿高層ビル街にある損保ジャパン東郷青児美術館に行けばいつでも見ることができる。
いつ見ても燦然と輝いている。この絵画が落札された当時は、その金額の高さゆえに非難を浴びたこともあったが、おかげで私たちはいつでもこの名画に会うことができるのも事実だ。その両側に、モネとゴーギャンが並んでいるが、ひまわりの圧倒的な存在感の陰に隠れて目立たないのがかわいそうだ。せめて、ゴーギャンの絵が、「アリスカンの並木路」ではなくてタヒチ時代の作品であれば、かなり違っていただろうけど…
ところで、今回の特別展はこの美術館主催による選抜奨励展だった。現代の作家、それも新進、中堅どころまでの人たちの作品なので知っている人はいない。数年前に来たときはほとんど素通りだった。
今回は何点か眼に留まる作品があった。大胆な構図と色使いの「花泥棒」や独自の描法で色を出していた「棚田」などだ。また、最近のアニメブームを反映してか、絵画というよりはイラストあるいはグラフィックデザインに近い系統が出品されていたのが目立った。これらの作品を見て瞬時に思い浮かんだのが「デジカメのプリントみたい」という言葉だ。
日本画と洋画の区別が曖昧になってきたのと同様に、これらの分野も境界線がいずれなくなっていくのだろうということを予感させる展覧会だった。
いつ見ても燦然と輝いている。この絵画が落札された当時は、その金額の高さゆえに非難を浴びたこともあったが、おかげで私たちはいつでもこの名画に会うことができるのも事実だ。その両側に、モネとゴーギャンが並んでいるが、ひまわりの圧倒的な存在感の陰に隠れて目立たないのがかわいそうだ。せめて、ゴーギャンの絵が、「アリスカンの並木路」ではなくてタヒチ時代の作品であれば、かなり違っていただろうけど…
ところで、今回の特別展はこの美術館主催による選抜奨励展だった。現代の作家、それも新進、中堅どころまでの人たちの作品なので知っている人はいない。数年前に来たときはほとんど素通りだった。
今回は何点か眼に留まる作品があった。大胆な構図と色使いの「花泥棒」や独自の描法で色を出していた「棚田」などだ。また、最近のアニメブームを反映してか、絵画というよりはイラストあるいはグラフィックデザインに近い系統が出品されていたのが目立った。これらの作品を見て瞬時に思い浮かんだのが「デジカメのプリントみたい」という言葉だ。
日本画と洋画の区別が曖昧になってきたのと同様に、これらの分野も境界線がいずれなくなっていくのだろうということを予感させる展覧会だった。