早稲田大学の篠田徹さんは「労働運動を考える」(第12回労働調査セミナー②)という講演の中できわめて興味深いことを言っています。篠田さんは「労働運動の径路依存性と運動レパートリー」という独特な言葉を使われています。この独特な言葉は、「これまで私たちが培ってきたレパートリーの棚卸しをどれくらいできるか」という意味として表現している言葉です。篠田さんは、労働運動を考えるために、「これまで私たちが培ってきたレパートリーの棚卸しをどれくらいできるか」がこれからの運動に必要だというのです。
こうした考え方は、何も労働運動だけにかぎらないと思います。
私がかかわってきた反貧困運動のあり方はどちらかといえば、篠田さんの論文「企業別組合を中心とした民衆組合とは」で整理されていた「社会運動的労働組合論」(ソーシャルムーブメントユニオニズム)に近似していると考えます。
篠田さんは次のように言っています。
「我々は、昔こういうのをやっていたよね、あるいは、ひょっとしたらこれは一見新しく見えるけれど、昔やっていたこれに似ているかもねと、レパートリーという考え方を入れることによってこれからやろうとすることに対してある種の可能性が出てくる」
「あまりにも難しいことを我々はやろうとしているのじゃないか、あるいは、もしそうならば我々がこれまでやってきたものの中でこれを使ってこういうふうに少し変えたらいいじゃないかというような別の代替策も出てくる」(「労働運動について考える」)
篠田さんは論を進めていくために、「労働運動の可塑性」という言葉を使われます。労働運動が機能しなくなってきたからこそ、今まで培ってきたレパートリーを入れ込むことで、労働運動の機能回復が生じます。それが「労働運動の可塑性」です。しかし、「可塑性」は、柔軟な姿勢なくして起こらないのではないかと思います。
篠田さんは、『世紀末の労働運動』の中で次のように言っています。
「そもそも組合とは、近代の渦中において、社会のあるべき姿を模索する数々の思想的営為の所産の一つとして、この世に生を受けたものである。だとするならば、人と人との豊かな関係を創造することこそ、組合が追求すべき本質的な課題であろう。職場において、地域において、組合員が他者との有機的な関係のなかで生きることができるよう援助することが求められる。そのためにも、組合はこれまで以上に外部との多元的な関係の構築が迫られているといえる。」
反貧困運動は「100年に一度の危機」「100年に一度の運動」と言われましたが、その可能性をひめながら結果的に「100年に1度の運動」になりませんでした。ただ、もちろん、運動が終わったわけではありません。
ここから何を学ぶか、です。私はそう思っております。
篠田さんの論文は労働運動についての提案として書かれたものですが、私たちの運動とも通底する大切な視点があります。
当法人のホームページは以下をクリックするとご覧いただけます。
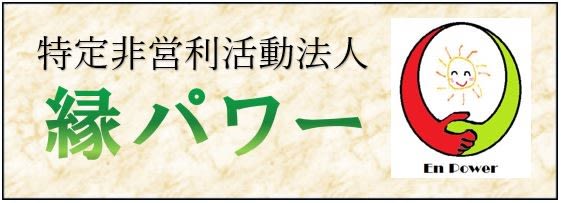
こうした考え方は、何も労働運動だけにかぎらないと思います。
私がかかわってきた反貧困運動のあり方はどちらかといえば、篠田さんの論文「企業別組合を中心とした民衆組合とは」で整理されていた「社会運動的労働組合論」(ソーシャルムーブメントユニオニズム)に近似していると考えます。
篠田さんは次のように言っています。
「我々は、昔こういうのをやっていたよね、あるいは、ひょっとしたらこれは一見新しく見えるけれど、昔やっていたこれに似ているかもねと、レパートリーという考え方を入れることによってこれからやろうとすることに対してある種の可能性が出てくる」
「あまりにも難しいことを我々はやろうとしているのじゃないか、あるいは、もしそうならば我々がこれまでやってきたものの中でこれを使ってこういうふうに少し変えたらいいじゃないかというような別の代替策も出てくる」(「労働運動について考える」)
篠田さんは論を進めていくために、「労働運動の可塑性」という言葉を使われます。労働運動が機能しなくなってきたからこそ、今まで培ってきたレパートリーを入れ込むことで、労働運動の機能回復が生じます。それが「労働運動の可塑性」です。しかし、「可塑性」は、柔軟な姿勢なくして起こらないのではないかと思います。
篠田さんは、『世紀末の労働運動』の中で次のように言っています。
「そもそも組合とは、近代の渦中において、社会のあるべき姿を模索する数々の思想的営為の所産の一つとして、この世に生を受けたものである。だとするならば、人と人との豊かな関係を創造することこそ、組合が追求すべき本質的な課題であろう。職場において、地域において、組合員が他者との有機的な関係のなかで生きることができるよう援助することが求められる。そのためにも、組合はこれまで以上に外部との多元的な関係の構築が迫られているといえる。」
反貧困運動は「100年に一度の危機」「100年に一度の運動」と言われましたが、その可能性をひめながら結果的に「100年に1度の運動」になりませんでした。ただ、もちろん、運動が終わったわけではありません。
ここから何を学ぶか、です。私はそう思っております。
篠田さんの論文は労働運動についての提案として書かれたものですが、私たちの運動とも通底する大切な視点があります。
当法人のホームページは以下をクリックするとご覧いただけます。
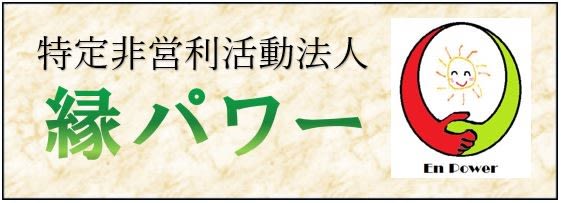




















※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます