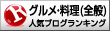・可視光線Visible radiation かしこうせん
唯一、人間の目に見える光として感知できる電磁波(波長の長い方から電波 100 μm 以上 ・光・X線・ガンマ線10 pm 以下など)のこととしています。波長領域は800nm(赤)~400nm(紫)であり、いわゆる可視光線の🌈虹の7色になります。波長の長短によって、赤から青紫まで色の感じ方が異なってくるようです。
可視光線は目の網膜に当たると、光が受容体の一種である錐体細胞という細胞に刺激を与え、 この刺激により、脳に信号を送り、視覚として感じる仕組みです。
波長の長いのが赤外線、紫より波長の短いものが紫外線で、範囲外どちらも目で見ることができない不可視光線と呼ばれています。
通常の虹の色が外側から赤、橙、黄、緑、青、藍、紫の順番で、副虹はその逆で内側から赤、橙、黄、緑、青、藍、紫となります。🌈虹は、空気中の水滴がプリズムとなって、太陽光の反射を受け、太陽光、ないし照明からの波長の違いによって色分けして見えjます。さまざまな波長の可視光線が混ざった状態では白色に見えるとしています。
晴れた空は青色、太陽の光は真上(付近)から入ってくるため、大気の層は薄く、散乱はあまり起きないので、このため、太陽は白色のままで、散乱された光で空は青くなるようです。
朝、夕の空の色が赤色になるのは、太陽から来た白色の光のうち、最も直進しやすい赤色の光が残ることによるといいます。太陽の光は斜めから入ってくるため、大気の層は厚く、散乱がたくさん起き、このことから、太陽は赤色になり、散乱されずに残った光で太陽周辺の空は赤くなるようです。夜は光がないので、やみ夜になります。
特にブルーライト(紫外線)は、肌の色の濃いタイプの人では日焼けの原因になりやすい光線です。
可視光線により、昼夜を識別し、交感神経、副交感神経の切り替えを行います。光によって生成、ないし抑制の脳内ホルモンのセロトニン、メラトニンなどに自然の色は、影響を与えます。例えば光合成を行う植物の葉は緑ですが、これは植物が光合成を行うためには、緑色の波長は必要ないため、反射させます。残りの6色は光合成に必要なため吸収しています。ゆえに私たちの目には緑色に見えるわけです。
いろいろの色フィルムを貼ったコップの中で、どの色の光がコップの中の植物に当たっているかは、みどり色のフィルムでは、太陽光のうち、みどり色以外の全ての色の光がフィルムによって吸収され、みどり色の光だけが通り抜けて植物にあたることになります。みどりの光は光合成に利用できない光ですが、みどり色のフィルターがどれくらい完全に他の色の光を通さないようにしているかによって、光合成の効率に影響します。他の色フィルムの場合でも同じように、フィルムの色以外の色の光がフィルターによって吸収されてしまいます。
海水は赤~黄色の光は良く吸収するので、深くなると青緑色に見えます。青色光は散乱されやすいので(空が青いように)、目には青色が強く感じられますが、実際は緑色の光強度も相当強いです。深いところに、緑色の光をよく吸収する紅藻類が生えているのも納得できます。紅藻類は通常赤色をして見えていますが、生育環境や深さによって緑色や茶色、青緑色などさまざまな色を帯びるのです。
また、暗闇に生きる生物の多くは、光を吸収する必要がなく、すべて反射させるため、白くなります。
反対に海藻などは、地上の植物よりも光が弱い環境で光合成を行うには、すべての光を吸収するため、黒くなります。
両極端の赤や青の色が出やすいのですが、朝日や夕日のタイミングで、稀に緑色の太陽が観られることがあり、グリーンフラッシュと呼ばれています。朝焼けの場合、東の空が赤く染まったと思ったらオレンジ色に変わり、やがて黄色くなり、次第に青く変化していきます。夕焼けはその逆になります。
虹では、まさに1.赤・2.橙・3.黄・4.黄緑・5.緑・6.青緑・7青が天候の変化により見られることになります。
ラジオ波・マイクロ波・赤外線・紫外線・X線・ガンマ線が不可視光線として知られます。
・ラジオ波:周波数30~300MHzの電磁波の総称で、高周波とも細胞を振動させ温めることで医療、美容の分野で利用しています。
・マイクロ波:周波数300MHz(メガヘルツ)~300GHz(ギガヘルツ)の電磁波の一種で波長1m~1mmで水分子を振動さ せた摩擦熱を利用し電子レンジに、携帯電話、テレビ放送、無線LANなど利用しています。
・赤外線:760~830nm以上の波長の光で、加熱調理機として食材にエネルギーを吸収させ 焼く事ができます。
・紫外線:波長が10 ~ 380 nm、360~400nm以下の波長の光で、日焼けの原因となります。260nm付近(100~280nm殺菌線)を照射し微生物を数秒で死滅に利用しています。医療や食品、水処理などの分野で幅広く用いられています。光は直進し、物体の裏側などの光の当たらない部分での殺菌効果は無いのでその使い方は限られます。
・X線:可視光線よりも波長が短く、波長が1 pm ~ 10 nm程度の電磁波で原子間を通り抜けることができレントゲン撮影などに利用しています。
・ガンマ線:γ線は10 pm よりも短い電磁波でラジウムより放出の放射線の一種で非常に透過力の強い光子であり、コンクリート壁や厚い銅板でないと遮断ができません。この高い透過力を利用し身体の奥の癌治療に、他に医療廃棄物や食品の滅菌などにも利用です。
電波、赤外線、可視光線、紫外線、X線、ガンマ線などはすべて電磁波に属し真空中を毎秒3×108mの速度で進行します。
可視光線も、📱スマートフォン・LEDライト(紫外光・可視光・赤外光とさまざまな波長で発光)の照明機器、💻ディスプレイ、📷カメラ、テレビなど身の回りの多くの製品に応用しています。また、太陽から地球に届く光のエネルギーのうち、約50%が可視光線の波長の光で、太陽電池では可視光線の光を効率よく吸収できる半導体を材料に使用しています。
可視光線のなどから出る光もブルーライト(青色光)と呼ばれる青色の光線も含み紫外線の次に波長の短い光で、エネルギーが強いため、目の奥まで届き目の疲れを招いています。
太陽光は6%の紫外光と50%の可視光、44%の赤外光の集まったものです。
朝焼けや夕焼けの観察していると朝焼けは、🌅日の出と共に東の空が赤く染まり次第にオレンジ色に、やがて黄色くなり、次第に青く変化していくようです。夕焼けはその逆で、この色の変化って「虹色」の順になります。朝焼け、夕焼けの刻々と変わる空の色は空気が澄んでくる時期では、より鮮やかに感じられます。
朝焼けは大気中を通る太陽光の距離が一番長くなるため、散乱しにくい赤い光で空を照らします。日が昇るにつれて波長が少しずつ短くなるオレンジ色、そして黄色が優勢になって空の色が変化しています。
朝焼け、夕焼けの空はなぜ赤くなるのか? 空は「虹色」の順に変化する - ウェザーニュース (weathernews.jp)
人間の目は、明るいところでは555nm、暗いところでは507nmの波長に対してもっとも感度が高くなる、つまり「見えやすくなる」と言われています。これらの波長にあたるのが明るい緑、黄緑としています。 このことにより、緑が他の色より人にとっては知覚しやすい目に優しい色だということがいわれています。可視光線により、この範囲内での、昼夜を識別し、交感神経、副交感神経の切り替えを行なっていることになります。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。