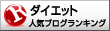◎ビタミンD Vitamin D びたみんでー
国民健康栄養調査では、カルシウムの摂取状況が推奨量を下回っている傾向にあり、その吸収を助けるビタミンDを必要としています。カルシウムとリンの代謝に関わり、それらの吸収と骨への沈着を促(うなが)す役割をしています。石灰化Calcificationに関係するSterolの代謝物であることからカルシフェロールCalciferolの化学名です。脂溶性のビタミンであり不足することによって骨粗鬆症、骨軟化症、くる病など骨の形成不良に陥ることになります。ビタミンDには、D2(エルゴカルシフェロールErgocalciferol)、D3(コレカルシフェロールCholecalciferol)、D4、D5、D6、D7の6種類が存在しその総称としてビタミンDと称しています。主にD2、D3が重要です。D1はD2とルミステロールとの混合物であることがわかり現在では存在していません。
1927年にドイツのヴィンダウスAdolf WindausとローゼンハイムO.Rosenheim、ウェブスターT. A. Websterがエルゴステロールが食品中のビタミンDのもととなる物質らしいと推定しています。その翌年にヴィンダウスは3種類のビタミンDを分離させました。2つは紫外線照射した植物ステロールから分離したもので、それぞれビタミンD1、D2としたのです。もう1つは紫外線照射した皮膚から取り出したビタミンD3です。 1931年に イギリスのアスキューF. A. Askewによって紫外線を照射した食品中のビタミンD活性がみられビタミンD2の構造が明らかにされて、これが前駆体分子のエルゴステロールからできることがわかっています。1936年には、ヴィンダウスによって7-デヒドロコレステロールの分子を合成し、それに紫外線を当ててビタミンD3に転換させることができました。この発見によってビタミンDを大量に安価に合成できるようになっています。
石灰化Calcificationに関係するステロールSterolの代謝産物であることからカルシフェロールCalciferolの化学名がついています。
後に紫外線照射によって2,2-ジヒドロ・エルゴステリンからビタミンD4が、7-デヒドロ・シトステリンからビタミンD5を生じることを確認しています。ビタミンD2とビタミンD3は、人、ネズミに対する有効性は同等とされていますが、ビタミンD4はD2の50~75%、ビタミンD5はD2のおよそ30%の効力といわれます。
ビタミンDは、カルシウム・リンの代謝を調節し利用率を高め、腸からのカルシウムの吸収、沈着を高めるには必須の栄養素でビタミンDの存在で不足気味のCa,Pでも骨への沈着を高め、ほぼ正常な骨の形成をさせることができます。ビタミンDは粘膜の浸透性を増大させる作用があり腸からのCa,Pを溶解してその吸収を良くするのです。さらにフィチン酸Caを分解、溶解することにも作用しP(リン)の利用率をよくします。
骨・歯の形成 に関与するビタミンDは肝臓に集まり、腎臓に移り、少しずつ活性化されて活性型ビタミンDに変化しています。血液、尿検査によって栄養状態の指標をみることができ、血中の基準値は、血中25ヒドロキシビタミンD(25-hydroxy-vitamin D:25-OH-D)が血液中のビタミンD代謝物の中で最も濃度が高く、体内ビタミンDレベルの指標として用いられています。血液中の25-OH-Dの基準値は15-40ng/mlとしています。日光浴による紫外線(波長280mμが最適)で体内でビタミンD3をコレステロールより生成します。
動物実験でコレステロールを7-デヒドロコレステロール(プロビタミンD)に変える酵素が小腸組織中に存在して生成された7-デヒドロコレステロールは紫外線Ultravioletにあたることによって皮膚でビタミンD3に転換するのです。D2,D3ともに効力は同程度としています。紫外線は太陽光線を浴びることによって得られますが、最近の栄養摂取状況では食事からのビタミンDで基準量を満たしているようです。
よって日光照射を受ければ食事からのビタミンDの摂取は少なくてもよいことになります。1日に必要なビタミンDは、手だけでも1日10~15分間程度の日光浴で充分に満たされるといわれており、紫外線の浴びすぎによる害の方に注意が払われる傾向です。窓ガラス越しの太陽光線からも、多少の紫外線を取り入れることができます。過度の日光浴は避けた方がいいといわれる傾向です。
熱・酸素に安定で主要なビタミンの中で安定性がよく普通に食材を処理している分では分解されにくいとしています。少しは体内で生成されるとも言われることもあります。人体では主に肝臓に蓄えられ脂溶性で D2(エルゴカルシフェロール)は植物性食品に、D3(7-デヒドロコレステロール・コレカルシフェロール、1936年鮪の肝油より抽出される)は動物性食品に含まれます。最近さらにD2は、抗がん作用、D3は、筋肉を作り脂肪代謝に関与することが知られるようになってきました。
欠乏症として、成長期の小児でくる病、成人では骨粗鬆症、骨軟化症、骨の形成不良があります。
骨灰分は、健康な人では脱脂した骨の乾物量中50%程度であるのに、くる病では、骨灰分は、脱脂した骨の乾物量中25~30%となりますがCa(カルシウム)/P(リン)の比率は、正常値を示しています。骨の主成分は燐酸カルシウムで骨の形成にはCaとPがバランスよく存在していることが必要なのです。
くる病では単に骨に燐酸カルシウムとして沈着する量が減少していることになり骨の成分が少ないことにより骨が軟弱になり湾曲、変形してしまいます。歯の発育にも影響を与え阻害されることになるのです。軟骨細胞の柱は伸びても、ビタミンDの不足でカルシウムが、あっても、その柱にカルシウムが沈着しないのです。
ビタミンDの欠乏によって血液中のCa(9~11mg/dl)量は減少していませんがP(りん:無機リン2.5~4.5mg/dl)の低下が認められています。燐酸の排出が盛んになって体内のリンが蓄積されなくなり、血液中のリン酸カルシウムの合成が出来なくなり減少し骨へのカルシウム沈着が困難な状況になってくるとされています。さらに、酸とアルカリのバランスがとれないアシドーシスAcidosisの状態となり骨の石灰化が妨げられるともいわれています。リンの摂取状況は日本人には過剰傾向で過剰摂取での弊害が心配されています。Pが多くなると酸性に傾き、Caの吸収を悪くします。
体内では血液中のカルシウムを一定に保つことに働き、カルシウムが不足の状態では骨からの流出によって調整されているのです。しかし有機物のリン酸エステルを加水分解してリンを遊離させる酵素のアルカリホォスファターゼAlkali phosphataseの著しい上昇が認められ、くる病の診断に使われています。さらにDの欠乏でクエン酸を投与することによってくる病を予防治癒できることが知られています。血液中のCa,P,クエン酸の量と比例することが調べられています。ビタミンDとクエン酸の代謝の関連があり、さらにリン脂質の生成にも関与しているとされています。
体内で利用され不用となったものは、尿、便中に排泄されています。欠乏症にはD剤75μg~125μg(3,000~5,000IU)をCa剤(乳酸Caを1~3g/1日)とともに服用することもあります。
必要量以上に摂取すると肝臓に貯えられ毎日、連日に取る必要はありませんが、しかし過度の過剰では、数ヵ月後に血中のCa上昇、気管、心臓、血管、尿道などにCaの沈着により腎結石、関節痛、筋力低下、発熱・嘔吐・消化障害の食欲減退、骨歯の異常な症状を起こすことがあります。ビタミンAと同時に取ることによって過剰症がでにくいとのことがいわれています。
国民健康栄養調査による平成29年の1日平均摂取量は6.9μgであり、1日の目安量5μgを満たしています。妊婦での目安量は+1.5μg、授乳婦での目安量は+2.5μgです。
上限量50μg、栄養機能食品としての上限が5.0μg(200IU)、下限0.9μg(35IU)とし示されています。国際単位としてビタミンD2で0.025μgの示す効力を1IU(1国際単位)としていました。食事中の油脂類と共に摂取することによって吸収が高まるので胆汁の分泌が悪いと吸収が阻害されます。
多く含む食品として100g中で、卵黄6μg、卵・ピータン6μg、さんま19μg、生鮭22μg、ほんまぐろ5μg、さば11μg、真いわし10μg、ぶり8μg、しらすぼし46μg、うなぎの蒲焼き19μg、いくら44μg、干ししいたけ17μg(生椎茸2μg)、乾燥黒きくらげ70μg(白きくらげ970μg)、えのきだけ1μg、まいたけ3μg、マッシュルーム1μg、松茸4μg、エリンギ2μgなどがあります。
おもに魚の肝油にとビタミンAともに多く含んでいますが、哺乳類の牛、豚などの肝臓(牛肝臓0・豚肝臓1μg/100g中)ではあまり多くは含まれていません。植物性食品では、ビタミンDそのものとしての存在はありません。ビタミンD2は人体でビタミンに変わる物質のプロビタミンDのエルゴステロールErgosterolがきのこ、納豆、酵母3μg%、糸状菌に含まれ紫外線照射によりビタミンD2となり、カルシフェロール、エルゴカルシフェロールともいいます。無色の結晶で融点が115~118度です。
ビタミンD3は、肝油などに含まれているプロビタミンDの7-デヒドロコレステロール:7-dehydro cholesterolを照射することによってできコレカルシフェロールCholecalciferolともいいます。主に動物性食品の青身魚、卵黄、からすみ、牛乳0.3μg%に含みます。無色の結晶で融点が82~86度です。
ビタミンD4は2,2-ジヒドロ・エルゴステリン:2,2-dihydro ergsterolから生じ、ビタミンD5は7-デヒドロ・シトステリン:7-dehydro sitosterolから合成されています。D6,D7とあるようですがD4~D7は、作用が弱く、食品に殆ど含まれていないことから重要視されていません。
ビタミンDは、骨折や様々な慢性疾患に関係することが、よく知られていますが、最近の研究で認知機能の低下との関係した研究、ビタミンDが欠乏した高齢者と多発性硬化症やパーキンソン病、脳卒中、心不全にかかる率が高くなるということの強い関連も示唆しています。
近年では、食事からビタミンDを充分に摂取できるようになったため以前ほど不足はなくなってきているといわています。1998年には、母子手帳から「日光浴」の記述が消え、「外気浴」という表示のみに変わっているようです。
ご愛読戴きましてありがとうございます。よりよい情報をお届けしてまいります。