2020/6/22
弥生時代に丹後が栄えていた。「丹後王国」とみなされる時代があった。
卑弥呼が活躍した時代である。丹後が栄えた時代と卑弥呼が歴史に登場する時代が一致している。
丹後の「間人(たいざ)」は、聖徳太子(厩戸皇子)の母が住んだ地である。おそらく丹後地方には、豪族の誰かがいたのであろう。その豪族との関係によって、母は「間人」の地に住み着いたのであろう。
古墳時代・飛鳥時代の頃、(大和朝廷の本拠地)大和地方と(弥生時代に栄えていた)丹後地方は何らかの関係があったと考えられる。
(ここから続きです。)
私が丹後に興味を持ったのは、『古代史の謎は「海路」で解ける』(長野正孝著)と『古代史の謎は「鉄」で解ける』(同著)の本を読んでからである。さらに『卑弥呼以前の倭国五〇〇年』(大平裕著)や八俣遠呂智氏の論文(ネットでの情報)などを読むようになってからである。
邪馬台国に関する議論に結論は出ていない。いろんな説があるだけで、確たる証拠もなく「永遠の論争」課題かもしれない。古代の歴史問題は、確定していない論争が多い。それがおもしろいのだろう。
学者はある程度「確たること」に基づいて論文を発表しければならないが、素人の者は気楽である。推定や想像したことを、夢でも見る気持ちで語っても誰からも文句は言われない。信用されなくなっても、生活に困るわけではない。
教授や学者たちは、気楽には意見が言えないようだ。信用を失うと立場がなくなるからだろう。
素人は気楽だから、かえって楽しい。
ブログ内容(丹後への興味)の本筋からずれてしまったので、元に戻したい。
丹後半島の付け根地域(西側)に豊岡市がある。円山川を下れば、日本海につながっている。豊岡市出石の袴狭(はかざ)遺跡で(1989年に)見つかったのが、船団線刻画である。日本海を走る16艘もの大船団が描かれていたのである。遺跡の出土物などの鑑定によると、紀元1世紀ごろのようだ。
卑弥呼が活躍していたのは、3世紀ごろ。つまり、この描かれた船団は、卑弥呼の時代よりもずっとずっと以前だったのだ。
それを補足する資料もある。『播磨風土記』である。
『播磨風土記』には、
「新羅の王子が播磨に来て、淡路島を拠点、王子が次々拠点を広げ、豊岡の出石にも拠点を置き、円山川河口から姫路の方に交易ルートを確保した」という内容が書かれているそうだ。(長野正明氏の説明による。)
『播磨風土記』をまだ実際には読んでいない私。そこで、長野氏の説明を参考に考えてみた。
紀元1世紀ごろ、朝鮮半島と淡路島をつなぐルートは、日本海ルートだったに違いない。対馬海流の流れに古代船が乗れば、(特段の断崖絶壁にさえぎられることはなく)丹後半島の西側海岸域まで難なく到達することができるように思われる。弥生時代、島根半島は島だったから。(しかし、丹後半島を古代船で回り、宮津まではたどり着けなかっただろう。)
丹後半島を古代船で回ることができるようになったのは、帆船ができてからであり、4・5世紀(?)ごろになってのこと。やっと外洋帆船が日本海ルートを航行できたようだ。若狭湾の敦賀が王国になっていったのは、外洋帆船が完成してから後のことらしい。(丹後王国は敦賀王国の繁栄につれて、衰退していくことになる。)
丹後半島の突端には経ヶ岬という断崖絶壁がある。(灯台があり、灯台好きな私は2度訪れている。)とにかく、すごい絶壁だった。古代船の時代、経ヶ岬近辺に近づいた船はすべて木っ端みじんに破壊されたことであろう。経ヶ岬に行かれた方は、海岸の恐ろしさをお分かりいただけるであろう。要するに、丹後半島をぐるっと回って、天橋立近辺や宮津に近づけなかったのである。
紀元1世紀ごろ、新羅(朝鮮半島にあった国の一つ)と淡路島をつなぐルートは、確かにあったに違いない。
この時代、淡路島には近畿地方最大の鉄加工(鉄鍛造所=鉄材を鉄製品に加工するところ)遺跡がある。淡路島・北淡(高速出入口)の近くにある「五斗長垣内(ごっさかいと)遺跡」である。この遺跡の発掘で分かったのは、紀元1世紀ごろ、約100年間鉄材を(朝鮮半島などから)輸入して、鉄加工をしていたことが分かったのである。
この「五斗長垣内(ごっさかいと)遺跡」を2年間に見学してきたが、淡路島西側の海・播磨灘を見下ろす高台にあった。鉄加工には火を必要とする。鉄に関する遺跡は高台地域にあることが多い。燃料にする木を必要としたからであろう。
巨大鉄遺跡である、鳥取県「妻木晩田(むきばんだ)遺跡」・丹後の「遠所遺跡」・淡路島の「五斗長垣内(ごっさかいと)遺跡」を見学して感じたことは、どこも燃料にする木が入手しやすい場所だなあ、という点。
いろいろな遺跡は海岸部で見つかることが多いのだが、古代の「鉄遺跡」はやや高台で見つかるようだ。(素人の私の感想だが・・・)
古代日本では製鉄(鉄鉱石などから鉄を作る)はまだできていなかった。鉄材を輸入し、加工して鉄製品を作ることしかできなかった。鉄加工の技術は、初めは渡来人が伝え、日本の各地に広まっていったに違いない。その証拠は日本各地の遺跡で見つかっている。
丹後半島の付け根の西側地域まで、比較的容易に鉄材は弥生時代に伝わっていたであろう。日本海ルートで鉄材と翡翠(日本産出品)などとの交易は、定期的に行われていたようだ。
(私が予想するに)
日本海ルートで豊岡にたどり着いた(船で運ばれてきた重い積み荷)鉄材は、円山川をさかのぼり、川が途切れる中国山地(分水嶺)地帯は、船を牛などの動物や人に曳かせ、陸上を移動。そして、揖保川(または市川)の上流域まで移動。揖保川(または市川)でその船を浮かべ、下って行ったのであろうと推測してみた。揖保川(またが市川)の河口は瀬戸内海・播磨灘である。播磨灘から西に向かうと淡路島(北淡町)が近い。目的地=五斗長垣内(ごっさかいと)集落地にたどり着くことになる。
この予想は、長野正孝氏が書かれていることである。「なるほど!」と地図を見ながら、同感したしだい。中国山地を船が越えたというはっきりとした証拠はない。しかし、そのうちに証拠も見つかるであろう。
古代船の底板は分厚い。陸地を曳きずることを想定して、そういう分厚い構造にしたのかもしれない。機会あれば、船の専門家に聞いてみたい。
丹後地方には鉄に関する遺跡や鉄に関するルートなど、いろいろな古代の関する話材を提供してくれる。丹後には、「海部氏」に関する資料など、魅力的なものがまだまだある。
海洋民族である、「倭人」と丹後の関係もまた別に機会に考えてみたい。
今回、長くなり集中力がなくなり、うまくまとまりませんでした。起承転転・・・になってしまいました。今回はここまで。(了)
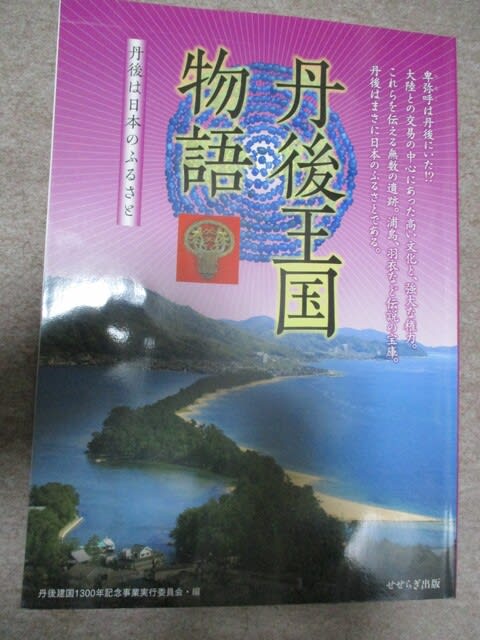
『丹後王国物語』表紙の写真
副題は「丹後は日本のふるさと」と書かれている。そして、表紙には、
卑弥呼は丹後にいた⁉
大陸との交易の中心にあった高い文化と、強大な権力。
これらを伝える無数の遺跡。浦島、羽衣など伝説の宝庫。
丹後はまさに日本のふるさとである。
と紹介されている。

50ヶ所ほどある史跡の位置が紹介されている。とにかく、すごい史跡の数である。古墳も多い。弥生時代の古墳や遺跡が多い。さらに古墳時代のものも多い。
大和朝廷中心に歴史をを見ることが多い学者群。日本書紀や古事記の内容に目を奪われて、丹後地方の歴史を扱う学者は少ない。
紹介されている50ヶ所の史跡群の中で、私が行ったことのある場所はたったの10ヶ所ほどである。観光ボランティアガイドをするようになって、古墳などに興味を持つようになり、丹後に注目するようになったが、訪れた箇所は本当に少ない。機会があれば、もっともっと「現地」へ足を運びたい。歴史の宝庫、魅力的「丹後」へ。
鳥取県・島根県・福井県などの遺跡群も魅力的だ! 日本の歴史発掘において、とにかく「日本海ルート」の発掘が遅れている。そのうち、日本海沿海地域で、「21世紀の大発見の遺跡」が見つかるだろう! 人口減の県での発掘はかなり難しいが・・・
丹後か越前地方(三国港近く)で、何かが発見されるのではないかな? と期待している。

2年前に 友人たちと丹後地方の遺跡巡りをした時
発掘中の遺跡(銚子山古墳)を目にしたのだった。

銚子山古墳からの眺め 網野の町と日本海が見えている。弥生時代・古墳時代を心に感じながら・・・

ニゴレ古墳 京都大学が発掘した古墳 古代の船の埴輪が発掘されている。写真右側に埴輪の写真。

五斗長垣内(ごっさかいと)遺跡 一部建物が再現されていた。

発掘されたものの写真(弥生時代の鉄を意識しながら、この時はたった一人で見学しました。)
卑弥呼が活躍した時代である。丹後が栄えた時代と卑弥呼が歴史に登場する時代が一致している。
丹後の「間人(たいざ)」は、聖徳太子(厩戸皇子)の母が住んだ地である。おそらく丹後地方には、豪族の誰かがいたのであろう。その豪族との関係によって、母は「間人」の地に住み着いたのであろう。
古墳時代・飛鳥時代の頃、(大和朝廷の本拠地)大和地方と(弥生時代に栄えていた)丹後地方は何らかの関係があったと考えられる。
(ここから続きです。)
私が丹後に興味を持ったのは、『古代史の謎は「海路」で解ける』(長野正孝著)と『古代史の謎は「鉄」で解ける』(同著)の本を読んでからである。さらに『卑弥呼以前の倭国五〇〇年』(大平裕著)や八俣遠呂智氏の論文(ネットでの情報)などを読むようになってからである。
邪馬台国に関する議論に結論は出ていない。いろんな説があるだけで、確たる証拠もなく「永遠の論争」課題かもしれない。古代の歴史問題は、確定していない論争が多い。それがおもしろいのだろう。
学者はある程度「確たること」に基づいて論文を発表しければならないが、素人の者は気楽である。推定や想像したことを、夢でも見る気持ちで語っても誰からも文句は言われない。信用されなくなっても、生活に困るわけではない。
教授や学者たちは、気楽には意見が言えないようだ。信用を失うと立場がなくなるからだろう。
素人は気楽だから、かえって楽しい。
ブログ内容(丹後への興味)の本筋からずれてしまったので、元に戻したい。
丹後半島の付け根地域(西側)に豊岡市がある。円山川を下れば、日本海につながっている。豊岡市出石の袴狭(はかざ)遺跡で(1989年に)見つかったのが、船団線刻画である。日本海を走る16艘もの大船団が描かれていたのである。遺跡の出土物などの鑑定によると、紀元1世紀ごろのようだ。
卑弥呼が活躍していたのは、3世紀ごろ。つまり、この描かれた船団は、卑弥呼の時代よりもずっとずっと以前だったのだ。
それを補足する資料もある。『播磨風土記』である。
『播磨風土記』には、
「新羅の王子が播磨に来て、淡路島を拠点、王子が次々拠点を広げ、豊岡の出石にも拠点を置き、円山川河口から姫路の方に交易ルートを確保した」という内容が書かれているそうだ。(長野正明氏の説明による。)
『播磨風土記』をまだ実際には読んでいない私。そこで、長野氏の説明を参考に考えてみた。
紀元1世紀ごろ、朝鮮半島と淡路島をつなぐルートは、日本海ルートだったに違いない。対馬海流の流れに古代船が乗れば、(特段の断崖絶壁にさえぎられることはなく)丹後半島の西側海岸域まで難なく到達することができるように思われる。弥生時代、島根半島は島だったから。(しかし、丹後半島を古代船で回り、宮津まではたどり着けなかっただろう。)
丹後半島を古代船で回ることができるようになったのは、帆船ができてからであり、4・5世紀(?)ごろになってのこと。やっと外洋帆船が日本海ルートを航行できたようだ。若狭湾の敦賀が王国になっていったのは、外洋帆船が完成してから後のことらしい。(丹後王国は敦賀王国の繁栄につれて、衰退していくことになる。)
丹後半島の突端には経ヶ岬という断崖絶壁がある。(灯台があり、灯台好きな私は2度訪れている。)とにかく、すごい絶壁だった。古代船の時代、経ヶ岬近辺に近づいた船はすべて木っ端みじんに破壊されたことであろう。経ヶ岬に行かれた方は、海岸の恐ろしさをお分かりいただけるであろう。要するに、丹後半島をぐるっと回って、天橋立近辺や宮津に近づけなかったのである。
紀元1世紀ごろ、新羅(朝鮮半島にあった国の一つ)と淡路島をつなぐルートは、確かにあったに違いない。
この時代、淡路島には近畿地方最大の鉄加工(鉄鍛造所=鉄材を鉄製品に加工するところ)遺跡がある。淡路島・北淡(高速出入口)の近くにある「五斗長垣内(ごっさかいと)遺跡」である。この遺跡の発掘で分かったのは、紀元1世紀ごろ、約100年間鉄材を(朝鮮半島などから)輸入して、鉄加工をしていたことが分かったのである。
この「五斗長垣内(ごっさかいと)遺跡」を2年間に見学してきたが、淡路島西側の海・播磨灘を見下ろす高台にあった。鉄加工には火を必要とする。鉄に関する遺跡は高台地域にあることが多い。燃料にする木を必要としたからであろう。
巨大鉄遺跡である、鳥取県「妻木晩田(むきばんだ)遺跡」・丹後の「遠所遺跡」・淡路島の「五斗長垣内(ごっさかいと)遺跡」を見学して感じたことは、どこも燃料にする木が入手しやすい場所だなあ、という点。
いろいろな遺跡は海岸部で見つかることが多いのだが、古代の「鉄遺跡」はやや高台で見つかるようだ。(素人の私の感想だが・・・)
古代日本では製鉄(鉄鉱石などから鉄を作る)はまだできていなかった。鉄材を輸入し、加工して鉄製品を作ることしかできなかった。鉄加工の技術は、初めは渡来人が伝え、日本の各地に広まっていったに違いない。その証拠は日本各地の遺跡で見つかっている。
丹後半島の付け根の西側地域まで、比較的容易に鉄材は弥生時代に伝わっていたであろう。日本海ルートで鉄材と翡翠(日本産出品)などとの交易は、定期的に行われていたようだ。
(私が予想するに)
日本海ルートで豊岡にたどり着いた(船で運ばれてきた重い積み荷)鉄材は、円山川をさかのぼり、川が途切れる中国山地(分水嶺)地帯は、船を牛などの動物や人に曳かせ、陸上を移動。そして、揖保川(または市川)の上流域まで移動。揖保川(または市川)でその船を浮かべ、下って行ったのであろうと推測してみた。揖保川(またが市川)の河口は瀬戸内海・播磨灘である。播磨灘から西に向かうと淡路島(北淡町)が近い。目的地=五斗長垣内(ごっさかいと)集落地にたどり着くことになる。
この予想は、長野正孝氏が書かれていることである。「なるほど!」と地図を見ながら、同感したしだい。中国山地を船が越えたというはっきりとした証拠はない。しかし、そのうちに証拠も見つかるであろう。
古代船の底板は分厚い。陸地を曳きずることを想定して、そういう分厚い構造にしたのかもしれない。機会あれば、船の専門家に聞いてみたい。
丹後地方には鉄に関する遺跡や鉄に関するルートなど、いろいろな古代の関する話材を提供してくれる。丹後には、「海部氏」に関する資料など、魅力的なものがまだまだある。
海洋民族である、「倭人」と丹後の関係もまた別に機会に考えてみたい。
今回、長くなり集中力がなくなり、うまくまとまりませんでした。起承転転・・・になってしまいました。今回はここまで。(了)
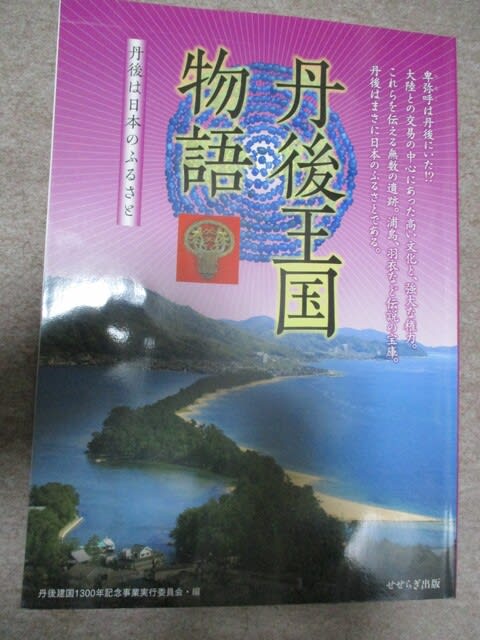
『丹後王国物語』表紙の写真
副題は「丹後は日本のふるさと」と書かれている。そして、表紙には、
卑弥呼は丹後にいた⁉
大陸との交易の中心にあった高い文化と、強大な権力。
これらを伝える無数の遺跡。浦島、羽衣など伝説の宝庫。
丹後はまさに日本のふるさとである。
と紹介されている。

50ヶ所ほどある史跡の位置が紹介されている。とにかく、すごい史跡の数である。古墳も多い。弥生時代の古墳や遺跡が多い。さらに古墳時代のものも多い。
大和朝廷中心に歴史をを見ることが多い学者群。日本書紀や古事記の内容に目を奪われて、丹後地方の歴史を扱う学者は少ない。
紹介されている50ヶ所の史跡群の中で、私が行ったことのある場所はたったの10ヶ所ほどである。観光ボランティアガイドをするようになって、古墳などに興味を持つようになり、丹後に注目するようになったが、訪れた箇所は本当に少ない。機会があれば、もっともっと「現地」へ足を運びたい。歴史の宝庫、魅力的「丹後」へ。
鳥取県・島根県・福井県などの遺跡群も魅力的だ! 日本の歴史発掘において、とにかく「日本海ルート」の発掘が遅れている。そのうち、日本海沿海地域で、「21世紀の大発見の遺跡」が見つかるだろう! 人口減の県での発掘はかなり難しいが・・・
丹後か越前地方(三国港近く)で、何かが発見されるのではないかな? と期待している。

2年前に 友人たちと丹後地方の遺跡巡りをした時
発掘中の遺跡(銚子山古墳)を目にしたのだった。

銚子山古墳からの眺め 網野の町と日本海が見えている。弥生時代・古墳時代を心に感じながら・・・

ニゴレ古墳 京都大学が発掘した古墳 古代の船の埴輪が発掘されている。写真右側に埴輪の写真。

五斗長垣内(ごっさかいと)遺跡 一部建物が再現されていた。

発掘されたものの写真(弥生時代の鉄を意識しながら、この時はたった一人で見学しました。)











