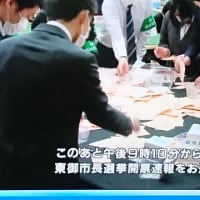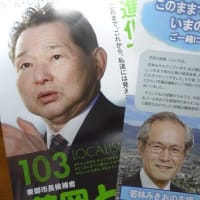11月6日は午後から「六分水」(ろくぶすい)の虫干しがありました。関係する区の役員さんが集まって江戸時代から伝わる古文書をひとつ一つ確認し、水路を描いた絵図面に目を通しました。

関係区の役員の方が古文書を広げその内容を確認しています。

江戸時時代から連綿と伝わっている絵図面を興味ぶかく見ています。
六分水とは水の配分システムのことです。私の住んでいる東御市滋野地区は浅間・烏帽子山麓の南斜面に位置する扇状地です。地区内を流れる川は烏帽子岳から流れる所沢川(しょざわがわ)から分かれる西沢川だけで、昔から水には苦労してきていました。
稲作のための水の確保をめぐって上流の村と下流の村との水争いが繰り返され、時に血も流されることもあったそうです。
それに加えて江戸時代にはこの地域は上流の原口・別府地区は祢津に代官屋敷を置く天領となっており、下流の中屋敷・片羽・大石・桜井は小諸藩だったこともあり、水をめぐる争いがその地域だけで解決できず、最終的には幕府による判断を待たなければなりませんでした。
地域ではそれぞれの村(当時は現在の区が村でした)の名主が集まり、幕府の裁許を求めるために何度も江戸に代表を派遣していたようです。その結果、幕府の裁許を得てつくられたものがこの「六分水」という仕組みでした。
すなわち、烏帽子山麓から流れ下る谷川の水を木で作った枠で6対4に分け、6は滋野地域に落とし、4は祢津地域に流れるようにしました。なぜ5対5ではないかというと、祢津地区には他に滝の沢からの水があるのでそこからの水も合わせればちょうど5対5になるというのです。
この取り決めはその後子々孫々にまで引き継がれ、水争いはなくなりました。今でも毎年5月には升場普請と称して、奈良原地区に設けられた六分水の川掃除が行われ、秋には六分水の虫干しと称して古文書の点検が行われ、六分水の精神が連綿として引き継がれています。
古文書はその時の幕府の裁許状、祢津領と滋野領の村の名主が相互に交換した覚書、水路を書き込んだ絵図面などです。
それにしてもこうして取り決めを結んだとしても水不足はどうしようもなかったはずです。わずかな谷川の水をみんなで公平に分かち合うということの中に、ご先祖様のやさしさや地域としての絆の確かさを感じます。滋野地区の人々の郷土愛やまわりの人々への思いやりの精神はこうした六分水によって育まれたのではないでしょうか。
今ではあちこちにため池ができ、菅平ダムから水を引いてきたりして水の苦労はなくなりました。しかし六分水の水は昔と変わらず滋野地区の真ん中を流れています。

関係区の役員の方が古文書を広げその内容を確認しています。

江戸時時代から連綿と伝わっている絵図面を興味ぶかく見ています。
六分水とは水の配分システムのことです。私の住んでいる東御市滋野地区は浅間・烏帽子山麓の南斜面に位置する扇状地です。地区内を流れる川は烏帽子岳から流れる所沢川(しょざわがわ)から分かれる西沢川だけで、昔から水には苦労してきていました。
稲作のための水の確保をめぐって上流の村と下流の村との水争いが繰り返され、時に血も流されることもあったそうです。
それに加えて江戸時代にはこの地域は上流の原口・別府地区は祢津に代官屋敷を置く天領となっており、下流の中屋敷・片羽・大石・桜井は小諸藩だったこともあり、水をめぐる争いがその地域だけで解決できず、最終的には幕府による判断を待たなければなりませんでした。
地域ではそれぞれの村(当時は現在の区が村でした)の名主が集まり、幕府の裁許を求めるために何度も江戸に代表を派遣していたようです。その結果、幕府の裁許を得てつくられたものがこの「六分水」という仕組みでした。
すなわち、烏帽子山麓から流れ下る谷川の水を木で作った枠で6対4に分け、6は滋野地域に落とし、4は祢津地域に流れるようにしました。なぜ5対5ではないかというと、祢津地区には他に滝の沢からの水があるのでそこからの水も合わせればちょうど5対5になるというのです。
この取り決めはその後子々孫々にまで引き継がれ、水争いはなくなりました。今でも毎年5月には升場普請と称して、奈良原地区に設けられた六分水の川掃除が行われ、秋には六分水の虫干しと称して古文書の点検が行われ、六分水の精神が連綿として引き継がれています。
古文書はその時の幕府の裁許状、祢津領と滋野領の村の名主が相互に交換した覚書、水路を書き込んだ絵図面などです。
それにしてもこうして取り決めを結んだとしても水不足はどうしようもなかったはずです。わずかな谷川の水をみんなで公平に分かち合うということの中に、ご先祖様のやさしさや地域としての絆の確かさを感じます。滋野地区の人々の郷土愛やまわりの人々への思いやりの精神はこうした六分水によって育まれたのではないでしょうか。
今ではあちこちにため池ができ、菅平ダムから水を引いてきたりして水の苦労はなくなりました。しかし六分水の水は昔と変わらず滋野地区の真ん中を流れています。