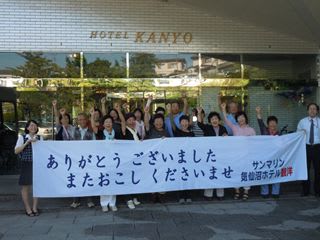11月24日、今年も恒例のくるみ料理コンテストが道の駅「雷電くるみの里」で行われました。この地域特産のくるみを使った料理を一般から募集し、くるみの消費拡大につなげようというこの取り組みは滋野地区活性化研究委員会が実施しているもので、今回で3回目になります。優秀作品の中からは道の駅の新メニューに取り上げられたものも出て来ています。料理コンテストにあわせてくるみの品評会や写真展なども行われました。
いま東御市ではくるみの栽培が盛んに行われています。この地域では昔からかしぐるみの栽培が盛んでしたが、一時期アメリカシロヒトリという害虫が大発生し生産も大きく落ち込んでいました。しかし、食材としてのくるみの良さが見直され、健康にもいいことから遊休農地対策として栽培が奨励されてきています。
アメリカシロヒトリに効果がある薬剤も開発され、消毒用の強力な動力噴霧器も町で貸し出すようになり、ここ数年くるみを植えつける方が増えてきています。わが家にもくるみの木は3本あり数年前に2本植えています。

道の駅でくるみ料理コンテストとくるみ品評会が行われました。

料理部門で最優秀の市長賞を受賞した「くるみいなり」です。どんな味なのか食べてみたくなりました。

くるみを撮った写真展も行われていました。
いま東御市ではくるみの栽培が盛んに行われています。この地域では昔からかしぐるみの栽培が盛んでしたが、一時期アメリカシロヒトリという害虫が大発生し生産も大きく落ち込んでいました。しかし、食材としてのくるみの良さが見直され、健康にもいいことから遊休農地対策として栽培が奨励されてきています。
アメリカシロヒトリに効果がある薬剤も開発され、消毒用の強力な動力噴霧器も町で貸し出すようになり、ここ数年くるみを植えつける方が増えてきています。わが家にもくるみの木は3本あり数年前に2本植えています。

道の駅でくるみ料理コンテストとくるみ品評会が行われました。

料理部門で最優秀の市長賞を受賞した「くるみいなり」です。どんな味なのか食べてみたくなりました。

くるみを撮った写真展も行われていました。