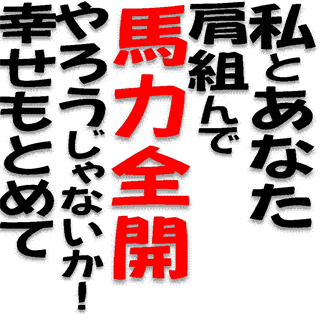昨日の「なぜ水戸黄門なのか?」の中で声をあげることが大切だと書きました。ご無理ごもっともではなく、おかしいことはおかしいという異議申し立てをしようではないかという内容でした。
そんな究極の異議申し立てを行った猛者がいます。「倍返し」で人気を博した「半沢直樹」です。人気の作家である池井戸潤さんの「オレたちバブル入行組」「オレたち花のバブル組」が原作となっています。昨年の夏にテレビで放映された直後から超人気で、主人公の決めセリフ「倍返し」は年末の流行語になりました。
皆さんはあのドラマをどのようにご覧になったでしょうか。私は理不尽なことに真正面から立ち向かう主人公の姿に拍手喝采した一人です。しかし同時に一抹の寂しさも感じていました。いつも主人公は一人ぼっちです。確かに主人公に共感して行動を共にする中小企業のおやじさんなども登場しますが、職場では主人公を庇う上司も、信頼を寄せる部下もいません。
私は現役の時は地方銀行の支店に勤務していました。バブルの崩壊やその後の厳しさも体験しています。振るわない業績のために胃が痛むほどの思いをしたこともあります。しかし、職場では上司も部下もお互いに信頼を寄せ、一体となって頑張ってきました。決してドラマのような「部下の手柄は上司のもの、上司の失敗は部下の責任」ということはありませんでした。
ドラマですから面白くするために誇張してあることは十分わかります。しかしそれでもこのドラマは私が馴染んできた職場環境とあまりにも異なります。ドラマとしてはとても面白いのですが、一人の金融マンとして見た場合とても寂しく残念です。主人公のセリフの「あの小さな明りの1つ1つの中に、人がいる。俺は、そういう人たちの力になれる銀行員になりたい」という思いは、真っ当な金融マンなら至極当然です。
水戸黄門には助さんや格さんがいて、情報は弥七やお銀の担当です。そしてなによりも三つ葉葵の紋所が入った「印籠」、すなわち権力を手にしていました。ですからいつも安全圏にいて勝負をかけることができました。しかし半沢直樹には妻の花さんや同期の渡真利ぐらいしかいません。すべて自分自身を信じて困難を打ち破ってきました。その実行力、精神力には驚嘆すべきものがあります。
しかし、それだけではつらいものがあります。半沢が理不尽と思ったことは、実は職場の誰もが感じているのです。半沢が快刀乱麻のごとく活躍しても職場も会社も何も変わりません。一人ひとりの理不尽なことに対する思いをみんなで共有することで、異議申し立てをした半沢を孤立させることなくみんなで支えて行くことができればと思っています。
現実はそんな甘いものではないことは重々理解できます。それでも私はそうした人を支えて行く存在でありたいと願っています。人が人を信じられない社会であっていいはずがありません。
そんな究極の異議申し立てを行った猛者がいます。「倍返し」で人気を博した「半沢直樹」です。人気の作家である池井戸潤さんの「オレたちバブル入行組」「オレたち花のバブル組」が原作となっています。昨年の夏にテレビで放映された直後から超人気で、主人公の決めセリフ「倍返し」は年末の流行語になりました。
皆さんはあのドラマをどのようにご覧になったでしょうか。私は理不尽なことに真正面から立ち向かう主人公の姿に拍手喝采した一人です。しかし同時に一抹の寂しさも感じていました。いつも主人公は一人ぼっちです。確かに主人公に共感して行動を共にする中小企業のおやじさんなども登場しますが、職場では主人公を庇う上司も、信頼を寄せる部下もいません。
私は現役の時は地方銀行の支店に勤務していました。バブルの崩壊やその後の厳しさも体験しています。振るわない業績のために胃が痛むほどの思いをしたこともあります。しかし、職場では上司も部下もお互いに信頼を寄せ、一体となって頑張ってきました。決してドラマのような「部下の手柄は上司のもの、上司の失敗は部下の責任」ということはありませんでした。
ドラマですから面白くするために誇張してあることは十分わかります。しかしそれでもこのドラマは私が馴染んできた職場環境とあまりにも異なります。ドラマとしてはとても面白いのですが、一人の金融マンとして見た場合とても寂しく残念です。主人公のセリフの「あの小さな明りの1つ1つの中に、人がいる。俺は、そういう人たちの力になれる銀行員になりたい」という思いは、真っ当な金融マンなら至極当然です。
水戸黄門には助さんや格さんがいて、情報は弥七やお銀の担当です。そしてなによりも三つ葉葵の紋所が入った「印籠」、すなわち権力を手にしていました。ですからいつも安全圏にいて勝負をかけることができました。しかし半沢直樹には妻の花さんや同期の渡真利ぐらいしかいません。すべて自分自身を信じて困難を打ち破ってきました。その実行力、精神力には驚嘆すべきものがあります。
しかし、それだけではつらいものがあります。半沢が理不尽と思ったことは、実は職場の誰もが感じているのです。半沢が快刀乱麻のごとく活躍しても職場も会社も何も変わりません。一人ひとりの理不尽なことに対する思いをみんなで共有することで、異議申し立てをした半沢を孤立させることなくみんなで支えて行くことができればと思っています。
現実はそんな甘いものではないことは重々理解できます。それでも私はそうした人を支えて行く存在でありたいと願っています。人が人を信じられない社会であっていいはずがありません。