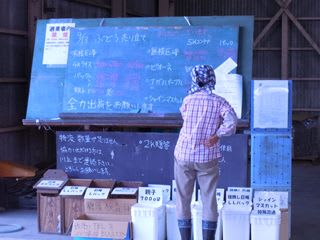「ミツバチの羽音と地球の回転」という不思議なタイトルのドギュメンタリー映画をご存知でしょうか。監督は鎌仲ひとみさん。いま全国あちこちで自主上映会が開かれており、ここ長野県でも佐久市、御代田町、上田市などで開催されてきました。上田市では映画館とタイアップして上映してきました。この映画を東御市でも上映したいという動きが始まっています。
この映画は日本のエネルギーの最前線、
上関原発計画に向き合う祝い島の人々と、
スウェーデンで持続可能な社会を構築する人々の取組みの両方を
一本の映画で描いている。
いかにして、自分たちのエネルギーの未来を切り開くのか?
現場からの問いかけは私達に選択を迫ってくる。
また同時に不可能と思われていたことを可能にする人間のエネルギーが、
私たちと同じ全く普通の人々の感性と思いが、
国の違いを超えて交差し新しいビジョンを描き出す。
(「ミツバチの羽音と地球の回転」の紹介より)
福島原発事故による深刻な放射能汚染の実態から、多くの人々の中に原子力発電所はこのままでいいのかという思いがあります。そんな中、中国電力の上関原発建設に反対して30年にわたって、粘り強く取り組んできたのが山口県上関町祝島の人々です。お金を使って懐柔しようとする中国電力に対して、「金なんかいらない、この海が命ちだ」として祝島の人々は団結してきました。
それではなぜいま、ここ東御市でこの映画を上映するのでしょうか。それには祝島と東御市の宅幼老所との3年間にわたる交流があります。今回の取組みの中心人物はNPO法人おもいやり乙女平の理事長のYさんです。おもいやり乙女平は滋野地区の乙女平区で「おひさま」という宅幼老所を開設しています。
物語は3年前にさかのぼります。Yさんによれば宅幼老所が開設される数日前、祝島から視察の電話があったそうです。住民主体で宅幼老所を開設した事案は全国にもあまりありません。祝島ではお年寄りが多く、行政に頼らず自分たちで宅老所を開設したいという思いがあり「おひさま」に注目したのです。
視察当日はるばる祝島から大勢の住民の方がやって来ました。それから3年間にわたって祝島と「おひさま」との交流が続き、7月10日には祝島の宅老所が開設され、Yさんはお祝いに駆けつけたそうです。その施設の名前も「おひさま」。乙女平と祝島と兄弟施設が立ちあがったのです。祝島でのNPO設立はこれからだそうですがそれぞれの思いが結実しました。
原発反対運動と地域住民が立ち上げた宅老所、一見何の関連性もないように見えます。原発で常に取りざたされるのはお金です。祝島でも原発に賛成すればお金をあげるといわれたそうです。上関町にもすでに国から多額の交付金がもたらされ、原発が来れば町は豊かになる、原発が来れば雇用も生まれるという中国電力の宣伝が行き渡っています。
原発による金で町が二分され利権が交錯し、住民の中に深刻な対立が生まれている中で本当に町おこしなんてできるのでしょうか。福島第一原発の地元では原発による固定資産税の増収で立派な建物が次々と建てられました。しかし長い年月の中で固定資産は償却され税収難に陥り、今度は町から原発の増設を願い出るありさまになっています。中には財政再建団体に陥っている町もあります。
地域を良くして行くためにはお金で地域の安心と安全を原発に売り渡すのではなく、地域住民の主体的な取組みが何よりも大切です。祝島と「おひさま」を結び付けているものはまさにこうした地域住民の自立への取組みだと思います。
この上映会に寄せるYさんの思いは熱くすでに上映実行委員会の準備会を立ち上げています。多くの皆さんにこの映画をごらんいただき、原発と自然エネルギーと地域の自立を考えていただきたいと思います。上映会の日程は以下の通りです。
鎌仲ひとみ監督作品上映会「ミツバチの羽音と地球の回転」
未来のエネルギーをどうするのか?
瀬戸内海の祝島やスウェーデンで原発と決別して
エネルギーの自立に取り組む未来をめざす人々の物語
テーマ:地域の自立エネルギーから介護まで
と き:9月25日(日)午後1時より
ところ:東御市文化会館(サンテラスホール)
第一部 講演「自然エネルギーによる地域の自立」1時~2時
講師 竹村 英明 氏(エナジーグリーン社事業部長)
第二部 映画「ミツバチの羽音と地球の回転」2時15分~4時30分
主催: 宅幼老所おひさま・ミツバチ上映実行委員会とうみ
問合せ先:0268-63-5969(吉田)