避難するか自宅にいるか?
1 被災した方は,
家の「被害状況が分かる写真等」
を撮っておくことをお勧めします。
そのフォトで「罹災証明の即時発行が可能」になる。
2 「災害救助法」に基づく、
「避難所」や「食品・飲物」や「日用品」の支給について、
国が自治体に補助する金額は、
例えば食費は一人1日1080円と書いてあるが、
状況次第でこれを上回る補助も出る。
言うまでもなく、お金よりも命が大切だから、
自治体は弾力的運用に努め、
被災者は我慢せずにニーズを出していくことだ。
⇒ http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/pdf/siryo7.pdf
3 国が発行している
「被災者支援に関する各種制度の概要」は、
現在のところ平成27年11月1日版が最新版だ。
関係者は把握しておくべきである。
⇒ http://www.bousai.go.jp/…/hisa…/pdf/kakusyuseido_tsuujou.pdf
4 銀行や証券会社は、
印鑑や通帳や証券がなくなっても、ちゃんと対応してくれる。
定期預金の期限前払い戻しや,
証券の再発行も,被災者目線で対応することになった。
保険の支払も迅速に。金融機関に国が要請したのだ。
これこそ,国がやるべきこと。
⇒ http://kyusyu.mof.go.jp/rizai/pagekyusyuhp016000094.html
5 地震被害を受けた住宅のローン(いわゆる二重ローン)等を
減免するガイドラインができたばかり。
国も、地元金融機関に、
手続きや効果等の説明や相談を呼び掛けた。
家が壊れたのにローンだけが残ってしまうという事態に、解決の目処がついた。
⇒ http://www.zenginkyo.or.jp/…/disaster_…/disaster-gl_leaf.pdf
6 水とラジオがあれば基本人は死なない。
まずは恐怖に駆られてパニックになり走り回らない事。
普通の家庭なら探せば1週間は持ちこたえられる。
まず、トイレのタンク、ふろの残り湯、なべ・冷蔵庫の水を確保しよう。
缶詰や棚にある食糧をきちんと把握して
自分や家族がどれくらい持ちこたえられるか計算しよう。
7 行政や医療,ボランティアの支援は,時々やってくる。
不安だと思いますがまずは「何とかなる」ことを信じよう。
地元としては、他からの支援の受入れ体制を準備する。
それが被災した方々の早期の安心回復につながる。
ただ、現実的には国や行政は正直遅い。
だから、家屋が安全な状態で、
物資があるなら無理に動かない判断も肝要です。
土砂崩れや津波など明らかな問題があれば直ちに退避しましょう。
友人や家族は電話で冷静にそこをヒアリングして、
煽らずまずは冷静に知識で支援してください。
1 被災した方は,
家の「被害状況が分かる写真等」
を撮っておくことをお勧めします。
そのフォトで「罹災証明の即時発行が可能」になる。
2 「災害救助法」に基づく、
「避難所」や「食品・飲物」や「日用品」の支給について、
国が自治体に補助する金額は、
例えば食費は一人1日1080円と書いてあるが、
状況次第でこれを上回る補助も出る。
言うまでもなく、お金よりも命が大切だから、
自治体は弾力的運用に努め、
被災者は我慢せずにニーズを出していくことだ。
⇒ http://www.bousai.go.jp/taisaku/kyuujo/pdf/siryo7.pdf
3 国が発行している
「被災者支援に関する各種制度の概要」は、
現在のところ平成27年11月1日版が最新版だ。
関係者は把握しておくべきである。
⇒ http://www.bousai.go.jp/…/hisa…/pdf/kakusyuseido_tsuujou.pdf
4 銀行や証券会社は、
印鑑や通帳や証券がなくなっても、ちゃんと対応してくれる。
定期預金の期限前払い戻しや,
証券の再発行も,被災者目線で対応することになった。
保険の支払も迅速に。金融機関に国が要請したのだ。
これこそ,国がやるべきこと。
⇒ http://kyusyu.mof.go.jp/rizai/pagekyusyuhp016000094.html
5 地震被害を受けた住宅のローン(いわゆる二重ローン)等を
減免するガイドラインができたばかり。
国も、地元金融機関に、
手続きや効果等の説明や相談を呼び掛けた。
家が壊れたのにローンだけが残ってしまうという事態に、解決の目処がついた。
⇒ http://www.zenginkyo.or.jp/…/disaster_…/disaster-gl_leaf.pdf
6 水とラジオがあれば基本人は死なない。
まずは恐怖に駆られてパニックになり走り回らない事。
普通の家庭なら探せば1週間は持ちこたえられる。
まず、トイレのタンク、ふろの残り湯、なべ・冷蔵庫の水を確保しよう。
缶詰や棚にある食糧をきちんと把握して
自分や家族がどれくらい持ちこたえられるか計算しよう。
7 行政や医療,ボランティアの支援は,時々やってくる。
不安だと思いますがまずは「何とかなる」ことを信じよう。
地元としては、他からの支援の受入れ体制を準備する。
それが被災した方々の早期の安心回復につながる。
ただ、現実的には国や行政は正直遅い。
だから、家屋が安全な状態で、
物資があるなら無理に動かない判断も肝要です。
土砂崩れや津波など明らかな問題があれば直ちに退避しましょう。
友人や家族は電話で冷静にそこをヒアリングして、
煽らずまずは冷静に知識で支援してください。










![[無料]初期投資がいらないビジネス](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/67/b4/41c51ed5961e026d59e7889d8b239c62.png)
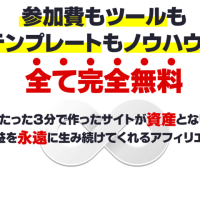






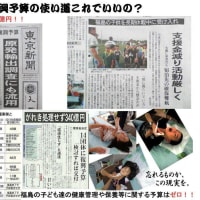

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます