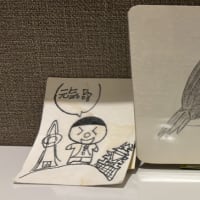「お施餓鬼」とは『お釈迦様の弟子が、亡くなった自分の母親が「餓鬼道」(地獄)へ落ちて苦しんでいるのを知り、お釈迦さまの『ご馳走を用意し、教を唱え供養しなさい』という教えを行ったことによって、母親を救うことができたという話に基づいているらしい。
「施餓鬼」とは餓鬼(地獄に落ちた死者)にご馳走などを施すということで、お盆には亡くなった人のために「施餓鬼法要」をする。
7月はじめにお寺に永代供養を頼んでいたので、8月7日「神於寺(こうのでら)」大日堂の法要に、寺の檀家の方たちと共に参列した。
「神於寺」についてリンクを貼ろうとしてちょっとびっくり。「神於寺」をクリックして読んでもらったらわかるだろう。
お借りした写真

塔婆(とうば)あるいは卒塔婆(そとうば)と呼ぶ細長い板の真ん中に、それぞれの家の亡くなった方たちの戒名と、供養をお願いする家族の人の名前が左下に施主として書かれたものを、本尊の前に並べてお坊さんが読経と共に供養して下さる。
塔婆(とうば)・卒塔婆(そとうば)とは、お釈迦様が入滅(亡くなった)した時に、供養のために建てた塔のことで、インドのサンスクリット語の「ストゥーバ」が由来。現代の日本ではこういう形の板で代用して供養するようになったそうだ。
こじんまりとしたそれほど広くない本堂には、昭和の初めごろからの(それ以前のものは少しずつ取り外されている)亡くなった方たちを永代供養した塔婆が、左右の壁の天井近く、奥から順にお参りの人たちの方へ並べられていて、新参の我が家のはお参りの人たちに一番近いところに掲げられている。
永代供養と、施餓鬼供養の読経は静かな山に響いていた。
「線香臭い」とか「抹香臭い」などという忌み嫌われるような言い方はあるが、小さなお堂に漂う山の気とまじりあった線香の香りは、前世、現世、来世をつなぐ悠久の流れをくゆらせているようで、思わず妹と「いいかおりやね」と言いながらそのひと時に浸っていた。こうして父の霊をお迎えした。