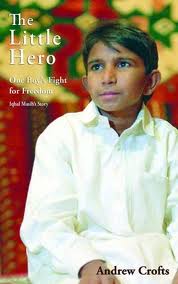昨夜、村上春樹さんが何かの授賞式で演説されているのをTVで見ました。スピーチの中で彼は、「効率」のために我々の日々の安全が犠牲にされている、という趣旨のことを言っていました。もちろん、原発事故のことを指してです。
電力の使用量がここまで増えてしまった背景には、「効率」だとか「便利さ」を求める我々の貪欲な欲求がありました。
一体、便座のフタが自動で上がらなければならない理由って何なのでしょう?車の外には快適な5月の青空が広がっているのに、窓をしめてエアコンを効かせる理由は何なのでしょう?センサーが反応して水が出てくるのと、蛇口を手でひねることの違いは?雨戸が電動で上がったり下がったりするのって、もはや「効率」というより「怠惰」?
そうはいっても、私だってマキを焚いてお風呂を沸かすのは面倒だし、洗濯機も冷蔵庫もなければやっていけません。夏にエアコンがないのも辛いです。決して偉そうなことは言えないのです。けれども、村上さん言うところの、“非現実的な夢想家”という謗りを受けながらでも、生活の安全について声をあげていかなければいけないと思っています。
何もかもがものすごい勢いで進化していく現代。私なんかはそういう方面に全く興味がないもので、「地デジ」って何?今のテレビでテレビが見られなくなるなら、見なくてもいいや、と思ってしまいます(見るに値する番組もそれほどないですし)。
昔、カセットテープを使っていたころは、カセットデッキが壊れることなどめったにありませんでした。ラジオやテレビだって、何十年も使えたでしょう?息子のipodは半年で壊れ、メーカーに問い合わせたら「修理」ではなく、別のipodと「交換」されました。音楽が何万曲も入るというその機械は小さくてスタイリッシュですが、一体、何万曲もの音楽を携帯する必然性がどこに?
人間の本質的な幸せというのは、便座の自動のフタでも、何万曲もの音楽でもなく、もっと原始的なところにあると思います。
突き詰めていくとそれは、自分以外の人間とどういう関係を築いていけるか、という点にかかっているように思います。私でいうなら、自分のもっとも身近にいる家族と幸せに過ごすことが幸福感の根本にあります。
今、原発事故によって、その根本を犠牲にされている人々がいます。圧倒的多数である、「原発事故には関係ない人たち」である我々が、少しの「効率」を犠牲にしてもいいのではないでしょうか。
電力の使用量がここまで増えてしまった背景には、「効率」だとか「便利さ」を求める我々の貪欲な欲求がありました。
一体、便座のフタが自動で上がらなければならない理由って何なのでしょう?車の外には快適な5月の青空が広がっているのに、窓をしめてエアコンを効かせる理由は何なのでしょう?センサーが反応して水が出てくるのと、蛇口を手でひねることの違いは?雨戸が電動で上がったり下がったりするのって、もはや「効率」というより「怠惰」?
そうはいっても、私だってマキを焚いてお風呂を沸かすのは面倒だし、洗濯機も冷蔵庫もなければやっていけません。夏にエアコンがないのも辛いです。決して偉そうなことは言えないのです。けれども、村上さん言うところの、“非現実的な夢想家”という謗りを受けながらでも、生活の安全について声をあげていかなければいけないと思っています。
何もかもがものすごい勢いで進化していく現代。私なんかはそういう方面に全く興味がないもので、「地デジ」って何?今のテレビでテレビが見られなくなるなら、見なくてもいいや、と思ってしまいます(見るに値する番組もそれほどないですし)。
昔、カセットテープを使っていたころは、カセットデッキが壊れることなどめったにありませんでした。ラジオやテレビだって、何十年も使えたでしょう?息子のipodは半年で壊れ、メーカーに問い合わせたら「修理」ではなく、別のipodと「交換」されました。音楽が何万曲も入るというその機械は小さくてスタイリッシュですが、一体、何万曲もの音楽を携帯する必然性がどこに?
人間の本質的な幸せというのは、便座の自動のフタでも、何万曲もの音楽でもなく、もっと原始的なところにあると思います。
突き詰めていくとそれは、自分以外の人間とどういう関係を築いていけるか、という点にかかっているように思います。私でいうなら、自分のもっとも身近にいる家族と幸せに過ごすことが幸福感の根本にあります。
今、原発事故によって、その根本を犠牲にされている人々がいます。圧倒的多数である、「原発事故には関係ない人たち」である我々が、少しの「効率」を犠牲にしてもいいのではないでしょうか。