雪国科学。「いったい何をやっている会社?」と思わせる社名だ。町屋敦司社長(52)がサラリーマン時代、長岡で雪かきをしていてひらめいた。社業の原点には、お年寄りを、除雪の重労働から解放できないか、という思いがある。が、脱サラしたものの、起業、そして経営が軌道に乗るまでは楽ではなかった。新潟市荻曽根1丁目の本社で、特許技術を生むまでの苦労話を聞いた。
◇
大学農学部卒業後、長野県内の食品卸問屋で営業を7年。そこで妻と知り合い、妻の地元の新潟市へ。設立1年目のコピー機販売会社に入り、再び営業マンとしてさらに7年。
――脱サラしたのは
「長岡営業所を任されていた80年代中ごろ、積雪2メートルの豪雪を経験。朝から晩まで雪かき。独立する機会があったら、この雪溶かしを仕事にしたいな、と思った。異動で長岡から新潟に戻ってきて辞めた。そのころ、まだ小さな娘が3人いた。毎日が飲み会で休日ぐらいしか顔を見ない。接する時間が全然なかった。今辞めなきゃ、子供がおかしくなっちゃう。35歳。人生を変えるなら今だと思った」
――まずやったのは
「薪ストーブのあるログハウスを自分の手で建てようと思い立った。父親が炎を扱う姿、薪割りする姿を子どもに見せたかった。収入がなくなって、突然の家造り宣言。妻は『企業戦士やってて人間ダメになるくらいならやりなさい』と支えてくれた」
知人の工務店に半年間住み込んだ。原木の皮むきから、すべて手伝った。
――暖房メーカーへのきっかけを見つけた
「床暖房の耐久性が、どうもあやしかった。家は100年近く使うのに床暖房の保証期間は1、2年。自分で長期保証の床暖房を作りたくなった。『自分で営業しますから』と社長に頼み込んで試作を始めた。といっても、機械はまったくの素人。まずは熱伝導の原理を学ぶため、中学2年の理科の参考書を買ってくるところから始めた」
「熱の伝わり方に、伝導、対流、放射があることがわかった。それまでの床暖房製品はこうした原理を踏まえておらず、床上に伝わる熱と同じくらい床下にも熱が逃げていた。断熱材を敷き詰めてもダメで、物と物が接している限り、外に漏れることに気づいた」
「床板に、対流が起きない程度の数ミリのすき間をつくった。さらに下面に反射材を張り、わずかな熱も逃さない構造にした。素人考えだが、理にかなっていた。大手だと既存の材料、データの蓄積がいっぱいあり過ぎて、案外見落としてしまう視点だった」
91年1月に完成、特許申請とともに会社を起こした。長岡で思いついた社名で。改良を重ね、95年に業界初の10年保証を実現。00年に、優良住宅部品の認定試験に出品すると、省エネ効率89%、群を抜いた日本一だった。合格値である60%を大きく超えていた。特許は02年に認められた。
――それから屋根融雪へ
「それまでの屋根融雪は、屋根の下に仕込むタイプが多く、改築は大規模になり、お金もかかる。それなら屋根の上に電熱線を出せないかと考えた。あらゆる素材を買い集めて研究した。フッ素樹脂加工に目をつけ、96年に商品化した。業界初だった」
98年ごろから薪ストーブの代理店も本格化。北欧・北米製で、内蔵の触媒で煙を出さない環境配慮型だ。
――薪ストーブは静かなブームですね
「工事費込みで100万円ほどかかるのに、意外だ。炎を囲んでいると、誰でも、本能的に、ほっとして優しくなれるからかもしれない」
「ボランティアで『自然倶楽部』という私塾をやっていた。自閉症の子など悩みを抱える家族が集まって、週末、自然の中で金をかけずに遊ぶ。すると、親子とも表情が生き返ってくるのがわかる。現代は、子供たちが病んでいるのではなく、家族が病んでいるんだと思う。そんな時代に、うちの製品が少しでも役に立てば、幸せですね」
■雪国科学■ 91年3月設立、社員13人。融雪や床暖房の開発、薪ストーブ販売など。96年、床暖房システム「ゆかだんサーミック」で、新潟市産業大賞優秀賞を受賞。同社製品を施工する代理店は東北・北陸を中心に23社。05年売上高約3億円、経常利益約1千万円。町屋社長は長野県出身、信州大卒。学生時代、野生動物の調査に夢中だったという自然派。
朝日新潟
◇
大学農学部卒業後、長野県内の食品卸問屋で営業を7年。そこで妻と知り合い、妻の地元の新潟市へ。設立1年目のコピー機販売会社に入り、再び営業マンとしてさらに7年。
――脱サラしたのは
「長岡営業所を任されていた80年代中ごろ、積雪2メートルの豪雪を経験。朝から晩まで雪かき。独立する機会があったら、この雪溶かしを仕事にしたいな、と思った。異動で長岡から新潟に戻ってきて辞めた。そのころ、まだ小さな娘が3人いた。毎日が飲み会で休日ぐらいしか顔を見ない。接する時間が全然なかった。今辞めなきゃ、子供がおかしくなっちゃう。35歳。人生を変えるなら今だと思った」
――まずやったのは
「薪ストーブのあるログハウスを自分の手で建てようと思い立った。父親が炎を扱う姿、薪割りする姿を子どもに見せたかった。収入がなくなって、突然の家造り宣言。妻は『企業戦士やってて人間ダメになるくらいならやりなさい』と支えてくれた」
知人の工務店に半年間住み込んだ。原木の皮むきから、すべて手伝った。
――暖房メーカーへのきっかけを見つけた
「床暖房の耐久性が、どうもあやしかった。家は100年近く使うのに床暖房の保証期間は1、2年。自分で長期保証の床暖房を作りたくなった。『自分で営業しますから』と社長に頼み込んで試作を始めた。といっても、機械はまったくの素人。まずは熱伝導の原理を学ぶため、中学2年の理科の参考書を買ってくるところから始めた」
「熱の伝わり方に、伝導、対流、放射があることがわかった。それまでの床暖房製品はこうした原理を踏まえておらず、床上に伝わる熱と同じくらい床下にも熱が逃げていた。断熱材を敷き詰めてもダメで、物と物が接している限り、外に漏れることに気づいた」
「床板に、対流が起きない程度の数ミリのすき間をつくった。さらに下面に反射材を張り、わずかな熱も逃さない構造にした。素人考えだが、理にかなっていた。大手だと既存の材料、データの蓄積がいっぱいあり過ぎて、案外見落としてしまう視点だった」
91年1月に完成、特許申請とともに会社を起こした。長岡で思いついた社名で。改良を重ね、95年に業界初の10年保証を実現。00年に、優良住宅部品の認定試験に出品すると、省エネ効率89%、群を抜いた日本一だった。合格値である60%を大きく超えていた。特許は02年に認められた。
――それから屋根融雪へ
「それまでの屋根融雪は、屋根の下に仕込むタイプが多く、改築は大規模になり、お金もかかる。それなら屋根の上に電熱線を出せないかと考えた。あらゆる素材を買い集めて研究した。フッ素樹脂加工に目をつけ、96年に商品化した。業界初だった」
98年ごろから薪ストーブの代理店も本格化。北欧・北米製で、内蔵の触媒で煙を出さない環境配慮型だ。
――薪ストーブは静かなブームですね
「工事費込みで100万円ほどかかるのに、意外だ。炎を囲んでいると、誰でも、本能的に、ほっとして優しくなれるからかもしれない」
「ボランティアで『自然倶楽部』という私塾をやっていた。自閉症の子など悩みを抱える家族が集まって、週末、自然の中で金をかけずに遊ぶ。すると、親子とも表情が生き返ってくるのがわかる。現代は、子供たちが病んでいるのではなく、家族が病んでいるんだと思う。そんな時代に、うちの製品が少しでも役に立てば、幸せですね」
■雪国科学■ 91年3月設立、社員13人。融雪や床暖房の開発、薪ストーブ販売など。96年、床暖房システム「ゆかだんサーミック」で、新潟市産業大賞優秀賞を受賞。同社製品を施工する代理店は東北・北陸を中心に23社。05年売上高約3億円、経常利益約1千万円。町屋社長は長野県出身、信州大卒。学生時代、野生動物の調査に夢中だったという自然派。
朝日新潟











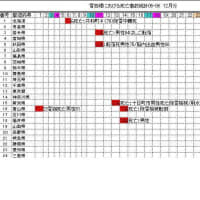
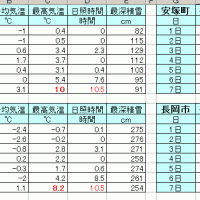
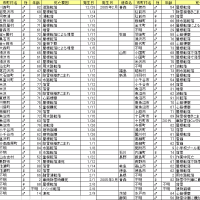







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます