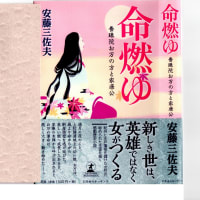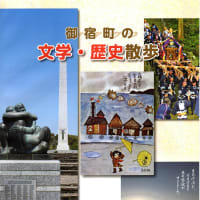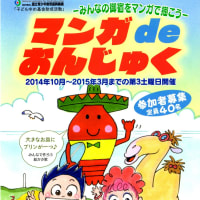石田ゆき緒句集『残礁』(日本伝統俳句協会)
海女集落として名高かった御宿町岩和田生まれ(大正7年)のホトトギス俳人の句集には、強風に耐え、荒波に向かって生きる漁民たちの魂の叫びが込められている。
私は、岩和田の海女を撮り続けたアマチュア写真家岩瀬禎之さんの写真集『海女の群像・習俗』(彩流社)全2巻の編集に携わったが、その映像は国際的に注目されている。それは、かつての漁村には、厳しい労働に取り組む健康でたくましい女性たちの肉体美の躍動をカメラによって証明しているからである。この浜には、まさに本物のビーナスが存在していたことを私は実感したのである。
句集『残礁』は、その写真集に比べても遜色のない短詩形文学作品である。おそらく日本全国の漁村を舞台とする多くの句集のいずれをとってもこの句集に匹敵する物はないと思われる。それほどにすべてを包み込んでいるのである。それは鉄道機関士の作者の母も妻もまた腕の良い海女さんであったことによろうと思われる。(機関士の妻として海女夏潮に)。
帽くれし妻のかひなの鮑傷
=鮑の固い貝がらによって、腕が傷だらけになった愛する妻の姿に感謝(申し訳なさ)と憐れみを抱いたのである。
つみびとの如くふるへ来若布刈海女
海底の若布を刈り取って上がって来た海女が罪人のように震えていた、と言うのは、今まで見過ごしていた厳しい労働への再認識なのである。「めかりあま」と読ませたい。
ふくれくる波の芯より若布刈海女
波を「ふくれくる」と描写し、「波の芯」とあらわし、その芯から海女がひょっこりと顔を現すと言う表現力に兜を脱ぐ。これは、写生に徹するホトトギス俳人の真骨頂である。作者は、昭和19年にホトトギスに初入選、その後、同人として漁村の習俗と海女の生き様を句作し続けた。
大岩に生まるるかげの添乳(そえじ)海女
出産後も休む間もなく労働に勤しむ海女への作者のまなざしは優しい。それは、自分自身も乳児の頃はそうであったに違いないと言う想像でもあろうし、海女の母への感謝の思いでもあろう。
寡婦として漁臭沁みたる木の葉髪
夫は、おそらく漁でもって命を奪われたのであろう。残された妻は、一家を背負って、寸暇を惜しんで漁業に勤しんでいて、髪の手入れもままならない。そばに寄れば、魚臭さが匂ってくる。
さざえ髪解いて祭の海女若し
前句の「木の葉髪」もそうだが、娘の海女の「さざえ髪」は、まさしく言い得て妙!
作者が、漁村に生まれ育ち、生活をしているからこそこう言う表現が出来るのである。
命樽月に叩いて踊る海女
祭りばやしに海女たちが踊る光景を巧みに描いている。それは「月に叩いて」のフレーズにある。月光の降り注ぐ浜辺に村人たちが大勢集まっている。そのまん中で海女たちが踊っている。しかも、海の中では、いつも命をかけている浮き輪を、リズムよく叩いて踊りまくっている。
浦明けの路地より籠のふれ合へり
待ちかねていた日がやって来た。漁の道具や着る物、弁当などを入れた駕籠を海女たちが背負って、一斉に狭い路地へ出て来たから触れ合うのだ。さぁ今日から漁に立ち向かうぞ!という勢いが感じられる句である。
句集抄 ※上記のほかに共鳴した俳句です。
海女ら解く髪に夕虹立ちそめし
=山からの絞り水で体を洗って家路につくのである。そのとき見事な虹が沖にかかった。美しいひと時である。
たんぽぽの絮とんで海動きけり
=微小な綿毛の富裕で、海が動くと言う壮大な感覚に脱帽する。
冬の濤倒れし音のおくれくる
=冬の怒涛が岩礁に激しく押し寄せる。その轟音を見つめていると、情景と音響の微妙なずれに気づく。その繊細な感性の句である。
春潮やまろぶがごとく礁(いくり)出づ
=潮の流れは、季節によって変わると感じたのである。春潮は岩礁群の中を転がるように流れ込んで、出ていくとは、よくも見たものである。見事に潮を凝視している。
春潮やこの岩ものびちぢみして
=万物が生命力を回復するのが春である。どっしりとした岩礁の岩までもが、あたかも生きているかのように伸縮自在に感じられる。
霜とけてゆく風紋のかがやけり
=なんとまぁ、よく凝視しているものだ。まさに写生句の真髄に迫っている。
潮先を縫ひつつ蝶のもつれとぶ
=こういう光景は、あまり見かけられないであろうが、海を庭のようにしている浜の人々は、時たま目にするのであろう。この雌雄の蝶の描写が、実に巧みだ。
ちちははの草刈る音の重なりし
=長く連れ添う父母の草刈りのリズムが、徐々に重なって行く。子供には、それが嬉しくも、羨ましいのだ。
鍬先に海のうごける畑を打つ
=鍬先に海が動いていることを実感しながら畑を耕している。のどかな光景である。
貧しくも鯖火明りの厨窓
=台所の窓から鯖を獲る船の漁火が見える。貧しくても一日が終わろうとする一家の平穏さを享受している。
防風ほる眉の上なる海青し
=春先の砂丘で、腰をかがめて浜ボウフウの若芽を掘る(サラダや刺身のつまにするのであろうか)。その眼先に青い海が見えている。美しい情景である。
御宿町の石田町長にお願いしていたお父上の大切な句集をいただいた。平成13年発行とあり、お手元には2冊のみしかないうちの1冊である。2読、3読と、拝読するうちにその練達の作品に感銘した。「実相観入」とは、まさにこのような俳句を言うのであろう。感謝をこめて拙文を記した。
2014年梅雨の頃 安藤 三佐夫
海女集落として名高かった御宿町岩和田生まれ(大正7年)のホトトギス俳人の句集には、強風に耐え、荒波に向かって生きる漁民たちの魂の叫びが込められている。
私は、岩和田の海女を撮り続けたアマチュア写真家岩瀬禎之さんの写真集『海女の群像・習俗』(彩流社)全2巻の編集に携わったが、その映像は国際的に注目されている。それは、かつての漁村には、厳しい労働に取り組む健康でたくましい女性たちの肉体美の躍動をカメラによって証明しているからである。この浜には、まさに本物のビーナスが存在していたことを私は実感したのである。
句集『残礁』は、その写真集に比べても遜色のない短詩形文学作品である。おそらく日本全国の漁村を舞台とする多くの句集のいずれをとってもこの句集に匹敵する物はないと思われる。それほどにすべてを包み込んでいるのである。それは鉄道機関士の作者の母も妻もまた腕の良い海女さんであったことによろうと思われる。(機関士の妻として海女夏潮に)。
帽くれし妻のかひなの鮑傷
=鮑の固い貝がらによって、腕が傷だらけになった愛する妻の姿に感謝(申し訳なさ)と憐れみを抱いたのである。
つみびとの如くふるへ来若布刈海女
海底の若布を刈り取って上がって来た海女が罪人のように震えていた、と言うのは、今まで見過ごしていた厳しい労働への再認識なのである。「めかりあま」と読ませたい。
ふくれくる波の芯より若布刈海女
波を「ふくれくる」と描写し、「波の芯」とあらわし、その芯から海女がひょっこりと顔を現すと言う表現力に兜を脱ぐ。これは、写生に徹するホトトギス俳人の真骨頂である。作者は、昭和19年にホトトギスに初入選、その後、同人として漁村の習俗と海女の生き様を句作し続けた。
大岩に生まるるかげの添乳(そえじ)海女
出産後も休む間もなく労働に勤しむ海女への作者のまなざしは優しい。それは、自分自身も乳児の頃はそうであったに違いないと言う想像でもあろうし、海女の母への感謝の思いでもあろう。
寡婦として漁臭沁みたる木の葉髪
夫は、おそらく漁でもって命を奪われたのであろう。残された妻は、一家を背負って、寸暇を惜しんで漁業に勤しんでいて、髪の手入れもままならない。そばに寄れば、魚臭さが匂ってくる。
さざえ髪解いて祭の海女若し
前句の「木の葉髪」もそうだが、娘の海女の「さざえ髪」は、まさしく言い得て妙!
作者が、漁村に生まれ育ち、生活をしているからこそこう言う表現が出来るのである。
命樽月に叩いて踊る海女
祭りばやしに海女たちが踊る光景を巧みに描いている。それは「月に叩いて」のフレーズにある。月光の降り注ぐ浜辺に村人たちが大勢集まっている。そのまん中で海女たちが踊っている。しかも、海の中では、いつも命をかけている浮き輪を、リズムよく叩いて踊りまくっている。
浦明けの路地より籠のふれ合へり
待ちかねていた日がやって来た。漁の道具や着る物、弁当などを入れた駕籠を海女たちが背負って、一斉に狭い路地へ出て来たから触れ合うのだ。さぁ今日から漁に立ち向かうぞ!という勢いが感じられる句である。
句集抄 ※上記のほかに共鳴した俳句です。
海女ら解く髪に夕虹立ちそめし
=山からの絞り水で体を洗って家路につくのである。そのとき見事な虹が沖にかかった。美しいひと時である。
たんぽぽの絮とんで海動きけり
=微小な綿毛の富裕で、海が動くと言う壮大な感覚に脱帽する。
冬の濤倒れし音のおくれくる
=冬の怒涛が岩礁に激しく押し寄せる。その轟音を見つめていると、情景と音響の微妙なずれに気づく。その繊細な感性の句である。
春潮やまろぶがごとく礁(いくり)出づ
=潮の流れは、季節によって変わると感じたのである。春潮は岩礁群の中を転がるように流れ込んで、出ていくとは、よくも見たものである。見事に潮を凝視している。
春潮やこの岩ものびちぢみして
=万物が生命力を回復するのが春である。どっしりとした岩礁の岩までもが、あたかも生きているかのように伸縮自在に感じられる。
霜とけてゆく風紋のかがやけり
=なんとまぁ、よく凝視しているものだ。まさに写生句の真髄に迫っている。
潮先を縫ひつつ蝶のもつれとぶ
=こういう光景は、あまり見かけられないであろうが、海を庭のようにしている浜の人々は、時たま目にするのであろう。この雌雄の蝶の描写が、実に巧みだ。
ちちははの草刈る音の重なりし
=長く連れ添う父母の草刈りのリズムが、徐々に重なって行く。子供には、それが嬉しくも、羨ましいのだ。
鍬先に海のうごける畑を打つ
=鍬先に海が動いていることを実感しながら畑を耕している。のどかな光景である。
貧しくも鯖火明りの厨窓
=台所の窓から鯖を獲る船の漁火が見える。貧しくても一日が終わろうとする一家の平穏さを享受している。
防風ほる眉の上なる海青し
=春先の砂丘で、腰をかがめて浜ボウフウの若芽を掘る(サラダや刺身のつまにするのであろうか)。その眼先に青い海が見えている。美しい情景である。
御宿町の石田町長にお願いしていたお父上の大切な句集をいただいた。平成13年発行とあり、お手元には2冊のみしかないうちの1冊である。2読、3読と、拝読するうちにその練達の作品に感銘した。「実相観入」とは、まさにこのような俳句を言うのであろう。感謝をこめて拙文を記した。
2014年梅雨の頃 安藤 三佐夫