
復刻された少年月刊誌「少年画報」を紹介するシリーズ、その10。
付録紹介シリーズとしては、その8。
今回は別冊付録「風小僧」である。
「風小僧」は、ウィキペディアによると・・「北村寿夫原作の「紅孔雀」に登場する「風の小六」の別名であり、また、彼を主役にした東映製作の時代劇」・・とある。
なんでも東映製作の初のテレビ作品だったらしい。初放送は1958年というから、今となっては50年以上も前の作品だったことになる。
主演は、山城新伍さんだったようだ。
私はこの復刻版「少年画報」を入手するまで、この作品のことは知らなかった。
まずこの作品を目にして、そして読んでみて思ったことは、画風のリアルさである。
それもそのはず、作画を担当された寺内鉄雄さんは、挿絵画家だったらしい。そのせいか、この作品は「漫画」という形態をとっていながらも、まるで絵物語でも読んでいるような感じだ。
それほど、1コマ1コマが格調高い。そう、「格調高い」という表現がしっくりくる。
良い意味での古風な絵柄で、今では新作としては中々お目にかかれないタイプの絵柄なので、かえって新鮮である。
画風という意味では、まさに「劇画」という呼び方がピッタリな感じだ。
当時の漫画の丸っこくデフォルメされた画風に慣れた子供たちにとっては、じゃっかん読みづらかったかもしれないが、実写ドラマを見るような感覚で読んでいたことだろう。
物語小説などを読んでると、たまに挿絵が描かれていることがあって、読み手はたまに出てくる挿絵から自分なりのイメージを広げたりした。そして挿絵はたまにしかなかったので、それだけに貴重にも思えた。
だが、この作品は、その「たまにしか出て来なかった挿絵」が、これでもかこれでもかとばかりに描かれ、その挿絵でストーリーがどんどん展開してゆく。なので、すごく贅沢でゴージャスな印象を受ける。
なにより、本格的で子供だましの絵ではない。
それこそ、大人の鑑賞に十分に耐えうる絵柄であったろう。
というか、今見ても、十分に大人の鑑賞に耐えうる。それどころか、むしろ大人向けといってもいいぐらいの本格的なリアルさだ。
今でこそ「少年マガジン」や「少年サンデー」などの少年週刊誌はコミックだけで埋め尽くされているが、昔はコミックだけでなく、挿絵画家によるグラビア図解なども「売り」であった。
そのグラビア図解は絵が緻密でリアルで本格的だったが、この「風小僧」は、そのグラビアがそのままコミックになっている感じで、ともかく絵の中身が濃い。
こういう絵柄は、子供たちが真似して描くのは・・・大半の子供は無理だったのではないか。
たとえこういう絵を描きたかったとしても、子供が簡単にまねできる絵柄とも思えない。
より本格的な絵ごころや、絵の基礎が出来た子じゃないと、マネはできなかったことだろう。
アトムや鉄人を描くことはできても、この「風小僧」は中々描けなかったことだろう。
マネできた子は、相当絵がうまい子だっただろう。
思えば・・・私が敬愛する水木しげる先生は若い頃に妖怪が出てくる時代劇漫画を描いていたりしたが、水木先生の描く時代劇に出てくるキャラは、どことなく、この「風小僧」のような「挿絵風」な味わいがあった。
当時は、こういう挿絵風の画風は、一般的だったのかもしれない。
だからこそ、挿絵画家が活躍するグラビア図解などの企画も多かったのだろう。
いつしかこうした挿絵風のコミックの絵柄は消えてしまった。
代わりに、萌え系のアニメ風な絵柄が全盛。
その一方でリアルな画風のコミックもあるけど、同じ「リアル」でも、挿絵風のリアルさとは少し違う。
だからこそ、今「挿絵風」な絵柄の新作コミックでもあったら、印象に残るだろうなあ。
古風で、緻密で、リアルで、格調高く、模倣がむずかしく、それでいてどこか妖しさを含み、1コマ1コマの絵に贅沢さを感じる絵柄・・・それが私の思う「挿絵」風の絵柄だ。
この別冊付録「風小僧」は、これだけ読んだだけでは、風小僧の設定がよく分からないが、とりあえず山彦剣法の使い手で、正義の味方であることは確かだ(笑)。
主人公「風小僧」こと「風の小六」の設定について調べたところ、ウィキペディアによれば・・
「奥州煙ヶ獄城城主・鈴木氏勝が元家臣の煙丸に謀殺され、煙ヶ獄城は煙丸に乗っ取られる。氏勝の子・小六は疾風之介に風神の術を学び、風小僧として風神の術を使い、煙ヶ獄城再興のため戦う。」
とのこと。それが物語の基本設定のようだ。
この別冊付録では小六は「殿」と呼ばれている若者姿なので、城再興は実現したように思える。
で、「風神の術」や「山彦剣法」で悪者と戦うわけだ。
この別冊付録に出てくる相手は、煙ガ岳(けむりがたけ)に住んで、300年もの間先祖の宝を守り続けている妖鬼「鶴姫」とその一党である。
この鶴姫が敵なのか味方なのかが、この1冊を読んだだけでは判別しにくい。
悪役の妖鬼っぽくはあるが、切ない過去もありそうで、一概に悪と決め付けられないような雰囲気も漂っている。
ともあれ、波乱万丈の冒険活劇時代劇劇画・・・・そんな作品であるのは間違いなさそうだ。
テレビ番組としては、かなり人気があったようだが、あいにく私は世代的に見れていない。
今回初めてこの劇画に触れ、なによりこの挿絵風の絵柄に魅力を感じた。
こんな挿絵風の絵柄で、若い漫画家が今の時代に登場してきたら・・・そう想像すると、けっこう楽しい。

↑ 別冊付録「風小僧」の裏表紙。表も裏も画風がリアルだ。










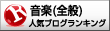







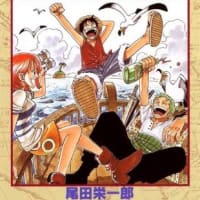
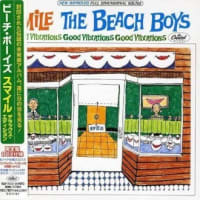







※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます