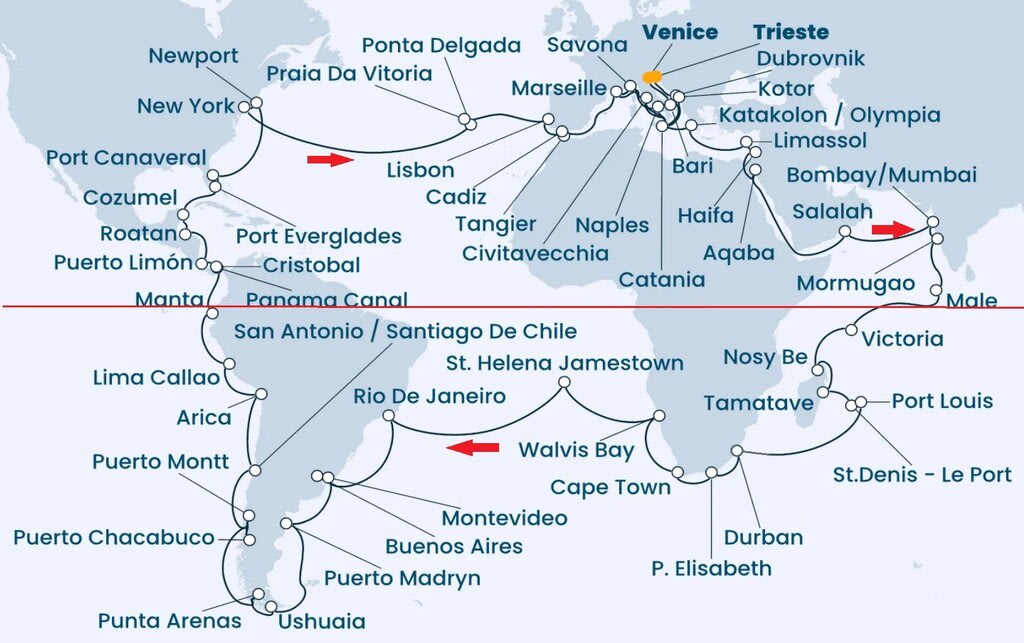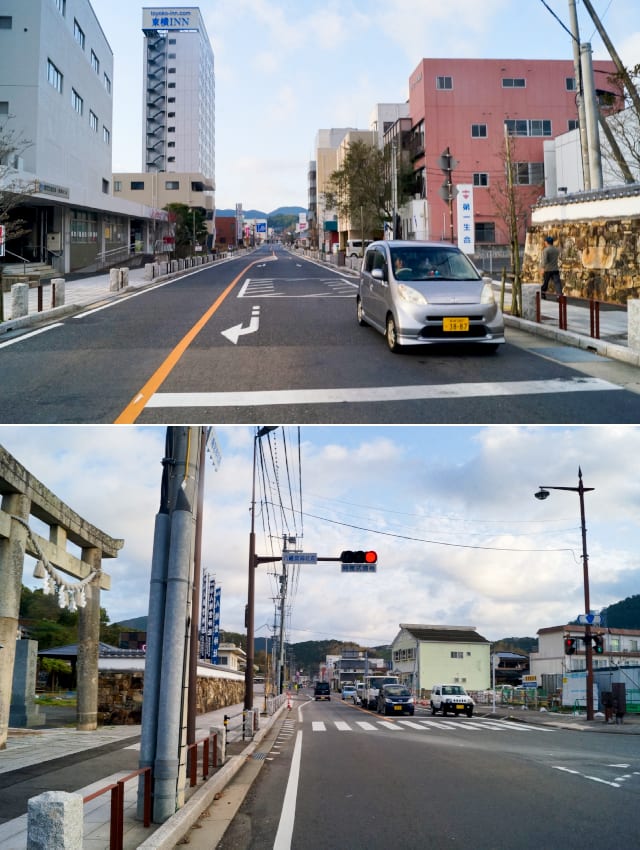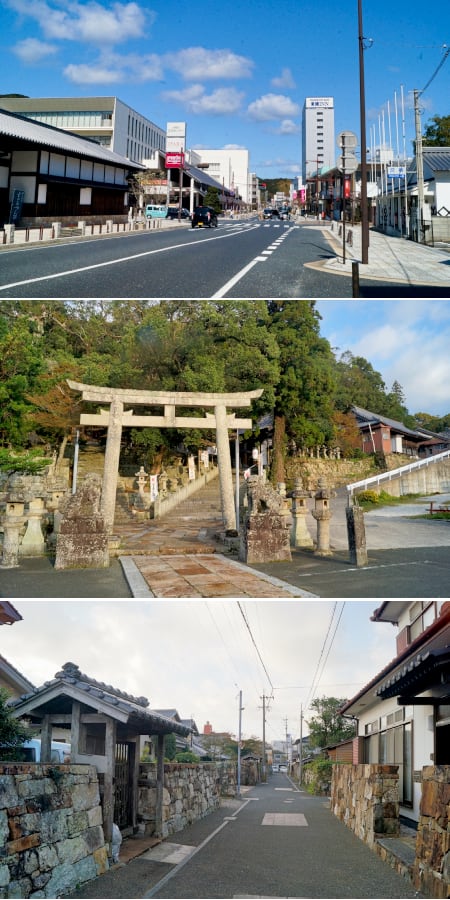*1
今回は、家族、教育、多民族、親切を切り口に北欧と中国を見ます。
そこから社会の適応力と多様性が見えて来ます。
これらは社会発展の原動力になっている。

< 2. 教育現場、北欧の公園にて >
上: ノルウェー、首都オスロ郊外の湖にて
平日の朝早く、湖を見に行った。
8時を過ぎると、中学生か高校生らしい十数名のグループがやって来て、スポーツを始めた。
下: デンマーク、ロスキルの公園にて
平日の1時半頃、公園内を通り抜けた時、至る所で小学生や中学生のグループが見えた。
どうやら先生が引率して、何か課外授業を行っているようでした。
12日間の旅行中、緑豊かな公園で生徒が先生と一緒に居る光景を数多く見た。
この時期、北欧は長い冬をやっと終え、正に待望の初夏到来だったからもあるだろうが、それにしても自然と共に過ごすことを重視している事に感銘を受けた。

< 3.垣間見たチャレンジ精神 >
オスロ湾の島に掛かる橋Ulvøya bridgeにて。
海面より10mの高さから中学生らしい男女のグループが飛び降りようとしていた。
平日の午後3時頃でした。
おそらく授業は終わったのだろうが、それにしても危険だとして禁止されている雰囲気は無かった。

< 4. 教育現場、中国の大学にて >
共に廈門大学の構内にて
この中国旅行で、私が教育に関わるものを見たのはこの大学だけでした。
この大学の見学は、友人の特別な計らいにより実現出来た。
中国の観光ツアー客もいたが、門でチェックを受けていた。
上: 最も目立った校舎
緑が多く広いキャンバスに校舎、図書館、博物館、寮、食堂などが点在している。
下: この区域には寮や食堂が多い
歩いている学生に東南アジア系の人が思ったより多くいた。
この大学は、中国の中では国際交流と留学生の受け入れに積極的だそうです。
構内を案内してくれた中国人は、大学の国際交流担当の係員で、日本に行ったこともあり日本語を流暢に話していた。
廈門大学には日本語・日本文学科がある。
中国国内を旅行していると分かるが、外国人を見かけることは少ない。
雲南に行くと、隣接すらからだろうが東南アジアの人をたまに見かけることがあるぐらいだ。
廈門空港で経験したが、外国人の移動には神経を尖らせているようだった(ツアー旅行ではないからかも)。
まだ中国は、広く一般の外国人を受け入れるつもりは無いようだ。
そうは言っても、中国人の海外への関心は高い。
中国からの海外旅行者の多さもそうだが、海外留学も年間70万人(2018年、約5年で倍増)に近く、50%以上が米国に行っている。
彼らが帰国して、中国の技術や経済の発展を支えることになる。
これは華僑の精神が、今も生き続けいてるからだろう。
同年の日本のからの海外留学生は9万人、その25%が米国だった。
人口比率で見ると日本の方が多いが、日本の場合は年々低調になっている。
また多くは1ヶ月ほどの語学留学になってしまった。
これでは日本が遅れ取っても不思議ではない。
* 北欧と中国の教育について
北欧では、スウェーデンのストックホルム大学の構内を散策したが、実に開放的でした。
校庭には学生グループに混じって親子連れなど一般市民が広い芝生で楽しく過ごしていました。
一方、中国は監視が厳しいので、これは出来ないようだ。
北欧では教育の場において、自然と共にのびやかに生きることを教えているようでした。
北欧の学費は無料だが、進学については先ずは休学して社会を経験し、自分の目指すことを見っけてから、再度、学びを始めることが可能になっている。
これを可能にする制度と社会の受け入れ態勢が出来ている。
これは日本に無い個人を尊重した文化の現れでしょう。
一方、中国では、聞くところによると、学歴(学力かも)が重視され詰め込み教育が為されているようです。
これは日本とそっくりと言えるが、海外への関心の高さは北欧に近い。
ただ、海外留学組は中国の裕福な家庭に限られるので、貧富の差が開き、固定化する可能性があるだろう。

< 5. 移民・多民族、北欧で >
上: スウェーデン郊外、Älvsjö にて
土曜日朝7時頃、鉄道駅の横のバス停にて。
これから出勤する所でしょうか、アフリカ系、白人、ヒスパニックかインド系、ムスリムも居るようです。
私の見るところ、談笑しているようでした。
この地域は、移民が多く住んでいる。
もっともスウェーデンでは外国に背景を持つ人は25%にもなります。
従ってこの地域の移民が30%を越えても特別では無い。
下: スウェーデン郊外、Märsta station の前にて
平日の午前11時前、駅に向かっていた。
この日は、私が北欧観光の1日目で、通勤の光景を見るのが始めてでした。
驚いたことに、白人に混じって、かなりの非西欧人が駅に向かって歩いていた。
34年前の北欧とはかなり雰囲気が異なりました。
当時もホテルのウェイターに非西欧人はいたが、町で見かけることはほとんど無かったように思う。
変化が凄い。
北欧三ヵ国は、大戦中、概ね中立を守り、特にスウェーデンの戦争被害が少なかった。
それ以前は貧しいかったので移民を出す国だったのだが、戦後復興を一早くやり遂げるために移民受け入れを精力的に行った。
当然、受け入れ態勢も、安く使い捨てすれば良いといものではなかった。
これが人口増加と経済成長を後押した。
北欧は、単に経済的な手段としてではなく、世界平和の観点から難民受け入れにも積極的だった。
こうして外国を背景にする人が溢れることになった。
なぜ日本のように移民や難民に閉鎖的では無いのだろうか?
二つの要因が大きいと考える。
やはり、ヴァイキング精神が息づいており、世界との繋がりをいつも意識している。
日本でも海外に勢力を広げた倭寇は存在したが、なぜか日本文化に影響を与えなかった。
今一つは、北欧が小国で、西欧や東欧の大国の意向に翻弄され、かつ適当に離れていたことが大きい。
従って、北欧は生き残るために、世界の国々による認知と支援が必要だった。
これはバルト三国にも通じる。
このことが、北欧が世界平和に積極的になった一因だろう。
こうして移民を受け入れた事と大戦を避けた事が幸いして、北欧の恵まれた社会が誕生したと言えそうです。
そうは言っても、北欧も移民問題では苦労し始めている。

< 6. 多民族、中国で >
上: 昆明の公園にて
下: 麗江の市場にて
昆明、麗江の紹介で詳しく記しましたので、詳細は省きます。
一言で言うと、多くの少数民族が保護され優遇され漢民族と共存している。
欧米ではマイノリティへの優遇策は最近縮小傾向にあるが(右翼化も一因)、中国では現在も有効なようです。
しかも日常的に民族衣装を来ている姿から、誇りすら感じているように思える。
共産主義だから息苦しと思っている人も多いだろうが、そう単純ではない。
* 北欧と中国の移民・多民族の共生について
北欧に民族問題は無いのか?
実はスカンジナビア半島北部に暮らすサーミ人は代表的な少数民族です。
北欧三ヵ国(ゲルマン系)とは人種・言語・生業(元は遊牧民)が異なります。
かつて苦労したようだが、現在、大きなトラブルはないようです。
中国は人口減の時代に突入したので、移民政策を採る必要があるだろう。
多民族国家を無難に乗り越えたが、香港やウイグル族の扱いのように、体制の転換を恐れるが為に、移民政策を進めることが出来ないかもしれない。
そうすれば経済成長にブレーキがかかるだろう。
翻って、日本はアイヌ以外に民族問題は無く、移民・難民を大きく制限しており、一見、安泰のように思える。
しかし、人口減の影響は大きく、移民を受け入れない影り、経済成長は期待出来ない。
ところが技能実習制度と呼ばれる隠れ蓑で、低賃金で汚い過酷な労働を担わせている。
これを放置すると、日本はやがて欧米と同じ移民問題で苦しむことになる。つまり、外国人労働者の低所得と低水準の教育が、悪循環を生み、やがて底辺層の治安悪化と日本人との仕事の奪い合い(賃金低下)に発展するだろう。

< 7.家族、北欧で >
上: オスロ、ベイエリア開発区の裏側にて
平日、午後4時前頃。
中近東系の男性がベビーカーを押している。
父親が子供を連れている姿を他でも見ることがあり、子連れの女性より男性の方が目だった。
下: スウェーデン郊外、Älvsjö にて
平日、朝7時半頃。
父親が娘二人を学校にでも連れていくようです。
北欧では、男女平等、夫婦共稼ぎが普通であり、祖父母と同居していないので、家事や子育ては夫婦で分担することになる。

< 8. 家族、中国で >
上: 麗江の古陳にて
土曜日、午後1時過ぎ頃。
中国ではどこに行っても、祖父母が孫をあやしている、または連れている光景を見る。
これは一人子政策の名残りと、若夫婦共稼ぎ、そして50歳代で祖父母が定年退職で年金暮らしになるからです。
少なくとも、祖父母には愉しみがあり、また家族の繋がりが強いとは言えそうです。
下: 廈門の公園にて
平日、午前9時半頃。
時折、お父さんが子供を連れている姿を見ることがありました。
特に子連れの女性が多いと言う印象は有りませんでした。
* 北欧と中国の家族について
意外に思えるのだが、北欧も中国も共稼ぎで、夫婦で家事や育児を分担している。
対極にある国のようだが、似ている。
一方、日本と言えば、両地域に比べ、共稼ぎの割合が低いにも関わらず、家事分担どころではなく男女平等とは程遠い。
だが中国と日本で似ている所もある。
それは祖父母と若夫婦の繋がりで、日本では祖父母と同居する率は高い。
中国の同居率を知らないが、毎日、孫の面倒を見れる距離に住んでいる人が多いのだろう。
これは儒教の影響だろうか。
北欧にも不思議なことがある。
あれだけ若い夫婦が家庭を大事にしているのに、子供は高校生ぐらいから独立を始める。
そして親は老齢になっても、子供と暮らすことを望まず、最後は一人暮らしを続ける。
東アジアの人間にすれば、寂しい人生に思えるのだが。
これもヴァイキング時代からの文化が根付いているのだろうか。
冷涼な北欧では、ヴァイキングは狩猟・漁労・農業とさらに交易で生計を立てなければならなかった。
つまり、子供に資産や土地などを残す術は限られていた。
そこで独立心と冒険心を植えることが子供への遺産だったのだろう。
この精神文化が今も健在とするなら驚くべきことです。
中国南部の山岳地帯に暮らした人々、客家もこれに似ている。
彼らは、漢民族の圧力に押されて南下したが、やがて海外に活路を求めた。これが華僑の始まりでした。

< 9. 親切、北欧で >
ツアー旅行で無いフリーの旅では、人の親切は身に沁みます。
またその国の国民性を直接感じることが出来ます。
北欧では多くの人の温かい一言や親切に触れました。
上: オスロの地下鉄駅にて
朝、地下鉄に乗ろうとして構内に入ったが、どのホームに向かうべきか迷っていた。
すると一人の夫人が、私に寄って来て、どちらに行くのかと聞いてくれた。
すると彼女は行くべきホームをジェスチャーを交えて英語で教えてくれた。
お陰で目的を達することが出来た。
彼女は通勤途中にも関わらず、時間を割いてくれた、有難い。
下: ストックホルムの中央駅近くにて
バス停を探しても見つからず、途方にくれている時、通りがかりの高齢の夫人に声をかけた。
バス停の位置を聞くと、写真の高架の上の道路上にあると言って、逆戻りして、階段の下まで私を案内してくれた。
案内を終えた時の彼女の笑顔が素敵でした。
北欧では、こちらから道などを訪ねた時の応対が実に親切で有難かった。
一方で、私が困っているを見て、声をかけてくれる人も度々いた。
特に日本に好印象を持っている人が多かったように思う。

< 10.親切、中国で >
上: 新幹線の開封北駅にて
開封駅では、2回も助けられた。
一回目は、外から駅構内に入る時、税関で手荷物検査をしている時でした。
係員が厳しい口調の中国語で、制止した。
困っていると、後の青年が「刃物が有るか」と英語で教えてくれた。
スーツケースを空けると、係員は小さな十徳ナイフを見つけ出し、確認後、通過を許してくれた。
二回目は、待合所で新幹線の到着を待っている時でした。
新幹線の車両は大変長く、改札は新幹線到着直前にしか開かないので、私は予めホームの何処を目指して行くべきか不安でした。
近くにいた若い女性を探し、英語で教えてくれと頼むと、快く引き受けてくれた。
改札が開くと、彼女は私ら夫婦を導いてくれて、ここで待つように言った。
そこには何の印も無かった。
やがて列車が停車すると、乗るべき車両の扉は私の前に来ていた。
下: 蘭州の街中にて
新幹線の駅からタクシーに乗り、都市の中心部まで来たが、運転手はホテルが分からず、迷ってしまった。
ぐるぐる都心部を回っていると、運転手は通りすがりの一人の青年に声をかけた。
青年は助手席に乗り、ホテルまで案内してくれた。
私は青年に感謝を伝え、そこで別れた。
爽やかな青年でした。
* 北欧と中国の親切について
二つの地域を比べて、どちらがより親切かを断言できない。
しかし両方共に、親切だったことは間違いない。
それでも少し違いはある。
理由は定かではないが、北欧では年配者ほど親切なようです。
一方、若い女性に尋ねた時は、良い返事が得られなかったことが多い。
ひょっとすると若い女性(駅で2回ほど)には、なぜか英語が通じなかったのかもしれない(移民の子女か)。
ただスウェーデンの鉄道駅や空港の係員には、英語が出来ないと冷たくあしらう人がいた。
一方、中国では、年寄りよりも若い人の方が親切でした。
若い人は日本に関心を持っており、英語の出来る人が多かった。
中年以上ではマナーが悪かったり、私が列に割り込んだ時「リーベンレン」と小さく吐き捨てるように言われたことがあった(私が悪いのだが)。
成都空港でタクシーに乗って運転手に近距離を頼むと、うるさく文句を言われ続けた(2回も)。
逆に、北京で中国版ウーバー(滴々出行)に乗った時、変な体験をした。
初めて乗ったは良いが、手違いで行先が間違っており、キャンセルや変更が出来ず、更に現金払いも出来ず、私達は途方にくれた。
結局、運転手は嘆き、私に文句は言うが怒ることはなく、私の現金も受け取らず、去っていった。
運転手はどうやら滴々出行の評価システムを気にしているようでした。
ここでも中国の新しい側面を見ることが出来た。
次回に続きます。