娘が、最近自分は暗くなったと悩んでいる。
以前のように、ノーテンキであっけらかんとした気分に
なれないのだと言う。
学校でも、もう馬鹿な真似をして騒がないものだから
クラスメートにも暗くなったと言われるらしい。
夜、ベッドに入ってからも、
「みんないづれは死んでしまうんだよなぁ・・・。」
などと考えて気持ちが沈んでしまうのだとか。
そうか。
娘よ、それが大人になるということだ。
世の無常に気付き、自分の存在に意味を求める。
答えの出ない問いに悩み、訳もなく悲しくなったりする。
私もそうだった。同じだったよ。
そう話すと、急に明るい顔になって
「そうなんだ。それでいいんだね。」と
救われたように元気な声を出した。
人生は複雑なものだ。
だから、複雑な思考に耐えるための
頭と心の準備が始まったのだよ。
暗いことを恐れることはない。
物事を深く考える時、人は誰でも暗くなるはずだ。
難しいことは考えたくないと何でもジョークで流すような
今風の明るくて軽い人間を私は信用しない。
暗くて結構。それでいいのだ。

以前のように、ノーテンキであっけらかんとした気分に
なれないのだと言う。
学校でも、もう馬鹿な真似をして騒がないものだから
クラスメートにも暗くなったと言われるらしい。
夜、ベッドに入ってからも、
「みんないづれは死んでしまうんだよなぁ・・・。」
などと考えて気持ちが沈んでしまうのだとか。
そうか。
娘よ、それが大人になるということだ。
世の無常に気付き、自分の存在に意味を求める。
答えの出ない問いに悩み、訳もなく悲しくなったりする。
私もそうだった。同じだったよ。
そう話すと、急に明るい顔になって
「そうなんだ。それでいいんだね。」と
救われたように元気な声を出した。
人生は複雑なものだ。
だから、複雑な思考に耐えるための
頭と心の準備が始まったのだよ。
暗いことを恐れることはない。
物事を深く考える時、人は誰でも暗くなるはずだ。
難しいことは考えたくないと何でもジョークで流すような
今風の明るくて軽い人間を私は信用しない。
暗くて結構。それでいいのだ。














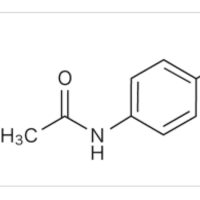











以前眼科医の方が書いておられた記事を思い出しました。現在日本では近視でない人の方がすくないようになりましたが、寝ている間部屋が明るすぎるのも原因の一つだそうです。目には暗闇が必要なのですね。
その話から、やはり心の発達にも闇が必要なのかもしれないと思います。
私は小学生の高学年のとき、ふと目にとめた「善の研究」ということばの意味がわからなくて、父に尋ねたことがあります。そのとき、世の中には哲学という学問があり、人の生きる意味とか、存在の意味を考えるのだよと教えられました。まあ、それからずっと生きる意味、存在の意味を考えつづけているのですけどね。大学で哲学を専攻しましたけど、入学するとき父がとても苦笑していたのを覚えています。答えのないことを問うのは不毛だと言われる方もいらっしゃいますが、私にはこの問いかけこそが、人生の醍醐味のように感じられるのです。
目にも心にも光と闇が必要とはなかなかに深い言葉ですね。
“思春期うつ病”という、いわゆるうつ病とは違う一過性の症状がありますが、これはまさに精神が成長している証拠なのですね。
>答えのないことを問うのは不毛だと言われる方もいらっしゃいますが、私にはこの問いかけこそが、人生の醍醐味のように感じられるのです
同感です。
答えが出ないことを恐れてはいけない。いつまでも、いつまでも、ただひたすらに答えを追い求めることも、人生には必要だと思います。
私も「心の発達にも闇が必要」だと思います。
私は哲学を勉強したわけではないのですが、人間が文明社会で生きていく限り、「哲学的なるもの」はいつも頭の「ちから」として必要だと思っています。私の記事はお二人のやり取りとは、ちょっと角度がちがうかもしれませんが、「こんな事も考えてます」という意味で書いてみました。
私が若い頃は「哲学=インテリ」というイメージで、憧れました。
ただ、全然理解できなかったけど
格好悪く生きよう
うわべだけ格好よくとも
それは自分ではないから。
明るいこと、軽妙さ。それは結構なことだと思いますが、それはまじめなこと、一生懸命に悩んだことを乗り越えたからこそ価値があるように思いますね。諧謔性は人間の一面であるけど、それだけではそれを「かろみ」とは言えないでしょうから。
自分ときちんと向き合い、そのときの自分との対話が自分の栄養になると思います。哲学というのは一種の態度であり、いつもそのときの真実への問いかけをしていくというだけです。
私もそう呼びかけたいですね。
若い人特有の生硬さが、今の時代失われつつあるような気がします。
もっと青臭くていいじゃないか。
それが若者の特権なのだから。
わけ知り顔になるのはまだ早いぞ。
そう言いたいです。