
先週の土曜日、地域の九条の会の人たちと、靖国神社の軍事博物館遊就館を見に行ってきました。
靖国神社の前は何度も通ったことがあり、いつもその異様に大きな鳥居に不気味なものを感じていましたが、中にはいるのは初めてでした。鳥居を入ってみると普通の神社風で屋台?が並んでいたりいろいろな人がのんびりと歩いている風です(何度も来たことがある人によれば物々しい感じの時もあるらしいですが)。軍隊創設に功労のあった大村益次郎の像にしても、まあ特に違和感はありません。
本殿のすぐ右横に綺麗な建物があるのでこれが遊就館かとおもったら、その奥に非常に立派な建物があり、そちらが本物でした。これは靖国神社全体から見てもやっぱり異様です。正面の左には東京裁判で日本に有利な主張をしたと言われているパール判事の大きな写真と彼が言った言葉が掲げられていて、右側には特攻隊の像に、彼らの犠牲の上に日本の平和が築かれたといった銘文が付けられていました。早くも靖国神社の主張が全面に押し出されていると感じました。不本意ながら800円を払って中に入ってみると、広い空間に零戦が展示されています。
そこから延々と展示が続くわけですが、その内容はとてもすべてを書き切れません、というよりとても1日では全部を見切れない量がありました。
全体の印象としては、お金をかけて彼らの主張が非常に効果的に並べられているということ。次のようなことが特徴と感じました。
このような内容が、これでもかこれでもか、と続くので、非常に疲れました。すっ飛ばして見ても2時間近くかかった。
さて、9月号の『世界』(岩波書店の月刊誌)に保坂正康さんが「靖国神社とA級戦犯」という文章を書かれていて、そこで
たとえば当時の靖国神社の宮司だった松平永芳という人は皇国史観で有名な東京帝大の平泉澄という人の影響を大きく受けていて、同じ平泉門下には終戦の時に反乱を起こした一団もいたということ(9月号文藝春秋『昭和天皇「靖国メモ」未公開部分の核心』など)。こういう人たちにとってはまさに戦前と戦後は連続しているのでしょう。そして戦後閉館とされた遊就館が1986年に新装というのは保坂さんのいう"クーデター"とも重なってきます。さらに2002年に苦しい財政事情にもかかわらず前述のような豪華な大改築を行ったというのは、教科書問題でのかれらの攻勢とも重なってくるようです。遊就館の展示はまさにこうした戦前からかわらない皇国史観を持った人たちが総力を挙げて作ったのだなあ、と恐ろしくなりました。このような神社にいろいろな形で国が関わっているということも許し難しことです。
見学コースの最後には売店があり、新しい歴史教科書をつくる会の歴史教科書、小林よしのりの『靖国神社』、そして安倍晋三の『この国を守る決意』などが並べられていました。新しい歴史教科書を作る会の主張は底流のところではこの遊就館の展示と重なってきます。子供たちがこのような内容で教育されたら本当に恐ろしいことになるなあ、と痛感させられた一日でした。
靖国神社の前は何度も通ったことがあり、いつもその異様に大きな鳥居に不気味なものを感じていましたが、中にはいるのは初めてでした。鳥居を入ってみると普通の神社風で屋台?が並んでいたりいろいろな人がのんびりと歩いている風です(何度も来たことがある人によれば物々しい感じの時もあるらしいですが)。軍隊創設に功労のあった大村益次郎の像にしても、まあ特に違和感はありません。
本殿のすぐ右横に綺麗な建物があるのでこれが遊就館かとおもったら、その奥に非常に立派な建物があり、そちらが本物でした。これは靖国神社全体から見てもやっぱり異様です。正面の左には東京裁判で日本に有利な主張をしたと言われているパール判事の大きな写真と彼が言った言葉が掲げられていて、右側には特攻隊の像に、彼らの犠牲の上に日本の平和が築かれたといった銘文が付けられていました。早くも靖国神社の主張が全面に押し出されていると感じました。不本意ながら800円を払って中に入ってみると、広い空間に零戦が展示されています。
そこから延々と展示が続くわけですが、その内容はとてもすべてを書き切れません、というよりとても1日では全部を見切れない量がありました。
全体の印象としては、お金をかけて彼らの主張が非常に効果的に並べられているということ。次のようなことが特徴と感じました。
- 日本の鎖国時代から欧米がアジアに進出してくるなかで、いかに日本の独立を守るために戦ってきたかということを一貫したテーマとしている
- 明治から現在までの日本を連続性でとらえ、そのために都合の悪いことは小さく扱う
- 20世紀初頭の世界では欧米各国がそれぞれ自国の利害のために他国への戦争を仕掛けていたということを強調
- 日露戦争"勝利"などは特に大々的に扱い、大画面の映像、音声を効果的に配置
- 民衆の戦争の被害、悲惨さなどは全く出てこない
このような内容が、これでもかこれでもか、と続くので、非常に疲れました。すっ飛ばして見ても2時間近くかかった。
さて、9月号の『世界』(岩波書店の月刊誌)に保坂正康さんが「靖国神社とA級戦犯」という文章を書かれていて、そこで
1987年にA級戦犯の合祀を画策したグループは、戦後社会の底流を流れている大日本帝国の戦争観であり、そして歴史観であった。私の見るところこの厚生省引き揚げ援護局、靖国神社総代会、そして靖国神社宮司の関係は、トライアングルの空間をつくっていて、それが一方的に、いわば国民の見えないところでA級戦犯合祀を進めたことがわかってくると述べ、
靖国神社へのA級戦犯14人の合祀は、実は戦後社会にあって密かに進められたクーデターのようなものだったのかもしれないとも言っています。
たとえば当時の靖国神社の宮司だった松平永芳という人は皇国史観で有名な東京帝大の平泉澄という人の影響を大きく受けていて、同じ平泉門下には終戦の時に反乱を起こした一団もいたということ(9月号文藝春秋『昭和天皇「靖国メモ」未公開部分の核心』など)。こういう人たちにとってはまさに戦前と戦後は連続しているのでしょう。そして戦後閉館とされた遊就館が1986年に新装というのは保坂さんのいう"クーデター"とも重なってきます。さらに2002年に苦しい財政事情にもかかわらず前述のような豪華な大改築を行ったというのは、教科書問題でのかれらの攻勢とも重なってくるようです。遊就館の展示はまさにこうした戦前からかわらない皇国史観を持った人たちが総力を挙げて作ったのだなあ、と恐ろしくなりました。このような神社にいろいろな形で国が関わっているということも許し難しことです。
見学コースの最後には売店があり、新しい歴史教科書をつくる会の歴史教科書、小林よしのりの『靖国神社』、そして安倍晋三の『この国を守る決意』などが並べられていました。新しい歴史教科書を作る会の主張は底流のところではこの遊就館の展示と重なってきます。子供たちがこのような内容で教育されたら本当に恐ろしいことになるなあ、と痛感させられた一日でした。










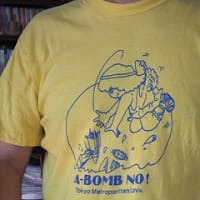




先だっては私のブログにコメントいただき、どうもありがとうございました。
私は、高校時代や大学時代にこそ、政治・経済への関心が高かったものの、このところは、「なんとなく反自民」程度の認識で惰眠をむさぼってきた人間でした。
それが、年々小泉政権の理不尽な政治への反感が高まっていき、昨年の総選挙以降、これは自分でも声を挙げないといけないと思うようになってブログを立ち上げました。以上の経緯なので、党派性は持っていません。
靖国問題と平和憲法のこと、それに新自由主義に特に関心があります。前者については、特定の政治思想を持ったグループにとどまらない広がりを追求していきたいと思っています。かつては、自民党支持者の間でさえ、平和憲法を維持すべきだという人の方が改憲論者より多かった時代もあったのですから。
ブログは2つ持っていて、サブというか雑感を書き散らしている方のブログからTBを送らせていただきました。今後ともよろしくお願いします。