平成18年憲法第2問・再現答案
1.(1) 本問の住民投票を設けることは憲法上明文規定がなく許されないのではないか。(←「違憲ではないか」の方がよかったか。)
この点、住民投票は国民の意思が反映される点で国民主権の原理(1条)を実質化することから国民主権の意義が問題となる。
(2) 思うに、憲法は前文で「国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威を国民に由来し」としており、国民主権には国家権力の行使を国民の名によって正当化されるという正当性の契機が含まれると解する。
他方で、憲法は79条2項、95条、96条1項において直接民主主義的な規定を設けており、国民主権には国家権力は国民によって行使されなければならないという権力的契機が含まれていると解する。
このように国民主権には正当性の契機の他に権力的契機も含んでいることから、憲法上明文規定なくして直接民主主義的規定を設けることは許されると解する。
(3) 本問でも、住民投票を設けることは憲法上明文規定がなくとも許される。
この点、国民投票についても同様に憲法上明文規定がなくとも許される。
2. それでは、本問の住民投票は「全国民の代表」と定める43条、議会の設置を定める93条1項に反し違憲ではないか。
(1) この点、43条は代表民主制を定めている。そして、43条が代表民主制を定めた趣旨は、代表者による討論と妥協を通じて統一的な国家意思を形成し、その過程で少数者の意思を反映させることで多数決の濫用による少数者の人権侵害を防止する点にある。
とすれば、少数者の意見を反映させることができない場合、多数決の濫用による少数者の人権侵害を防止できないから43条に反すると解する。具体的には、住民投票の結果に拘束される場合に43条に反すると解する。
(2) そして、93条1項が議会の設置を定めたのは、地方自治においても代表民主制を採用する趣旨であり、43条の上記趣旨が妥当する。
(3) この点、国民投票については、内閣及び国会は、国民投票の結果に従わなければならないとしており、内閣及び国会が国民投票の結果に拘束されていることから43条に反し違憲と考える。
(4) これに対し、本法律の住民投票についてはどうか。
ア この点、本法律の住民投票については、市長及び議会は、住民投票の結果に従わなければならないとしており、市長及び議会が住民投票の結果に拘束されていることから、43条及び93条1項に反しているとも思える。
イ(ア) しかし、地方自治においては、92条により「地方自治の本旨」に従うことが要請される。この「地方自治の本旨」には、地方自治は住民の意志に基づかなければならないとする住民自治の原則が含まれる。そして、(この住民自治の原則からは)地方の日常生活に身近な事務については住民の意思が反映されるべきであるから、本法律の住民投票は92条の「地方自治の本旨」の要請に適う。
(イ) 他方、国政と異なり住民投票では生活に身近な事情に関するものであり住民個人で判断が可能である。そして、国民投票と異なり、住民投票では規模が小さく、討論と妥協を通じた統一的な住民意思の形成が可能であり、その過程で少数者の意見を反映させることができる。このため、多数決の濫用による少数者の人権侵害を防止することも可能である。(←「可能であり、43条及び93条1項の趣旨にも反しない。」とした方がよかった。)
ウ したがって、本法律の住民投票は43条及び93条1項には反しない。(←「反せず、合憲である。」とした方が良かった。)
以上(3頁52行目まで)
評:B評価
2問目の方はそこそこ書けたんじゃないかと思います。
(個人的には、1問目のミスをカバーしてくれたんじゃないかという気がします。)
① 各予備校で何度か出された問題なので皆それなりの答案準備をしている。それなりの水準の層がかなり厚いと予想。書き負けたり、構成がイビツになったら大きくへこむおそれ大。いわば、差をつけにくいが容易に差をつけられる問題だと思います。
② 受験生一般の構成は、「国民投票→代表民主制の原則から×。住民投票→地方自治の本旨から修正して○。」というオーソドックスな構成だろうから、この構成に従うことに。(まずは平均評価の確保。)
③ あとは、少しずつ印象を良くする工夫をして、他の答案とちょっとづつ差をつけていく。
まずは、問題文に食らいつく姿勢を明示。住民投票を国民投票と比較して論じる問題なので、あくまで住民投票が主、国民投票が従。この姿勢を答案においてアピールすべく、再現答案では主として住民投票を論じ、住民投票を論じるに際の比較の対象として国民投票について軽く触れる形にしました。たぶん、これだけで前段住民投票、後段国民投票といった安直な構成と差がつく。
次は、憲法の条文を解釈しているんだという姿勢を明示。必ず憲法のどの条文が問題になるのかを再現答案でも意識しました。これで、安直に国民主権の意義を長々と述べる答案よりも差が付くとおもいます。
最後に、「地方自治の本旨」による修正のかけ方。予備校の模範答案などでは、「地方自治の本旨」・「住民自治の原則」から地方自治においては住民投票は憲法上許容される、と書かれていることが多い。ここを多少厚く書けば、差がつく気がします。必要性と許容性という観点から修正の論理を考えると修正に厚みが出ます。再現答案では、「地方自治の本旨」を修正の必要性の原理として捉え、「地方自治の本旨」からは修正が強く要請されることを強調。そして、代表民主制の原則を修正の許容性の原理として捉え、修正しても代表民主制の原則には反しないことをしっかりと論じました。このように代表民主制の原則を許容性の原理として扱うことで、この代表民主制の原則が再現答案を大きく貫く原理となり、答案の印象を良くした感じがします。本問では、国政における代表民主制の原則が地方自治においてどこまで貫かれるべきかという点に出題の意図があったとおもわれるので、これに適した答案構成になったのではないかと思います。
1.(1) 本問の住民投票を設けることは憲法上明文規定がなく許されないのではないか。(←「違憲ではないか」の方がよかったか。)
この点、住民投票は国民の意思が反映される点で国民主権の原理(1条)を実質化することから国民主権の意義が問題となる。
(2) 思うに、憲法は前文で「国政は国民の厳粛な信託によるものであって、その権威を国民に由来し」としており、国民主権には国家権力の行使を国民の名によって正当化されるという正当性の契機が含まれると解する。
他方で、憲法は79条2項、95条、96条1項において直接民主主義的な規定を設けており、国民主権には国家権力は国民によって行使されなければならないという権力的契機が含まれていると解する。
このように国民主権には正当性の契機の他に権力的契機も含んでいることから、憲法上明文規定なくして直接民主主義的規定を設けることは許されると解する。
(3) 本問でも、住民投票を設けることは憲法上明文規定がなくとも許される。
この点、国民投票についても同様に憲法上明文規定がなくとも許される。
2. それでは、本問の住民投票は「全国民の代表」と定める43条、議会の設置を定める93条1項に反し違憲ではないか。
(1) この点、43条は代表民主制を定めている。そして、43条が代表民主制を定めた趣旨は、代表者による討論と妥協を通じて統一的な国家意思を形成し、その過程で少数者の意思を反映させることで多数決の濫用による少数者の人権侵害を防止する点にある。
とすれば、少数者の意見を反映させることができない場合、多数決の濫用による少数者の人権侵害を防止できないから43条に反すると解する。具体的には、住民投票の結果に拘束される場合に43条に反すると解する。
(2) そして、93条1項が議会の設置を定めたのは、地方自治においても代表民主制を採用する趣旨であり、43条の上記趣旨が妥当する。
(3) この点、国民投票については、内閣及び国会は、国民投票の結果に従わなければならないとしており、内閣及び国会が国民投票の結果に拘束されていることから43条に反し違憲と考える。
(4) これに対し、本法律の住民投票についてはどうか。
ア この点、本法律の住民投票については、市長及び議会は、住民投票の結果に従わなければならないとしており、市長及び議会が住民投票の結果に拘束されていることから、43条及び93条1項に反しているとも思える。
イ(ア) しかし、地方自治においては、92条により「地方自治の本旨」に従うことが要請される。この「地方自治の本旨」には、地方自治は住民の意志に基づかなければならないとする住民自治の原則が含まれる。そして、(この住民自治の原則からは)地方の日常生活に身近な事務については住民の意思が反映されるべきであるから、本法律の住民投票は92条の「地方自治の本旨」の要請に適う。
(イ) 他方、国政と異なり住民投票では生活に身近な事情に関するものであり住民個人で判断が可能である。そして、国民投票と異なり、住民投票では規模が小さく、討論と妥協を通じた統一的な住民意思の形成が可能であり、その過程で少数者の意見を反映させることができる。このため、多数決の濫用による少数者の人権侵害を防止することも可能である。(←「可能であり、43条及び93条1項の趣旨にも反しない。」とした方がよかった。)
ウ したがって、本法律の住民投票は43条及び93条1項には反しない。(←「反せず、合憲である。」とした方が良かった。)
以上(3頁52行目まで)
評:B評価
2問目の方はそこそこ書けたんじゃないかと思います。
(個人的には、1問目のミスをカバーしてくれたんじゃないかという気がします。)
① 各予備校で何度か出された問題なので皆それなりの答案準備をしている。それなりの水準の層がかなり厚いと予想。書き負けたり、構成がイビツになったら大きくへこむおそれ大。いわば、差をつけにくいが容易に差をつけられる問題だと思います。
② 受験生一般の構成は、「国民投票→代表民主制の原則から×。住民投票→地方自治の本旨から修正して○。」というオーソドックスな構成だろうから、この構成に従うことに。(まずは平均評価の確保。)
③ あとは、少しずつ印象を良くする工夫をして、他の答案とちょっとづつ差をつけていく。
まずは、問題文に食らいつく姿勢を明示。住民投票を国民投票と比較して論じる問題なので、あくまで住民投票が主、国民投票が従。この姿勢を答案においてアピールすべく、再現答案では主として住民投票を論じ、住民投票を論じるに際の比較の対象として国民投票について軽く触れる形にしました。たぶん、これだけで前段住民投票、後段国民投票といった安直な構成と差がつく。
次は、憲法の条文を解釈しているんだという姿勢を明示。必ず憲法のどの条文が問題になるのかを再現答案でも意識しました。これで、安直に国民主権の意義を長々と述べる答案よりも差が付くとおもいます。
最後に、「地方自治の本旨」による修正のかけ方。予備校の模範答案などでは、「地方自治の本旨」・「住民自治の原則」から地方自治においては住民投票は憲法上許容される、と書かれていることが多い。ここを多少厚く書けば、差がつく気がします。必要性と許容性という観点から修正の論理を考えると修正に厚みが出ます。再現答案では、「地方自治の本旨」を修正の必要性の原理として捉え、「地方自治の本旨」からは修正が強く要請されることを強調。そして、代表民主制の原則を修正の許容性の原理として捉え、修正しても代表民主制の原則には反しないことをしっかりと論じました。このように代表民主制の原則を許容性の原理として扱うことで、この代表民主制の原則が再現答案を大きく貫く原理となり、答案の印象を良くした感じがします。本問では、国政における代表民主制の原則が地方自治においてどこまで貫かれるべきかという点に出題の意図があったとおもわれるので、これに適した答案構成になったのではないかと思います。












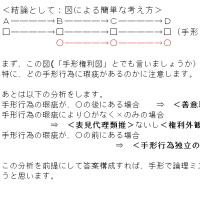
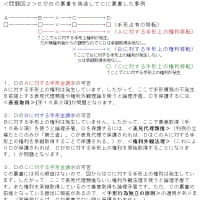
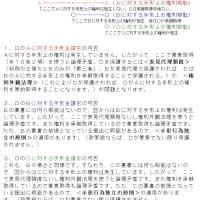
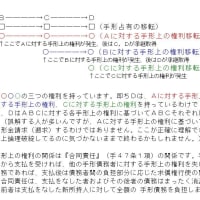


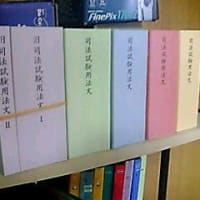
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます