平成18年憲法第1問・再現答案
1. 本法律は放送局の広告放送を制限し、これに違反した場合、放送免許を取り消すものとしており、これは放送局の放送の自由を侵害し違憲か。
2. まず放送の自由については憲法上明文の規定はない。
しかし、放送は事実の報道や制作した番組を通じて意見を発表するものであり「表現の自由」に含まれ、放送の自由は21条1項により保障される。
3. もっとも、放送の自由といえども無制約ではなく、13条後段の「公共の福祉」による制約を受ける。
4.(1) それでは、本法律は「公共の福祉」の範囲内の制約か。合憲性判断基準が問題となる。
(2) 思うに、放送の自由は精神的自由権であり、一旦侵害されれば、民主政の過程によって回復することができない人権である。
そして、放送の自由は、事実の報道や制作した番組により意見を発表することを通じて放送関係者の人格の発展に資するほかに、特に国民の議論の端緒となることで立憲民主政の維持に資し、重要な価値を有する。
とすれば、厳格な基準によるべきである。
もっとも、本法律は放送内容に着目した規制ではなく放送の時間、態様に着目した内容中立規制であり、放送の自由に対する侵害の危険は(内容中立規制に比べ)類型的に小さいから基準をやや緩和し、①目的が重要で②手段がより制限的でない手段が存在しない限り違憲であると解する。
(3)ア 本法律についてみると、本法律の目的は視聴者の多様で質の高い番組へのアクセスの確保にある。現代の情報の送り手と受け手が分離した社会では、表現の自由も受け手側から再構成され知る権利として保障されており、(知る権利が保障されている点に着目すれば)国民にとって判断材料となる情報の多様化(及びその質の確保)は不可欠である。
イ(ア) 手段についても、たしかに午後6時から同11時までの時間帯の広告放送を制限すれば、同時間帯が多くの視聴者がいるゴールデン時間帯であるから多様で質の高い番組へのアクセスを確保できる。
そして、違反者に免許取消処分をすることは、規制の実効性を確保することにつながる。
(イ) しかし、放送局の収入の多くは上記時間帯における広告収入であり、ここでの収入を番組制作費に回しているのが現実である。本法律により数十億円も減収すれば、多様で質の高い番組の制作が困難となり視聴者にとって不利益が大きい。
そして、放送は新聞と異なり電波が有限であるとはいえ、家庭にビデオといった録画機器が普及した現在では、上記時間帯以外の他の時間帯に多様で質の高い番組を放送することでも視聴者の多様で質の高い番組へのアクセスを確保することが可能である。
また、違反した場合に免許を取り消すことは放送に萎縮的効果をもたらし、放送の自由の重要性からはより軽減された過料といった実効性確保のための行政罰により実効性を確保すべきである。
(ウ) したがって、他の時間帯における規制と過料といった実効性確保のための行政罰という他に制限的でない手段が存在するから②を欠く。
(4) よって、本法律は「公共の福祉」による制約を超え、放送の自由を侵害し(21条1項に反し)違憲である。
以上(3頁52行目まで)
<( )内の語句は読みやすくするための事後的な加筆です。>
評:B評価
① 広告放送を制限しているのに、<放送の自由>の制限として捉えたのがマズかった。かなり減点を喰らったと思う。(もしくは配点がもらえなかった。)<広告放送の自由>の制限として構成した方が素直。広告放送を制限することで、放送の自由を制限しているという構成は問題の本質からややズレている。
② 加えて、本法律を内容中立規制にしたことがどうだったか。広告放送の自由構成で内容中立規制とすれば、アウトだったと思う。(広告放送という内容に着目した点を重視するでしょうから。)でも、放送の自由構成で内容中立規制だったから助かったのかも。
③ 問題文に、「国会が午後6時から同11時までの時間帯における広告放送時間の拡大が、多様で質の高い放送番組への視聴者へのアクセスを阻害する効果を及ぼしている」という立法事実が書かれているから、この立法事実を検討することは必須。本再現答案では、LRAの基準を使って検討しました。
④ 数十億円の減収、午後6時~11時の時間帯、免許取り消し、といった事実には点が振ってあるだろうから、あてはめに必須。あとは、これらの事実をどう評価するかでどれだけ点が伸びるかが問題となると思います。
⑤ 本問では、放送局の営業の自由や収益の減少という財産権の侵害も問題となりますが、明らかに放送の自由(広告放送の自由)が制約を受けているを考慮すればメインではない。紙面と持ち時間、配点との関係上、独立に論じるだけの実益がないと思います。収益の減少を29条3項の損失補償として論じていくのも一つの手ですが、あまり費用対効果は高くないでしょう。(むしろ論理ミスのリスクの方が怖い。本法律を合憲とするのなら損失補償ですが、本法律を違憲とした場合、違法な措置ですから国賠請求にしなければなりません。このミスは“論点先にありき”で論点に飛びついた印象を与えかねないので、ある意味イタイ気がします。)
⑥ 結局、問題文の「広告放送を1時間ごとに5分以内に制限」との文言から、<広告放送の自由を侵害し違憲か。>とし、広告放送という内容に着目した規制である点と営利的表現の自由の価値に着目して<内容規制であるが自己統治の価値が希薄→厳格な基準より緩やかな基準(LRA)>として構成するのが良かったとおもいます。あとは、「国会が午後6時から同11時までの時間帯における広告放送時間の拡大が、多様で質の高い放送番組への視聴者へのアクセスを阻害する効果を及ぼしている」という立法事実を検討していけばいい。その際に、「視聴者のアクセス」「午後6時から同11時までの時間帯」「1時間ごとに5分以内に制限」「違反には放送免許取消」「1社平均で数十億円の減収」といった事実をどう評価するかがポイント。再現では、放送の自由に対する過渡の制約事実として捉えました。
ちなみに、「1時間ごとに5分以内に制限」については使いませんでしたが、この事実をどう評価するかも面白い点だったかもしれません。(これを重い制約だと考えれば、例えば、仮に広告放送が1時間毎に30分なされていた場合に果たして重い制約なのかなど、どこまでなら合理性があるのか考える余地が出てきます。実際、番組の見所を中断して無関係なCMを1分近くも見せられればイライラしますし。)合憲の根拠とできる事実として分析できたかもしれません。
⑦ もっと素直に答案構成すればよかったと思います。
1. 本法律は放送局の広告放送を制限し、これに違反した場合、放送免許を取り消すものとしており、これは放送局の放送の自由を侵害し違憲か。
2. まず放送の自由については憲法上明文の規定はない。
しかし、放送は事実の報道や制作した番組を通じて意見を発表するものであり「表現の自由」に含まれ、放送の自由は21条1項により保障される。
3. もっとも、放送の自由といえども無制約ではなく、13条後段の「公共の福祉」による制約を受ける。
4.(1) それでは、本法律は「公共の福祉」の範囲内の制約か。合憲性判断基準が問題となる。
(2) 思うに、放送の自由は精神的自由権であり、一旦侵害されれば、民主政の過程によって回復することができない人権である。
そして、放送の自由は、事実の報道や制作した番組により意見を発表することを通じて放送関係者の人格の発展に資するほかに、特に国民の議論の端緒となることで立憲民主政の維持に資し、重要な価値を有する。
とすれば、厳格な基準によるべきである。
もっとも、本法律は放送内容に着目した規制ではなく放送の時間、態様に着目した内容中立規制であり、放送の自由に対する侵害の危険は(内容中立規制に比べ)類型的に小さいから基準をやや緩和し、①目的が重要で②手段がより制限的でない手段が存在しない限り違憲であると解する。
(3)ア 本法律についてみると、本法律の目的は視聴者の多様で質の高い番組へのアクセスの確保にある。現代の情報の送り手と受け手が分離した社会では、表現の自由も受け手側から再構成され知る権利として保障されており、(知る権利が保障されている点に着目すれば)国民にとって判断材料となる情報の多様化(及びその質の確保)は不可欠である。
イ(ア) 手段についても、たしかに午後6時から同11時までの時間帯の広告放送を制限すれば、同時間帯が多くの視聴者がいるゴールデン時間帯であるから多様で質の高い番組へのアクセスを確保できる。
そして、違反者に免許取消処分をすることは、規制の実効性を確保することにつながる。
(イ) しかし、放送局の収入の多くは上記時間帯における広告収入であり、ここでの収入を番組制作費に回しているのが現実である。本法律により数十億円も減収すれば、多様で質の高い番組の制作が困難となり視聴者にとって不利益が大きい。
そして、放送は新聞と異なり電波が有限であるとはいえ、家庭にビデオといった録画機器が普及した現在では、上記時間帯以外の他の時間帯に多様で質の高い番組を放送することでも視聴者の多様で質の高い番組へのアクセスを確保することが可能である。
また、違反した場合に免許を取り消すことは放送に萎縮的効果をもたらし、放送の自由の重要性からはより軽減された過料といった実効性確保のための行政罰により実効性を確保すべきである。
(ウ) したがって、他の時間帯における規制と過料といった実効性確保のための行政罰という他に制限的でない手段が存在するから②を欠く。
(4) よって、本法律は「公共の福祉」による制約を超え、放送の自由を侵害し(21条1項に反し)違憲である。
以上(3頁52行目まで)
<( )内の語句は読みやすくするための事後的な加筆です。>
評:B評価
① 広告放送を制限しているのに、<放送の自由>の制限として捉えたのがマズかった。かなり減点を喰らったと思う。(もしくは配点がもらえなかった。)<広告放送の自由>の制限として構成した方が素直。広告放送を制限することで、放送の自由を制限しているという構成は問題の本質からややズレている。
② 加えて、本法律を内容中立規制にしたことがどうだったか。広告放送の自由構成で内容中立規制とすれば、アウトだったと思う。(広告放送という内容に着目した点を重視するでしょうから。)でも、放送の自由構成で内容中立規制だったから助かったのかも。
③ 問題文に、「国会が午後6時から同11時までの時間帯における広告放送時間の拡大が、多様で質の高い放送番組への視聴者へのアクセスを阻害する効果を及ぼしている」という立法事実が書かれているから、この立法事実を検討することは必須。本再現答案では、LRAの基準を使って検討しました。
④ 数十億円の減収、午後6時~11時の時間帯、免許取り消し、といった事実には点が振ってあるだろうから、あてはめに必須。あとは、これらの事実をどう評価するかでどれだけ点が伸びるかが問題となると思います。
⑤ 本問では、放送局の営業の自由や収益の減少という財産権の侵害も問題となりますが、明らかに放送の自由(広告放送の自由)が制約を受けているを考慮すればメインではない。紙面と持ち時間、配点との関係上、独立に論じるだけの実益がないと思います。収益の減少を29条3項の損失補償として論じていくのも一つの手ですが、あまり費用対効果は高くないでしょう。(むしろ論理ミスのリスクの方が怖い。本法律を合憲とするのなら損失補償ですが、本法律を違憲とした場合、違法な措置ですから国賠請求にしなければなりません。このミスは“論点先にありき”で論点に飛びついた印象を与えかねないので、ある意味イタイ気がします。)
⑥ 結局、問題文の「広告放送を1時間ごとに5分以内に制限」との文言から、<広告放送の自由を侵害し違憲か。>とし、広告放送という内容に着目した規制である点と営利的表現の自由の価値に着目して<内容規制であるが自己統治の価値が希薄→厳格な基準より緩やかな基準(LRA)>として構成するのが良かったとおもいます。あとは、「国会が午後6時から同11時までの時間帯における広告放送時間の拡大が、多様で質の高い放送番組への視聴者へのアクセスを阻害する効果を及ぼしている」という立法事実を検討していけばいい。その際に、「視聴者のアクセス」「午後6時から同11時までの時間帯」「1時間ごとに5分以内に制限」「違反には放送免許取消」「1社平均で数十億円の減収」といった事実をどう評価するかがポイント。再現では、放送の自由に対する過渡の制約事実として捉えました。
ちなみに、「1時間ごとに5分以内に制限」については使いませんでしたが、この事実をどう評価するかも面白い点だったかもしれません。(これを重い制約だと考えれば、例えば、仮に広告放送が1時間毎に30分なされていた場合に果たして重い制約なのかなど、どこまでなら合理性があるのか考える余地が出てきます。実際、番組の見所を中断して無関係なCMを1分近くも見せられればイライラしますし。)合憲の根拠とできる事実として分析できたかもしれません。
⑦ もっと素直に答案構成すればよかったと思います。












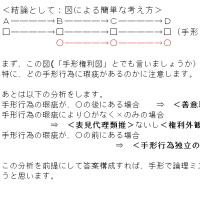
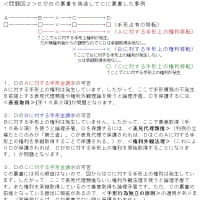
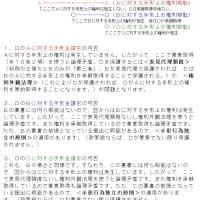
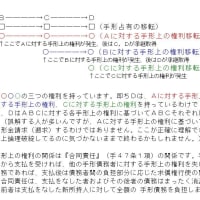


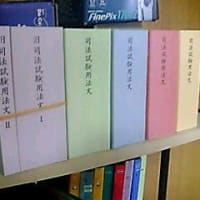
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます