
すでに新聞評の紹介やスコアデスクでの鑑賞記、そして先日はわたしの影のない女持論なんかもバイエルンの公演にかこつけてコメント欄で延々お喋りしていたのに、またもやしつこく影のない女とユロフスキねたの記録、ですので、関心のない方はさっさと飛ばしてくださいまし。
今回ジュリアード管とのコンサートは別記事にしましたが、その前日に行われたNYワーグナー協会のユロフスキ、キャスト、舞台ディレクター(それぞれ別枠トーク)の影のない女のお話会については、一部の今回の公演に関する情報だけこの記事でふれることにします。それにしてもお話会、ユロフスキはわたしは解釈を演奏を通じて聴くのも大好きですけれど、なんというかあの自己宣伝や他人の批判とかの余計なことは言わない知的なストレート・トークというか、聞き手はくどくど多くの言葉で説明されないでも何が言いたいかズバッと簡潔に分かるような大胆な言い回しをする独自の(ユーモアの?)センスがもうとってもつぼにはまるものですから、話を聞くのも大好きなので、大変楽しみました。ユロフスキは、例えばこんにちの大掛かりで派手な舞台装置を形容するのに、突然、「チャールズ二世時代ばりの」(参考:王政復古した際、クロムウェルが禁止した舞台劇を復興)とか、「ワーグナー禁止の家だったので、当然シュトラウスはワーグナーに夢中になり」(参考)とか、「シュトラウスはえせワグネリアン、というかワグネリアンぶってただけで」(参考:実際はベルリンのロイター教授を引用してたのですが、シュトラウスが影響を受けたのは、オーケストレーションとかの音楽的な面だけで、ワーグナーの神話的や形而上学的なところはスコンと抜けてることを指してるんだと思う)、とか、「シュトラウスはまともな指揮者でしたから」とか、「速度指示通りにやるべき、そうするとオーケストレーションが厚い部分は実質的に音符の半分は演奏不可能になりますから」(注:指示に通りにやると大仰でリッチな爆演じゃなく、シュトラウスが意図した通りの音色が混じり合った風合いが出る) とかの言い回しとか、あの午後は格別ユロフスキ節全開な感じで、わたしはもうずっと感動で笑い転げてました。でもわたしが訳すと、そして文脈がないと、ちっとも面白さが伝わらないですね。
前に紹介したFTの評などで、今回の初演時に空席が目立ったことは世に伝わってるかもしれないですけれど、この公演、さすがにメディア力、オペラ好きの口コミパワー、NYC近辺の潜在的オペラファン観客の規模を実感しました。それは既に二日目の週末夜の公演(一斉に絶賛評が出た後)、当日チケット受取りの列が非常に長くて(直前に買うと郵送じゃなくて自動的に窓口受取りになる)、これはどうも評判がいいから見に来ることを決めた人が多いんだろうな、という感触がありましたが、行く度に観客が増えていったような。一般的に一番観客数が多そうな土曜のマチネなどは、最上階席もあの後早速ソールド・アウトになってましたし、あの日はHD映画上演日かのような数のお客さんだった。シュトラウス好きで、なかなか上演がない作品をいい形でやってくれている今回の公演はやっぱり予定を変えて複数回見に行くことにしたコアなファンのリピーターも多くいた感触もありましたが、今回のがゴーキの「スター誕生」公演で、将来のブリュンヒルデをいち早く聴いておきたいという人々も多かったでしょう。どちらにしてもいいものはやっぱりキャッチしたいというお客さん、やっぱりかなりの数いるのだな、でした。今回のが、事前の宣伝ギミックがなくても、スターパワーがなくても、一般的には人気度が高くはない、しかも13年前の演出の二度目の再演で平日には敬遠されそうな長ーい演目だったとしても、やっぱり優秀な指揮者率いる一座がいいものを出せば、世が認めてお客さんも入るのだ、の手本になって、今後のメトのレパートリー選択やキャスティングに影響してくれると喜ばしいのだけれど・・・、現在の支配人だとあやしいもんです。
7, 12, 16, 20, 23, 26 Nov
Vladimir Jurowski ヴラディーミル・ユロフスキ 指揮
皇后: Anne Schwanewilms * アンネ・シュヴァネヴィルムス (Meagan Miller * ミーガン・ミラー 16日のみ)
皇帝: Torsten Kerl トルステン・ケルル
バラク妻: Christine Goerke クリスティン・ゴーキ
バラク: Johan Reuter ヨハン・ロイター
乳母: Ildikó Komlósi イルディコ・コムロジ
ファルケ: Jennifer Check ジェニファー・チェック
伝令: Richard Paul Fink リチャード・ポール・フィンク
せむしの兄弟: Allan Glassman アラン・グラスマン
片目の兄弟: Daniel Sutin ダニエル・サティン
片腕の兄弟: Nathan Stark * ネイサン・スターク
声: Maria Zifchak マリア・ジフチャック
護衛: Andrey Nemzer * アンドレイ・ネムゼル
幻の若者: Anthony Kalil * アンソニー・カーリル
夜警: David Won, Jeongcheol Cha *, Brandon Cedel * デイヴィッド・ウォン、ジュンチュル・チャー、ブランドン・セデル
召使: Haeran Hong, Dísella Làrusdóttir, Edyta Kulczak
生まれてない子: Jihee Kim */ Anne-Carolyn Bird, Ashley Emerson, Monica Yunus, Megan Marino *, Renée Tatum, Danielle Talamantes *
David Chan (vn solo) デイヴィッド・チャン, Jerry Grossman (vc solo) ジェリー・グロスマン
Scott Weber (ファルケ役バレエ), Matt Gibson * (幻の若者のダブル)
Herbert Wernicke ヘルベルト・ヴェルニケ 演出・装置・照明
J.Knighten Smit J.ナイトン・スミット 舞台ディレクター
* 今回メトデビュー
今回の主役級四人はそれぞれ自分の歌手としての持ち味が分かっている上に役の掘り下げも素晴らしい歌手が揃っていて、非常に成熟した歌唱・演技表現、ほんと理想的なものだった。こんな理想的なプロダクションが堪能できる機会はなかなかないもんです。初日なんかは熱狂的なゴーキへそしてユロフスキへの喝采が目立ってましたが、じわじわとその魅力が浸透してったのでしょうか、シュヴァネヴィルムスやロイターへの喝采も最後の方にはそれに劣らず熱烈なものだったです。

シュヴァネヴィルムス
皇后、シュヴァネヴィルムスが最高に素敵だったのは前にも言ったのですけれど、歌唱表現も演技も、たおやかで柳腰で神秘的な美しさのある、そしておしとやかだけれど一本筋が通った皇后、わたしはもうすっかり恋に落ちてしまいました。最初の目が覚めるように美しいけどちょっとぼんやりしたお嬢さんが、バラクの家で控えめながらも色んなことを謙虚におしとやかに、しかししっかりと吸収して学んでいる演技もとっても素敵。でもなんたって目覚めの場面、そしてIch will nicht! と人生の究極の選択、父や魔法界からの決別の素晴らしかったこと! この世のものとも思われないような美しい歌唱だけじゃなくて、シュヴァネヴィルムスは歌わないせりふ部分も完璧な発音・ニュアンスですし、Ich will nichtの部分も、単純に大声で叫ぶというんじゃなくて、Ich will… と宣言を始めても、愛する人を救えない自分の無力さと、しかし間違ったことはどうしてもできないというニュアンスを込めた絞り出すようなnichtの囁きときたら・・・ 彼女が同時代に活躍してくれてて、今回彼女で皇后が聴けたメトの延べ二万人弱のお客さん、非常に幸運なことだったと思います。
実際のシュヴァネヴィルムスは、見かけが非常に美しいだけじゃなくて、まるで(会ったことないけど多分)ディートリッヒのようなオーラというか、古い言葉だけれどああいうハンサム・ウーマンみたいなno bullshitのかっこよさがあって、ディーヴァぶらない自然体なのに魅力ビームをガンガンに発散してるひと、さらに大好きになってしまいました。ご本人が大好きで歌えるのが幸せというシュトラウスもん、特にマルシャリンはもちろん、モーツァルトでもなんでも、再び早くメトに戻ってきていただきたいです。
一公演分だけ、今回メト・デビューを飾ったメトのリンデマン出身のミーガン・ミラー、まぁこんなのは「メトで活躍する歌手」と今後宣伝できる箔付けのような出演でしょうし、皇后としてどうおかしかったか・足りなかったか、なんてことをことさら書くのはかわいそう? なぜか往年のディスコクィーンのような派手なセンス悪いメイクだったせいかもしれないけれど、品には欠けてもまぁ美人、だけどアメリカ人若手にありがちな、声量も技術的なところもしっかりして音符的にはちゃんと歌えていて聴き応えがなくはないのだけれど表現が・・・なにを考え・感じてるのかさっぱり伝わってこない歌唱表現も、近所の気品はないけどいっつも口が半開きでおばかっぽいセクシーな魅力がある美人なおねえさん的な、深み・複雑さがないディズニーチックな演技も、わたしにとってはいまいち以下。それにしても今回「ミラーの皇后は良くなかった」と言って構わないな、と思ったのは、奇跡が起こったあとのロイヤル・デュエット(ふふ)で、あんた邪魔っ、という感じで、すれちがいざまにケルルのケープをバサッとぞんざいに払ったこと。皇后は一緒に死ぬ覚悟だったところに奇跡、なんという幸せ!という場面なのに、かなり興ざめ、あれは酷い。もうわたしはそれまで観客として冷ややかな目・耳になっていたところに、あれは致命的な追い討ちだった。今回あの土曜の夜だけの鑑賞で彼女に当ってしまったお客さんが不憫なような気もしますが、ミラーに関してはデビューの緊張で我を忘れてたのかもしれないし、今回の一回で判断しないで一応次回に期待、ということにしておきます。

ケルル
わたし自身はシュヴァネヴィルムスの次に好きだったのは実は皇帝のケルル。メトは歴史的にも圧倒的な声量の歌手の活躍するハウスだったし、今でも評論家もお客さんも大迫力爆音歌手好き過ぎやしないかい?の傾向があるようにわたしは思うのですが、そのせいかメトのお客さんウケはさほどではなかったかもしれません。そして11月はマイルドに始まってぐっと冷え込んだりもしたので、4日目の公演あたりから、あ、調子悪くなったのだな、という感じで高音がぶれたこともあったし、めちゃくちゃ寒かったお話会の日も最終日の前に大事をとって唯一欠席していて、ご本人の役作りの話なども聞けなくて残念でした。でもその分最終日では少し慎重だったとしても素敵に盛り返してくれて嬉しかった!
シュトラウス&ホフマンスタール作品って魅力的な男性不在か、極端に活躍度や聴かせどころが少ないと思いますが、これはシュトラウスがソプラノと比べると異様にテナー使い下手だからもあるのかな。皇帝は登場機会も活躍度も低いし、非現実的な感じもして実際何考えてるか分かりずらい、共感しにくいかもしれないのですが、狩人的な男性的魅力があってもマンドリーカ(はバリトンですが)みたいに馬鹿っぽくなくて、「そなたが言わずともわしは分かっておる」みたいな高潔で寛容な殿の魅力というか、現実離れして、口から出る事がすべて和歌になってるような平安時代風貴族の趣きみたいなのがあったりして、わたし結構好きです。この演出・衣装もそういう五月人形とかお内裏さまのような感じがあったりするのもようございました。
ケルルは生で聴いた方がその魅力がよく分かる人。声質は、モーツァルト以来の繊細なハンサム・テナーらしい若々しい清々しい風味と、キンと空気を切るような潔さ、男性的な魅力もあるヘルデン的な響きの迫力が大げさでなく、ちょうどいい按配で混ざりあった感じで、それはそれはこの役にほんとふさわしい色合いなのが素晴らしかった! 皇帝はモーツァルト同様テナーが得意の(ふふふ)シュトラウスのお陰で、歌唱がとても難しい割りには活躍度も少なくて、おいしくない役かもしれないのに、今回出てくれて、わたしたちがケルルで聴けて幸運でした!

ゴーキ
バラク妻は地元もいいところ、NYロングアイランド出身・NJ育ち/ 在住、今回の公演で一躍メトの新生スターになったゴーキ。次期ブリュンヒルデ発表になってからそういう耳で聴くと、うーんブリュンヒルデとしては声の鋭さや切れが足りやしないか、豊かな低音の深みは全く問題ないにしても、高音の連続パワーに関しては大丈夫か、なんてことも思いましたが、そんな先の心配は置いといて、バラク妻は歌唱も演技もかなりのはまり役、文句なしです。
バラク妻は、マーラーの書簡集にも登場する女傑、シュトラウスのモーレツ奥さんのパウリーネがモデルだそうですが、演出や役作りによっては、不平不満ばかりでいけすかないビッチになるんでしょうけれど、バラク妻は鼻っぱしだけは強気でキツイ言動をするんだけど、それは、わたしは夫からお金で買われた機能的に便利な主婦という存在なだけじゃないか、赤ちゃんもできなくてあたし何してんだろ、なんていう不安や不満を素直に打ち明けるのが怖くてつっぱってるだけで、本当はかわいい赤ちゃんと愛する旦那さまとのしあわせを望んでいる少し甘えんぼかもしれない女の子、という解釈のほうが、わたしはしっくりくるような。実際まぁその後ヒステリーを起こして家を飛び出すにしても、アンメの誘惑にギリギリでどうしても手を出せずに、バラク起きて!、と彼に「助けてシグナル」を出したりしてるわけですから。
ゴーキは、実際はNJやPAでよく見かける肝の据わったような低い声のしっかりした若いママという感じですけれど、太っててもおばさん的でなくて、舞台上ではタヌキちゃんみたいな大きなたれ目がかわいいくて、あたしはこんな苦悩してるのになんであんたはそんな呑気でいられるの! 夫だなんて名ばかりであたしのことなんて全然分かってくれてない! とか爆発する前は、例えばバラクが出かける時などは、一応控えめに微笑んでいってらっしゃい、してたり、意地悪する時も夫から視線を外して言葉を投げたりするのは、やっぱり傷つけるのは悪いという気持ちもどこかにあるんだろうなぁとか、不満はあっても根は優しいいい子なんだな、とちゃんと観客に伝わってくるので、どうにも憎めないどころかかなり共感できます。
そういう複雑な人物を演技上でも大げさでなくしっかり演じきっていたのも凄いですし、低音部の表現がソプラノとは思えないほどの表情豊かな深みがあるので、色々考えて悩んでるんだな、この子の本音と出てくる言葉は微妙に違うかも、というのがちゃんと観客に伝わってきます。ゴーキ・バラク妻だと、夫の自分に対する愛情、そして自分の夫への愛情に気づいて、素直に本心を伝えられるようになってほんと良かったね、やっと本当の意味で夫婦になれて良かったね、と素直に一緒に喜べたような。この演出ではバラクがキスしようとするのを拒否したりするんですが、それも少々恥らいの風味も入ってイヤ、とやるのは、とげとげしさがなくて共感しやすいし、最後、バラクがねどこを元の二人用にもどしている間、アンメに貰ったヘアバンドをしばし手にとってそれを置いた後、前にバラクが町の子供たちとごちそうを持って帰ってきた時にお土産に持ってきた薔薇をそっと大切に取り上げる時の奥ゆかしさも娘らしいし、貰ったときはふん、なんてやってたけどやっぱりあなたはあの薔薇、大切にとっておいたのね、なんて、この二組の夫婦の試練を一緒に辿ってきた観客としてもじんとくるものがあって、とても良かったです。
今回、誰もが口をそろえてケミストリー、チームの団結・協調力が格別凄かった(それは難しい作品だからもある)と言ってましたが、それは鑑賞してても感じられたもの。ゴーキも今回のチームにはかなりの愛情があって、もうすぐ別れるのがつらい、とまで言ってましたが、それは観客としても同じ思いだったです。

ロイター、ゴーキ
バラクのロイターは特筆するような美声でも声量が凄いわけではないですし、姿も声質もバラクにしては若めかもしれませんが、役作りが知的というか、歌唱表現も演技も素晴らしかった。バラクは仕事熱心だけどめしだけ出せばにこにこしている単純な気の利かない朴訥な男と解釈してもいいのかもしれないですけれど、ロイターだとさらにつっこんだことをやっていて、悩んだりしながらもそれをあえて表に出さないで一生懸命妻を喜ばせたいと思っている男の、そういう表面上と内面との複雑な層の面白みがあるのが凄くいい。彼がやると、人がなんと言おうと、かんしゃくを起こされようとも大切な奥さん、ハンフリー・ボガードじゃないですけれど、Kidなんて呼んで、若妻がかわいくてかわいくてしょうがないのが手に取るように感じられるバラク。バラクは家族思いで子供好きで寛容、仕事も大変そうなのに不平も言わずに明るくつとめたり、外で大盤振る舞いして一人でいい気分で帰ってきてもいいのに、「誰も来ない家」なんて不平を言ってた奥さんのためにわざわざみんなを家に連れてきて、奥さんを交えてごちそうパーティしようとしたり(そんなのはすべて妻の神経を逆なでして空回りするのですが)、この子は根はいい子だと信じて疑いもしない、そしてかなり忍耐強い我慢の人。浮気はともかく、妻が彼女自身や次の世代を傷つけるようなこと「影を売った」のを聞くまでは、ちょっぴりたりとも怒りもしない真面目で優しいいい人、そんな人物をロイターは妻を優しく見つめる大人な演技で聴かせてくれたのも良かったです。
この作品の二つの夫婦は少々パラレルになっているところがあって、それだから皇后も色々学ぶところがあったんだと思いますが、物語の最初では、奥さんは二人とも気持ちの上では結婚のきずなに100%コミットしてない。皇帝は狩人として皇后のガゼールを射止めたわけで、アンメなんかは単純なおつむしかない狩人が獲得した獲物を愛でてるだけ、肉体的な愛情しかない結婚であるかのような示唆をしますが、バラクも妻の実家にお金を払って結婚したという即物的な経緯があっても、わたしはバラクの妻に対する愛も皇帝の愛も、精神的な面も含めた大きな包容力のある愛だったと思いたいです。バラクの場合は「そういうものだ」との単純な思い込みだったかもしれませんが。
ロイターは下記のクリップのアムスの時から、これはコンサート形式だとはいえ、いい味の表情の演技をつけてやってくれていたので、メトの舞台ではその解釈と表現がどれほどさらに磨かれて活きていたか察していただけると思います。
ワーグナー協会のイヴェントでは歌手のみなさん、役柄になりきって冗談を言ったりの楽しいトーク中、ちょっと謙遜もあったんだと思いますが、バラクは奥さんと違って劇中成長しない少々詰まらない人、なんてロイターは言ってましたが、すかさずシュヴァネヴィルムスが、さすがバラクのいい人ぶりに啓発される皇后らしく、でもわたしはバラクは相手を手放しで信用できる人なのがほんとに素晴らしいと思うわ、などと言ってました。
ロイターはシュトラウスならマンドリーカをやってみたい、実際には次のメトの公演のために長ーい役を勉強し始めたということ。(具体的に言うのは避けてましたけれど、ゴーキに「別れてる期間は長くないね」と言っていたのがヒントでしょう。)
アンメのコムロジの衰えたような喉の歌唱は最初はショックでしたが、演技や表現は良かった、実際公演中にもだんだん良くなっていったのじゃないでしょうか。明らかにピークを過ぎた喉でもこんな音楽的にも演技上も難しい役をあそこまで歌えるのは大したものかもしれません。彼女自身は難しすぎてリハーサルに入ってからも降りようか迷ったようなことを言ってましたけれど、それはアンメの言ってる内容と美しい旋律の齟齬がどうも咀嚼しきれないから、ということが大きかったようで、ユロフスキもコムロジが心配になったんだか、わざわざ控え室に尋ねてきて一緒におさらいしたらしい。その時、ユロフスキが、そう、その歌唱です、それでいいんです、と言ってくれたものだから、思わずその悩みを打ち明けたら、その齟齬こそがアンメの人となりを表現している重要な要素なんですよ、と言われてやっとしっくりきた、と言ってました。
ユロフスキ自身はフンパーディンクのヘンゼルとグレーテルの魔女との共通点も指摘しながらも、この作品で一番共感するというかかわいそうに思うのは乳母、となんともユロフスキらしい心優しいことを言ってましたけれど、詳しくはまた後ほど。確かに少しはさっさと魔界に復帰したいという個人的思惑はあったとしても、皇后のためによかれと思って保護者としてあれだけ頑張ったのに、最後は皇后が自立して自分から離れてしまっただけでなく、一人だけああいうことになってしまうんですから、分かる気がします。
ゴーキも「あたしの欲しそうなものが分かって弱みに付け込むヤリテおばさん」みたいなことを言って、コムロジもそれに悪乗りしながらも、最後は、でもねぇ彼女はほんとに皇后を心の底から愛していたのよ、あれは皇后への愛でやってたのよ、みたいに締めてたのは印象的でした。
フィンク、コムロジ
今回、ピークを過ぎた喉を庇うのに叫ぶような調子でやってたのかもしれませんが、歌唱がとても雑な印象で、何度聴いても残念に思うフィンクの伝令とリズム感の悪いファルケ以外は、その他歌手陣すべて非常に素晴らしかったと思います。
また話題の新人のブランドン・セデルくん以下、多くの若手がデビューを飾ったのも思い出深いです。とりわけ記録に残したいのは、以前も響きが凄いと言っていた護衛のネムゼルくん。もともとホフマンスタールは3人のカウンターテナーの護衛というキッチュな設定を提案したそうですが、シュトラウス自身はこの役は「ソプラノ、あるいはとりわけ優秀なファルセット」と楽譜に指示しています。そんな注意書きがあるのは、尋常でなく素晴らしいカウンターテナーじゃなければカウンターテナーを使ってくれるな、ということだったのかもしれませんが、シュトラウスの時代はどうだったか知りませんが、いま現在は優秀なカウンターテナー花盛りの時代、ネムゼルくんはまぁ奇跡のような美しい色合いの音色、そして朗々とした響きはヴェルディをやるようなテナー・スター並みの迫力、これだったらシュトラウスも文句は言わない筈です。今回メトでは初めてこの役をカウンターテナーがやったのですが、ロイターも舞台ディレクターも、ユロフスキがカウンターテナーでやりたいと固持した、ユロフスキがネムゼルを見つけてきた・連れてきた、と言っていました。
ユロフスキとはモスクワ・コネクションもあるのでしょうけれど、実際にはネムゼルは2012年のメトのナショナル・カウンシルの5人のファイナリストの一人で、先シーズンのチェーザレのカバーをしてたそうですから、メトの子でもあるよう。だけど入賞者がメトデビューするのには何年かかかりますし、カウンターテナーが出る演目はただでさえ少ないので、ユロフスキがそうしてくれなかったら実際にネムゼルくんをメトで聞けるのは5,6年後だったかもしれないのに、早い時期にネムゼルの素晴らしい歌唱を多くの観客が聴けるこういう機会があったのも喜ばしいこと。
ネムゼルくんはもともとスピント・テナーだったのに、6年前くらいにアルトのパートが楽々歌えることに気づいてカウンターテナーのトレーニングを始めたそうですけれど、美しい喉の上にカウンターテナー歌手からは今まで聴いたことのないような肉付きというかしっかりしたヴォリュームの迫力、少なくともわたしにとっては、また今だかつてない新たなタイプのカウンターテナー登場、またまた凄い人が出てきましたなぁ、でございます。彼の才能は既存の作品群に上手く嵌らないところもあるかもしれませんが、次の鑑賞機会が楽しみです。(参考クリップ:ラフマニノフの夜のしじまの中で)。
何度もしつこく引用してますけれど、もうこれが最後か、なので、今回のメトの公演の萌芽がまざまざと見て取れる2月のアムスのコンサート形式のクリップをば...
- その2に続く










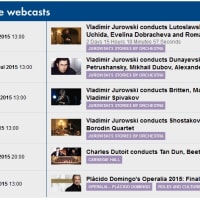

![[Summer 2015] Mostly Mozart: George Benjamin モーストリーモーツァルトのベンジャミン特集](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/7e/75/86269acbcad34761132575feb03d125f.jpg)
![[Summer 2015] Mostly Mozart: George Benjamin モーストリーモーツァルトのベンジャミン特集](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/79/07/0c1611b6ea026eed0a0b094175423d2c.jpg)
![[Summer 2015] Mostly Mozart: George Benjamin モーストリーモーツァルトのベンジャミン特集](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/03/7b/050b793778320ffdd0ee65e474b84a24.jpg)
![[Summer 2015] Mostly Mozart: George Benjamin モーストリーモーツァルトのベンジャミン特集](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/0b/1f/86664af8b7c7633697df5b104d2e7724.jpg)
![[Summer 2015] Mostly Mozart: George Benjamin モーストリーモーツァルトのベンジャミン特集](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/66/e2/b84c41a2579268d55f363286f23b1002.jpg)
![[Summer 2015] Tanglewood: Nelsons & Friends タングルウッドのネルソンス & フレンズ](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/18/08/c4d0391455c0920b0ec523a41cd3d726.jpg)
![[Summer 2015] Tanglewood: Nelsons & Friends タングルウッドのネルソンス & フレンズ](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/52/23/d9c577dfb8141fea8bd128d6023cd6cd.jpg)
![[Summer 2015] Tanglewood: Nelsons & Friends タングルウッドのネルソンス & フレンズ](https://blogimg.goo.ne.jp/image/upload/f_auto,q_auto,t_image_square_m/v1/user_image/33/36/7b199e47cf9aaa3c0353f6d09f978e83.jpg)
長い間ご無沙汰で失礼いたしました.今日、やっと少し時間が出来たのでユロさまのワーグナー協会でのお話会の抜粋を拝見いたしました。
そうして、感心してあなたの『影のない女』の評、1と2を読ませていただき、びっくりいたしました。
私は頭が古くてタラの乾物とあまりちがわないので、あなたやマエストロ・ユロのような頭脳明晰な方の新鮮なお話を聞いたり書き物(ブログでも)読んだりすると全く圧倒されてしまいます。それに少しも見落としなく、完全に隅から隅まで話題をカバーしてあんなに長いブログを二つもお書きになるなんて、それも同時にあなたのブログ・スペースでいつも他のいろんな音楽情報を記事にして皆さんに知らせてくださってるらしいので、まるで超人的な才能だ、と驚きました。
私は『影なし』をよく知らないので、この間ババリアのすごく映像の悪いストリーミングを見た時、大昔に見たはずのオペラなんて全然覚えていませんし、ドイツ語は全然わからないし、話の筋書きや経過事情はよくわかりませんでした.そうして私の印象ではバラクの妻は全くしょうのない人のように見えたのですが、そうじゃないんですね.多分Kinoxさまのおっしゃるように、 心に思っている事、夫を愛している事など照れくさくって言えないような可憐な女性なのでしょう。バラク夫妻の関係も皇帝と皇妃の関係も深い含蓄があるべきで、ホフマンスタールとシュトラウスがそういう 、現実にありそうな面白い関係をオペラで表現する事を目的として書いたのでしょうね。あなたはそういう事情を奥の奥底まで見通して(聴き通して)解釈分析なさってるので,ふーーーんとうなってしまいました。私みたいにオペラが好きと吹聴しながら実は生半可な知識とケチな好奇心しかなく、本当に理解する努力も少しもしない人間はオペラを見る資格はありませんね。
「ほんとヴェルニケは光・色彩の魔術師だったんだなぁ」とおっしゃっていろいろな美しい色や照明の効果を描写していらっしゃるので、何度もちゃんとご覧になったあなたが羨ましかったのですが、時間はなし、あってもわざわざ見に行ったかどうかわかりません。
けれども舞台装置の夢幻的な色、照明、鏡をふんだんに使ったステージの効果なんて想像するとうっとりします。書いていらしたアクシデントで生まれた照明効果なんて面白いですね。ヴェルニケが十二年前にちゃんとした基礎的演出を残してくれたのですね。ユロさんは、それをスミットさんが少し変えて復活させたのだが、良い点は歌手たちが自由に歌い(解釈も?)演技できるようにしたことだと言っていらっしゃいましたね。十二年前はヴェルニケの独り舞台の演出だった、音楽以外はワンマン・ショウだったとおっしゃってましたね。今度の演出では歌手の方達がある程度の自由を得て思うままに歌い演技できたからすばらしい結果が得られたのでしょう。主役級の歌手達の息が合うという事は全く大切で、一人だけがいくら素晴らしく歌ってもチームワークができていなければオペラの効果は台なしです。Opera はほんとうに Opusの集まりですものね。
これを成功させたのは全くユロさまの統一能力とカリズマでしょう。オケだけでなくオペラのプロダクション全体を奮い立たせ最善を尽くさせる力を持った方なのでしょう。
たしかにそんなに成功したオペラをHDで見せてくれなかったゲルプが恨めしい。「このプロダクションはヴォルピのbabyだからゲルブはHD上映しないのだ」説は、ほんとらしく思えます。私はトスカやボエームやリゴレットなんて見飽きたものをHDにいれないで、『ファルスタッフ』や『鼻』やこのオペラなど、珍しいものを見せていただきたいのですが....
もちろん、あまりオペラを見ない人たちにカルメン、トスカ、ボエームなどを紹介してこれから見に来てもらう事も大切ですね。
この記事に入れてくださった写真をみると、アムステルダムの公演の時の歌手達の印象とずいぶん違いますね。アム版ではこんなにきれいには見えなかったので、この写真を見てあれ!違う人?と思ってしまいました。シュヴァネヴィルムスさん、ケルルさん、本物を見聴きしたかったなあと思いました。オペラのステージってのは全く普通の演劇では見られない幻想を実現してくれますね。でもいくらゴージャスな衣装を着て天下の美人が何十人も出て来て踊ったり歌ったりしても、ハリウッドやラスヴェガスのショウなんて全然魅力ないので、やはりオペラは特別だと思います。
ネムゼルさんのリサイタルでのラフマニノフの歌唱を聴かせていただきましたが、確かに素晴らしく大きく美しい声ですね.普通の背広を着てひげを生やした男が立っていて何も期待していなかったのに、急にすごく高い大きいソプラノの声が出て来たのでびっくりしました。大きいだけでなく、すごく華やかでよく響く、ずんとおなかに響いて来る声です。難を言えばもう少しダイナミックスに変化を付けてほしいですね.でもほんとに優れた、変わったカウンターテナーだと思います。
では無意味なおしゃべりはやめて、お礼だけで閉じます。
どこへ投稿すればいいかわからないので、個々で失礼いたします。
エラス・カサドのオランダのTVドキュメンタリーを拝見いたしました.フィラでの会談が取り消しになったので、このリンクをいただけて嬉しく思いました。
彼は本当に若くてほっそりしていて学生みたいですね.そうして学生の様なエネルギーを体にみなぎらせて飛び回っている方のようですね。ざっと拝見した印象では、じっとしていられない、いつも音楽作りに関わっていなければ気の済まない人らしいという印象を持ちました。(最後の友人とのパーテイ以外は)。
しかし自分の音楽作りに関してははっきりした意見を持ち、人生すなわち音楽、音楽すなわち人生、という態度.演奏も曲の解釈を細かい所まで心得ていて絶対になおざりにしない方で頼もしく思います。ショスタコヴィッチは個々の楽器の音を彼の要求する音によく近づけていたと思いますが、テンポがちょっとレギュラーすぎると言う感じでした。もうすこし冒険してもいいんじゃないかしら。でも彼の指揮のスタイルは 自分の思っている事を、表情、体や手の動きで実によく正確につたえることが出来ていると思います。要求も多くて、メトでのリゴレットのリハーサルの時など、ひんぱんにオケをとめては指示を与えていましたね。自分でどんな音が聞きたいか、その音が頭のなかにあるので妥協できないのでしょう。生活のテンポが実に早い人らしいので、見てて疲れます。けれども今の時代Daniel HardingやAndris Nelsonsなどと共に嘱望されていい若手指揮者だとおもいます。
ネクタイを結ぶのに手伝ってもらわなければならないというのは可愛らしいですね.音楽の方はちゃんと老成していらっしゃるようですが。
グラナダ出身とは嬉しいですね。アルハンブラのある美しい町ですよね。あの宮殿と庭は忘れられません。ああいう美的感覚のするどい町に生まれ、友人や家族と実に密接な関係を保って育って来た人が今世界中を駆け回って音楽作りをしているのだと思うと嬉しくなります。
リンクありがとうございました。
> エラス・カサドのオランダのTVドキュメンタリー
> 学生の様なエネルギーを体にみなぎらせて飛び回っている方のよう
> 生活のテンポが実に早い人らしいので、見てて疲れます
少々intenseな若者ですかね。コーヒーもダブルで二杯、なんて頼んでますし、わたしはまるで自分の10何年前を見るような感じもして、少々微笑ましいです。監督をやっているSt.ルークスのNYCのペースには合ってるんじゃないでしょうか。ショスタコはSt.ルークスで同曲を聴かせてもらいましたが、なかなか聴き応えがありました。
> 自分の思っている事を、表情、体や手の動きで実によく正確につたえることが出来ている
> 演奏も曲の解釈を細かい所まで心得ていて絶対になおざりにしない方で頼もしく思います
> Daniel HardingやAndris Nelsonsなどと共に嘱望されていい若手指揮者
> ああいう美的感覚のするどい町に生まれ、友人や家族と実に密接な関係を保って育って来た人が
> 今世界中を駆け回って音楽作りをしている
そうですね、この間レイネさまとお喋りしてましたが、この人は古典から現代音楽まで、今までメディアを通じてでも聴いたことがある中では妙なことをやっていた記憶はないです。オペラ以外では毎週違う街のオケを振るスケジュールは大変でしょうが、しっかりと自分を持っている人のようですから大丈夫でしょう。まだコアなドイツロマン派ものをしっかり聴かせてもらったことはないので、それも楽しみに待ってます。はい、わたしもかなり今後を期待している若者でございます。
ハーディングもboy wonder、天才少年(青年?)時代を脱却しつつあるようですね。先日BPOで見たインタビューも興味深かったので添付いたします。ハーディングはアバドには随分色んなことを教えてもらったんだろうと察しますが、これからも頑張ってもらいたいです。
http://www.digitalconcerthall.com/en/interview/16941-2
http://www.digitalconcerthall.com/en/interview/16939-2
以下は先週末に書いていてポストし損ねた影のない女に関するお返事です
つらつら長いばかりの感想文を読んでいただいて、恐縮です。そしてCSTMさまはあんまり褒めすぎです :-)
だけど今回の影のない女については、公演が終わって脱力して呆けてて、結局一ヶ月後くらいに出した記事でしたが、これはやっぱり、こんな手間ひまかける物好きはいないだろう、やっぱりユロフスキ一座のみんながとっても頑張っていいものを出してくれたこと、誰かが敬意を表して記録に残すべき、なんて少々自分に鞭打って、なんとか書いたところもあります。なので読んで頂いて、しかもこんな丁寧なコメントも頂いて、大変うれしいです。
> バラクの妻
> 心に思っている事、夫を愛している事など照れくさくって言えないような可憐な女性
そうですね、そして彼女はバラクが殺そうとするほど怒るまでは、バラクに本当に愛されてるか不安でもあったのでしょう。
> ホフマンスタールとシュトラウスがそういう 、現実にありそうな面白い関係をオペラで表現する事
まさにその通りだと思います。フロイト的なのかもしれませんけれど、近代人的感覚で描いてますよね。だから今われわれが見てもとっても納得というかうんうん、分かる、というところがあるのもほんと面白い作品だと思います。
> 主役級の歌手達の息が合うという事は全く大切
> 一人だけがいくら素晴らしく歌ってもチームワークができていなければオペラの効果は台なし
それはほんとそうだと思います。わたしなんかはシナジーなんていってますけれど、それぞれの音楽家が足し算じゃなくて掛け算になってる、お互いの力がスパークして、全体的にも素晴らしいし、それぞれも普段以上の実力が発揮できてる、という公演はほんと特別、なかなか出会えるものではないですよね。
これは最近の公演で思ったのですが、そしてそんなことを一般的に目安にしたくはないのですが、そういうチームワークのシナジーが成立してない公演って、カーテンコールの時にあからさまに分かりますね。スカラの椿姫なんて、まったくお辞儀のタイミングがばらばらだったし、まぁ薬や酒瓶があったので邪魔だったこともありますが、ルチーチなんて渋い顔で演出のちぇるさんなんかと手がつなげるもんか、みたいな表情だった。わたしはアンサンブル・オペラとしては少々納得できなかったメトのファルスタッフもまぁ皆さん笑顔だったけれど、何人か自分さえよければいい、みたいな人もいましたから、お辞儀のタイミングとか、ばらばらで、ふーんやっぱりなぁ、と思いました。そんなのぜーんぜん意味深いことじゃないのではあるのですけれど。
> 成功させたのは全くユロさまの統一能力とカリズマ
> オケだけでなくオペラのプロダクション全体を奮い立たせ最善を尽くさせる力を持った方
はい、わたしもそうだと思います。わたしはユロフスキはもうしばらく注目しているので、かなり頭のいい、そして人間として魅力的でカリスマのあるリーダー、だということはそこここで感じます。しかしスーパーマン的な意味じゃなくて、成功させられるかどうか、プロジェクトに参加する前にもきちんと検討した上で、慎重にやってるから、なんでもかんでもオファーされるものを引き受けるわけじゃないから、そしてある程度は妥協もする寛容さを持ちつつもいい意味で頑固だから、そうできてるんじゃないかと思いますよ。そういう意味でもこの人なら、と信頼できて(たとえいまいちな時でも納得できて)、ついフォローしてしまいます。
> 歌手達
> アム版ではこんなにきれいには見えなかった
> オペラのステージってのは全く普通の演劇では見られない幻想を実現
全く同意でございます。演劇でもやっぱり舞台上のマジックってあると思いますけれど、あの特殊な空間の世界の魅力は凄いですよね。確かにアムスの時は歌手たちへのライティングもよくなくって、シュヴァネヴィルムスは髪がべたっとしてるようだったり、ゴーキはうわぁでかいなぁ、という感じですけれど、彼女たち、今回の舞台上ではほんと魅力的でした。
最近はなんでもかんでも現実的な、隣のみよちゃんだか近所のおっさんだか薬漬けの有閑マダムとかの話にしてしまう演出も珍しくないですけれど、今回の演出はほんとストレートな視線で作品が堪能できて、ほんと良かったです。
> ネムゼルさん
> 大きいだけでなく、すごく華やかでよく響く、ずんとおなかに響いて来る声
> もう少しダイナミックスに変化を付けてほしい
いや全くその通りです。凄い技量を持ってるんですけれど、わたしもこの曲の解釈・表現に関しては、単調だなぁと思いました。色んな経験をしたり、喧々諤々やれるパートナー的なアコンパニストに恵まれたりしたら、また違ってくるかもとも思うし、これだけのものを持った人、化けたら物凄く面白いかも、と次回の機会が楽しみなような新人さんです。
http://www.nntt.jac.go.jp/opera/dietotestadt/staff/index.html
この間からオリジナル版の運命の力とか、わたしが熱望するシュヴァネヴィルムスのマルシャリンもあるなんて聞こえてきて羨ましいと思っていたのに、死の都?、いいなぁ、日本はいいなぁ。
> トルステン・ケルル(ケール?)がパウル役で登場予定!と思うたら、
> ミーガン・ミラーもマリエッタ/マリー役で一緒についておりましたw
おぉ、皇帝&皇后コンビがそのままそちらでも! ミラーは今回のメトの公演に関しては、厳しいことを言っちゃいましたが、かなり歌える若手だとは思ってます。二人とも頑張っていただきたいです。わたしもご報告、楽しみにしております!