
「女神」
(邦題「女神たちよ」)
監督・脚本 Karthik Subbaraj
音楽 Santhosh Narayanan
撮影 Sivakymar vijayan
出演 S.J.Suria,Vijay Sethupathi,Bobby Simha, Kamalinee Mukherjee, Anjali, Pooja Devariya
公開: 2016年6月3日/タミル語・153分
ヴィジャイ・セードゥパティの国家映画賞受賞記念(?)に3月30日にアップした記事をうっかり消してしまったため(泣)同じ内容を再執筆しました。少々加筆もあり(ネタばれはありません)。
◆ストーリー
彫刻家のダース(ラーダー・ラヴィ)は、病に倒れ寝たきりとなった妻のミーナークシ(ヴァディヴカラシ)を、長年ないがしろにしてきた事への懺悔の思いを込め世話する日々。ダースの息子で映画監督のアルル(S・J・スーリヤ)はプロデューサーとの不仲により自作を公開できず、酒に溺れてあちこちでトラブルを起こし、共働きの妻ヤーリニ(カマリニ・ムカルジー)を悩ませていた。
ダースのアシスタント・ジョン(シーヌ・モーハン)の甥であり、彼らが経営する美術品店で働くマイケル(ヴィジャイ・セードゥパティ)は、寡婦マラルヴィリ(プージャー・デーワリヤー)との結婚を望んでいた。だがマラルは、体だけの関係と割り切り彼の気持ちに応えない。2人の関係を知ったジョンは、マイケルを見合い相手のポンニ(アンジャリ)と結婚させることを決める。一方、大学で美術研究を専攻するアルルの弟ジャガン(ボビー・シンハー)は、古寺から女神像を盗んで密売し大儲けする計画を立てていた。
アルルのアルコール依存症からの再起を図るため、ダースとジョン、ヤーリニはプロデューサーのムクンダンを訪ね、映画の公開を交渉する。ある事情のため交渉は決裂したかに見えたが、思い直したムクンダンが彼らに映画の権利の購入を持ちかけてくる。
カネさえあれば、アルルの映画を公開できる…ダースとジョン、アルル、マイケル、ジャガンの5人は、ミーナークシが眠る病室で6千万ルピーもの大金をどうやって工面するか頭を悩ませていた。そこでジャガンが思わぬ提案をする。「みんなが俺の案に乗ってくれるなら、カネは簡単に手に入る」ジャガンが持ち出したその案とは…。
◆まとめ
スッバラージ監督の前作「ジガルタンダ」とは趣が異なり、男たちと、彼らのエゴに翻弄される妻たちの姿を描いた濃厚な人間ドラマ。打ち捨てられた古寺の女神像に妻たちの姿が重ねられており、そして女神を粗末に扱った者はその報いを受けることに。
「夫は妻を虐げるな」「女たちよ、しがらみを捨てて自由になれ」というメッセージは明確だけど、その描かれ方が独特で何ともスリリング。その中で「雨に濡れるか濡れないか」が女性の生き方の象徴としてくり返し登場するのが、美しい雨の描写と併せて印象的。
また「ジガルタンダ」から伝わってきた「映画とは芸術」という監督の信念が、前作とはまた異なる形で描かれてもいる。関連して映画業界への皮肉もバンバン登場し、劇中でアルルに言わせた「言いたいことは映画で語れ」を地で行っている。ちなみに私は「いつでもハッピーエンドのマス映画」も大・大好きです。
じつは初見時は、その衝撃の展開と結末に「私はいったい何を見たのか」とクラクラし、監督の意図を考えてあれこれ思い悩んだ。そこでこれまた劇中のアルルのセリフ「映画とは人の心を揺さぶり思索を与えるべきもの」というセリフを思い出し、こりゃ監督の思うツボじゃないかと気がついた。
監督の他作品とはテイストが異なるように見えて、実はこれもまた、監督の映画づくりのポリシーとこだわりが徹底され、さらに観客は初回観賞後再見し、ひそかに敷かれていた伏線に気づき味わいが増すという「ザ・カールティク・スッバラージ」な映画に思える。謎めいたシリアスなストーリーと、安易に観る者を喜ばせてくれない作りに好みは分かれるかもしれないが(現地でも賛否あり)私は大変気に入っている。
また、シリアスなのに時折ニューウェーブ作品がらみの小ネタが登場する意外性もいい。ジャガンが唐突に「キケンな誘拐」のパガラヴァン化したり(笑)「ジガルタンダ」のサングラス大好きサウンダル、君は転生してここにいたのか!となったり(笑)
※残念ながらリンク先の記事が消えてしまっていました(泣)。かわりにティーザーを貼っておきます↓
◆S・J・スーリヤ(アルル)
この作品は、役者さんたちの地味に見えて実は非常に研ぎ澄まされた演技に目を奪われるんだが、中でも凄まじいのがS・J・スーリヤ。芝居がかった大げさな演技とリアルな演技とが絶妙にミックスされたというような、その独特の味にハマる方もあるかも。私は最初から最後まで彼の演技に目がクギヅケだったし、クライマックスシーンのあれには大泣きした。
アルルが映画について語るセリフには、おそらくスッバラージ監督自身の思いが込められていると思うけど、それを本人も映画監督であるSJSが発するというこの重構造がニクい。彼については、日本では「Mersal(マジック)」での憎たらしいダニエル医師など、役者としての顔を思い浮かべる方のほうが多いかも。
◆ヴィジャイ・セードゥパティ(マイケル)
甘える彼、傲慢な彼、無理をして笑う彼、ブチ切れる彼、子犬のような目をした彼…と千変万化の表情を堪能できる。彼の演技の巧さをとことん味わえる作品はほかにあると思うけど、本作での彼のお芝居の、物語に合わせて3人の主要人物の中であえて突出しないというさじ加減はさすが。
特に印象に残ったのはラスト近くの美術品店のくだりの彼の姿で、ズシャーン、ズシャーンというサウンドと彼の表情、さらに問題のシーンの直後の「空振り」のリアルさ、そのインパクトには震えあがった。
◆ボビー・シンハー(ジャガン)
例えば「ジガルタンダ」の極道セードゥ役に比べると、割と地味なキャラクターなので、ストーリーを追うことに集中してしまう初見時には彼の巧さが少し分かりにくいかも。
ところがですよ。ラストまで見て彼の性格や考え方を把握したのちに再見すると、彼が前半からきちんとそれを思わせる細かい芝居をしているのが分かる。そして、作品を見返すほどに味わいが増す。やはり本作は、ぜひ複数回のご鑑賞をおすすめしたいところです。
◆ラーダー・ラヴィ(ダース)、シーヌ・モーハン(ジョン)
おなじみラーダー・ラヴィは、悪徳政治家や悪徳政治家、そして悪徳政治家を演じる彼とは異なり、裕福ながら家族の問題を抱える、年老いた彫刻家ダースを淡々と演じている。あまり変化のないその表情に折々の感情がじんわりにじみ出るという、いぶし銀のお芝居。病室で話し合うシーンやプロデューサーとの交渉シーン、アルルと語り合うシーンなど、印象に残る深いお芝居がいくつもあった。
本作に登場する男性キャラクターの中でひとり異彩を放つのがジョン叔父さんの存在で、彼だけは人物にクセがなく、妻とも思ったことを率直に話し合い理解し合っていて、とても仲が良さそう。全てを目撃してきた、物語の語り部とも言える彼だけは女神を虐げていないという所に趣がある。
そのジョンを演じたシーヌ・モーハンは惜しくも2018年に他界されたが、もっと彼のお芝居を見たかったです。クライマックスからラストにかけては、彼にも泣かされ通しだった。
◆アンジャリ(ポンニ)、カマリニ・ムカルジー(ヤーリニ)、プージャー・デーワリヤー(マラル)、ヴァディヴカラシ(ミーナークシ)
ポンニとヤーリニ、育ってきた環境も生き方も、夫との接し方も正反対と思われた2人の女性の、雨をめぐるセリフと最終的な選択の対比、その描かれ方に胸を打たれる。それも、夫に翻弄される妻の内面の変化を、派手さのない落ちついたお芝居で細やかに表現するアンジャリとカマリニの演技あってこそ。とくに少女から新妻となり母となっていくポンニの、繊細な表情の変化にご注目。
さらに、かつては2人と同じ立場にありながら、まったく違う新しい生き方をするマラルをプージャー・デーワリヤーが演じているけど、ヒリヒリする場面の多い本作の中で、マラルとジョンが話し合うシーンもまたかなりのヒリヒリ度だった。
全編ほぼ眠ったままのミーナークシの存在が私には謎だったが、作品に登場する女性たち、そして世のすべての女性たち〜すべての「Iraivi」の象徴であり、実はこの物語の真の主人公なのかも。また眠ったままの彼女の姿は寺にたたずむ物言わぬ女神像のようだし、彼女に食事をさせるダースは女神像にお供えをする男にも見えて、男たちによって生ける女神が祭壇に祀られた女神とされていく、その姿を見ているよう。
ヴァディヴカラシは超ベテランの女優さんで、作品リストを見るに絶対にどこかで見ているはずなんだが、思い出せないのがお恥ずかしい(汗)
◆その他の俳優
カルナーカランは、作品の雰囲気に合わせてか少し控えめなお芝居。バガヴァティ・ペルマールやセンディル・クマーラン、監督のお父様ガジャラージといった、スッバラージ監督作品でおなじみの面々の顔を見つけるのも楽しい。ラーマチャンドラン・ドゥライラージもチョイ役で出てるけど、髪とヒゲがないとこんなにも人相が変わるのかとビックリ。
また「ジガルタンダ」の端役の人たち、例えばマドゥライのサリー屋の兄ちゃんや、ディンディガルのドンの娘、テレビ番組のスタッフなどなど、結構な数の人が本作にも顔を出していて面白い。ご覧になる方は、ぜひ見つけてみてください。
◆カンナギについて
タミルの古代叙事詩「シラッパディハーラム」の女主人公カンナギ。劇中で、女神像密売のターゲットとして、また大学の授業の題材や「カンナギを悪魔から解放せよ」というセリフの形で何度もくり返し登場する、この作品の最重要の女神だ。
※カンナギについては、ぜひともPeriplo様の素晴らしいコラムをご一読ください。↓
監督は、カンナギが「夫に大切にされなかった妻(比喩としての女神)」であると同時に「神格化され崇められている女神(本物の女神)」でもあるので、二重の意味でのIraiviということでクローズアップしたのか、などと考えていたんだが…
IMWさん発信のトリヴィアによると「実はカンナギは、現代のタミルではさほど人々に省みられず、忘れられた女神となっている」とのことだ。するとカンナギは、かつては省みられない妻(忘れられた女神)であった女神が忘れられているという、二重どころか三重の意味でのIraiviだということになる。この重構造、監督の頭の中はどーなってるんだ…
◆音楽
サントーシュ・ナーラーヤナンの音楽も、作品の雰囲気に合わせて控えめ…かと思いきや、これもまた見直すたびジワジワと味わいが増してくる。エンディングのソング「Manidhi」の美しさが際立つけど、「Otayille」でのアントニー・ダーサンの哀切な歌声、そしてその歌詞にも泣く。
最も印象に残るのは「お前は悪魔だ〜」のソング「Doshuta」。監督によると、このシーン=マイケルの幻覚には「彼の内なる葛藤が投影されている」とのこと。女性キャラクターの衣装の色にもご注目。私は初見時、このソングの歌詞、映像、雰囲気、すべてを「怖っ!」と思ったんだが、実はよく見ると細かな映像が非常に凝っており、ポンニ、ヤーリニ、マラルも踊るコンテンポラリーなダンスの振り付けもカッコよくて、以来お気に入りのダンスシーンとなった。
さらに、それぞれの場面で涙を誘ってきたり胸をえぐってきたりする、バリエーション豊富な(そして改めてSaNaの音楽的引き出しの多さに唸らされる)バックグラウンドスコアも秀逸。
「Kaadhal Kappal」ソングでの、SaNaの生歌披露も見どころ。なぜか彼に邪険にされるボビー・シンハーも(笑)
◆追記
6月3日のIraivi公開5周年を記念して、バックグラウンドスコアのサントラが発表された。
まとめて聴くと、改めて本作のバックグラウンドスコアは凄まじいですね。SaNaが担当する他の作品でもそうなんだけど、これらのメロディを聴いているだけで、それぞれのシーンが浮かんできて作品の世界にどっぷりと浸れてしまう。監督は9番「Kaatril」がお気に入りだそうだけど、私は1、2、4、5、8、11…いやもう全部(号泣)これは必聴サントラです。
ということで、トレイラーの代わりに、発表ホヤホヤのこのサントラのリンクを貼っておきます。っていうか、何で今まで出てなかったのかな。
★非常におすすめ★














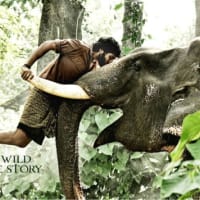

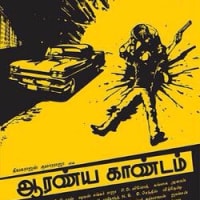
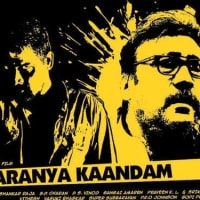










※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます