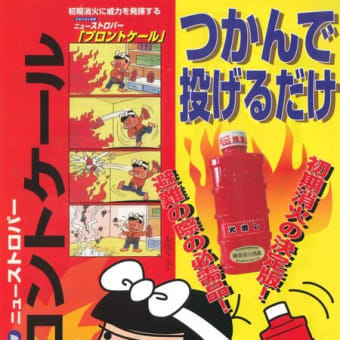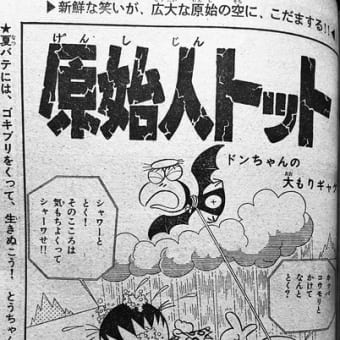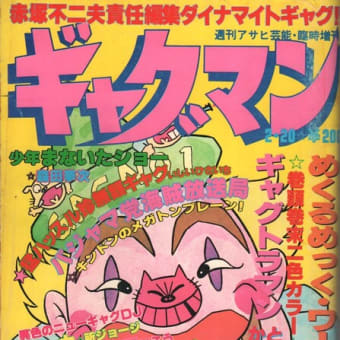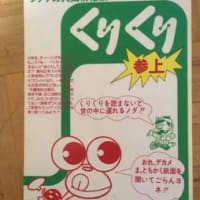台本では『狼少年ケン』、スタジオ・ゼロメンバーが原案の『レインボー戦隊ロビン』、ちばてつやの『あかねちゃん』、石ノ森章太郎の『ドンキッコ』に『海賊王子』、つのだじろうの『ピュンピュン丸』。アニメ化に至らなかったものばかりの企画書では水野英子の『ハニーハニーのすてきな冒険』、石ノ森章太郎の『オーとうちゃん』に『ボンボン』、『コンキィ・ポンキィのなんでも教室』、『サイダーマン』、『タイム・アドベンチュア』、『スリラーコメディ お化けだよーん』(藤子不二雄(A)の『怪物くん』そっくりのキャラが“バケ坊”という名で描かれている!!)。アニメ資料では『もーれつア太郎』八百×の見取り図などがあったのだが、その中には赤塚ファンが驚く品も紛れ込んでいた。
それは、赤塚不二夫の『風のカラッペ』、『大バカ探偵白痴小五郎』のアニメ化企画書と『もーれつア太郎』アニメ第1期放送開始に際したイベント『もーれつア太郎 もーれつまつり』の台本である。
幸いなことに、3点すべてを赤塚ファン・コミュニティ内で入手出来た。当ブログで全て紹介する事をお約束したい。
今回は『風のカラッペ』のアニメ化企画書である『カラー連続テレビまんが 風のカラッペ 企画書』(本文・全8頁)を読み解きたい。カラスのカラッペ、カラス天狗のカラテン、金太郎ならぬ土太郎らが活躍する任侠・股旅物である赤塚漫画を、東映動画はどのようにしてアニメ化しようとしたのだろうか。
★
『風のカラッペ』作品データ
・連載
『旅ガラスカー太郎』「週刊少年キング」1970年4・5号(各種単行本では第1話として収録)
『風のカラッペ』1970年8号~1971年14・15号
『おれはバカラス』1971年17号~30号(後続連載・現代版『風のカラッペ』)
・解説
喧嘩と賭けと女を好み、三度笠と合羽のコスチュームで関西弁を「~やんけ」と話す旅ガラス・カラッペ。カラス天狗のカラテンを子分とし、拾い子の金太郎ならぬ土(ど)太郎を連れて、今日も義理人情の旅を続けるやんけ!!
1970年に「週刊少年キング」で連載がスタート。この頃の『もーれつア太郎』のニャロメが牽引した赤塚ブームのさなか、編集部からの強い要望もあってだろう、単発の読切作『旅ガラスカー太郎』をカムバックさせる形で連載がスタートする。当初は隔週連載で、すぐに連載となった。
多忙な赤塚をサポートする形で、途中よりアシスタントである佐々木ドンが作画を担当していることもポイントである。初単行本化となった少年画報社のヒットコミックス版(全2巻)では、赤塚と連名でクレジットされている。
連載最初期からガムとアイス(カネボウハリス)、プラモデル(青島文化教材)、ノート(セイカ)が発売され、ガムのオマケであったシールやバッジは今でもレトロ・コレクター達に人気がある。また、2004年にフルタが発売したジオラマフィギュア付きの食玩『20世紀漫画家コレクション7 赤塚不二夫の世界』(全10種)にもラインナップされた。
・単行本
少年画報社・ヒットコミックス『風のカラッペ』全2巻 著/赤塚不二夫・佐々木ドン
第1巻 1971年10月25日刊
第2巻 1972年1月15日刊(『旅ガラスカー太郎』と『風のカラッペ』を収録)
曙出版・曙コミックス『風のカラッペ』全4巻 著/赤塚不二夫
第1巻 1976年7月30日刊
第2巻 1976年8月20日刊
第3巻 1976年10月20日刊
第4巻 1976年11月12日刊(『旅ガラスカー太郎』と『風のカラッペ』を収録)
小学館・オンデマンド版赤塚不二夫漫画大全集・『風のカラッペ』全4巻
2005年9月30日刊 (底本・曙コミックス版)
★
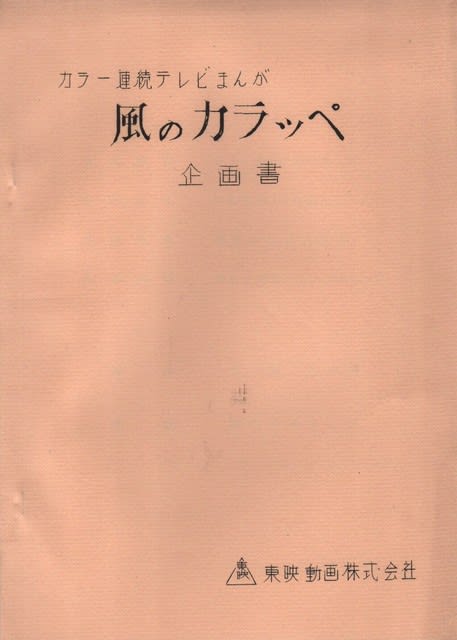
企画書は、以下の構成になっている。全8頁だが、3頁目より、下部に頁数が記載されている。
1頁/放映種目・放映形式・放映対象・放映時間・原作・連載
2頁/白紙
3頁(1頁)/企画意図
4頁(2頁)/登場キャラクター
5頁(3頁)~8頁(6頁)/サンプル・ストーリー
では、順に見ていこう。
★
放映種目 カラー連続テレビまんが
放映形式 一回完結15分物シリーズ
放映対象 児童から大人まで
放映時間 午後7時30分~7時45分
1頁目の一部を転載した。“一回完結15分物シリーズ”とは、かつて放送されたテレビアニメ『カバトット』や『チャージマン研!』のようなショート作品になる予定だったのだろうか。放送時間も決まっているようだが、当時、この時間に放送されたアニメ番組はなかったはずだ。
次頁以降の「企画意図」、「登場キャラクター」、「サンプル・ストーリー」からは、この企画書が書かれた時期が特定出来る。まずは「企画意図」全文を転載しよう。
義理に生きるか、女に死ぬか、男カラッペ三度笠!!
颯爽!カラスの旅鴉、「風のカラッペ」の登場です。
生国と発するところ、御存知人気少年週刊誌「少年キング」、生みの親はギャグの王様、赤塚不二夫とフジオプロの御一統さんでござんす。
今年の初め、少年キング誌に「旅ガラス、カー太郎」の名で登場早々の馬鹿人気、その名もかっこ良く、カラッペと名を改めての隔週連載。人気が人気を呼んで、今では同誌の看板男、おかげで少年キングの発行部数もうなぎ登りとか………。
熱血根性スポーツ物とかが大流行の御時世に、ギャグを引っ提げての殴り込み。
笑いが一杯、面白さ抜群の視聴率稼ぎ、テレビ漫画界のゲバゲバゲリラでござんす。
「風のカラッペ」、強いよ。
ここで『風のカラッペ』の連載史をおさらいしたい。「週刊少年キング」1970年4・5号に読み切り『旅ガラスカー太郎』(各種単行本では第1話として収録)が掲載される。これをプロトタイプに1970年8号より連載となり改題。1971年14・15号で連載が終了した後も、舞台を現代に移した『おれはバカラス』が1971年17号~30号にかけて連載されている。
「カラッペと名を改めての隔週連載。」と上の「企画意図」に書かれたように、連載開始当初は隔週連載であった。連載最初期の掲載状況をリスト化してみよう。
1970年8号・2月15日号/『風のカラッペ』第1回、表紙カット登場
9号・2月22日号/休載
10号・3月1日号/『風のカラッペ』第2回、表紙画に登場
11号・3月8日号/休載
12号・3月15日号/『風のカラッペ』第3回
13号・3月22日号/『風のカラッペ番外地』第1回
14号・3月29日号/『風のカラッペ』第4回、関連記事『㊙まんが家列伝』第1回「赤塚不二夫のニャロメ人生」
15号・4月3日号/『風のカラッペ番外地』第2回
16号・4月12日号/『風のカラッペ』第5回
17号・4月19日号/『風のカラッペ番外地』第3回
18号・4月26日号/『風のカラッペ』第6回
19号・5月3日号/『風のカラッペ番外地』第4回
20号・5月10日号/『風のカラッペ』第7回
21号・5月17日号/『風のカラッペ』第8回、表紙画に登場
22号・5月24日号/『風のカラッペ』第9回
23号・5月31日号/『風のカラッペ』第10回
24号・6月7日号/『風のカラッペ』第11回
25号・6月14日号/『風のカラッペ』第12回
以上が1970年8号~25号の連載状況である。最初期は隔週連載であり、休載号には佐々木ドンによる『風のカラッペ番外地』が掲載されていた。これは、いわば『バカ田大学』のような、ギャグ・パロディ記事である。(赤塚の実母の急死に伴い、原稿を落とすまいとアシスタントの佐々木ドン、古谷三敏、とりいかずよし、長谷邦夫が総出で執筆した『天才バカボン番外地』(「週刊少年サンデー」1970年38号、原題は『ああ!!大脱獄』))のネーミングは、これから来ているのかもしれない。)
そもそも、隔週連載を採用した最大の理由は、折しもの赤塚ブームからフジオ・プロに膨大な仕事が舞い込んでいたことが原因だろう。この時期は『もーれつア太郎』に登場したネコのニャロメが大ブームとなっていた時期であり、「「週刊少年キング」にも赤塚漫画を載せたい!」という意向があったに違いない。『風のカラッペ』はガム(カネボウハリス)、プラモデル(青島文化教材)、ノート(セイカ)など商品化もされており、(現物を確認出来た)1970年25号にはもう、ガムとアイス、プラモデルの広告があったことを鑑みても、連載最初期・・・もしくは連載前から赤塚不二夫の最新作としてプッシュされ、各所に売り込まれていたはずだ。
また、4頁目の「登場キャラクター」の主要キャラクターはカラッペとカラテンのみで追加キャラである土太郎はおらず、5頁目~8頁目の「サンプル・ストーリー」が1970年10号掲載の連載第2回「カラッペの女だすけやんけ」(曙コミックス第1巻ほかに収録)を「ルリ子のお顔はブスだった」という題で起こしたものであることをみても、企画書が書かれたのは1970年の(「サンプル・ストーリー」原作の1970年10号が発売された)2月~(「企画意図」にある“隔週連載”の最終号が発売された)4月頃とみて間違いないだろう。
★
もしも、『風のカラッペ』のアニメ化が叶っていたら、赤塚史は大きく変っていたに違いない。何にせよまず知名度が優先される中で、『カラッペ』は様々な誌面に再録されただろうし、『天才バカボン』などと同じく再アニメ化の際には赤塚がリバイバル連載を行っただろう。この作品の連載開始と同じ1970年に入社後、早くも1973年頃にはフジオ・プロを退社し、それ以降一切メディアに顔を見せない佐々木ドン(と、妻のヒロコさん)も、もっと日の目を浴びた可能性だってある。
当時の読者投稿ページを見ても、おおむね好評だったようだし、今読んでみても、ギャグの中に義理人情のムードはある。カラッペ出生の秘密が描かれる(なんと、人間の女性が誤飲した卵が体内でかえり、屁と共に出産される!)回などはとても珍奇で面白い。
カラッペの小粋な姿は完成されており、『おた助くん』の一郎をベースとしたカラテン、のちに『レッツラゴン』のゴンのベースとなる土太郎のデザインもいい。
だが、連載が1年持たず、ヤケッパチで現代版『おれはバカラス』へと連載が移行してしまったところを見ても、赤塚が作画に関わっていないという影は大きかった。『風のカラッペ』に限らず『ニャロメ』でも、『大バカ探偵 はくち小五郎』でも、テレビマガジン連載版『元祖天才バカボン』でも何でもいいのだが、一度赤塚が作画に関わっていない作品のページを開いてほしい。どのページを見ても、どこか垢抜けておらず、赤塚の不在の大きさを思い知らされるばかりなのだ。
この企画書の発見から、赤塚史における叶わなかった大きなポイント(=「週刊少年キング」が仕掛けた『風のカラッペ』ブームの不発)の大部分が明らかになったと言えるだろう。
★
次回は『大バカ探偵 はくち小五郎』のアニメ化企画書を取り上げる。
★
<追記>
カラッペのキャラクター・デザインは、1946年に放送されたアメリカのテレビアニメ『ヘッケルとジャッケル』が元になっているのではないだろうか。日本も放送され、かつては東芝のイメージ・キャラクターとして採用されていたようである。
カネボウハリス「カラッペガム」にはアニメCMがあり、「出たんで、カラッペ、日本晴れ」というコマソンが歌われたという。この企画書が発見されたことをみても、製作はおそらく東映動画だろう。
カネボウハリス「カラッペガム」の点数券を集めて貰えるオマケ“ハレハレシール”をほぼ全種を掲載しているサイトを見つけた。→http://moza.jp/collection/harehare/index.html
カネボウハリスと「週刊少年キング」の関係は『風のカラッペ』以前よりあり、ほかに『猫目小僧』(楳図かずお)、『おやじバンザイ』(山根あおおに)、『マボロシ変太夫』(藤子不二雄(A))などが商品化されている。
佐々木ドンの妻・ヒロコさんは、赤塚不二夫と関係があった田村セツコの妹である。『ギャグゲリラ』「生きがい」(「週刊文春」1973年4月23日号)のタイトル部分の写真には、二人の写真が使われている。
大地丙太郎が制作し、Twitterなどで公開したアニメ『ばっとびすっとび忠治くん』の主人公のスタイルは、カラッペが下敷きになっているようだ。
秋本治の漫画『こち亀』第49巻の「両さんの受験勉強の巻」には、カラッペのプラモデルが登場する。
企画書の「登場キャラクター」の「其の他」を転載する。原作に登場しないキャラクターも挙げられている。
悪親分、豪傑、可愛い子ちゃん、可愛いくない子ちゃん。
若き日の宮本武蔵、佐々木小次郎、スムズ一家など、スターが一杯。