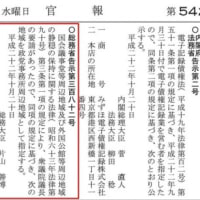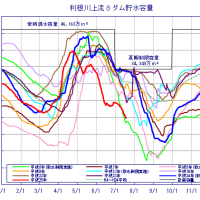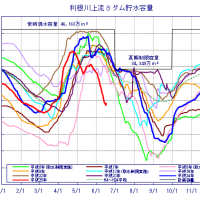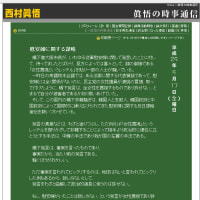大陸国家(群)と海洋国家(群)、この二分法はリムランド論とセットだ。米英は後者であり、日本は時として揺れ動くリムランドだ。ただ、近代から現代に向かい、有無相通ずる自由貿易は世界秩序の基本となったから、既に世界中が海洋国家原理に帰依する条件は整ったはずだ(こうした海洋歴史観については、日本財団 図書館:うみのバイブル第3巻が参考になる)。
#アメリカは大陸だから、USAが海洋国家であって大陸国家でないというのは、説得力に欠けるような気がするが、要はアメリカがアングロサクソン的な自由貿易の信奉者であり、その価値観を極端に推し進める歴史的役割を担ったという事だ。かつて中南米にあったように、専制的な国家がアメリカ大陸に依拠する可能性はゼロではないのだ。歴史的な偶然により、イギリス的なエートスがイングランド島から北米大陸に拡大されただけなのだ(多分)。
古代の日本は、大陸の干渉から独立する、半鎖国政策をとり、それが日本のアイデンティティとなった。それは大陸向けの顔と、国内向けの顔と、二重性(ダブルスタンダード)を帯びていた。維新新政府は、両者を一致させた。現代では情報化も進み、なおさら二重性の維持は難しくなった。
ヨーロッパが成長し、海洋ネットワークが成立すると、日本は海洋国家群と大陸国家群の間を揺れ動く性質があるようだ。思えば秀吉の大陸進出も、当時の海洋化の波に刺激を受けたものだ。維新後も再海洋化の必然として大陸進出があったように思われる。秀吉の当時は、日本のバックアップとなる海洋国家が無かったから、単独進出となり、成功の可能性は元々薄かった。近代においては米英のバックアップを受け、その支持する限りにおいて大陸で成功する事ができた。しかし大陸であまりに成功し、権益を独占しようとしたため、アメリカの中国志向を阻害する事になり、結局取り除かれてしまった。
現在、日中の貿易関係は重度の相互依存関係になってしまった。ここまで来ると、どちらの側からも相手を切り離すことが出来ない。こうした貿易関係は、それだけを捉えれば、紛れもなく海洋国家的なものだ。ユーザの役に立つ良い商品が、リーズナブルな価格で提供され、商売繁盛という、Win-Winの関係だ。現実に保釣連合(?)なんとかの首謀者に日本製品排斥の動機があるように、自由貿易と不公正な貿易妨害志向の二項対立は確かに存在する。不公正な貿易妨害は、中国の利益とならないから、結局上手くいかないと予測できる。
究極的には、全ての大陸国家を、海洋国家的なエートスで染めてしまうのが目標だ。それが日本の戦略の基本ともなる。
#日本における、アジア重視とかアジア友好の強調は(東アジア共同体とかも含む)、どうも左巻きの傾向がある。左巻きはなぜか大陸志向だ。「日ソ協商」「アジアは一つ」「アジアの友好」は皆同根だ。左巻きにならない友好関係は、海洋国家的なエートスの貫徹によって得られるだろう。
#蒋介石は日華衝突に乗り気ではなく、むしろ強烈な反共主義者だった。その意味では海洋志向だったといえるのかもしれない。台湾が海洋国家傾向が強いのと符号するのは興味深い。そういえば、親日=海洋志向のような気もしてきた。てことは、反日や抗日=大陸志向か。う~む、笹川がB&Gで海洋志向だったのは、そのせいだったのか(嘘
#アジアのユニティは、大陸志向か海洋志向かが問題だ。東南アジアは... 海洋的なんだろうな。そういえば、中世末には猛烈に日本人が進出した事があったし。
#アメリカは大陸だから、USAが海洋国家であって大陸国家でないというのは、説得力に欠けるような気がするが、要はアメリカがアングロサクソン的な自由貿易の信奉者であり、その価値観を極端に推し進める歴史的役割を担ったという事だ。かつて中南米にあったように、専制的な国家がアメリカ大陸に依拠する可能性はゼロではないのだ。歴史的な偶然により、イギリス的なエートスがイングランド島から北米大陸に拡大されただけなのだ(多分)。
古代の日本は、大陸の干渉から独立する、半鎖国政策をとり、それが日本のアイデンティティとなった。それは大陸向けの顔と、国内向けの顔と、二重性(ダブルスタンダード)を帯びていた。維新新政府は、両者を一致させた。現代では情報化も進み、なおさら二重性の維持は難しくなった。
ヨーロッパが成長し、海洋ネットワークが成立すると、日本は海洋国家群と大陸国家群の間を揺れ動く性質があるようだ。思えば秀吉の大陸進出も、当時の海洋化の波に刺激を受けたものだ。維新後も再海洋化の必然として大陸進出があったように思われる。秀吉の当時は、日本のバックアップとなる海洋国家が無かったから、単独進出となり、成功の可能性は元々薄かった。近代においては米英のバックアップを受け、その支持する限りにおいて大陸で成功する事ができた。しかし大陸であまりに成功し、権益を独占しようとしたため、アメリカの中国志向を阻害する事になり、結局取り除かれてしまった。
現在、日中の貿易関係は重度の相互依存関係になってしまった。ここまで来ると、どちらの側からも相手を切り離すことが出来ない。こうした貿易関係は、それだけを捉えれば、紛れもなく海洋国家的なものだ。ユーザの役に立つ良い商品が、リーズナブルな価格で提供され、商売繁盛という、Win-Winの関係だ。現実に保釣連合(?)なんとかの首謀者に日本製品排斥の動機があるように、自由貿易と不公正な貿易妨害志向の二項対立は確かに存在する。不公正な貿易妨害は、中国の利益とならないから、結局上手くいかないと予測できる。
究極的には、全ての大陸国家を、海洋国家的なエートスで染めてしまうのが目標だ。それが日本の戦略の基本ともなる。
#日本における、アジア重視とかアジア友好の強調は(東アジア共同体とかも含む)、どうも左巻きの傾向がある。左巻きはなぜか大陸志向だ。「日ソ協商」「アジアは一つ」「アジアの友好」は皆同根だ。左巻きにならない友好関係は、海洋国家的なエートスの貫徹によって得られるだろう。
#蒋介石は日華衝突に乗り気ではなく、むしろ強烈な反共主義者だった。その意味では海洋志向だったといえるのかもしれない。台湾が海洋国家傾向が強いのと符号するのは興味深い。そういえば、親日=海洋志向のような気もしてきた。てことは、反日や抗日=大陸志向か。う~む、笹川がB&Gで海洋志向だったのは、そのせいだったのか(嘘
#アジアのユニティは、大陸志向か海洋志向かが問題だ。東南アジアは... 海洋的なんだろうな。そういえば、中世末には猛烈に日本人が進出した事があったし。