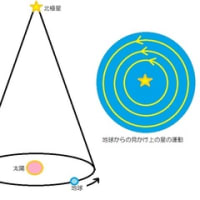■③ 奴隷廃止の政治力学■
小ブログ記事「故郷アフリカは遥かに遠く」(映画《アミスタッド》に関して)を参照のこと。
この作品では、19世紀半ば近くになっても大西洋・カリブ海域では盛んに奴隷貿易が繰り広げられていたことが描かれていた。そして、ほとんどのヨーロッパ諸国家が奴隷貿易や奴隷を労働力とする産業・経営を維持しているなかで、国家としてはブリテンだけが奴隷制度に反対し、制海権をに握る海域では奴隷貿易を禁圧し取り締まっていたことも。
ところで、いまや(単なる王権国家ではなく)国民国家としてのレジームを完成したブリテンにとっては、奴隷制度の廃止と奴隷貿易の禁圧は、世界システムやヨーロッパ国際関係のなかでの最優位と覇権を維持し続けるための政策ないし戦略となっていた。
ほかの列強諸国家は、植民地帝国の経営や国際競争での優位のために奴隷制を容認していた。それらの国家は、ことに植民地では奴隷労働が農業や鉱業の高い利潤率を確保するための重要な手段となっていることを知っているからこそ、奴隷制を維持し続けていたのだった。
フランスは市民革命で「人間(ただし男性)と市民の権利宣言」を高く掲げたにもかかわらず、植民地や属領では奴隷制が廃止されなかった。
奴隷制を利用した産業形態ほど利益の上がる経営はなかったのだ。
ブリテンは、植民地経営や世界貿易でこれほど利潤率が有利な奴隷制を、国家の制度(理念)=イデオロギーとして掲げて、自ら放棄したのだ。そして、奴隷制の廃絶をほかの列強諸国民に押しつけようとした。
フランス革命のイデオロギーや「人権宣言」に対抗して、王政や身分制=貴族制の固守を中心とする政治的保守主義を「国是:ナショナルなモラル」と掲げたブリテンが、この時期になにゆえに意識的に奴隷制を廃絶し、「人種による差別と隷属」を禁止するイデオロギーや制度を打ち出したのか。
ブリテン連合王国では、18世紀末から奴隷制の廃止や奴隷労働の禁止を求める民衆運動や有力政治団体の結成が目立つようになった。そして、1830年ごろまでには、奴隷制廃止という要求はウェストミンスター議会(とくに庶民院)の多数派意見となっていた。一般民衆への政治参加権や選挙権の拡大を回避・拒否していたエリート層が、自ら進んで奴隷制廃止運動の担い手となろうとしたのだ。
エリートたちは、貴族と庶民との身分的格差は「あってしかるべき仕組み」と何の躊躇もなく言い張る貴族やシティの有力者たちの多くが、奴隷制の廃止や奴隷の解放については、ためらいなく「しかるべし!」と拳を振り上げていた。
というわけで、1833年には奴隷廃止法が成立した。
西インド諸島(カリブ海)の植民地にも所領を保有して砂糖プランテイションを経営する貴族や地主たちが、本国の議会では、サトウキビ農園の不可欠の労働力だったアフリカ人奴隷を解放し、奴隷労働を禁止する法案に賛成したのだ。
そして、世界最強の海軍(海洋権力)を持つブリテンは、航海法を駆使し、また制海権のおよぶ海域(つまりはカリブ海を含む大西洋の全域、インド洋、太平洋の西部とオセアニア方面)の主要航路に艦隊を派遣して、通常の商船貿易の保護や海賊の取り締りと並んで、奴隷貿易船の摘発・拿捕を展開することになった。
なぜ、いかにして、こういう次第になったのか。
答えをごく単純化して言えば、ヨーロッパおよびアメリカなどの諸国家との対抗のなかで、ブリテン諸島と海外植民地の支配層を国民(nation)として統合し、国民国家的な政治的凝集を組織化していく過程が、奴隷制廃止、奴隷貿易禁圧の政策とイデオロギーを生み出し高揚させ、国家の戦略にまでつくり上げていったのだ。
●「国民」とは何か●
ところで、「国民:nation」とは何かを、再度述べておこう。
日本では「国民=ネイション」という用語は、今になっても、ついに社会科学の用語としても、政治用語としても、正確な定義において定着することはなかった。太平洋戦争中からのミリタリズムが生み出した「国民」観念が、いまだにマスメディアと学術の世界を呪縛し続けているからだ。
日本の支配的なメディアと学術では、nationではなくpeopleを日本語の「国民」の照応語として当てている。
この呪縛は、日本国憲法(現行憲法)にも深くおよんでいて、憲法の規範は虚妄を含んだ規定になっていて、正確な用語によっては記述されていない。私は、日本国憲法が占領軍の政治的=軍事的ヘゲモニーのもとに制定されたと認識し、今のところ、そのようなものとしての英語版原案に正確に対応した日本語条項記述にひとまず復元すべきだと思っている。
本来、日本国憲法は、国民として国籍を与えられたカテゴリーの人びとではなく、peopleに市民権や人権を保証しているはずである。そこには差別を持ち込まないはずなのだが、現行憲法(日本語版)は国籍法による差別を日本での基本的人権に持ち込む論拠になっているのだ。
話を戻そう。
国民=ネイションとは、単一の国家制度によって総括され統合された複数の民族・人種集団からなる人間集合である。例外はない。日本イコール「単一民族」という虚妄は相手にしない。言い換えれば、国民とは、国家市民としての複数の民族や人種からなる人間集合なのである。
この統合=凝集(一体感や結束とも言えるか)は、歴史的に形成されてきたものである。国家の支配層は、上から一体感や団結を組織化しようとし、他方、民衆の側はさまざまな権利(市民権)や政府による保護や支援政策を獲得するために、国民という集合への参加・集結を求めてきた。
で、ブリテンの国民形成の話題はどうだろうか。
●イングランドからブリテン王国への拡張●
名誉革命ののち、イングランド王権と政府は、ブリテン諸島をイングランド教会という象徴のもとに統合しようとしてきた。とはいえ、イングランド教会は多数の宗派を許容したが、フランス、エスパーニャなどの大陸のカトリック諸国との対抗上、ことさらに「プロテスタント」王権が統治する王国であらねばならないというイデオロギーを掲げていた。
プロテスタントとは、この場合、教義や祈祷方法による厳格な峻別というよりも、国家の統治組織としての教会の指導に服することを受容する者というくらいの意味である。
それゆえ、カトリックを信奉する王による統治を拒絶してきた。イングランド王は、国家の元首であると同時にイングランド教会の首長であらねばならないという法も制定した。
18世紀になると、土地と政治への参加資格を(教会が許容する)プロテスタントだけに限定する厳格・狭隘な制限を緩めていった。また、イングランド人(民族)だけでなく、ウェイルズ人の信者にも統治への参加を受け入れていった。
そして、1707年にはスコットランドとイングランドという2つの王国を合同させる法が成立する。グレイト・ブリテン連合王国ができ上がる。とはいえ、ブリテン王国の大行政区としてのスコットランド王国には、独自の議会と行政に関する立法権が認められていた。
やがて、アイアランドもブリテン=イングランド王権による統治のもとに包合される。
そうなると、イングランド王や貴族、スコットランド貴族などが支配する海外植民地領(の住民)もまた、ブリテンに属することになる。
こうして、イングランド王はブリテン王として、主な民族集団として、イングランド人に加え、スコットランド人、ウェイルズ人、アイアランド人、海外植民地の住民である人種や民族を統治=保護することになった。
●統合の担い手としての「国民」●
王権と議会は、ヨーロッパ諸列強との(軍事的・政治的・経済的・イデオロギー的)対抗関係のなかで、優位を手に入れるためにも国家=国民としての統合を強化していかなければならない。とはいえ、王権国家の権威の受容は「ありがたみ」をどれほど感じるかに依存する。有力貴族やロンドンの富裕商人などのエリート階級は、自分たちの利害を議会や王権政府装置の政策や運営に組み込むことができるから、「ありがたみ」を切実に感じている。
ところが、一般民衆(下層階級)にとっては、王や王権とは「雲の上」よりもさらに遠い存在だった。民衆の日常生活は、各都市や地方(それも居住区域)ごとに分断されていて、「お上の権威」といえば、地元の行政区を管理する治安判事とか領主(地主貴族)やその従者ぐらいのものだった。
こういう意味では、国家の政治に参加し国家的統合を担う「国民」の内に値する人間集団は、王と有力貴族、地方の地主貴族やロンドンや有力諸都市の富裕商人(もちろん男性に限る)くらいに限られていた。
とはいえ、親分が王である教会では、聖職者たちが祈祷や集会(敬虔な民衆の参加率は概して高かった)のたびに、イングランド王を祝福し、その権威や徳を讃え、ブリテン王国の臣民であることの「幸福」や「ありがたさ」を説教することで、一般庶民にも王権や王国の観念は漠然とではあれ、浸透していくだろう。
やがて、庶民院の選挙権資格は、地主貴族以外にも、ある程度の資産を保有する階層に拡大されていく。工場経営者とか地方町の有力商人、借地農経営者とか都市の専門職層などが、選挙(選挙運動や投票など)による政治に参加するようになる。
一般民衆にはアクセスできない特権を受けるのは、優越感を感じるし、名誉なことであり、自分の社会的地位の上昇や認証、威信を実感するものである。ひとかどの人間となった気分になる。
国家やレジームに対する参加意識や「ありがたみ」を感じるようになり、教会活動への参加や治安判事の行政活動への協力姿勢も強まる。
こうして、「国民」の範囲はどんどん拡大していく。国家の制度や統治装置の周囲により多くの人びとが結集し、政治的に組織化されていく。
●王権の側が感じた「国民」の「ありがたみ」●
18世紀全体をつうじて、ブリテン国家は大小の戦争や戦闘を繰り返していく。世界経済や貿易で最優位を手にしているネーデルラントと対抗して戦うこともあったし、フランスとは海外植民地領土をめぐってアメリカやアフリカやアジアで熾烈にやり合った。なにしろ18世紀は、エスパーニャ王位継承戦争(フランスとの戦い)から始まって、フランス革命とナポレオン戦争で暮れるという時代だった。
危うい局面もあったが、ブリテンは巨大なフランスを相手に優位を確保し続けた。
鍵は、戦争に投入する財政資金をほかのどの国家よりも潤沢に手に入れることができたからだ。イングランド銀行(国家が認可した民間銀行)が、戦争債権も含めた公債発行を取り仕切り、政府に豊富なポンド紙幣を供給してくれた。
結局は、シティの富裕金融家や地主貴族が(高い利回りを保証された)国債を大量に買い入れてくれたせいだが、やがて、選挙権を獲得した富裕中間階級も戦争債や公債を買い入れてくれるようになった。なにしろ、人口が貴族よりも圧倒的に多いから、彼らは総額で巨額の国家財政資金を背負ってくれることになった。
ブリテンの世界貿易での優越や植民地の拡大は、中間階級にも商工業や投資での大事な利殖機会を保証してくれたし、いまや市民権を得た彼らは、王権国家と自分たちの利害の一致を切実に感じていたのだ。その王権国家の軍事的敗北は、自分たちの経済的上昇の可能性を奪い取る危険をもたらすだろう。逆に勝利は、ブリテンの優位を拡大して、さらなる利殖機会を提供してくれる。
なにしろ、夕方パブでブリテンの戦勝を祝って飲む酒の味は格別だし、参加者全員との強い絆や一体感を感じるし、優越感も感じる。やがて、街に戦勝祝賀パレイドに繰り出すことにもなる。
こうした動きは、フランス革命期に活発化する。
とはいえ、アメリカ独立戦争での「敗北」(東部植民地13州同盟の独立とブリテン帝国からの離脱)は、ブリテンのエリートにも中間層にも、大きな打撃だった。
その喪失感や屈辱感から解放されるためにも、フランス革命派やナポレオンに対する勝利は不可欠だった。
●「国民」としての優越感や「愛国精神」の誕生●
この戦争は、戦争の近代化への大きな転換点だったが、統治装置や政治的指導者によるマスメディアを利用した組織化された宣伝戦を生み出した。
互いに相手に対する自国のレジームの優位や美徳=「善なること」を主張し、相手のレジームの邪悪さや欠点を誇張した。敵対国の内部に分裂や亀裂を生みだし、自分たちの協力者を見つけようとした。他方で、自分の側の団結や結集をより強く巧妙に組織化しようとした。
無数のパンフレットや新聞、書籍が発行され、街頭でのアジテイションや示威行進が組織された。行進や行列への参加は、人びとに一体感や連帯意識を生み出し増幅していった。
人びとは、そういう活動への参加で日ごろの憂さを晴らしたり、アメリカ独立戦争での敗北の屈辱感を払拭していくことにもなった。
ヨーロッパ的規模(文脈)では、まさにフランス革命とナポレオン戦争が「国民」(国民形成へのダイナミズム)を生み出した。フランスの支配者=指導者は、外国からの反革命戦争と干渉に対して、「フランスなるもの」を守るためにの統合と結束・団結を訴え、近隣の諸国への侵略や戦争を鼓舞して、民衆を駆り立てた。
侵略や侵攻を受けた側では、はじめは「貴族の特権」の廃止を訴える革命思想に共感したが、侵略軍の収奪や掠奪、秩序と生活の破壊に対して強く反発し、フランス軍の侵略を跳ね返せるような強い国家=中央政府の樹立や「近代化」を求めるようになっていく。フランスに対抗する「国民」を形成しなければ、ヨーロッパの競争で生き残れない、と。
ことにドイツでは、プロイセン王権とオーストリア王権が対抗しながら、周囲の中小領邦を併合統合して中央ヨーロッパ=ドイツの国民国家的統合を求めるようになっていく。
ブリテンは、イングランド銀行(シティの金融資本家連合)による借款供与をつうじて国民形成と産業育成をめざすヨーロッパ諸王国を支援していく。それは、ロンドンを中心とする金融循環と貿易システムにこれらの諸王国を組み込んで(すなわち従属させて)いく戦略でもあった。
ところで、18世紀はじめのブリテンでは、地主貴族階級や金融・貿易商人などの飛び抜けて富裕な階層への選挙権は拡大したが、住民全体からみれば、まだまだ「国民」はほんの一握りの少数派だった。彼らの下に位置する階級や階層も選挙をつうじての政治参加を求めていた。
とりわけ、スコットランド人やウェイルズ人、アイアランド人たちは、ウェストミンスター議会の選挙に参加することだけではなく、世界貿易と植民地帝国を支配するイングランドが確保しているブリテン帝国の権益や商業機会に参入するために、団体を結成して運動した。
さらに、ブリテン全域で中下層民衆もまたさまざまな政治運動=団体に参加するようになっていく。
これらの団体=運動は概して、「プロテスタント王国としての美徳や優越」を誇示する政策や思想を政権や議会が掲げるよう求める傾向が強かった。外国との戦争の勝利を祝う行事にも大々的に参加した。そうあうることで、帝国臣民としての一体感や参加意識を感じたりする場を求めていた。いうまでもなく、ブリテン臣民としての「まとまり」や一体感には、外国に対する対抗意識や侮蔑的な優越感が含まれていた。
ナショナルな意識というものは、他国への対抗心や優越願望がなければ形成されないものなのだ。
こういうわけで、より下層の民衆への市民権の拡大は、民衆による「下からの統合への参加」運動と連動するようになっていく。こうして、「愛国精神:patriotism」なるものが生まれ始めた。
そして、新たに投票権や被選挙権を獲得して自分の社会的地位の上昇のためにこうした権利や機会を利用しようともくろむ者たちは、民衆の支持を獲得するために「愛国心」なるものに訴えるようになる。とはいえ、相対立する利害や思想、政策が、おなじブリテンへの「愛国心」スローガンのもとに喧伝されることになった。
「愛国心」なるものを利用して民衆を扇動して、自分の権威や地位の上昇を露骨に狙う者どもも排出した。世界最初の「ポピュリスト」として頭角を現したジョン・ウィルクスを侮蔑し非難がましい評価を与えたサミュエル・ジョンスンが、「愛国心は悪党(食わせ者)の最後の逃げ場である」という有名な格言を著したのは、このような文脈であった。
●「奴隷制度廃止」こそは「優等国民の理性」である!●
こうしてみると、一定の地理的範囲(領土)の内部で諸階級が特殊なレジームに内部に統合されている状態は、支配機構としての国家装置だけがおこなう作用の結果ではないことがわかる。単に支配階級が一方的に下位の諸階級を支配し従属させているわけではないのだ。従属的諸階級もまたレジームの内部での権利や利益機会を手に入れるために、さまざまな政治過程への参加(世論形成への関与というべきか)を求めて団体や運動を組織していったことが見える。
それはまた、国境の外部の諸力(他国民など)と排他的に区分された集合に自らを組織化していく過程でもあった。それゆえまた、他国民との根強い対抗意識(戦争時には敵対心)を形成していくことになり、国民的イデオロギー(ナショナリズム)を生み出していくことになった。
さて、19世紀前半のブリテンでは、さまざまな団体=運動の組織化という形で、外国と比べてプロテスタントが支配する国民としての優位を自己確認するための美徳(としての政治的目標)の追求が繰り広げられた。そのなかで、とりわけ幅広い支持を獲得した課題の1つが「奴隷制度の廃止」「奴隷の解放」であった。
それまで、ヨーロッパのいかなる国民=国家も「奴隷制」を道徳的・政治的に非難されるべき、それゆえ廃止されるべき悪しき制度であるとは認識していなかった(もちろん、個々人や個別団体の次元ではさまざまな論難があった)。
「神の前の人間の平等」というプロテスタントの理想とも合致する「奴隷制廃止」は、それゆえ「神から最も深く祝福されたブリテン国民」こそが人類全体を良き理想に向けて導くためのスローガンになりうる。ヨーロッパで最良かつ最優に立つブリテンこそが、率先して追求すべき政治的=道徳的目標となるべきだ。
こういう理念=イデオロギーがまさにブリテン規模で支持されようになった。
この理念は、ことにアメリカ独立戦争での敗北で、それとなく道徳的=政治的に劣位を意識させられた支配階級や指導的階級にとって、名誉を自ら挽回し自己威信を取り戻そうとする欲求にかなっていた。アメリカ植民地の支配集団の主力は、ブリテンの指導層と同じくプロテスタントだったので、WASPどうしが戦ってブリテンが敗れたという後味の悪さを払拭する、またとない理念であった。」
というのも、ブリテンへの従属を嫌悪し住民の平等を主張した、あのアメリカ独立同盟にしてからが、綿花栽培やタバコ栽培などの農業では奴隷労働が支配的ではないか。奴隷労働と奴隷貿易を是としてるアメリカ独立同盟に対して、奴隷制廃止の理想を求めるブリテンは、まさに道徳的=政治的に優位に立っているのだから、と。
ブリテン国内では劣位の経営環境におかれた綿工業では、いまだにアメリカ南部の奴隷労働によって生産された綿花を原料措として安価に輸入しているものの、この産業はすでに産業利潤獲得(資本蓄積)の基軸から落ちこぼれて久しい。だから、安価な綿花がアメリカから輸入できなくなっても、さほどの痛痒を感じることはない。綿花の主要な輸入先(ブリテンの国内産業のためではなく、再輸出によって遅れて工業化を開始した諸国に売りつけるため)は、もはやインド植民地や中東、北アフリカ・エジプトへと移動している。
さらに、海洋権力(制海権)に裏打ちされながら世界貿易を支配している地位を利用して、輸出品を生産している諸国に奴隷労働の廃止を強制すれば、奴隷労働によって高い利潤を獲得している競争相手の諸国の利潤率を切り崩すこともできる。とりわけフランスやアメリカ、エスパーニャなどに対して。
つまり、奴隷制廃止は、ライヴァル諸国民や敵対諸国民の利潤機会と権益を切り崩すための戦略手段となるわけだ。
たとえば、カリブ海域のフランスやエスパーニャなどの植民地ではアフリカからの奴隷輸入によって安価な労働力を確保して、砂糖やタバコ、熱帯農産物の栽培プランテイションが維持され、植民地統治のための財政が保たれていた。だから、大西洋・カリブ海域でブリテン海軍の艦船による奴隷貿易船の摘発・拿捕を強化したことで、これらの島嶼植民地の経済と財政は傾き始め、軍事的・政治的防衛力は弱体化し、ブリテンによる支配の浸透拡大にはきわめて好都合の状況をもたらした。
さなきだにブリテンの貿易覇権に屈しかけていた地域だったのだから。
カリブ海や南アメリカのエスパーニャ植民地は、名目上はエスパーニャを宗主国としながらも、経済的・財政的にはロンドンに従属する構想が築かれていった。
ブリテン艦隊が拿捕した奴隷貿易船舶から保護されたアフリカ系黒人奴隷は奴隷身分から解放され、ブリテン本国への移住を望めば「自由人」としての居住が認められた。背後には、ブリテン国家の覇権戦略や利益追求がたらいていたとしても、奴隷制廃止と奴隷解放は人道的、道徳的に大きな意味合いを持っていた。
こうして、ひとたび「奴隷制廃止」や「奴隷解放」がブリテンという影響力の大きなレジーム(植民地帝国)で既成事実化すると、そのインパクトは世界的規模で広がっていった。
アメリカでは、ブリテンの奴隷制廃止法(1833年)の制定直後から、この問題をめぐって政治的論争が展開され、北部と南部との対立(というよりも南部の北部への政治的従属)が顕著になっていった。ルイジアナ(ルイ王の支配地という意味)を中心とする地域は、(ブリテンのライヴァル)フランスとの経済的・文化的結びつきが深かったから、北部による支配の強化は、アメリカへのフランスの影響力を削ぐためにも重要だった。
小ブログ記事「故郷アフリカは遥かに遠く」(映画《アミスタッド》に関して)を参照のこと。
この作品では、19世紀半ば近くになっても大西洋・カリブ海域では盛んに奴隷貿易が繰り広げられていたことが描かれていた。そして、ほとんどのヨーロッパ諸国家が奴隷貿易や奴隷を労働力とする産業・経営を維持しているなかで、国家としてはブリテンだけが奴隷制度に反対し、制海権をに握る海域では奴隷貿易を禁圧し取り締まっていたことも。
ところで、いまや(単なる王権国家ではなく)国民国家としてのレジームを完成したブリテンにとっては、奴隷制度の廃止と奴隷貿易の禁圧は、世界システムやヨーロッパ国際関係のなかでの最優位と覇権を維持し続けるための政策ないし戦略となっていた。
ほかの列強諸国家は、植民地帝国の経営や国際競争での優位のために奴隷制を容認していた。それらの国家は、ことに植民地では奴隷労働が農業や鉱業の高い利潤率を確保するための重要な手段となっていることを知っているからこそ、奴隷制を維持し続けていたのだった。
フランスは市民革命で「人間(ただし男性)と市民の権利宣言」を高く掲げたにもかかわらず、植民地や属領では奴隷制が廃止されなかった。
奴隷制を利用した産業形態ほど利益の上がる経営はなかったのだ。
ブリテンは、植民地経営や世界貿易でこれほど利潤率が有利な奴隷制を、国家の制度(理念)=イデオロギーとして掲げて、自ら放棄したのだ。そして、奴隷制の廃絶をほかの列強諸国民に押しつけようとした。
フランス革命のイデオロギーや「人権宣言」に対抗して、王政や身分制=貴族制の固守を中心とする政治的保守主義を「国是:ナショナルなモラル」と掲げたブリテンが、この時期になにゆえに意識的に奴隷制を廃絶し、「人種による差別と隷属」を禁止するイデオロギーや制度を打ち出したのか。
ブリテン連合王国では、18世紀末から奴隷制の廃止や奴隷労働の禁止を求める民衆運動や有力政治団体の結成が目立つようになった。そして、1830年ごろまでには、奴隷制廃止という要求はウェストミンスター議会(とくに庶民院)の多数派意見となっていた。一般民衆への政治参加権や選挙権の拡大を回避・拒否していたエリート層が、自ら進んで奴隷制廃止運動の担い手となろうとしたのだ。
エリートたちは、貴族と庶民との身分的格差は「あってしかるべき仕組み」と何の躊躇もなく言い張る貴族やシティの有力者たちの多くが、奴隷制の廃止や奴隷の解放については、ためらいなく「しかるべし!」と拳を振り上げていた。
というわけで、1833年には奴隷廃止法が成立した。
西インド諸島(カリブ海)の植民地にも所領を保有して砂糖プランテイションを経営する貴族や地主たちが、本国の議会では、サトウキビ農園の不可欠の労働力だったアフリカ人奴隷を解放し、奴隷労働を禁止する法案に賛成したのだ。
そして、世界最強の海軍(海洋権力)を持つブリテンは、航海法を駆使し、また制海権のおよぶ海域(つまりはカリブ海を含む大西洋の全域、インド洋、太平洋の西部とオセアニア方面)の主要航路に艦隊を派遣して、通常の商船貿易の保護や海賊の取り締りと並んで、奴隷貿易船の摘発・拿捕を展開することになった。
なぜ、いかにして、こういう次第になったのか。
答えをごく単純化して言えば、ヨーロッパおよびアメリカなどの諸国家との対抗のなかで、ブリテン諸島と海外植民地の支配層を国民(nation)として統合し、国民国家的な政治的凝集を組織化していく過程が、奴隷制廃止、奴隷貿易禁圧の政策とイデオロギーを生み出し高揚させ、国家の戦略にまでつくり上げていったのだ。
●「国民」とは何か●
ところで、「国民:nation」とは何かを、再度述べておこう。
日本では「国民=ネイション」という用語は、今になっても、ついに社会科学の用語としても、政治用語としても、正確な定義において定着することはなかった。太平洋戦争中からのミリタリズムが生み出した「国民」観念が、いまだにマスメディアと学術の世界を呪縛し続けているからだ。
日本の支配的なメディアと学術では、nationではなくpeopleを日本語の「国民」の照応語として当てている。
この呪縛は、日本国憲法(現行憲法)にも深くおよんでいて、憲法の規範は虚妄を含んだ規定になっていて、正確な用語によっては記述されていない。私は、日本国憲法が占領軍の政治的=軍事的ヘゲモニーのもとに制定されたと認識し、今のところ、そのようなものとしての英語版原案に正確に対応した日本語条項記述にひとまず復元すべきだと思っている。
本来、日本国憲法は、国民として国籍を与えられたカテゴリーの人びとではなく、peopleに市民権や人権を保証しているはずである。そこには差別を持ち込まないはずなのだが、現行憲法(日本語版)は国籍法による差別を日本での基本的人権に持ち込む論拠になっているのだ。
話を戻そう。
国民=ネイションとは、単一の国家制度によって総括され統合された複数の民族・人種集団からなる人間集合である。例外はない。日本イコール「単一民族」という虚妄は相手にしない。言い換えれば、国民とは、国家市民としての複数の民族や人種からなる人間集合なのである。
この統合=凝集(一体感や結束とも言えるか)は、歴史的に形成されてきたものである。国家の支配層は、上から一体感や団結を組織化しようとし、他方、民衆の側はさまざまな権利(市民権)や政府による保護や支援政策を獲得するために、国民という集合への参加・集結を求めてきた。
で、ブリテンの国民形成の話題はどうだろうか。
●イングランドからブリテン王国への拡張●
名誉革命ののち、イングランド王権と政府は、ブリテン諸島をイングランド教会という象徴のもとに統合しようとしてきた。とはいえ、イングランド教会は多数の宗派を許容したが、フランス、エスパーニャなどの大陸のカトリック諸国との対抗上、ことさらに「プロテスタント」王権が統治する王国であらねばならないというイデオロギーを掲げていた。
プロテスタントとは、この場合、教義や祈祷方法による厳格な峻別というよりも、国家の統治組織としての教会の指導に服することを受容する者というくらいの意味である。
それゆえ、カトリックを信奉する王による統治を拒絶してきた。イングランド王は、国家の元首であると同時にイングランド教会の首長であらねばならないという法も制定した。
18世紀になると、土地と政治への参加資格を(教会が許容する)プロテスタントだけに限定する厳格・狭隘な制限を緩めていった。また、イングランド人(民族)だけでなく、ウェイルズ人の信者にも統治への参加を受け入れていった。
そして、1707年にはスコットランドとイングランドという2つの王国を合同させる法が成立する。グレイト・ブリテン連合王国ができ上がる。とはいえ、ブリテン王国の大行政区としてのスコットランド王国には、独自の議会と行政に関する立法権が認められていた。
やがて、アイアランドもブリテン=イングランド王権による統治のもとに包合される。
そうなると、イングランド王や貴族、スコットランド貴族などが支配する海外植民地領(の住民)もまた、ブリテンに属することになる。
こうして、イングランド王はブリテン王として、主な民族集団として、イングランド人に加え、スコットランド人、ウェイルズ人、アイアランド人、海外植民地の住民である人種や民族を統治=保護することになった。
●統合の担い手としての「国民」●
王権と議会は、ヨーロッパ諸列強との(軍事的・政治的・経済的・イデオロギー的)対抗関係のなかで、優位を手に入れるためにも国家=国民としての統合を強化していかなければならない。とはいえ、王権国家の権威の受容は「ありがたみ」をどれほど感じるかに依存する。有力貴族やロンドンの富裕商人などのエリート階級は、自分たちの利害を議会や王権政府装置の政策や運営に組み込むことができるから、「ありがたみ」を切実に感じている。
ところが、一般民衆(下層階級)にとっては、王や王権とは「雲の上」よりもさらに遠い存在だった。民衆の日常生活は、各都市や地方(それも居住区域)ごとに分断されていて、「お上の権威」といえば、地元の行政区を管理する治安判事とか領主(地主貴族)やその従者ぐらいのものだった。
こういう意味では、国家の政治に参加し国家的統合を担う「国民」の内に値する人間集団は、王と有力貴族、地方の地主貴族やロンドンや有力諸都市の富裕商人(もちろん男性に限る)くらいに限られていた。
とはいえ、親分が王である教会では、聖職者たちが祈祷や集会(敬虔な民衆の参加率は概して高かった)のたびに、イングランド王を祝福し、その権威や徳を讃え、ブリテン王国の臣民であることの「幸福」や「ありがたさ」を説教することで、一般庶民にも王権や王国の観念は漠然とではあれ、浸透していくだろう。
やがて、庶民院の選挙権資格は、地主貴族以外にも、ある程度の資産を保有する階層に拡大されていく。工場経営者とか地方町の有力商人、借地農経営者とか都市の専門職層などが、選挙(選挙運動や投票など)による政治に参加するようになる。
一般民衆にはアクセスできない特権を受けるのは、優越感を感じるし、名誉なことであり、自分の社会的地位の上昇や認証、威信を実感するものである。ひとかどの人間となった気分になる。
国家やレジームに対する参加意識や「ありがたみ」を感じるようになり、教会活動への参加や治安判事の行政活動への協力姿勢も強まる。
こうして、「国民」の範囲はどんどん拡大していく。国家の制度や統治装置の周囲により多くの人びとが結集し、政治的に組織化されていく。
●王権の側が感じた「国民」の「ありがたみ」●
18世紀全体をつうじて、ブリテン国家は大小の戦争や戦闘を繰り返していく。世界経済や貿易で最優位を手にしているネーデルラントと対抗して戦うこともあったし、フランスとは海外植民地領土をめぐってアメリカやアフリカやアジアで熾烈にやり合った。なにしろ18世紀は、エスパーニャ王位継承戦争(フランスとの戦い)から始まって、フランス革命とナポレオン戦争で暮れるという時代だった。
危うい局面もあったが、ブリテンは巨大なフランスを相手に優位を確保し続けた。
鍵は、戦争に投入する財政資金をほかのどの国家よりも潤沢に手に入れることができたからだ。イングランド銀行(国家が認可した民間銀行)が、戦争債権も含めた公債発行を取り仕切り、政府に豊富なポンド紙幣を供給してくれた。
結局は、シティの富裕金融家や地主貴族が(高い利回りを保証された)国債を大量に買い入れてくれたせいだが、やがて、選挙権を獲得した富裕中間階級も戦争債や公債を買い入れてくれるようになった。なにしろ、人口が貴族よりも圧倒的に多いから、彼らは総額で巨額の国家財政資金を背負ってくれることになった。
ブリテンの世界貿易での優越や植民地の拡大は、中間階級にも商工業や投資での大事な利殖機会を保証してくれたし、いまや市民権を得た彼らは、王権国家と自分たちの利害の一致を切実に感じていたのだ。その王権国家の軍事的敗北は、自分たちの経済的上昇の可能性を奪い取る危険をもたらすだろう。逆に勝利は、ブリテンの優位を拡大して、さらなる利殖機会を提供してくれる。
なにしろ、夕方パブでブリテンの戦勝を祝って飲む酒の味は格別だし、参加者全員との強い絆や一体感を感じるし、優越感も感じる。やがて、街に戦勝祝賀パレイドに繰り出すことにもなる。
こうした動きは、フランス革命期に活発化する。
とはいえ、アメリカ独立戦争での「敗北」(東部植民地13州同盟の独立とブリテン帝国からの離脱)は、ブリテンのエリートにも中間層にも、大きな打撃だった。
その喪失感や屈辱感から解放されるためにも、フランス革命派やナポレオンに対する勝利は不可欠だった。
●「国民」としての優越感や「愛国精神」の誕生●
この戦争は、戦争の近代化への大きな転換点だったが、統治装置や政治的指導者によるマスメディアを利用した組織化された宣伝戦を生み出した。
互いに相手に対する自国のレジームの優位や美徳=「善なること」を主張し、相手のレジームの邪悪さや欠点を誇張した。敵対国の内部に分裂や亀裂を生みだし、自分たちの協力者を見つけようとした。他方で、自分の側の団結や結集をより強く巧妙に組織化しようとした。
無数のパンフレットや新聞、書籍が発行され、街頭でのアジテイションや示威行進が組織された。行進や行列への参加は、人びとに一体感や連帯意識を生み出し増幅していった。
人びとは、そういう活動への参加で日ごろの憂さを晴らしたり、アメリカ独立戦争での敗北の屈辱感を払拭していくことにもなった。
ヨーロッパ的規模(文脈)では、まさにフランス革命とナポレオン戦争が「国民」(国民形成へのダイナミズム)を生み出した。フランスの支配者=指導者は、外国からの反革命戦争と干渉に対して、「フランスなるもの」を守るためにの統合と結束・団結を訴え、近隣の諸国への侵略や戦争を鼓舞して、民衆を駆り立てた。
侵略や侵攻を受けた側では、はじめは「貴族の特権」の廃止を訴える革命思想に共感したが、侵略軍の収奪や掠奪、秩序と生活の破壊に対して強く反発し、フランス軍の侵略を跳ね返せるような強い国家=中央政府の樹立や「近代化」を求めるようになっていく。フランスに対抗する「国民」を形成しなければ、ヨーロッパの競争で生き残れない、と。
ことにドイツでは、プロイセン王権とオーストリア王権が対抗しながら、周囲の中小領邦を併合統合して中央ヨーロッパ=ドイツの国民国家的統合を求めるようになっていく。
ブリテンは、イングランド銀行(シティの金融資本家連合)による借款供与をつうじて国民形成と産業育成をめざすヨーロッパ諸王国を支援していく。それは、ロンドンを中心とする金融循環と貿易システムにこれらの諸王国を組み込んで(すなわち従属させて)いく戦略でもあった。
ところで、18世紀はじめのブリテンでは、地主貴族階級や金融・貿易商人などの飛び抜けて富裕な階層への選挙権は拡大したが、住民全体からみれば、まだまだ「国民」はほんの一握りの少数派だった。彼らの下に位置する階級や階層も選挙をつうじての政治参加を求めていた。
とりわけ、スコットランド人やウェイルズ人、アイアランド人たちは、ウェストミンスター議会の選挙に参加することだけではなく、世界貿易と植民地帝国を支配するイングランドが確保しているブリテン帝国の権益や商業機会に参入するために、団体を結成して運動した。
さらに、ブリテン全域で中下層民衆もまたさまざまな政治運動=団体に参加するようになっていく。
これらの団体=運動は概して、「プロテスタント王国としての美徳や優越」を誇示する政策や思想を政権や議会が掲げるよう求める傾向が強かった。外国との戦争の勝利を祝う行事にも大々的に参加した。そうあうることで、帝国臣民としての一体感や参加意識を感じたりする場を求めていた。いうまでもなく、ブリテン臣民としての「まとまり」や一体感には、外国に対する対抗意識や侮蔑的な優越感が含まれていた。
ナショナルな意識というものは、他国への対抗心や優越願望がなければ形成されないものなのだ。
こういうわけで、より下層の民衆への市民権の拡大は、民衆による「下からの統合への参加」運動と連動するようになっていく。こうして、「愛国精神:patriotism」なるものが生まれ始めた。
そして、新たに投票権や被選挙権を獲得して自分の社会的地位の上昇のためにこうした権利や機会を利用しようともくろむ者たちは、民衆の支持を獲得するために「愛国心」なるものに訴えるようになる。とはいえ、相対立する利害や思想、政策が、おなじブリテンへの「愛国心」スローガンのもとに喧伝されることになった。
「愛国心」なるものを利用して民衆を扇動して、自分の権威や地位の上昇を露骨に狙う者どもも排出した。世界最初の「ポピュリスト」として頭角を現したジョン・ウィルクスを侮蔑し非難がましい評価を与えたサミュエル・ジョンスンが、「愛国心は悪党(食わせ者)の最後の逃げ場である」という有名な格言を著したのは、このような文脈であった。
●「奴隷制度廃止」こそは「優等国民の理性」である!●
こうしてみると、一定の地理的範囲(領土)の内部で諸階級が特殊なレジームに内部に統合されている状態は、支配機構としての国家装置だけがおこなう作用の結果ではないことがわかる。単に支配階級が一方的に下位の諸階級を支配し従属させているわけではないのだ。従属的諸階級もまたレジームの内部での権利や利益機会を手に入れるために、さまざまな政治過程への参加(世論形成への関与というべきか)を求めて団体や運動を組織していったことが見える。
それはまた、国境の外部の諸力(他国民など)と排他的に区分された集合に自らを組織化していく過程でもあった。それゆえまた、他国民との根強い対抗意識(戦争時には敵対心)を形成していくことになり、国民的イデオロギー(ナショナリズム)を生み出していくことになった。
さて、19世紀前半のブリテンでは、さまざまな団体=運動の組織化という形で、外国と比べてプロテスタントが支配する国民としての優位を自己確認するための美徳(としての政治的目標)の追求が繰り広げられた。そのなかで、とりわけ幅広い支持を獲得した課題の1つが「奴隷制度の廃止」「奴隷の解放」であった。
それまで、ヨーロッパのいかなる国民=国家も「奴隷制」を道徳的・政治的に非難されるべき、それゆえ廃止されるべき悪しき制度であるとは認識していなかった(もちろん、個々人や個別団体の次元ではさまざまな論難があった)。
「神の前の人間の平等」というプロテスタントの理想とも合致する「奴隷制廃止」は、それゆえ「神から最も深く祝福されたブリテン国民」こそが人類全体を良き理想に向けて導くためのスローガンになりうる。ヨーロッパで最良かつ最優に立つブリテンこそが、率先して追求すべき政治的=道徳的目標となるべきだ。
こういう理念=イデオロギーがまさにブリテン規模で支持されようになった。
この理念は、ことにアメリカ独立戦争での敗北で、それとなく道徳的=政治的に劣位を意識させられた支配階級や指導的階級にとって、名誉を自ら挽回し自己威信を取り戻そうとする欲求にかなっていた。アメリカ植民地の支配集団の主力は、ブリテンの指導層と同じくプロテスタントだったので、WASPどうしが戦ってブリテンが敗れたという後味の悪さを払拭する、またとない理念であった。」
というのも、ブリテンへの従属を嫌悪し住民の平等を主張した、あのアメリカ独立同盟にしてからが、綿花栽培やタバコ栽培などの農業では奴隷労働が支配的ではないか。奴隷労働と奴隷貿易を是としてるアメリカ独立同盟に対して、奴隷制廃止の理想を求めるブリテンは、まさに道徳的=政治的に優位に立っているのだから、と。
ブリテン国内では劣位の経営環境におかれた綿工業では、いまだにアメリカ南部の奴隷労働によって生産された綿花を原料措として安価に輸入しているものの、この産業はすでに産業利潤獲得(資本蓄積)の基軸から落ちこぼれて久しい。だから、安価な綿花がアメリカから輸入できなくなっても、さほどの痛痒を感じることはない。綿花の主要な輸入先(ブリテンの国内産業のためではなく、再輸出によって遅れて工業化を開始した諸国に売りつけるため)は、もはやインド植民地や中東、北アフリカ・エジプトへと移動している。
さらに、海洋権力(制海権)に裏打ちされながら世界貿易を支配している地位を利用して、輸出品を生産している諸国に奴隷労働の廃止を強制すれば、奴隷労働によって高い利潤を獲得している競争相手の諸国の利潤率を切り崩すこともできる。とりわけフランスやアメリカ、エスパーニャなどに対して。
つまり、奴隷制廃止は、ライヴァル諸国民や敵対諸国民の利潤機会と権益を切り崩すための戦略手段となるわけだ。
たとえば、カリブ海域のフランスやエスパーニャなどの植民地ではアフリカからの奴隷輸入によって安価な労働力を確保して、砂糖やタバコ、熱帯農産物の栽培プランテイションが維持され、植民地統治のための財政が保たれていた。だから、大西洋・カリブ海域でブリテン海軍の艦船による奴隷貿易船の摘発・拿捕を強化したことで、これらの島嶼植民地の経済と財政は傾き始め、軍事的・政治的防衛力は弱体化し、ブリテンによる支配の浸透拡大にはきわめて好都合の状況をもたらした。
さなきだにブリテンの貿易覇権に屈しかけていた地域だったのだから。
カリブ海や南アメリカのエスパーニャ植民地は、名目上はエスパーニャを宗主国としながらも、経済的・財政的にはロンドンに従属する構想が築かれていった。
ブリテン艦隊が拿捕した奴隷貿易船舶から保護されたアフリカ系黒人奴隷は奴隷身分から解放され、ブリテン本国への移住を望めば「自由人」としての居住が認められた。背後には、ブリテン国家の覇権戦略や利益追求がたらいていたとしても、奴隷制廃止と奴隷解放は人道的、道徳的に大きな意味合いを持っていた。
こうして、ひとたび「奴隷制廃止」や「奴隷解放」がブリテンという影響力の大きなレジーム(植民地帝国)で既成事実化すると、そのインパクトは世界的規模で広がっていった。
アメリカでは、ブリテンの奴隷制廃止法(1833年)の制定直後から、この問題をめぐって政治的論争が展開され、北部と南部との対立(というよりも南部の北部への政治的従属)が顕著になっていった。ルイジアナ(ルイ王の支配地という意味)を中心とする地域は、(ブリテンのライヴァル)フランスとの経済的・文化的結びつきが深かったから、北部による支配の強化は、アメリカへのフランスの影響力を削ぐためにも重要だった。