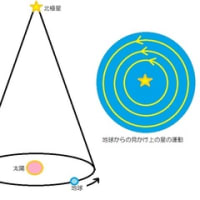◆◆物語性と演技(それぞれと両者の関係)を考える◆◆
ここで扱うのは、映画作品のための物語(story or drama)と演技(role-playing)である。そして、物語が登場人物たちの言動とかかわり合いをつうじて織りなされ表現れる限り、演技は物語性の不可欠の、ほとんど本質的ともいえる要素となるだろう。舞台演劇の演技は、歴史的かつ構造的に見て映画(のための演劇)の基礎にあるものだが、ここでは直接には扱わない。
1 映像物語とは何か
映像物語としての映画作品を考えるためには、物語それ自体が何かを語らなければならないかもしれない。
では、物語とは何か。
人びとの言動によって織りなされる出来事、因果関係や起承転結という流れや組み立てのあるエピソード(の集合)である。
物語は、戯曲=演劇によっても、小説によっても、オペラや楽劇によっても、表現される。文字としての言葉、音声としての言葉によって人の行動や姿が語られ、事件の意味や人物の心理が描かれる(暗示される)。したがって、必ず(少なくとも背景には)文脈がある。因果関係や起承転結、すなわち言動や場面を結びつけ、一連の流れに連結する連関がある。
では、物語は、何をめざしているのか、物語が求めるものは何か。
人びとの共感や感情移入を呼び起こし、登場人物の心理や性格について考えさせ、人生や社会(世の中)についてな何がしかのイメイジを抱かせるため。説得のため。あるいは扇動のため、つまりプロパガンダのため。要するに、作品としてすぐれているものには、必ず一定の価値観や人生観、世界観などが込められていることになる。
そのための形としては、喜劇、滑稽劇、悲劇などであり、人びとの心に安心感や愉快な気分、笑い、あるいは恐怖、驚愕を呼び起こすことになる。
そうすると、映画=映像物語とは、どういうものか。
物語=劇を映像にして編集構成することによって、以上のような目的を追求するためだ。そして、映画がすぐれて現代的な社会現象であり、現代資本主義的文明の所産であってみれば、所詮、経営体による利潤獲得の手段、1つの形態として営まれているということになる。
とはいえ、資本主義的経営の1つの形態=手段であるという次元の問題は、ここではひとまず脇に置いておく。映像劇=映画に内在的なことがらだけを扱うことにする。
映像物語にしても舞台演劇にしても、小説にしても、物語が説得性や訴求性をもつためには、リアリティや存在感など、感情移入(嫌悪や拒否感などネガティヴな感情移入も含む)を呼び起こす道具立てが必要になる。あるいは、興味や好奇心を呼び起こす、人びとの想像力を刺激するといってもいいかもしれない。
人びとが目の前で展開している出来事に引きつけられなければならない。
その出来事が人びとの言動(の絡み合い・相互作用。もちろん独り劇もあるが)から構成されるとすれば、人びとを引きつけるのは、登場人物の言動であり、つまりは役者の演技のリアリティや存在感、訴求力・説得力が求められることになる。
物語がどれほど奇想天外でありそうもないような事件を描こうとも、シーンやシークェンスに人びとを引きつけなければならない。そのさいに、人物の存在感は決定的な重要性を持つだろう。
2 演技とは何か
演技(role-playing)とは何か。ロールプレイングという言葉からわかるように、登場人物の役割を演じることである。一定の状況下での登場人物たちの役割=言動が物語の展開を推し進め、織り上げていく。
以前に考察したように、映画作品では場面の装置や備品・道具、背景設定がリアリティや存在感を与えるために重要になるが、そういうものを背景にした人物たちの言動に魅力がなければ、興ざめである。
観客の感情移入を誘導する〈driving forces〉(観客を引きつけながら物語を駆動していく力)のなかでも決定的に重要な要素こそ、演技なのである。
ロールプレイングは、人物の存在感を表現する手段なのである。顔の表情や眼差し、声音や話し方、身ぶり手ぶり、もちろん俳優がもって生まれた雰囲気や性格というものもあろう。もちろん、経験と学習、努力によって資質や素質を磨かなければ光らない。
■印象に残る演技■
映画作品の実例で考えてみよう。
たとえば、《レインマン》のダスティン・ホフマン。小ブログ記事〈遺産と兄弟の絆と〉参照。
「自閉症」のレイモンド(チャーリーの兄)の行動パターン、さらにはその精神状態もみごとに演じ切っている。外界からの情報や影響をできるだけ拒否し、自分が馴染んでいる世界だけにとどまろうとするレイモンドの精神的傾向が如実にわかる。
次に《レナードの朝》のロバート・デニーロ。小ブログ記事〈30年後の目覚め、そして…〉参照。
ロバート・デニーロの迫真に迫る演技とか人物造型の巧みさは、世界の映画界でもすこぶるつきの定評がある。ほかにも《ゴッドファーザー2》、《ディアハンター》と数えればきりがない。
このブログで取り上げた作品に登場する名優たちもすごい。アル・パチーノ、ジュリア・ロバーツ、ロビン・ウィリアムズ…。
日本でも三国連太郎や志村喬、緒方拳、北林谷江…。名優をあげれば、これまたきりがない。
これらの名優の演技のすごさは、どこにあるのか。
役づくり=人物造型はもちろん。存在感と表現力、人物になり切る迫力。
私たち観客から見ると、「うん、そうだろうな。こういう人物ならば、こう動くだろう、こう言うだろう。なるほど!」と感動する。というよりも、劇=物語のなかに引きずり込まれてしまう。
つまりは、人物の性格や心性、生い立ちや経験からして必然的に見える言動を演じる技量・存在感である。
しかし、それぞれの登場場面で、役者たちは「今、これこれの性格、これこれの心理の人物を演じています」などとは解説してくれない。解説するわけにもいかない。だから、観客がそのように受け取ってくれるように演じて説得するしかない。つまり、彼らは説得的に演じているわけだ。演技そのものによって、この人物はこういう性格だ、こういう経験を積んできた、と説得しなければならない。
もちろん、映画では、そういうすぐれた演技の背景には、演技や存在感を補い強調するような場面設定や人物配置、効果音などの「道具立て」が用意されている。時代考証や背景設定でのリアリティがとことん追求されている。
言い換えれば、舞台演劇と違って、映画演劇では、場面・背景のリアリティの度合いが高いので、それだけ俳優の演技や雰囲気が場面や背景状況に合致しなければならない。違和感を醸すほどに、浮き上がってもいけないわけだ。
もちろん、喜劇タッチで浮き上がるほどに誇張された演技が求められる場合もある。しかし、物語の展開を壊したり阻止してしまうようではいけない。
こうして、物語の展開・場面設定や演技力は、観客の想像力や観察力を刺激するわけだ。その刺激を受けて観客は引きつけられ感情移入しながら、物語の動きと登場人物演技=言動を注意深く観察し、感じ、分析し関連づけ(総合)をおこなわなければならない。
この分析と総合は、物語の展開方向や背景、状況設定などに俳優たちの演技がどれほど合致、適合しているかを吟味し、評価することでもある。
■人物造型を「それらしく」見せる演技術■
「演技が真に迫っている」と感じるということは、「そういう性格・来歴・心理の人物であればいかにもそういう言動をするだろう」と、私たちが納得(同意)するということだ。言い換えれば、物語全体をつうじてある人物のあれこれの言動は、一定のキャラクター・ペルソナ(人物像)を描き上げるための個々の部品なのである。それらの部品は、(矛盾や不合理に満ちた人格を描くとしても)ある首尾一貫した流れ=傾向性のなかに位置づけられていなければならない。
つまり、人物についてのイメイジと演技(の持続・累積)とは、「必然的」な連関を持たなければならない。
その人物の性格や心理にとって不整合な言動が少しでもあれば、私たちは、やはり違和感を感じたり、イメイジした人物像に揺らぎが生じてしまう。「あれはおかしい」と。
つまりは、物語のなかで、人物のアイデンティティ(自己同一性)が保たれていなければならない。
もとより、そのような性格・心性の人物が、あの場面では、なぜそのような言動をしたのか、と観客に考えさせるような問題提起をあえておこなうようなこともあっていい。
そうなると、脚本には一般的に書かれているのだが、映画の制作陣が設定した人物像にきっちり整合・適合するように、役者たちはしかるべく演技(言動所作だけでなく、雰囲気やかすかな表情や雰囲気の表現を)しなければならない。
人物の心理や心性・性格に応じて、いかにも内発的で自然な言動となるように演技すべきだという方法論として、〈スタニスラフスキー・システム〉というものがある。
1930年代にロシアの演劇人(俳優・脚本家・演出家)、コンスタンティン・セルゲーイヴィッチ・スタニスラフスキーによって提唱された演技方法論が基本となって、1960年代のハリウッドで演技方法論(methodical-acting-theory)として精緻化された考え方である。
人物像(心理や性格、生い立ち・家庭環境、経験)にとって自然で必然的な演技を、あらゆる場面で首尾一貫して、系統的におこなう、すなわち人物設定のリアリティを根拠づける演技、立ち振る舞い、所作を考え出し、実践する方法論である。
演技技術を高めるためには訓練・練習が必要だ。けれども、同じせりふや動作、それに込める感情などを何度も反復練習すると、どうしても技巧的な匂いが染みつく(つくりものめいてくる)。誇張や単純化も生じるかもしれない。
だが、練習や訓練なしに演技すると、ぎこちなかったり、表現不足になる。
してみると、何度も訓練したうえで、しかも新鮮ではじめておこなったような演技に見せなければならない。
そのためには、動作やせりふの訓練よりも、役者が、その場面・状況で、その人物の心理や心情になり切るしかない。つまり、芝居の稽古そのものよりも、心理分析や精神分析、性格洞察がより重要になってくる。というよりも、演技の稽古は、そのような心理分析、性格洞察の基礎の上に立って組み立てられなければならない。
してみれば、人物の心の動きや性格・心性の場面や状況に応じた変化・対応のありようを研究・考察する必要が高まる。
俳優は、台本・脚本を読みながら、自分が演じる人物の来歴や経験、心理や性格・心性を深く洞察し、せりふや行動の奥にある人物の心情・心理をつかみ、そこからくる行動パターンや反応スタイルを読み解かなければならない。
つまりは、演技のマインドコントロールをするわけだ。演技の制御は精神のありようの統制とイコールという関係にするわけだ。
3 人物造型と演技
結局のところ、すぐれた役者は観察力や洞察力、想像力に富んでいるということになるだろう。そしてすぐれた心理分析者ということになる。もちろん、演技によって外形(言動、姿形、表情など)に表現するために、その限りにおいてだが。
演技というのは、登場人物の役割を演じるということだ。ある個性=パースナリティを持つ人物が、ある状況(場面・人間関係)のもとで、どんな意識・感情を抱き、どんな言動をするかを演じ分けるということだ。つまり、見る者に、人物の性格や心理を理解させ、想像させるために最も効果的な動きや言い方、表情などの表現方法を取ることができるということだ。
主な筋書きや人びとの動き、せりふは脚本=台本に書かれている。しかし、それは、場面ごとの演技によって具体化されければならない。
役者は、脚本を読み込み、登場人物の性格や生い立ち、心情などを分析し、把握し、世の中や人間の観察から得た表現を考え、こういう人物なら、こういう場面ではこう動き、こういう言い方をし、こういう表情をするだろう・・・と 演技の肉付けをおこなう。
ところが、撮影の場面で、具体的な背景、備品や人物配置のなかで動いてみると、脚本では描き切れていない独特の雰囲気(緊張や緊迫感、あるいはのどかさ、穏やかさ)が醸し出される。となると、同じせりふにしても、言い方や抑揚の付け方、テンポは少し違ってくる。動き方にしてもそうだ。
同じ人物にしても、状況ごとに心理や心情は変わってくる。
そこに、脚本から相対的に独立した演技者ごとの解釈や評価が入り込む余地が、少なからず生まれてくる。またそこに、演出家やディレクターたちの腕の振るいどころがあるのだろう。
さらにまた、場面・シークェンスの持続や流れのなかで生じる累積効果というものもあるだろう。たとえば、いくつもの場面での人物の言動や表情、雰囲気などの積み重ねによって、その人物の性格、場合によっては生い立ちや家庭環境さえも描き出すことになる。
そういうものは、物語の奥行きや広がりをもたらすものだ。
物語が、薄っぺらで平板なものに終わるか、深い奥行きやどっしりとした厚みを持つかどうか、そこで決まることもあるだろう。観客が集中して、緊張感を持続させて観るかどうかは、そこにかかっているかもしれない。というよりも、どれほど巧みなプロットでも、登場人物たちがステレオタイプで人生の経験・厚みを感じさせなければ、観る側が受けるインパクトは大きく異なるだろう。
4 物語性と人物(意思・思惑)のぶつかり合い
近代文学や演劇では、人は特定化されうる意思や意識の担い手として描かれる。したがって、人びとの絡み合い、ぶつかり合いは、意思や意識の絡み合い、ぶつかり合いとなる。してみると、物語の構造と展開もまた、人びとの意識や意思(がめざすもの、目的意識)の絡み合い、ぶつかり合いによって事件が繰り広げられていく過程として描かれる。
言い換えると、人物ごとの部分物語が絡み合い、ぶつかり合いながら、大構造の物語(大河)を織りなしていくことになる。
私が大好きな映画作品を例にとって、物語の展開、人物(意思や意識の担い手)配置、絡み合い・ぶつかり合いを考察してみよう。
作品は、日本映画で、岡本喜八監督の《大誘拐》。小ブログ〈おばあちゃんの国家論〉参照。
物語の起承転結を大雑把に示しておくと、
ケチな犯罪で刑務所を出たばかりの若者3人が、人生の再設計のために、紀州一番の大富豪のおばあちゃんを誘拐して、身代金を奪おうと企てた。で、いざ誘拐してみると、人生の経験の深さ、人間のスケイルが桁違いのおばあちゃんによって誘拐計画を乗っ取られてしまう。身代金は何と100億円(当初は5000万円の計画)となり、和歌山県警全体を敵に回しての知恵比べになってしまった。
人生が残りわずかと覚悟したおばあちゃんが、国を相手にひと泡吹かせる大冒険となった。
誘拐団は、おばあちゃんの見事な采配で、警察やマスメディアを出し抜き、100億円を手に入れた。この冒険のなかで、若者たちは、おばあちゃんの姿から人生への取り組みの姿勢、覚悟の深さや潔さを学んでいく。
というようなストーリーだ。ファンタジックな喜劇である。
主要人物=意思・意識の絡み合い・ぶつかり合いの構図を見ておこう。
①もともとの誘拐団の3人の若者:
服役後の社会復帰のために「まとまった金」を手に入れようと、大富豪のおばあちゃんの拉致を企む。だが、誘拐計画の精神は「フェアプレイ」である。3人のうち、首謀者の青年は、誘拐の相手であるおばちゃんを尊敬している。がゆえに、誘拐対象に選んだのだ。
②おばあちゃん:
自分がガンになって余命いくばくもないと勘違いし、紀州の広大な山林資産が相続税としてあらかた国に持っていかれることに憤った。というのも、国はかつては太平洋戦争で愛する息子2人と娘1人の命を取り上げた。国から奪われるだけの人生で終わっていいのか、と反骨心を奮い起こした。
で、誘拐を機に、頼りない跡継ぎたちの性根を鍛え直し、お国にひと泡吹かせてやろう、と企んだ。巨額の身代金の調達にさいして、課税をめぐる「国のお目こぼし分」を最大限利用してやろうというのだ。
③和歌山県警本部長の井狩大介:
おばあちゃんを人生の大恩人と敬愛してやまない。その大恩人を誘拐した犯人たちをとことん追い詰め捕縛してやろうと意気込む。腹の据わった、洞察力と行動力では飛び抜けた人物。
ところが、誘拐事件を捜査していくうちに、誘拐から身代金の受け取りまでの計画に「悪賢い犯罪者」ではなく「王者の風格」の匂いを嗅ぎつけた。
事件は警察側の敗北で終わった。身代金は奪われ、おばあちゃんは約束通り無事に帰された。が、警察は容疑者の特定すらできなかった。
けれども、事件後しばらくしてから、井狩大介は、誘拐計画を途中から乗っ取って、空前のスケイルの大戦略を繰り広げたのは、おばあちゃんではないかと気がついた。
こうして、この物語では、3つの大きな目論見・願望・意図が出会い、ぶつかり合い、絡み合う。三者の周囲に配置された人物たちは、いずれも個性豊かな面々で、物語の展開に広がりと奥行き、彩りを添える。
普通のまじめな青年たちは、厳しい少年時代の環境のなかでケチな犯罪をおこして刑務所に入ってしまった。そして、誘拐計画も、あくまで律儀でまじめである。誰をも傷つけず、約束は必ず守る。
いや、主要な登場人物たちは、すべて律儀で正直でまじめで好感のもてる人びとだ。
大富豪の跡取り娘として生い立ち、修羅場もくぐり抜け、大がかりな資産の運営・経営を成功裏に切り回してきた、おばあちゃんの風格と人生が、抑制されながらも、みごとに表現されている。
そして、事件では、おばあちゃん・若者グループと対決する警察本部長、腹の据わり具合や読みの深さ、組織統率の妙技、部下あしらいのうまさなどが、にじみ出てくる。
さて、意図や思惑のぶつかり合いの構図は、上に見たとおり、じつに鮮やかである。
で、喜劇タッチであるからということで、俳優たちの演技は大雑把かというと、さにあらず、じつに細部まで統制・整序されている。もちろん、人物配置と対峙の構図が明確になるように、人物像はそれぞれ際立ったパターンに造形化されている。
だが、奥行きや膨らみのある人間像をつくり出している。
見る側には、ものすごく説得力がある人物たちの出会いと絡み合い、ぶつかり合いである。
たとえば、山のなかでお付きの女の子(喜美子)とともに誘拐団によって拉致されようとするときに、おばあちゃんは、喜美子には手を出さないようにと説得し、合意すると誘拐団との「手打ちの式」(三三七拍子)を取り仕切る。
腹の据わりかげんと人間としてのスケイル・包容力を見せつけるシーンだ。この「手打ちの式」を切り出すタイミングと表情、せりふの言い回し方、北林谷江の演技は圧巻である。
そして、その「手打ち」の提案にうまく乗せられてしまう誘拐団の人の良さとまじめさも、また巧妙に演じられている。
そして、誘拐団からの身代金要求の手紙(100億円を要求)の提案にしたがって、和歌山テレヴィの番組で誘拐団に逆に「挑戦状」を叩き付け返す井狩の、誠実だが豪胆な態度、迫力。緒方拳の演技は見ものだ。
このほか、
おばあちゃんの脛をかじるだけかじってきたボンボンの役を、独特の気品と斜に構えたインテリ風貌、粋さかげんを備えた岸部一徳が、これまた見事に演じる。
おばあちゃんをひたすら信じ尊敬するクーちゃんを演じる樹希木林の存在感がすごい。
喜劇なので、人物像はいささか誇張気味に描かれている。登場する役者たちは、誰もが見事にツボを押さえている。しかも、誇張と自己抑制のバランスが絶妙である。
やはり、日本人の演劇人は、映画では、欧米流のリアリズムよりも、いやそれに比べて、喜劇タッチの軽妙な演技に長じているのだろうか。
ここで扱うのは、映画作品のための物語(story or drama)と演技(role-playing)である。そして、物語が登場人物たちの言動とかかわり合いをつうじて織りなされ表現れる限り、演技は物語性の不可欠の、ほとんど本質的ともいえる要素となるだろう。舞台演劇の演技は、歴史的かつ構造的に見て映画(のための演劇)の基礎にあるものだが、ここでは直接には扱わない。
1 映像物語とは何か
映像物語としての映画作品を考えるためには、物語それ自体が何かを語らなければならないかもしれない。
では、物語とは何か。
人びとの言動によって織りなされる出来事、因果関係や起承転結という流れや組み立てのあるエピソード(の集合)である。
物語は、戯曲=演劇によっても、小説によっても、オペラや楽劇によっても、表現される。文字としての言葉、音声としての言葉によって人の行動や姿が語られ、事件の意味や人物の心理が描かれる(暗示される)。したがって、必ず(少なくとも背景には)文脈がある。因果関係や起承転結、すなわち言動や場面を結びつけ、一連の流れに連結する連関がある。
では、物語は、何をめざしているのか、物語が求めるものは何か。
人びとの共感や感情移入を呼び起こし、登場人物の心理や性格について考えさせ、人生や社会(世の中)についてな何がしかのイメイジを抱かせるため。説得のため。あるいは扇動のため、つまりプロパガンダのため。要するに、作品としてすぐれているものには、必ず一定の価値観や人生観、世界観などが込められていることになる。
そのための形としては、喜劇、滑稽劇、悲劇などであり、人びとの心に安心感や愉快な気分、笑い、あるいは恐怖、驚愕を呼び起こすことになる。
そうすると、映画=映像物語とは、どういうものか。
物語=劇を映像にして編集構成することによって、以上のような目的を追求するためだ。そして、映画がすぐれて現代的な社会現象であり、現代資本主義的文明の所産であってみれば、所詮、経営体による利潤獲得の手段、1つの形態として営まれているということになる。
とはいえ、資本主義的経営の1つの形態=手段であるという次元の問題は、ここではひとまず脇に置いておく。映像劇=映画に内在的なことがらだけを扱うことにする。
映像物語にしても舞台演劇にしても、小説にしても、物語が説得性や訴求性をもつためには、リアリティや存在感など、感情移入(嫌悪や拒否感などネガティヴな感情移入も含む)を呼び起こす道具立てが必要になる。あるいは、興味や好奇心を呼び起こす、人びとの想像力を刺激するといってもいいかもしれない。
人びとが目の前で展開している出来事に引きつけられなければならない。
その出来事が人びとの言動(の絡み合い・相互作用。もちろん独り劇もあるが)から構成されるとすれば、人びとを引きつけるのは、登場人物の言動であり、つまりは役者の演技のリアリティや存在感、訴求力・説得力が求められることになる。
物語がどれほど奇想天外でありそうもないような事件を描こうとも、シーンやシークェンスに人びとを引きつけなければならない。そのさいに、人物の存在感は決定的な重要性を持つだろう。
2 演技とは何か
演技(role-playing)とは何か。ロールプレイングという言葉からわかるように、登場人物の役割を演じることである。一定の状況下での登場人物たちの役割=言動が物語の展開を推し進め、織り上げていく。
以前に考察したように、映画作品では場面の装置や備品・道具、背景設定がリアリティや存在感を与えるために重要になるが、そういうものを背景にした人物たちの言動に魅力がなければ、興ざめである。
観客の感情移入を誘導する〈driving forces〉(観客を引きつけながら物語を駆動していく力)のなかでも決定的に重要な要素こそ、演技なのである。
ロールプレイングは、人物の存在感を表現する手段なのである。顔の表情や眼差し、声音や話し方、身ぶり手ぶり、もちろん俳優がもって生まれた雰囲気や性格というものもあろう。もちろん、経験と学習、努力によって資質や素質を磨かなければ光らない。
■印象に残る演技■
映画作品の実例で考えてみよう。
たとえば、《レインマン》のダスティン・ホフマン。小ブログ記事〈遺産と兄弟の絆と〉参照。
「自閉症」のレイモンド(チャーリーの兄)の行動パターン、さらにはその精神状態もみごとに演じ切っている。外界からの情報や影響をできるだけ拒否し、自分が馴染んでいる世界だけにとどまろうとするレイモンドの精神的傾向が如実にわかる。
次に《レナードの朝》のロバート・デニーロ。小ブログ記事〈30年後の目覚め、そして…〉参照。
ロバート・デニーロの迫真に迫る演技とか人物造型の巧みさは、世界の映画界でもすこぶるつきの定評がある。ほかにも《ゴッドファーザー2》、《ディアハンター》と数えればきりがない。
このブログで取り上げた作品に登場する名優たちもすごい。アル・パチーノ、ジュリア・ロバーツ、ロビン・ウィリアムズ…。
日本でも三国連太郎や志村喬、緒方拳、北林谷江…。名優をあげれば、これまたきりがない。
これらの名優の演技のすごさは、どこにあるのか。
役づくり=人物造型はもちろん。存在感と表現力、人物になり切る迫力。
私たち観客から見ると、「うん、そうだろうな。こういう人物ならば、こう動くだろう、こう言うだろう。なるほど!」と感動する。というよりも、劇=物語のなかに引きずり込まれてしまう。
つまりは、人物の性格や心性、生い立ちや経験からして必然的に見える言動を演じる技量・存在感である。
しかし、それぞれの登場場面で、役者たちは「今、これこれの性格、これこれの心理の人物を演じています」などとは解説してくれない。解説するわけにもいかない。だから、観客がそのように受け取ってくれるように演じて説得するしかない。つまり、彼らは説得的に演じているわけだ。演技そのものによって、この人物はこういう性格だ、こういう経験を積んできた、と説得しなければならない。
もちろん、映画では、そういうすぐれた演技の背景には、演技や存在感を補い強調するような場面設定や人物配置、効果音などの「道具立て」が用意されている。時代考証や背景設定でのリアリティがとことん追求されている。
言い換えれば、舞台演劇と違って、映画演劇では、場面・背景のリアリティの度合いが高いので、それだけ俳優の演技や雰囲気が場面や背景状況に合致しなければならない。違和感を醸すほどに、浮き上がってもいけないわけだ。
もちろん、喜劇タッチで浮き上がるほどに誇張された演技が求められる場合もある。しかし、物語の展開を壊したり阻止してしまうようではいけない。
こうして、物語の展開・場面設定や演技力は、観客の想像力や観察力を刺激するわけだ。その刺激を受けて観客は引きつけられ感情移入しながら、物語の動きと登場人物演技=言動を注意深く観察し、感じ、分析し関連づけ(総合)をおこなわなければならない。
この分析と総合は、物語の展開方向や背景、状況設定などに俳優たちの演技がどれほど合致、適合しているかを吟味し、評価することでもある。
■人物造型を「それらしく」見せる演技術■
「演技が真に迫っている」と感じるということは、「そういう性格・来歴・心理の人物であればいかにもそういう言動をするだろう」と、私たちが納得(同意)するということだ。言い換えれば、物語全体をつうじてある人物のあれこれの言動は、一定のキャラクター・ペルソナ(人物像)を描き上げるための個々の部品なのである。それらの部品は、(矛盾や不合理に満ちた人格を描くとしても)ある首尾一貫した流れ=傾向性のなかに位置づけられていなければならない。
つまり、人物についてのイメイジと演技(の持続・累積)とは、「必然的」な連関を持たなければならない。
その人物の性格や心理にとって不整合な言動が少しでもあれば、私たちは、やはり違和感を感じたり、イメイジした人物像に揺らぎが生じてしまう。「あれはおかしい」と。
つまりは、物語のなかで、人物のアイデンティティ(自己同一性)が保たれていなければならない。
もとより、そのような性格・心性の人物が、あの場面では、なぜそのような言動をしたのか、と観客に考えさせるような問題提起をあえておこなうようなこともあっていい。
そうなると、脚本には一般的に書かれているのだが、映画の制作陣が設定した人物像にきっちり整合・適合するように、役者たちはしかるべく演技(言動所作だけでなく、雰囲気やかすかな表情や雰囲気の表現を)しなければならない。
人物の心理や心性・性格に応じて、いかにも内発的で自然な言動となるように演技すべきだという方法論として、〈スタニスラフスキー・システム〉というものがある。
1930年代にロシアの演劇人(俳優・脚本家・演出家)、コンスタンティン・セルゲーイヴィッチ・スタニスラフスキーによって提唱された演技方法論が基本となって、1960年代のハリウッドで演技方法論(methodical-acting-theory)として精緻化された考え方である。
人物像(心理や性格、生い立ち・家庭環境、経験)にとって自然で必然的な演技を、あらゆる場面で首尾一貫して、系統的におこなう、すなわち人物設定のリアリティを根拠づける演技、立ち振る舞い、所作を考え出し、実践する方法論である。
演技技術を高めるためには訓練・練習が必要だ。けれども、同じせりふや動作、それに込める感情などを何度も反復練習すると、どうしても技巧的な匂いが染みつく(つくりものめいてくる)。誇張や単純化も生じるかもしれない。
だが、練習や訓練なしに演技すると、ぎこちなかったり、表現不足になる。
してみると、何度も訓練したうえで、しかも新鮮ではじめておこなったような演技に見せなければならない。
そのためには、動作やせりふの訓練よりも、役者が、その場面・状況で、その人物の心理や心情になり切るしかない。つまり、芝居の稽古そのものよりも、心理分析や精神分析、性格洞察がより重要になってくる。というよりも、演技の稽古は、そのような心理分析、性格洞察の基礎の上に立って組み立てられなければならない。
してみれば、人物の心の動きや性格・心性の場面や状況に応じた変化・対応のありようを研究・考察する必要が高まる。
俳優は、台本・脚本を読みながら、自分が演じる人物の来歴や経験、心理や性格・心性を深く洞察し、せりふや行動の奥にある人物の心情・心理をつかみ、そこからくる行動パターンや反応スタイルを読み解かなければならない。
つまりは、演技のマインドコントロールをするわけだ。演技の制御は精神のありようの統制とイコールという関係にするわけだ。
3 人物造型と演技
結局のところ、すぐれた役者は観察力や洞察力、想像力に富んでいるということになるだろう。そしてすぐれた心理分析者ということになる。もちろん、演技によって外形(言動、姿形、表情など)に表現するために、その限りにおいてだが。
演技というのは、登場人物の役割を演じるということだ。ある個性=パースナリティを持つ人物が、ある状況(場面・人間関係)のもとで、どんな意識・感情を抱き、どんな言動をするかを演じ分けるということだ。つまり、見る者に、人物の性格や心理を理解させ、想像させるために最も効果的な動きや言い方、表情などの表現方法を取ることができるということだ。
主な筋書きや人びとの動き、せりふは脚本=台本に書かれている。しかし、それは、場面ごとの演技によって具体化されければならない。
役者は、脚本を読み込み、登場人物の性格や生い立ち、心情などを分析し、把握し、世の中や人間の観察から得た表現を考え、こういう人物なら、こういう場面ではこう動き、こういう言い方をし、こういう表情をするだろう・・・と 演技の肉付けをおこなう。
ところが、撮影の場面で、具体的な背景、備品や人物配置のなかで動いてみると、脚本では描き切れていない独特の雰囲気(緊張や緊迫感、あるいはのどかさ、穏やかさ)が醸し出される。となると、同じせりふにしても、言い方や抑揚の付け方、テンポは少し違ってくる。動き方にしてもそうだ。
同じ人物にしても、状況ごとに心理や心情は変わってくる。
そこに、脚本から相対的に独立した演技者ごとの解釈や評価が入り込む余地が、少なからず生まれてくる。またそこに、演出家やディレクターたちの腕の振るいどころがあるのだろう。
さらにまた、場面・シークェンスの持続や流れのなかで生じる累積効果というものもあるだろう。たとえば、いくつもの場面での人物の言動や表情、雰囲気などの積み重ねによって、その人物の性格、場合によっては生い立ちや家庭環境さえも描き出すことになる。
そういうものは、物語の奥行きや広がりをもたらすものだ。
物語が、薄っぺらで平板なものに終わるか、深い奥行きやどっしりとした厚みを持つかどうか、そこで決まることもあるだろう。観客が集中して、緊張感を持続させて観るかどうかは、そこにかかっているかもしれない。というよりも、どれほど巧みなプロットでも、登場人物たちがステレオタイプで人生の経験・厚みを感じさせなければ、観る側が受けるインパクトは大きく異なるだろう。
4 物語性と人物(意思・思惑)のぶつかり合い
近代文学や演劇では、人は特定化されうる意思や意識の担い手として描かれる。したがって、人びとの絡み合い、ぶつかり合いは、意思や意識の絡み合い、ぶつかり合いとなる。してみると、物語の構造と展開もまた、人びとの意識や意思(がめざすもの、目的意識)の絡み合い、ぶつかり合いによって事件が繰り広げられていく過程として描かれる。
言い換えると、人物ごとの部分物語が絡み合い、ぶつかり合いながら、大構造の物語(大河)を織りなしていくことになる。
私が大好きな映画作品を例にとって、物語の展開、人物(意思や意識の担い手)配置、絡み合い・ぶつかり合いを考察してみよう。
作品は、日本映画で、岡本喜八監督の《大誘拐》。小ブログ〈おばあちゃんの国家論〉参照。
物語の起承転結を大雑把に示しておくと、
ケチな犯罪で刑務所を出たばかりの若者3人が、人生の再設計のために、紀州一番の大富豪のおばあちゃんを誘拐して、身代金を奪おうと企てた。で、いざ誘拐してみると、人生の経験の深さ、人間のスケイルが桁違いのおばあちゃんによって誘拐計画を乗っ取られてしまう。身代金は何と100億円(当初は5000万円の計画)となり、和歌山県警全体を敵に回しての知恵比べになってしまった。
人生が残りわずかと覚悟したおばあちゃんが、国を相手にひと泡吹かせる大冒険となった。
誘拐団は、おばあちゃんの見事な采配で、警察やマスメディアを出し抜き、100億円を手に入れた。この冒険のなかで、若者たちは、おばあちゃんの姿から人生への取り組みの姿勢、覚悟の深さや潔さを学んでいく。
というようなストーリーだ。ファンタジックな喜劇である。
主要人物=意思・意識の絡み合い・ぶつかり合いの構図を見ておこう。
①もともとの誘拐団の3人の若者:
服役後の社会復帰のために「まとまった金」を手に入れようと、大富豪のおばあちゃんの拉致を企む。だが、誘拐計画の精神は「フェアプレイ」である。3人のうち、首謀者の青年は、誘拐の相手であるおばちゃんを尊敬している。がゆえに、誘拐対象に選んだのだ。
②おばあちゃん:
自分がガンになって余命いくばくもないと勘違いし、紀州の広大な山林資産が相続税としてあらかた国に持っていかれることに憤った。というのも、国はかつては太平洋戦争で愛する息子2人と娘1人の命を取り上げた。国から奪われるだけの人生で終わっていいのか、と反骨心を奮い起こした。
で、誘拐を機に、頼りない跡継ぎたちの性根を鍛え直し、お国にひと泡吹かせてやろう、と企んだ。巨額の身代金の調達にさいして、課税をめぐる「国のお目こぼし分」を最大限利用してやろうというのだ。
③和歌山県警本部長の井狩大介:
おばあちゃんを人生の大恩人と敬愛してやまない。その大恩人を誘拐した犯人たちをとことん追い詰め捕縛してやろうと意気込む。腹の据わった、洞察力と行動力では飛び抜けた人物。
ところが、誘拐事件を捜査していくうちに、誘拐から身代金の受け取りまでの計画に「悪賢い犯罪者」ではなく「王者の風格」の匂いを嗅ぎつけた。
事件は警察側の敗北で終わった。身代金は奪われ、おばあちゃんは約束通り無事に帰された。が、警察は容疑者の特定すらできなかった。
けれども、事件後しばらくしてから、井狩大介は、誘拐計画を途中から乗っ取って、空前のスケイルの大戦略を繰り広げたのは、おばあちゃんではないかと気がついた。
こうして、この物語では、3つの大きな目論見・願望・意図が出会い、ぶつかり合い、絡み合う。三者の周囲に配置された人物たちは、いずれも個性豊かな面々で、物語の展開に広がりと奥行き、彩りを添える。
普通のまじめな青年たちは、厳しい少年時代の環境のなかでケチな犯罪をおこして刑務所に入ってしまった。そして、誘拐計画も、あくまで律儀でまじめである。誰をも傷つけず、約束は必ず守る。
いや、主要な登場人物たちは、すべて律儀で正直でまじめで好感のもてる人びとだ。
大富豪の跡取り娘として生い立ち、修羅場もくぐり抜け、大がかりな資産の運営・経営を成功裏に切り回してきた、おばあちゃんの風格と人生が、抑制されながらも、みごとに表現されている。
そして、事件では、おばあちゃん・若者グループと対決する警察本部長、腹の据わり具合や読みの深さ、組織統率の妙技、部下あしらいのうまさなどが、にじみ出てくる。
さて、意図や思惑のぶつかり合いの構図は、上に見たとおり、じつに鮮やかである。
で、喜劇タッチであるからということで、俳優たちの演技は大雑把かというと、さにあらず、じつに細部まで統制・整序されている。もちろん、人物配置と対峙の構図が明確になるように、人物像はそれぞれ際立ったパターンに造形化されている。
だが、奥行きや膨らみのある人間像をつくり出している。
見る側には、ものすごく説得力がある人物たちの出会いと絡み合い、ぶつかり合いである。
たとえば、山のなかでお付きの女の子(喜美子)とともに誘拐団によって拉致されようとするときに、おばあちゃんは、喜美子には手を出さないようにと説得し、合意すると誘拐団との「手打ちの式」(三三七拍子)を取り仕切る。
腹の据わりかげんと人間としてのスケイル・包容力を見せつけるシーンだ。この「手打ちの式」を切り出すタイミングと表情、せりふの言い回し方、北林谷江の演技は圧巻である。
そして、その「手打ち」の提案にうまく乗せられてしまう誘拐団の人の良さとまじめさも、また巧妙に演じられている。
そして、誘拐団からの身代金要求の手紙(100億円を要求)の提案にしたがって、和歌山テレヴィの番組で誘拐団に逆に「挑戦状」を叩き付け返す井狩の、誠実だが豪胆な態度、迫力。緒方拳の演技は見ものだ。
このほか、
おばあちゃんの脛をかじるだけかじってきたボンボンの役を、独特の気品と斜に構えたインテリ風貌、粋さかげんを備えた岸部一徳が、これまた見事に演じる。
おばあちゃんをひたすら信じ尊敬するクーちゃんを演じる樹希木林の存在感がすごい。
喜劇なので、人物像はいささか誇張気味に描かれている。登場する役者たちは、誰もが見事にツボを押さえている。しかも、誇張と自己抑制のバランスが絶妙である。
やはり、日本人の演劇人は、映画では、欧米流のリアリズムよりも、いやそれに比べて、喜劇タッチの軽妙な演技に長じているのだろうか。