2014/05/20
「この御代に一族の者遣わせて服従せぬを討ちにいかせり
(1 大毘古の命[孝元天皇の第一皇子]:高志の道
,2 建沼河別の命[大毘古の命の第一皇子]:東の方面の十二道[伊勢、尾張、参河、遠江、駿河、甲斐、伊豆、相模、武蔵、総[上総、下総、安房]、常陸、陸奥]
,3 日子坐の王ミコ:旦波タニハの国の玖賀耳の御笠を征伐
)」
「大毘古が高志にいく道幣羅坂で歌をよみたる少女がいたり(幣羅坂で腰裳をつけた少女ヲトメ:京都府相楽郡木津町)」
「
御真木入彦はや
御真木入彦はや
おのが命を 盗ヌスみ殺シせむと
後シリつ戸よ い行き違ひ
前マヘつ戸よ い行き違ひ
窺ウカガはく 知らにと
御真木入彦はや
(歌謡#23)」
「天皇よ御真木入彦汝が命狙い殺さん動きがありし(歌謡#23の意訳)」
「大毘古は奇妙に思い馬返し少女に理由聞けば知らぬと(意味はわからずただ歌を詠みしと)」
「大毘古は都に戻り報せれば建波邇安が叛く徴シルシと(天皇にとって大毘古は伯父さんで、建波邇安は大毘古の腹違いの兄[庶兄ママセ])」
「軍率い日子国夫玖ヒコクニブクをつけて遣り山代の国へ向かわせました(和邇の祖で日子国夫玖ヒコクニブクは和邇坂に忌瓮イワイベを埋め山代にいく)」
「山代の和訶羅河ワカラガワにて伯父の軍待ち構えては互いに挑む(木津川を挑み[伊杼美]と言うはこのときの逸話が元も今は伊豆美に)」
「忌矢イワイヤを互いに打てば日子国夫玖の矢が射殺せる建波邇安を()」
「これにより建波邇安の軍ども破れて散りぬ久須婆の渡りに(兵ツワモノが追い詰められて糞漏らし袴にかかり糞袴といふ[久須婆=楠葉の語源])」
「逃げたるを斬れば鵜のごと死体浮きその河名付け鵜河といふ(兵を斬った死体を放りたるその地名付けて波布理曾能[京都府精華町祝園]といふ)」
「大毘古は日子国夫玖と天皇に復命をして高志に向かえり()」
「この時に子の建沼河別と大毘古は福島の地で往き遇いたると(お互いに遇える地名付け『相津』といふ高志にいくのに会津は途中?)」
「この御代に天下平らぎ人民オホミタカラは調ミツギを貢タテマツらしむ
(1 男は弓端の調:獣皮等の類
,2 女は手末の調:織物や糸類
)」
「かくのごと御世は栄えて初国を知らしし御真木の天皇といふ
()」
「この御代に灌漑用の池作り農業の糧を増やせり
(1 依り網の池:大阪市堺市池内辺り
,2 軽の酒折の池:橿原市大軽町辺り
)」
「天皇は168歳で亡くなって御陵は勾マガの岡の上にあり(山野辺の道の勾岡)」
「崩年が戊ツチノエの寅の十二月シワスらし古事記で干支始めてつける(戊寅は西暦258年と思われる。±60nの誤差はあるが)」
最新の画像[もっと見る]










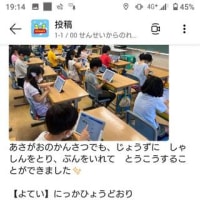
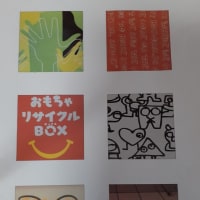








※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます