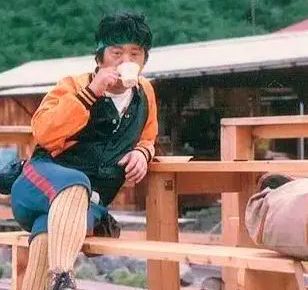昨日は、琵琶湖博物館の「魚の寄生虫を調べよう」講座でした。
10時から4時半まで、お昼の休憩時間を除いて、きっちりと勉強してきました。
琵琶湖博物館のグライガー先生と滋賀県立大の浦部先生が、親切に教えて下さったんですが、生徒は二人だけで、なんとも残念に思いました。
午前中はパワーポイントとビデオを使った授業、サンプル標本の観察で、午後からは実際に自分で魚を解剖して、ひれ、えら、内臓から寄生虫をみつけだす作業でした。
私は小さい魚を2尾解剖したのですが、寄生虫をみつけることができませんでした。
私が解剖した魚の内臓を調べられた浦部先生は、数匹の寄生虫をみつけられました。(さすがです。)
生きている寄生虫を顕微鏡で見ると、「こいつらもけっこう頑張っとる」と思えて、なんか可愛くなってしまいましたよ。いや、参りました。
上の写真は、浦部先生が「こうして解剖するんですよ」と教えて下さってるところです。
(写真は、事務局の女性が写して下さいました。)

グライガー先生が、資料(寄生虫の拡大写真)の説明をされています。
私は、神妙に聞いております。

二人の生徒が、プレパラート標本を観察しているところです。

魚を解剖して、ひれ、えら、内臓などを顕微鏡で見て、寄生虫を探しているところです。
(私は、みつけることができませんでした。)

こんなに熱心に勉強したのは久しぶりですよ。

浦部先生が解剖された15センチぐらいのハスの内臓からは、50匹を越える数の寄生虫がみつかりました。いやー、これにはびっくりしましたねー。
私は、仕事柄、魚に寄生虫がいるのは当たり前と思っておりますから、まあ、こういう作業をしてもなんともないですけど、なれてない人なら、当分の間、お魚は食べられないでしょうね。
でも、これが事実ですから、きちんとした知識を持って対処することが大事だと、あらためて思いました。
10時から4時半まで、お昼の休憩時間を除いて、きっちりと勉強してきました。
琵琶湖博物館のグライガー先生と滋賀県立大の浦部先生が、親切に教えて下さったんですが、生徒は二人だけで、なんとも残念に思いました。
午前中はパワーポイントとビデオを使った授業、サンプル標本の観察で、午後からは実際に自分で魚を解剖して、ひれ、えら、内臓から寄生虫をみつけだす作業でした。
私は小さい魚を2尾解剖したのですが、寄生虫をみつけることができませんでした。
私が解剖した魚の内臓を調べられた浦部先生は、数匹の寄生虫をみつけられました。(さすがです。)
生きている寄生虫を顕微鏡で見ると、「こいつらもけっこう頑張っとる」と思えて、なんか可愛くなってしまいましたよ。いや、参りました。
上の写真は、浦部先生が「こうして解剖するんですよ」と教えて下さってるところです。
(写真は、事務局の女性が写して下さいました。)

グライガー先生が、資料(寄生虫の拡大写真)の説明をされています。
私は、神妙に聞いております。

二人の生徒が、プレパラート標本を観察しているところです。

魚を解剖して、ひれ、えら、内臓などを顕微鏡で見て、寄生虫を探しているところです。
(私は、みつけることができませんでした。)

こんなに熱心に勉強したのは久しぶりですよ。


浦部先生が解剖された15センチぐらいのハスの内臓からは、50匹を越える数の寄生虫がみつかりました。いやー、これにはびっくりしましたねー。
私は、仕事柄、魚に寄生虫がいるのは当たり前と思っておりますから、まあ、こういう作業をしてもなんともないですけど、なれてない人なら、当分の間、お魚は食べられないでしょうね。
でも、これが事実ですから、きちんとした知識を持って対処することが大事だと、あらためて思いました。