2008年5月から始めた「うぐいすの丘日記」は、10年を経過し、皆様方にご愛顧をいただいていました。昨年二度にわたって病気をし、その後新しい投稿をずっと休んでおりました。
その間に、投稿した2093の記事から約400を抜粋し、写真のような冊子にまとめました。一部の方にはご送付いたしましたが、多くの方には何もご案内することなく、現在に至っております。
長年のお立ち寄りに感謝いたしますとともに、終了の御挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。
「うぐいすの丘日記」主


2008年5月から始めた「うぐいすの丘日記」は、10年を経過し、皆様方にご愛顧をいただいていました。昨年二度にわたって病気をし、その後新しい投稿をずっと休んでおりました。
その間に、投稿した2093の記事から約400を抜粋し、写真のような冊子にまとめました。一部の方にはご送付いたしましたが、多くの方には何もご案内することなく、現在に至っております。
長年のお立ち寄りに感謝いたしますとともに、終了の御挨拶をさせていただきます。ありがとうございました。
「うぐいすの丘日記」主


大阪天王寺・阿倍野に二本一高いビル阿倍野ハルカスがある。学生時代の友人S君との待ち合わせでそこに出掛けた。天王寺界隈は秀吉の時代から知られており、大坂の陣では茶臼山には家康が陣を張った場所でもあり、真田幸村が活躍した場所でもある。近年では大阪みなみの繁華街として、なんばと共に栄え新世界・通天閣・天王寺動物園があり観光客で賑やかである。また聖徳太子が建立した四天王寺もある。折角のチャンスでもあり、S君とハルカスの展望台に上り天空からの景色を楽しんだ。
ハルカスからの眺め
新世界界隈。その中央部に通天閣が聳えているが、高さは100m程である。
天王寺公園と動物園。北端に茶臼山がある。
四天王寺。
北側からの展望。大阪駅・梅田方向。
西方向。大阪湾・淡路島が遠望できる。







































































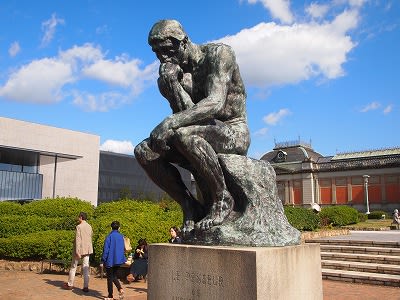






檀上伽藍の北側には徳川家霊台があり、初代将軍・家康と二代将軍・秀忠の霊が祀られている。1643年三代将軍・家光によって建立された江戸時代江戸時代前期を代表する建築である。
徳川家霊台
霊台への入り口。
家康公の霊屋。夫々三間四面宝形造で鋼瓦で葺き頂上に露盤を乗せている。家康公の霊台には鳥居が設けられている。
一辺の長さが6~7mの小さな堂ではあるが、彫刻・彩色・蒔絵・飾金具
など善美をつくしている。

秀忠公の霊屋。
霊屋の正面。煌びやかな扉から様子を伺える雰囲気である。